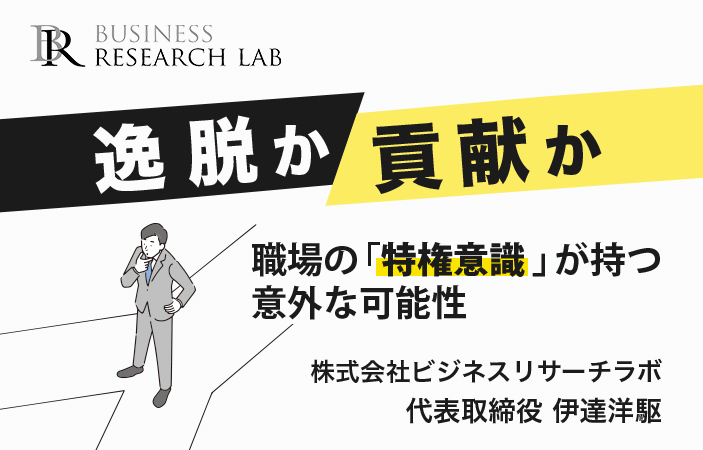2025年4月23日
逸脱か貢献か:職場の「特権意識」が持つ意外な可能性
人は職場において、自分がどのように扱われているのかを意識しています。なかでも「自分は他者よりも優遇されるべきだ」という思いを強く抱く心理を、「心理的特権意識」と呼びます。
心理的特権意識は、組織の中で不正行動や逸脱行動に結びつくという指摘がある一方で、別の条件下では助け合いや前向きな行動を引き出す要素になり得ます。義務感や組織からの支援といった要因が、特権意識との兼ね合いで行動を左右するという報告もあります。すなわち、周囲の環境が整っているかどうかによってその働きが変わりやすいと言えます。
本コラムでは、心理的特権意識が生み出す行動を、研究知見を手がかりに紐解いていきます。初めに、心理的特権意識と義務感が合わさることで、不正行動や助け合いにどのような形で影響が及ぶかを掘り下げます。続いて、自律性が高い仕事環境で特権意識がどう振る舞うかについて調査を見ていきます。そして最後に、従業員の関与を促すようなチーム風土があると、特権意識を抱える人が貢献意欲を高めるという報告を確認します。
本コラムを通じて、人の心の中にある「自分は特別扱いされて当然」という感覚が、どのような条件下で組織を良い方向にも悪い方向にも導きうるのか、その微妙なバランスを考えるきっかけになると嬉しいです。
心理的特権意識が義務感と不一致だと、不正行動が増える
心理的特権意識には「自分こそがもっと優遇されるべきだ」という思いが根づいています。そこに「周囲や組織に対して尽力しなければいけない」という義務感がどの程度伴っているかが、行動を左右するという報告があります。研究では、心理的特権意識と義務感のそれぞれをアンケートで測定し、両者の組み合わせが助け合い行動や不正行動にどう関わるかを分析しました[1]。
心理的特権意識を測る項目としては、「自分は他のメンバーよりも多く報われる資格があると思う」「他者よりも優先的に配慮されるべきだと感じる」などの問いが用意されています。義務感については、「組織全体の目標達成を支えようとする責任を感じる」「周囲に何か不都合が生じないように率先して動く必要があると思う」などが尋ねられました。
そして、従業員が職場でどのような行動をとっているかを調べるために、不正行動(ルール違反や就業時間中の私用行為など)や助け合い行動(忙しい同僚への手助けなど)の頻度を問う設問も同時に実施しています。
回答結果を整理する際には、特権意識と義務感がそれぞれ高いか低いかという組み合わせに着目し、行動の違いを比較しました。その過程でわかったのは、両方がともに高い従業員は、助け合いを行う度合いが高く、不正をする可能性は低い点です。
さらに、義務感が高く特権意識が低い従業員は、仕事に前向きに取り組む姿勢が強く、不正行動が生まれにくいこともわかりました。一方で、義務感が低いのに特権意識だけが強い従業員の場合、倫理観が揺らぎやすく、不正行動のリスクが高まりました。
興味深いのは、たとえ特権意識が高くても、それと同時に義務感がしっかり育っていれば、組織に対する前向きな関わりを保てるところです。特権意識の高い人ほど自分の欲求を優先する思いが強いのですが、義務感や責任感を自覚していれば、そのエネルギーが他者を支えることに向かうこともあり得ます。義務感を欠いたまま特権意識が突出すると、「自分はもっと報われるべきだ」という不満から、ルール違反や不公正な振る舞いにつながりやすいわけです。
研究が着目したもう一つの軸に、エンゲージメントがあります。義務感と特権意識のバランスがとれている人ほど、仕事に対して高いエネルギーを注ぎやすく、助け合い行動が増え、不正行動が減少します。一方、義務感が低く特権意識が強調される場合、エンゲージメントが下がりやすく、不正行動に陥るリスクが相対的に高くなります。
この研究では、多様な業種や職務内容の人々が対象となりました。しかし、異なる職種間で心理的特権意識や義務感に大きな平均差が出るわけではなく、個人差のほうが顕著に表れました。業種を問わず、「自分がもっと評価されるべきだ」と思う人や、「周囲のために尽くすのが当然だ」と考える人が一定数存在することをうかがわせるものです。
総合すると、心理的特権意識と義務感の組み合わせが従業員の行動を左右することがわかります。義務感を伴わないまま特権意識が強いと、不正行動や倫理観の欠如につながる一方、義務感と特権意識がそろって高ければ、前向きな行動を引き出すということです。
では、自律度の高い仕事や自由度が大きい環境では、心理的特権意識がどのように姿を変えるのでしょうか。
心理的特権意識が高いと、自律性が職場逸脱行動を助長する
先ほどは義務感と心理的特権意識が組み合わさったときの問題を取り上げましたが、続いては、仕事の自由度や自律性が特権意識と絡んだときに生じる懸念について扱います。ある研究では、特権意識が強い従業員ほど、高い自律性を許された職場環境で職場逸脱行動をしやすくなるという結果が示されています[2]。
テレワークやフレキシブルな勤務制度のもとで働く従業員を中心に、心理的特権意識の度合い、職務上の裁量権の広さ、そして職場逸脱行動の発生状況を尋ねました。職場逸脱行動とは、組織の秩序を乱すような行為や、同僚に対して攻撃的または協力的でない態度をとる行為を指し、例えば、期限を平然と破ったり、オンライン会議を無断で欠席したりすることが挙げられます。
特権意識の強い個人は、自分が特別扱いされるのが当然だという思いがあるため、組織のルールに従う必要性をあまり感じなくなるのではないか、という仮説が立てられました。
調査のプロセスとしては、まず心理的特権意識の度合いをアンケートで聞き、次に各人がどれくらいの範囲で仕事上の意思決定を行えるかを回答してもらいました。最後に、職場逸脱行動に該当する行いについて、自己申告方式でどの程度あてはまるかを答えてもらう手法がとられています。
その結果、心理的特権意識が強く、かつ仕事の自由度が高い従業員ほど、職場規範を逸脱する行動を起こしやすいことが明らかになりました。自律性が高い状況では、上司や同僚による監督がゆるくなるため、「少々勝手をしても咎められない」という感覚が生まれるのではないでしょうか。
特権意識を抱く人は、規律違反や不正に対して「自分は例外として扱われるはずだ」と考える可能性もあり、その末に職場の秩序を乱すのです。
職場逸脱行動をいくつかの面に分割して検討している点は注目に値します。例えば、組織の物的資源を毀損するような行動と、他者を傷つけるような行動を区別し、それぞれがどの程度増えるかを見比べました。自律性が高まるほど、自分への監視が弱まると感じる人もおり、特に特権意識が強い場合には、周囲の批判を「過敏すぎる」と捉えて、不満を覚えた際に極端な行動に出やすいのではないかとも説明されています。
なお、このとき、組織からのサポートや評価が十分に感じられる場合には、「多少ルールを破っても許されるだろう」という思いがやわらぎます。その結果、反生産的とみなされる行為を抑える効果がわずかに高まります。
一方、リモート下で孤立を感じたり、上司との連絡が滞ったりすると、特権意識の強い従業員が「自分ばかりが冷遇されている」という思いを募らせ、逸脱的な行動を選択しやすくなります。柔軟な働き方がもたらす創造性や主体性が期待される一方、特権意識との相互作用が裏目に出て、規律違反が横行し得る点を研究者たちは懸念しています。
別の見方では、特権意識を持つ従業員が常に悪い成果を生むというわけではなく、自律性が増すことで高いモチベーションを発揮すると指摘されています。ただし、同時に周囲との協調や道徳的な行動を軽んじる傾向も混在するため、その自由度の高さが不正行動にもつながる両義性が存在するということなのでしょう。
ここまで見てきたように、心理的特権意識は義務感との関係だけでなく、自律性の程度とも相互作用し、望ましくない行動を招きやすくなります。次は、特権意識がネガティブな面ばかり生むわけではないという報告を取り上げましょう。
心理的特権意識は、関与の職場風土次第で貢献も阻害もする
義務感や自律性との相互作用を通じ、心理的特権意識が逸脱行動に結びつくシナリオを見てきました。しかし、従業員が職場で発言や提案を行いやすい関与の風土を持つと、特権意識が前向きに働くという報告があります[3]。
具体的には、中国の大手自動車メーカーに所属する41のワークチームを対象とし、合計231組の管理職と部下ペアからデータを収集して分析しました。研究者は、心理的特権意識が高い従業員ほど「自分は他者よりも多くを得るに値する」と考えると踏まえたうえで、チーム単位で意思決定に参加できる度合いが高い、すなわち従業員関与の風土が形成されている場合に、どういった結果が生じるかを調べました。
従業員関与の風土とは、チームのメンバー全員が集まって意見を交わし、業務方針や方法を一緒に考え、そのプロセスで各人の意見が尊重される環境を指します。そうした場が整うと、特権意識があっても「ここなら自分の考えを理解してもらえる」という安心感が生まれ、他者への貢献度も上がるのではないかと考えたのでした。
調査では、心理的特権意識を測定する質問に加えて、チームとしてどのくらい関与型の方針をとっているかを問う項目や、組織市民行動の度合いを評価する項目が用いられました。従業員関与の風土を判断する際には、「意見を提案しやすいと思う」「提案が公正に扱われると感じる」といった質問がメンバー全体に示され、管理職による観察もあわせて確認されました。そして、従業員がどれだけ自主的に組織や仲間を支えているかを示す、組織市民行動の指標とあわせて分析が行われました。
従業員関与の風土が強いチームほど、特権意識がある従業員であっても、自分のスキルやアイデアを活発に発揮し、周囲を手助けする場面が増えます。逆に関与の度合いが低いチームでは、特権意識のある人ほど「どうせ意見を聞いてもらえない」と感じ、組織市民行動が著しく下がります。
従業員が発言しやすく、かつその意見を取りこぼさない仕組みがあるかどうかが、本人の「自分を認めてもらいたい」という欲求を満たすうえでの条件になっています。
心理的特権意識の高い従業員の貢献を引き出すには、「自分を認めてもらいたい」という気持ちを充足する場を整えることが肝要です。関与の風土を重視する姿勢は、社会的交換が不公平だと感じさせにくくし、「自分ばかりが割を食っている」という不満をやわらげる効果があります。
逆に言えば、メンバーの意見を取り合わない雰囲気が強い環境では、特権意識のある従業員は「ここで発言しても無駄だ」と思い、組織のために動こうという意欲を失ってしまう可能性が高まります。
総じて、従業員関与の風土がどの程度しっかりしているかによって、心理的特権意識が組織市民行動の増加につながるか、あるいは阻害するかが変わってくるという結論が導かれました。
これは義務感や自律性とはまた異なる観点で、特権意識がもたらすダイナミクスを捉える手がかりになります。特権意識の高い従業員が「より優遇されるべきだ」という考えを抱えていたとしても、意見を吸い上げる場が整えば、むしろそのエネルギーが建設的な方向性に向かうわけです。多様な人材が集まる組織で、いかに個々人の能力を生かせるかを考える上で、なかなか興味をそそる示唆です。
加えて、この研究は、情緒的コミットメントという概念にも焦点を当てています。情緒的コミットメントとは、組織に対して愛着を抱き、そこに所属していることを喜ばしく思う感情的な結びつきを指します。
心理的特権意識の高い従業員は、本来であれば「自分が得をするかどうか」を重んじる思考が働きやすいのですが、関与の風土が強いチームで自分の意見を尊重してもらえると感じれば、組織に愛着を持ちやすくなります。そうして生まれた情緒的コミットメントによって、同僚への支援や組織市民行動への意欲が高まるのです。
研究者は、このメカニズムを検討しました。その結果、チームの関与度が高いほど、特権意識の高さが情緒的コミットメントと結びつきやすくなり、その情動的コミットメントを介して組織市民行動が増える筋道が支持されました。
言い換えれば、「自分は特別扱いされて当然だ」という欲求をいかに組織やチームが受け止めるか次第で、特権意識をプラス方向に活用できる余地があります。こうした議論は、不公平感をできるだけ小さく抑えながら、人それぞれの意欲を引き出す取り組みがチームワークに影響することをうかがわせます。
脚注
[1] Chen, Q., Shen, Y., Zhang, L., Zhang, Z., Zheng, J., and Xiu, J. (2023). Influences of (in) congruences in psychological entitlement and felt obligation on ethical behavior. Frontiers in Psychology, 13, 1052759.
[2] Bizri, R. M., and Kertechian, S. K. (2024). Investigating the link between psychological entitlement and workplace deviance: Moderations and post hoc analysis. International Journal of Organizational Analysis, 32(10), 2177-2204.
[3] Schwarz, G., Newman, A., Yu, J., and Michaels, V. (2023). Psychological entitlement and organizational citizenship behaviors: The roles of employee involvement climate and affective organizational commitment. The International Journal of Human Resource Management, 34(1), 197-222.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。