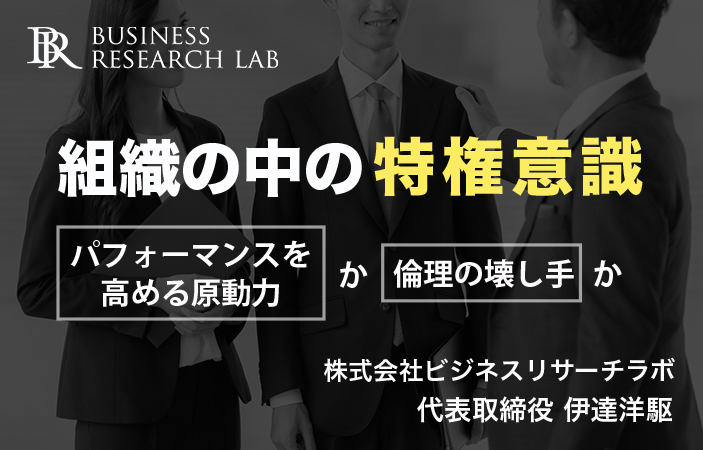2025年4月22日
組織の中の特権意識:パフォーマンスを高める原動力か、倫理の壊し手か
組織で働く人々の心理を理解する上で、「心理的特権意識」という概念が示唆を与えてくれます。心理的特権意識とは、「自分は他者より優位な扱いを受けるべきだ」という感覚を指します。従来、この特権意識は職場の人間関係を損なう厄介な要因として語られることが一般的でした。確かに、過度な自己中心性は周囲との軋轢を生み、チームワークを阻害し得ます。
しかし、近年の研究は、この特権意識が持つ意外な側面に光を当て始めています。例えば、特権意識の強い人ほどキャリア開発に熱心で、仕事への没入度が高まる傾向が指摘されています。自分は特別な存在だという認識が、職場での成功を追求する原動力となっているのです。
その一方で、組織の利益を名目に倫理的な境界線を越えてしまうリスクも指摘されています。公正な処遇を受けていないと感じた際には、組織に対して破壊的な行動をとる可能性も報告されており、特権意識の複雑な性質が浮き彫りになっています。
本コラムでは、心理的特権意識がキャリアへの意欲を高める肯定的な側面と、職場での倫理や公正さを歪める負の側面の両方について、研究成果をもとに検討していきます。
組織との一体感が強いほど不正行為を正当化しやすくなるという知見や、公正感の有無が従業員の態度を左右するという発見など、具体的なデータに基づいて特権意識の多面性に迫ります。
学術的な視点から積み重ねられた知見は、私たちが「自分は特別だ」という感覚を持ったとき、その心理がどのように行動を導くのかを理解する手がかりとなるはずです。
キャリア志向が強く仕事に積極的
ある研究では、心理的特権意識を従来の否定的イメージだけで捉えず、むしろ仕事への意欲を高める下地になるかもしれないという発想に注目し、調査を行いました[1]。
調査の参加者は、まず心理的特権意識を測る尺度に回答しました。そこでは「自分には他者より有利な待遇が当然だと思うか」「自分のような人物には格別の配慮が与えられるべきだと感じるか」などが問われ、どの程度そう考えているかを数値化していきます。
加えて、キャリアに対してどれほど前向きな姿勢を持っているのかを探る設問が用いられました。「給料アップや昇進のためにどんな努力も惜しまないか」「今の会社で成功を収めることをどのくらい優先しているか」といった項目で、将来の仕事人生をどれだけ真剣に見ているかが計測されました。
研究者たちは、心理的特権意識の高さとキャリア志向との間の関連を統計モデルによって検討し、特権意識が強い人ほど「自分の評価を高めるために昇進や報酬を求めるだろう」という見立てを得ました。
自分は特別だという感覚を持つことで職場内での成功を強く意識し、その結果、キャリアに打ち込む度合いが増すという仮説です。分析では、ジョブ・インボルブメントと呼ばれる仕事への心理的な没頭度も測定し、キャリア志向を媒介とする形で仕事への熱中が深まる構造が見出されました。
研究チームはさらに、自己効力感(課題をうまくこなせるという自信)が高いかどうかを調整変数として設定し、その存在がキャリア志向と仕事への没頭にどの程度かかわるかを検証しました。
そこでは、特権意識からキャリア志向へ、そして仕事への意欲が高まるという流れに関して、自己効力感が予想していたほどの強い調整作用を持たないという結果が得られました。つまり特権意識が強い人は、自分の能力認知の強弱にかかわらず、「当然それくらいの報酬を得られる」と思いやすく、キャリアに注力する姿勢を維持するのでしょう。
一連の結果から、心理的特権意識は職場内でネガティブな局面をもたらすだけではなく、人をキャリアに向けた活動へ駆り立てる活力として働く面もあることがわかります。特権意識を持つ従業員が企業にどれだけ貢献しようとするかを見極めるには、他の心理要因との組み合わせをさらに検討すべきでしょう。
このように、特権意識が肯定的なキャリア観と結びつき、当人の仕事への関わり方を厚くするという事例は、特権意識の見方を従来とは異なる角度から捉え直すきっかけとなります。ただし、これはあくまでも一面であり、後述のように利己的な動機から不正を行ってしまう現象も報告されており、特権意識が複雑な性質を帯びていることを示唆しています。
組織のために非倫理的行動をとる
特権意識が強い人が、昇進や経済的成功を得るために熱心に働く可能性がある一方、自身のイメージや評価を維持するために周囲を巻き込む行動をとることも指摘されています。
ある研究では、従業員の心理的特権意識が組織の利益を追求する場合に非倫理的行動に走るかどうかを調べました[2]。参加者は300名ほどで、質問紙を用いて、心理的特権意識の度合いや組織への帰属意識、そして非倫理的行動の頻度に関して回答する形式がとられました。
研究の独自性としては、組織にとって有益ではあってもモラル上は問題をはらむ行動(非倫理的向組織行動)だけでなく、逆に会社の利益を損ねる行動(非生産的職務行動)についても同時に測定し、心理的特権意識が両者にどう関係するかを整理しているところです。
非倫理的向組織行動には、会社を守るために顧客に過度に誇張した情報を伝えたり、経理報告に手を加えたりといった行動が含まれます。一方、非生産的職務行動には、企業への不満や対立から生じる破壊的行為や組織資源の乱用などが該当します。
分析では、心理的特権意識が非倫理的向組織行動を高める作用が認められ、非生産的職務行動にはやや抑制的な作用が働くという結果が導かれました。すなわち特権意識が高い人は、組織が得をするならば多少の不正でも行う態度を見せつつ、企業にダメージを与える行為からは距離を置くような姿が浮かんだのです。
さらに研究では、組織アイデンティフィケーションという心理プロセスが取り上げられました。組織アイデンティフィケーションが強いほど従業員は「自分と会社が一体だ」と感じるため、その結果「会社の利益が自分の成果と直結する」と考える可能性があります。
心理的特権意識の強い人が組織アイデンティフィケーションまで高いと、非倫理的向組織行動に関与するリスクが増すことが見出されました。
ただし、「自分だけが損をしている」という剥奪感が強いときには組織のために動きにくくなるというパターンも示唆されています。「自分が冷遇されている」と思うと会社を利する行動を取りたがらないからでしょう。
組織の利益を守る目的であればルール違反も行い得るといった行動を、心理的特権意識が強化する図式が見えてきます。個人としては、自分にふさわしい承認を得るためであれば、多少の倫理的問題は目をつむってしまうのかもしれません。
組織のために不正を働きやすい
似た視点をもつ別の研究でも、心理的特権意識が不正行為の加速要因になるかを調べています[3]。調査では、まず組織への帰属意識を測る尺度が用いられました。「自分の所属する組織を誇りに感じる」「組織が低く見られると、自分も侮辱されたように感じる」などを尋ね、その強弱を点数化します。
次に、心理的特権意識の尺度を加え、例えば「自分ほどの人材は特別扱いされて当然だと思う」といった項目の答えを集計しました。そして、不倫理的な行動と関連づける部分として、非倫理的向組織行動の尺度を導入し、会社にとってプラスになるのなら情報を捻じ曲げたり秘密を隠蔽したりした経験があるかを評価しました。
こうした手続きにより得られた結果を分析すると、組織アイデンティフィケーションが高い人ほど心理的特権意識を抱きやすく、その組み合わせが非倫理的向組織行動につながりやすいパターンが見出されました。
そこには、操作的な性格をもつ従業員がさらに特権意識を強化する可能性があるという示唆も得られ、会社への協力を大義名分とする不正を積極的に行う道筋が指摘されています。例えば、自分に都合の良いように情報を捏造してでも組織を守ることが、自分の評価を上げると理解している人ほど、不正行動に足を踏み入れるわけです。
このような「不正行為を組織のためとみなす現象」は組織アイデンティフィケーションの正面だけでなく、その裏面にも注意を向けさせる結果です。本来、組織アイデンティフィケーションは企業への貢献意欲を高め、団結心を育むポジティブな働きとしても取り上げられます。
しかし、心理的特権意識のように「自分は特別である」という感覚がそこに混ざると、帰属感が過剰に強まって倫理観がゆがむ可能性があります。特に、操作的な性格が高い従業員は自分の利益と組織の利益を重ね合わせ、「会社のため」という理屈で得られる成果を手にすることを優先するとの見立てが示されました。
不正を正当化しやすい
心理的特権意識が高まると、それによって「自分は正しいことをしている」という認知上の作用が生まれます。例えば、「自分のような能力ある人間が組織を支えるのは当然で、その過程で少しばかりルールを逸脱しても構わない」といった考え方をしやすくなるのです。これを道徳的逸脱と呼びます。
研究によれば、心理的特権意識が強い人ほど、自身の行為を正当化しやすい特徴があります[4]。業績を盛る行為を「組織にとって必須のアピールだ」と言い換えたり、顧客を誤解させるような説明を「会社のブランド力を守るための方策だ」と捉えたりして、道徳的な関心を薄れさせるのです。
さらに、特権意識の高い人のなかでも会社を強く意識し、そこからの報酬や評価を期待している層が、不正行動に踏み切る割合を押し上げています。組織アイデンティフィケーションが高い従業員、つまり「会社の成功が自分の成功とイコールである」と感じる心理が強い従業員ほど、仮に不正であっても「組織を助ける」目的があるなら受容してしまいます。組織と自分が分かちがたく結びついている感覚が、過大な自己正当化の土台となっています。
一方で、道徳的逸脱が働くとき、公正感の評価が低い人は会社に逆らう行動へ向かいやすいという研究もありました。自分だけが不当に扱われていると思ったときには、「こんな不正な仕打ちをしている組織なら逆にコストを与えても構わない」と開き直るのです。
このように、心理的特権意識の高さと道徳的逸脱、組織への同一化、そして職場の公正感との組み合わせが、どちらの方向へ不正行動を正当化するかを左右するという複雑な様相が浮かび上がります。
心理的特権意識が強い人は常に攻撃的なわけではなく、環境次第で結果は変わり得るという結果とも言えるでしょう。会社に利する形での不正を選ぶか、あるいは自分が被害者だと思う方向に転じて会社へダメージを与えるかは、その人が置かれた状況と認知のあり方に依存します。自らを特別だと感じることは、場合によっては職場に貢献する熱意を引き出す一方、道徳意識を弱めて危うい行動をもたらす側面も含んでいます。
二つの顔を持つ心理的特権意識
職場における心理的特権意識にまつわる研究を見ると、同じ特権意識であってもキャリアへの強い意欲につながりやすい場合と、不正行動に走りやすい場合の両面があることがわかります。キャリアアップを望む気持ちは、当人のパフォーマンスを上げる可能性を秘めていますが、それと同時に、企業の利益を理由づけとしてモラル上のラインを越えかねないとも考えられます。
周囲から見れば「真面目にがんばっている」と映るかもしれませんが、実態としては数値や情報を操作してでも業績をよく見せたいという歪んだ思惑が隠れているかもしれません。
特権意識は必ずしもどんな場面でも厄介なものとは限らない一方、人の倫理的な判断を都合よく曲げるきっかけになることもあります。職場内の様々な人間関係や本人の精神的な要因と組み合わさることで、特権意識は千差万別のふるまいを導きます。
職場のマネジメントを考える上で、このような心理的特権意識の二面性を踏まえておくと良いでしょう。自分を特別だと考える従業員は仕事に全力で取り組み、その成果が企業に貢献するかもしれませんが、同時に不正行為を正当化する懸念も伴います。
人が自己肯定感と会社の目標をどのように結びつけているのかや、公正さをどのくらい感じているのかといった点は軽視されてはいけません。そうした観点を見失うと、当初は有望だった人材が予想外の行動をとり、周囲を巻き込む混乱を生むリスクがあります。
脚注
[1] Lin, S. Y., Chen, H. C., and Chen, I. H. (2022). The bright side of entitlement: Exploring the positive effects of psychological entitlement on job involvement. Evidence-based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, 11(1), 19-34.
[2] Aqeel, M., and Siddiqui, D. A. (2020). Psychological entitlement and unethical workplace behavior in Pakistan: The role of status striving, moral disengagement, organizational identification, and egoistic deprivation. Sarhad Journal of Management Sciences, 6(3), 597-618.
[3] Lee, A., Schwarz, G., Newman, A., and Legood, A. (2019). Investigating when and why psychological entitlement predicts unethical pro-organizational behavior. Journal of Business Ethics, 154, 109-126.
[4] Naseer, S., Bouckenooghe, D., Syed, F., Khan, A. K., and Qazi, S. (2020). The malevolent side of organizational identification: Unraveling the impact of psychological entitlement and manipulative personality on unethical work behaviors. Journal of Business and Psychology, 35, 333-346.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。