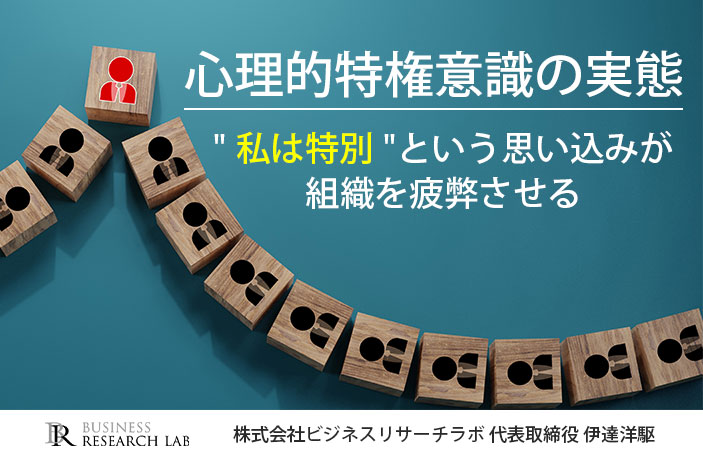2025年4月21日
心理的特権意識の実態:“私は特別”という思い込みが組織を疲弊させる
誰でも、他者より自分こそが高く評価されてほしいと願う瞬間があるかもしれません。ところが、その思いが強まって「自分だけは特別な待遇に値する」という意識にまで及ぶと、人間関係や職場の雰囲気を厳しい状態へ導くことがあります。
心理的特権意識という言葉は、まさに「自分は当然のように優先されるべきだ」といった思い込みを指します。この意識をもつ人は周囲との折り合いに苦心しやすく、互いの信頼が築きにくくなる危険があります。さらに、そこに攻撃的な感情や独断的な態度が結びつくと、周囲に対するネガティブな感情を高め、知識や情報を共有しようとしない様子まで生まれます。
これまでの研究では、心理的特権意識と関連する行動を調べる過程で、利己的・攻撃的な行動から対人関係の破壊的行為、上司への不信感に基づく知識の隠匿など、いくつもの負の作用が見出されてきました。
本コラムでは、いくつかの研究知見をもとに、心理的特権意識がどのように人間関係や職場の雰囲気を荒らすかを述べます。利己的で攻撃的な行動に結びつく様相、対人関係における逸脱的な振る舞い、上司を不当に扱う認知を背景とした知識隠蔽、そして独断性や謙虚さの欠如との関連について見ていきます。
利己的で攻撃的になりやすい
自分だけは手厚く扱われるべきだという心情が強まると、自分こそが一番であるという思いがいっそう高まり、他者と穏やかに協調しようとしなくなります。
一連の学術的な検討によって、心理的特権意識が高い人は、他者からの評価や処遇が自分の思惑より少しでも低いと感じると、怒りや憎しみを示しやすいと報告されています[1]。自分が当然の扱いを受けていないと感じた瞬間に、不満や苛立ちが沸き上がるためです。
例えば、特権意識の度合いを測り、それが対人コミュニケーション上のトラブルとどのように関連するかを調べた研究があります。そこでは、特権意識の強い回答者が仮想の場面で「他者と資源を分かち合うか」という選択を求められるとき、利他的配分より自分の取り分を大きくしようとする行動が目立つという結果が得られました。
こうした自己中心の行動は、当人が大事にされていないという認知を抱いた瞬間に攻撃的な発言や態度へと転じやすい側面も含んでいます。客観的にはわずかな批判であっても、特権意識の強い人にとっては「自分の特別性を脅かす行為」だと捉えられるために、そこから敵対的な反応に移りやすいのです。
心理的特権意識を高く持つ参加者に批判的フィードバックをわずかに与えた段階で、その被験者が怒りを抱いたり、いわゆる攻撃性に近い行動をとるかどうかを測定しました。結果、特権意識が高いほど攻撃的な発話が出現しやすいことが見えてきました。
ただし、特権意識を伴う自己評価が高い人は、一見すると自信家のように見える一方で、実際には自尊感情が不安定であるとの見方も示されています。自分の地位が脅かされそうだと感じると、一気に反発し、言動のトゲを強めることがあるというわけです。
心理的特権意識が背景にあるとみられる場面では、自分の特別性を守ろうとする意識が強いほど、外部からの不満や指摘を素直に受け止めようとしなくなります。厳しい環境で育ち「もう失いたくない」という思いが強まったケースでも、特別な待遇を求める気持ちが研ぎ澄まされ、少しの脅威に対して攻撃的にふるまってしまう様子も報告されています。
対人逸脱行動をとりやすい
組織研究の領域では、逸脱行動という言葉で職場内での反社会的な振る舞いを扱います。対人逸脱行動は、同僚や他者に対して敬意を欠いたやり方で接したり、困らせたりするような言動や態度を取る状態を指します。ここで心理的特権意識が関わると、どうして問題が深刻化するのかを探索した研究が存在します。
実験や調査を組み合わせた研究では、特権意識が高い人を対象に「剥奪感」と「逸脱行動」の関係を分析しようと試みました[2]。そこでは、特権意識が強い人ほど、自分が本来得るべき報酬や待遇が得られていないと考え、その感情を抑え込みきれずに対人関係で逸脱した行いに走ることが確認されています。
ここでいう対人面の逸脱とは、同僚を傷つける言葉を発したり、後ろ向きな噂を流したりするといった行動を含みます。対人トラブルは業務効率だけでなく、組織全体の雰囲気を暗くする要因になります。
ただし、興味をそそる点としては、特権意識が剥奪感を通じて対人的な逸脱に結びつく一方で、組織全般を狙った逸脱、例えば、会社への器物破損や財務上の不正などとは直結しなかったということです。
要するに、自分が「同僚や周囲の人々から本来の評価や待遇を得ていない」という思いが強まると、身近な個人を攻撃する行動へ向かいやすいが、組織そのものに対しては必ずしも矛先が向かないのです。特権意識の高い人の感情は「目の前の人間に対する怒りや苛立ち」に集中しやすいのかもしれません。
特権意識が高い人は「自分は不当な扱いを受けた」と考えると、その不満を職場仲間への迷惑行為などで晴らそうとすることが報告されています。その上、剥奪感がいっそう大きくなるほど、対人での摩擦が拡大する危険が増します。
この話は、周囲とのコミュニケーションが円滑に進まず、誰が正しいのか、どのような判断がふさわしいのかといった点を落ち着いて議論できなくなることを示唆します。一度そうした対人トラブルが加速すると、対立意識が生まれ、修復が難しい可能性もあります。
対人逸脱行動が横行すると、業務効率の低下にとどまらず、全体の士気が下がり、協力関係が崩れます。職場であれ集団であれ、悪意や衝突が連鎖する場合、その土台には「自分だけは恵まれるはずだ」という特権意識が根を下ろしていることがあります。
上司を不当視し知識を隠す
職場の人間関係において、上司に対する不信感が強くなると、チームの間で知識共有が進みにくくなる事態が生じます。心理的特権意識を高くもつ従業員の場合、上司からの指示や評価が自分の当然の期待に及ばないと感じたとき、それを「虐げられた」と見なすという調査結果があります。この認識がさらに強まると、知っている情報やノウハウを隠そうとする行動に向かいやすいというのです。
ホスピタリティ業界の従業員を対象にした研究において、特権意識が高い人ほど「自分の上司は非友好的で攻撃的だ」と捉える度合いが上がり、その結果、知識を共有せず、あえて隠す行動へ移るとの報告が出ています[3]。
ここで鍵となるのは、実際に上司が虐げる態度をとったかどうかではなく、従業員側が「侮辱的だ」と感じる主観的な認知だということです。特権意識が強い人は、ちょっとした指摘やアドバイス、注意なども敵対的に解釈しやすく、「自分の特別性が認められていない」と受け止めます。このようにして生じた不信感は知識隠蔽につながることがあります。
知識隠蔽の具体的な手段には、曖昧な説明をして質問者をごまかす行為や、手助けを約束しつつ実際には情報を渡さない行為などが含まれます。特権意識が高い人は周囲を警戒しているため、あえて情報格差を残して自分の地位を守ろうとする意図が働くのかもしれません。「上司は自分のことを低く扱う存在だ」という意識が強ければ、積極的に協力しようという動機は生まれにくくなります。
この現象を説明する理論のひとつに、帰属バイアスが関係していると指摘されています。特権意識の高い人が、自分にとって気に入らない出来事を上司の悪意に帰してしまうという認知の偏りです。
ある研究で「敵対的帰属バイアス」という言葉を用いて指摘されていたのは、まさに自分が正当に扱われていないと感じたとき、周囲の行動に悪意の意図を見出す心理を示すものです。こうした偏りが加わると、上司を「自分を陥れる者」と考えてしまい、知識共有などあり得ないと感じるのでしょう。
組織内での情報伝達が滞ると、サービスの質が下がることや、新しいアイデアが生まれにくくなることが予測されます。知識を握った当人も、周囲から協力を得られない状態に陥り、チーム全体のコミュニケーションが不安定になりかねません。
独断的で謙虚さに欠ける
特権意識の強い人には「自分の主張こそが正しい」と信じ込む傾向があります。ここで言う独断性とは、他者の意見に耳を貸さず、自分の信念を絶対視する態度を指します。ある調査では、特権意識を測る尺度と独断的な傾向を測る尺度の間に正の相関が見られました[4]。特権意識が高い人は、ほんの少しの異論すら「自分への挑戦」だと受け止め、主張を曲げることを拒む可能性があります。
この種の態度は他の場面にも及び、特権意識が強い人が「自分こそが正しい知識をもっている」と過信しているという結果も存在します。信念の確実性が極端に高い人ほど、対立するデータや新しい発見に対して柔軟に対応しにくいのです。「自分が受けるはずだった特別扱い」を正当化するために、論理的な検証や反証可能性を受け入れにくくなります。
謙虚さの観点からいえば、特権意識が高い人ほど「自分の能力や功績を誇り、周囲に配慮する態度が弱まる」という指摘がなされています。「自分を大きく捉える」図と「他者を大きく捉える」図のどちらを選ぶかという視覚的な質問紙が用いられ、特権意識が強い人は自分を大きく描いた図を選択するという報告がありました。このことは、自分を優先に考える心理を表していると考えられます。
謙虚さに欠けると、他者の助力を得るきっかけも逃します。周囲から見ると、特権意識が強く独断的な人は「どうせ聞く耳をもたない」と思われ、意見交換が成立しにくくなります。そうして孤立感が強まると、本人はより一層「自分だけが正しく、周囲が間違っているのだ」との思いを抱き、ますます独断性を強めます。ここには、心理的特権意識が生む悪循環が潜んでいます。
人は集団で暮らしていくうえで、謙虚さや柔軟性を発揮しながら助け合う局面を持ちます。ところが、特権意識を過度にもってしまうと、その性質が周囲との協調を遮り、孤立や対立が長期化しやすくなります。
職場における特権意識の代償
心理的特権意識は、ある意味で少しうらやましがられるほどの自信に映る一方、その裏で対人トラブルや対立を招きやすい面を持っています。本コラムでは、利己的で攻撃的になりやすい側面、周囲との衝突を深める逸脱行動、上司を不当視して知識を隠す振る舞い、独断的で謙虚さに欠ける態度などを見てきました。
どれも当人が自らを特別に扱ってほしいという思いから始まるものの、それが職場や人間関係を混乱へ導く契機になる点は見逃せません。とりわけ、自分の特別性が脅かされていると認識したときに、苛烈な言動を取りやすいことは深刻です。
職場のマネジメントを考える上では、こうした心理的特権意識がいかなる形で表面化し、人間関係を弱めるかを冷静に理解しておくことが欠かせません。このような考えが組織に存在すると、知識や情報の共有が進まず、攻撃的な態度を放置すれば全体の士気にも悪い結果を招きます。
心理的特権意識は組織全体のパフォーマンスに影響を及ぼす要因となり得ます。例えば、特権意識の強い従業員が存在することで、チーム内のコミュニケーションが歪められ、創造的な議論や意見交換が阻害される可能性があります。これは組織の革新性や適応能力を低下させかねません。
また、心理的特権意識は、一度顕在化すると、その影響が組織内で連鎖的に広がっていく危険性もあります。特権意識を持つ個人の行動が、他のメンバーの不信感や警戒心を誘発し、それがさらなる対立や分断を生むという悪循環に陥りやすいのです。この連鎖を断ち切るためには、早期の段階で介入や対策を講じる必要があります。
心理的特権意識への対応において重要なのは、この問題を個人の責任として片付けるのではなく、組織文化や職場環境の観点から包括的に捉えることです。特権意識が生まれる背景には、例えば、過度な競争原理や成果主義、あるいは不明確な評価基準といった組織的な要因が潜んでいるかもしれません。
したがって、この問題の解消には、個々人の意識改革を促すだけでなく、公平で透明性の高い評価システムの構築、コミュニケーションを促進する組織文化の醸成、そして心理的安全性が確保された職場作りなど、多面的なアプローチが求められます。
脚注
[1] Campbell, W. K., Bonacci, A. M., Shelton, J., Exline, J. J., and Bushman, B. J. (2004). Psychological entitlement: Interpersonal consequences and validation of a self-report measure. Journal of personality assessment, 83(1), 29-45.
[2] Vatankhah, S., and Raoofi, A. (2018). Psychological entitlement, egoistic deprivation and deviant behavior among cabin crews: an attribution theory perspective. Tourism Review, 73(3), 314-330.
[3] Khalid, M., Gulzar, A., and Khan, A. K. (2020). When and how the psychologically entitled employees hide more knowledge? International Journal of Hospitality Management, 89, 102413.
[4] Curry, C. C. (2010). Expanding the nomological network: Entitlement and associated constructs (Doctoral dissertation, Pacific University).
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。