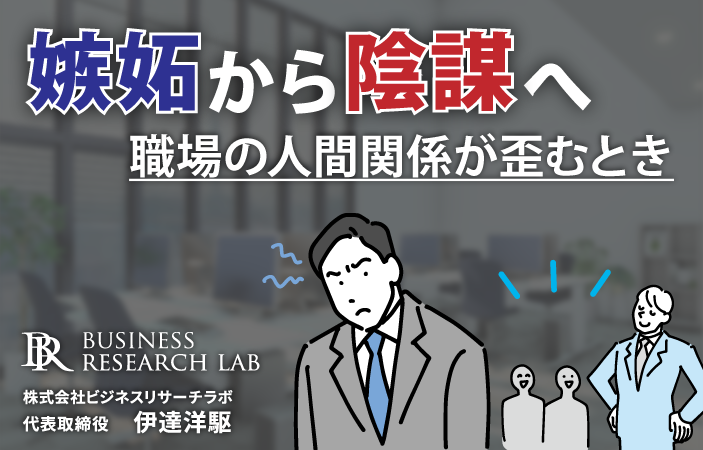2025年4月17日
嫉妬から陰謀へ:職場の人間関係が歪むとき
人と人が協力して働く職場では、裏表のない関係が大事だと感じることが多いかもしれません。けれども、業務上の競い合いや感情のもつれなどが重なると、目に見えにくいかたちで他者を不利に導く振る舞いが生まれることがあります。
そうした行動が積み重なると、人間関係がぎくしゃくして不信感が高まり、仕事のやりとりやチームワークに暗い影が落ちる場合があるのです。職場での些細なすれ違いから、明け透けには話しにくい妨害行動まで、こうした表立ちにくいやりとりを指して「社会的陰謀」と呼びます。
ここでは、いくつもの検討で取り上げられた事例を手掛かりに、いったいどのような思考や感情が社会的陰謀を誘発するかを探りたいと思います。嫉妬やライバル意識、あるいは自分の将来の立場への不安など、さまざまな要素が関与しうることがわかっています。
周囲の人をうらやんだり疑ったりする感情は、自分自身の意欲を高める小さな刺激にもなり得ます。しかし、その感情が妙な方向へ先鋭化すると、仲間を突き落とそうとする言動に発展し、チーム全体の結束を脆くしかねません。こうした複雑な力学を背景とする社会的陰謀の成り立ちを明かそうとする試みは、職場の集団心理を理解するうえで意義深いものです。
本コラムでは、嫉妬が引き金になるケース、道徳観の混乱が働くケース、政治的な駆け引きが絡むケース、将来の展望に対する不安が誘因となるケース、そしてストレスに満ちた状況で生じるケースを順番に見ていきます。
嫉妬が社会的陰謀を助長する
ある分析では、通信関連の職場に勤める複数の従業員を対象に、質問票への回答を集約して統計手法を用いた検証が行われました[1]。嫉妬をめぐる感情が仕事の人間関係にどう絡むかに焦点を当て、回答者一人ひとりの心情を数値化し、それが周囲に対して陰のある振る舞いをするかどうかと関連づけられたのです。
とりわけ、相手の地位を引きずり下ろそうとする行動がどれほど起こりやすいかを見極めようとする試みです。質問票には、同僚に対して「真似をして上回りたい」「無力感を抱えているので妨害したい」「悪意をもって出し抜きたい」「公然と敵対行動に踏み切りたい」といった感情がどの程度あるかを測る項目が用意されていました。そして、従業員のタイプを複数に分類し、その分類ごとに社会的陰謀との結びつきを捉えています。
結果をおおまかに見ると、嫉妬を抱く人は、そうでない人に比べて周囲の評価や地位を落とそうとする行為に走りやすいとされました。さらに、その嫉妬が競争相手に負けたくないという模倣的な気持ちか、何もできない無気力な気持ちか、あるいは意地の悪さが前面に出た気持ちか、といった違いによって、妨害の方向性や度合いに差が生じるという点も確認されています。
模倣型の嫉妬をもつ人は一見向上心を重んじているようでも、心のどこかで他人を落とす方向へ進む場合があるようです。また、意地の悪い思いが強い場合は、同僚の評判を失墜させる言動に踏み込みやすいという結果が得られました。
この検証から考えられるのは、嫉妬が必ずしも向上への原動力にならず、周囲への敵意をかき立てる危険があるという点です。外から見ると大きな対立がないように見えても、内面で「なぜ自分だけがこんな立場か」という落差の意識がくすぶると、いつの間にか同僚を妨げる考えに至る可能性があるかもしれません。そして、その行動は周囲に伝わりにくい形で行われるので、当事者同士以外は気づきにくいという怖さがあります。
嫉妬が道徳的脱却を介して社会的陰謀を強める
別の取り組みでは、嫉妬がどのように心の中の倫理観をゆるがせてしまうかに注目が向けられました。大病院の従業員や学生チームなどを対象に、複数回にわたるアンケートが実施され、日常的な嫉妬感情が「道徳的脱却」と呼ばれる心的プロセスを経由して、周囲の存在を陰で傷つける行動へと導くかどうかを掘り下げています[2]。
最初の段階として、「同僚が成功をおさめているのを見て、どのように感じるか」という心理面の質問に答えてもらいました。その上で、一定期間をあけて「仲間に有形無形の妨害をしたことがあるか」という項目を尋ねています。さらに、人は他者を批判したり貶めたりするときに、心のバランスを保つために倫理観をねじ曲げて正当化する傾向をもつという仮説に基づき、道徳観が緩む度合いも測られました。
結果、嫉妬が強い人ほど、道徳観を弛緩させる状態に陥りやすく、それが同僚に対する陰湿な仕打ちの発生と関連づけられていました。さらに、職場やチーム内の仲間意識が低いほど、このプロセスがいっそう深刻化するという示唆が得られています。職場への愛着が薄い人ほど、「多少の悪口や噂話は正当化しても構わない」と自分の行動を内面で肯定してしまうのです。
そこから考えると、嫉妬が一人の心に起こるだけでなく、チーム全体のつながりや規範の薄弱さとも結びつきやすい点が浮かび上がります。道徳的なブレーキが外れた状態では、自分だけが得をしようとする思考が先に立ち、同僚に悪い印象を広めたり情報を隠したりする方向へ逸脱しやすくなると言えます。こうした内面の作用はなかなか表立って指摘されにくいため、周囲はうわべの協調だけを見て安心してしまうかもしれません。
政治的スキルが社会的陰謀を招く
仕事の場で情報収集や人脈づくりがうまい人は、周囲を味方につけたり状況を整理したりするのが得意で、成果をあげるイメージがあるかもしれません。ところが、そうした「政治的スキル」が高い人ほど、かえって仲間からの疑いを買い、陰謀の的にされやすいという報告も存在しています[3]。ここでは、そのメカニズムを探ろうとする検証が重ねられています。
まず、職場内で政治的に器用な人がいると、周囲は「自分の立場を脅かすかもしれない」という思いにとらわれることがあります。いくつかの実験や質問回答の集計から、高い政治的スキルを備えた従業員が成果を上げやすい場面に遭遇すると、周りの人は「その人だけが注目をさらってしまう」と感じて地位への脅威を意識しやすくなることが示されています。
しかし、この脅威の意識がすぐに表立った対立に結びつくわけではありません。むしろ、ライバルだと心の中で決めつけた相手を少しずつ疎外しようとする行動が裏で起こるのだと考えられています。
これは、あからさまな衝突に出るよりも、影で信用を低下させるほうが自分への反撃をかわしやすいという心理も働いているのではないでしょうか。政治的スキルを駆使する人は往々にして社内の情報や人間関係を把握する能力が高いので、逆に同僚たちはその存在をより強く自分への脅威と感じてしまうのです。
ここで注目されるのは、ライバル意識の強さという要素です。人によっては、そこまで熱心に競争を感じない場合もあります。一方、競争心が高い環境や評価制度があると、政治的に優れた人をターゲットにして陰で弱体化を図る行動が起こりやすくなります。
これらの知見は、「高いスキル」がいつでも歓迎されるわけではなく、意外な形で周囲からの嫉視や対抗意識を誘発する可能性を示唆するものです。組織内のステータスや評価の仕組みによって、人々の隠れた思惑が加速されやすいという結果も得られています。
将来の脅威が社会的陰謀を招く
もう少し時間軸を広げて考えると、「今は自分より下の立場にいるけれど、将来伸びてきそうな人」に対する反応が問題になる場合があります。ある長期の追跡と実験的なやりとりから、「近い将来、自分を追い抜くかもしれない」という不安が高まると、今の段階でその人物を妨げるような行為を始めることがあります[4]。
参加者が「同じ組織で働く別の人の成長の度合い」を振り返り、その人が今後どれほど台頭してくるかをイメージする場面が設定されました。次いで、「相手が勢いづいて自分の立場を脅かすかもしれない」という認識が生まれた際に、どのような感情や態度が生じるかを尋ねています。その上で、後日、同じ相手に関してどのような評判を流したかや、業務をサポートせず不利に追い込んだ経験はあるかなどを問い、全体の様子が整理されました。
その結果、将来の脅威を感じた時点で抱える嫉妬や不安が、あとになって社会的陰謀に近い振る舞いとして表出することが確かめられました。加えて、職場内の競争が激しいほど、この動きが強くなるという傾向が見られています。「今はそこまで目立っていない人」に対しても、潜在的に有能だと見なされると早めにつまずかせようとする働きが起こり得るのです。
このように、自分と同格または自分よりやや下だと思っていた相手を「未来の強敵」と認識すると、その評価を落とす行動を前倒しで行う可能性があります。これは現在だけを見た単純な比較とは異なり、時間の推移を踏まえた社会的比較です。こうした視点を取り入れると、同僚の過去からの伸び具合や潜在力がどれほど警戒の念を呼ぶかという、やや複雑な感情の動きを理解できるでしょう。
ストレスが社会的陰謀を招く
最後に、ストレスや対立が生むやりとりについて、オンラインなどの仮想的な仕事環境を対象に精査された調査結果があります[5]。情報通信技術を介して業務を行う場面では、顔を合わせる頻度が少なかったり、メッセージだけで指示を出し合ったりすることが多くなるため、相手の気持ちを汲み取る余裕が減りやすいと言われます。
ここでは、複数の組織でリモートワークを経験している人たちに、ストレスをどの程度認識しているかを問うと同時に、メンバー間のタスクに関するいざこざや、感情面のいがみ合いがどれだけ起こっているかを尋ねました。
タスクをめぐるもめ事は当初は業務上の手順や意見交換の食い違いから起こるものですが、それがやがて感情を傷つけ合う状態に移行しはしないかが注目点となりました。さらに、そのあと他者を引きずり下ろそうとする言動につながっているかどうかも測定されました。
分析を進めると、業務上の対立が先に生じると、それが人間関係の対立へと波及しやすく、最終的には相手を貶めるような言葉を投げたり、あえて情報を伝えなかったりして足をすくう行動が生じやすい、という経路が抽出されました。
加えて、ストレスを強く感じる人ほど、この連鎖的な流れの中で相手との衝突をいっそう深めやすいことが認められました。メッセージやオンライン会議だけでコミュニケーションを済ませると、微妙な空気が伝わりにくいため、ひとたび意見の食い違いがあると、誤解が雪だるま式に大きくなるのかもしれません。
考察として示されたのは、バーチャルな職場に特有の心理的負担が互いの不信を助長し、それが社会的陰謀と呼ばれる行為につながりやすい点です。タスクでの衝突が単なる意見交換にとどまらず、人間関係のいさかいへと拡大し、やがて悪い噂を流すなどの行動を誘発する状況があり得ます。オンラインで顔を合わせない間に、相手の意図を誤って解釈したり、わざと嫌がらせを仕掛けたりするといったリスクもあります。
組織の影で起きていること
ここまで、様々なかたちで人の心を揺さぶり、社会的陰謀へと導き得る要因を取り上げてきました。嫉妬はお互いを刺激するだけでなく、内面的な正当化を伴って陰の動きを後押ししやすいことがわかります。政治的な駆け引きに長けた人は、一部から尊敬を集める反面、別のグループからは邪魔者として見なされるおそれがあります。
成長が見込まれる同僚がいる場合、「これから先で抜かれてしまうのではないか」という思いが早期の妨害行動を引き起こすケースもあり、現在の上下だけで判断できない複雑さが見られます。
さらに、やりとりの多くをオンラインで済ませるようになると、相手の感情の動きを読み取る機会が限られ、ストレスと衝突が深まっていく中で隠れた対立が膨らむ場合もあると考えられます。
職場のマネジメントの観点からすれば、こうした状況を放置すると、互いに足を引っ張り合う空気が蔓延し、業務を回すうえでの信頼が失われかねません。誰かが突出すると嫉妬が生じ、競争関係が激化し、些細なトラブルが個人的な対立へと転じてしまう流れは、極力避けたいところです。
一方で、人間の心にはごく自然に競争意識や嫉妬心が湧く面もあります。どれほど優秀な能力を持っている人でも、他者からの牽制を浴びるかもしれず、突発的な波風が立つことは免れないかもしれません。
そうしたとき、適切に人間関係のズレを把握し、対立が深刻化するまえに何が起こっているかを見届ける土壌が欠かせないでしょう。職場の上長やチームのメンバーが、お互いの不満や疑念を抱え込まないよう気を配れるかどうかが大切になってきます。
競争や比較の要素をうまく扱わないと、業績面での成果とは裏腹に、水面下で信用が揺らぐ局面が生じるのではないでしょうか。
人間同士の微妙な心理のぶつかり合いは簡単には解消しにくいものでしょう。しかし、本コラムで取り上げられた手順や結果からは、集団や個人の感情がどのように結びついて人間関係を変容させるかが明らかになりました。
競争や嫉妬、不安やストレスに直面すると、うまく感情を消化できず、陰の方へ動いてしまう人がいることは否定できません。職場を運営していくうえでは、一人ひとりがそうした心理的要素を軽く考えないようにし、どこに火種が潜んでいるかを知る姿勢が求められると言えるでしょう。
脚注
[1] Yarivand, M. (2024). How envy drives social undermining: An analysis of employee behavior. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 9(7), 2005-2011.
[2] Duffy, M. K., Scott, K. L., Shaw, J. D., Tepper, B. J., and Aquino, K. (2012). A social context model of envy and social undermining. Academy of management Journal, 55(3), 643-666.
[3] Sun, S. (2022). Is political skill always beneficial? Why and when politically skilled employees become targets of coworker social undermining. Organization Science, 33(3), 1142-1162.
[4] Reh, S., Troster, C., and Van Quaquebeke, N. (2018). Keeping (future) rivals down: Temporal social comparison predicts coworker social undermining via future status threat and envy. Journal of Applied Psychology, 103(4), 399-415.
[5] Shahzad, M. U. (2024). Perceived stress as a stimulant of social undermining in the virtual workplace: A serial mediation model. International Journal of Management Research and Emerging Sciences, 14(1), 29-48.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。