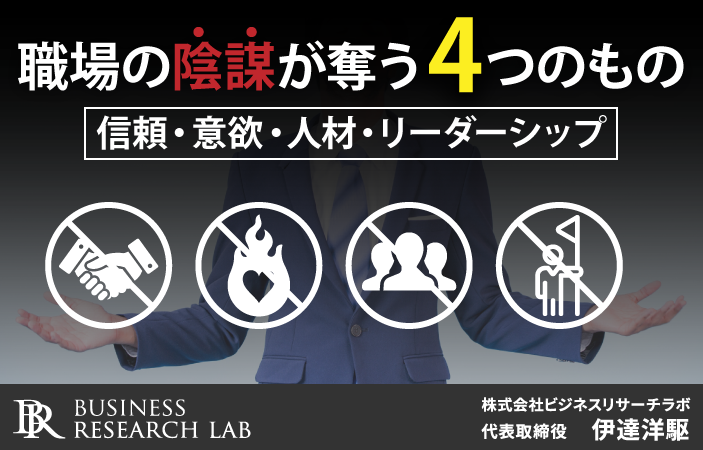2025年4月16日
職場の陰謀が奪う4つのもの:信頼・意欲・人材・リーダーシップ
組織の中で他者を揶揄し、陥れ、あるいは信用を損なおうとする言動が目立つようになると、人間関係の摩擦が深まるだけでなく、職務意欲やチームワークにも暗い影を落とします。こうした悪意を帯びた行為は、あからさまな暴言や攻撃だけでなく、さりげない無視や陰口などの形で進行するケースもあるため、当事者が気づきにくい厄介さがあります。
とりわけ「社会的陰謀」と呼ばれる行為は、周囲の人間関係や仕事の進捗を巧妙に妨げるものとして指摘されることがあり、被害を受けた側が精神的に疲弊したり、自分の職務に消極的になったりする状況が報告されています。
ある調査では、ホテルや教育機関、医療施設など、対人接触の多い現場で社会的陰謀が発生しやすいとされ、働く人々が受け取る心理的ダメージや仕事ぶりへのマイナスの帰結が分析されています。
ひとたびこうした仕打ちが日常化すると、相手を信用できなくなったり、職場全体の空気がギスギスしたりして、一部の優秀なメンバーほど傷つきやすくなります。それにもかかわらず、一見すると表に出にくい振る舞いが多いため、組織内部に深刻なわだかまりを生むまで見過ごされてしまうことがあるのです。
本コラムでは、社会的陰謀にまつわる複数の研究を取り上げながら、それらがどのように人々を疲弊させ、信頼を失わせ、ときに能力ある人材を追い詰め、リーダーが示そうとする正しい道すら弱めてしまうかを考えてみましょう。
社会的陰謀が疲弊と先延ばしを招く
まず取り上げたい事例として、高級ホテルのフロントライン従業員を対象に実施されたアンケート調査があります[1]。そこでは、フロントで接客にあたる人たちが周囲の嫌がらせを認知すると、感情的な疲れが進み、業務上の課題を後回しにしやすくなる様子が浮き彫りになりました。
韓国の一部ホテルで自己記入式の質問票を用い、300名以上のサンプルから統計解析を行った結果、当事者が社会的陰謀を痛感すると、それに伴う精神的負担が大きくなるという点が捉えられています。質問項目には、周囲が意図的に邪魔をしていると感じた頻度や、身内から冷たい扱いを受けたと自覚する度合いなどが含まれていました。
調査では、周囲からの陰謀が重なるほど従業員の感情的な消耗度合いが増す点が定量的に示された上で、その消耗が深刻になると仕事を先延ばしにする行動へつながるという流れが示されています。
精神が疲れていると作業に対する意欲が薄れ、自分の職分を後回しにしてしまうのです。そうした先延ばしが繰り返されると、集団全体のパフォーマンスが落ち込み、企業にとって望ましくない事態が生まれるでしょう。
加えて注目されたのは、感情的に落ち込んだ状態が媒介となり、陰謀をきっかけにして先延ばしが増幅されるというメカニズムです。直接妨害を受けた従業員が「なんとか気力を保とう」と踏ん張っていても、嫌がらせによる精神的ダメージが蓄積すると、いずれは行動面に良くない変化が生じやすくなるということです。
ここで興味深いのは、高い自己肯定感を抱いて働く人でも、陰謀の度合いが激しくなると疲労困ぱいに至り、後回しの行動が顔を出すリスクが見過ごせない点です。実務現場の声を反映する調査から、そのような負の連鎖がはっきりと確認されました。
一方、前向きな態度を維持することで、一部の従業員は多少の無礼行為をやり過ごせる傾向もあり、ポジティブな心理資本を高めるとマイナスの帰結が和らぐかもしれないという分析が加えられています。ただし、ここでは、社会的陰謀がダメージを大きくし、結果的に行動面の後ろ向きさを深める様子を認識しておくべきでしょう。
社会的陰謀が信頼を損ない行動を歪める
続いて注目するのは、同僚の陰謀がチームや組織への信頼感を大きく下げてしまう場面です。マレーシアの500名を超す従業員を対象に、二種類の質問紙を用いてデータを集めた報告があります[2]。
そこでは構造方程式モデリングという手法で、同僚による陰謀がどのように職務態度や行動にまでつながっているかが分析されました。結果として浮かんできたのは、ネガティブな行為にさらされると人は周囲を信用しにくくなり、その不信が仕事上の姿勢を否定的な方向へ導く、という構図です。
研究デザインとしては、従業員側のアンケートだけでなく、周囲の同僚からも評価を得る形をとり、複数の視点から関係性を検証しています。例えば、ある人が同僚から悪口や邪魔を繰り返し受けたと感じると、それまで築きあげてきた信用が急速に崩れ、それに伴い自主的なサポートや同僚への思いやりが低下することが確かめられています。ここで使われた項目には、例えば「周囲が協力してくれそうに思えなくなり、結果としてわざとやる気を失ったりするか」などという点が含まれていました。
信用喪失は、積極的に周囲を助ける姿勢のみならず、職場全体に対する建設的行動までも弱めるきっかけとなり得ます。その反面、同僚や組織に対して害をもたらす振る舞い、つまり他者に不便を強いるような行動をとる心情が高まることにもつながります。
陰謀という負荷がかかると、自発的に行動しようとするエネルギーが奪われるだけでなく、周囲に迷惑をかけるような振る舞いが起こりやすくなるという二重の問題が起こるわけです。
詳細に目を向けると、同僚への信頼を媒介にして仕事ぶりが変わる点が検出され、社会的陰謀が間接の形でも従業員の姿勢を歪ませる可能性が語られています。表面的には「嫌がらせを受けたから即座に反発した」という単純な話ではなく、「信頼されていないと感じるからこそ協力しようと思えなくなる」という心理が影に潜んでいるのです。
そこでは、言葉や態度で傷つけられた記憶が、同僚や組織全体への帰属意識を損ない、建設的な行動をとろうとする気持ちもそがれてしまうのでしょう。どの程度で人は不信に陥るのか、その境界線は個人差がありますが、組織内の衝突や無関心を深める火種になり得ます。
同じ報告では、チームや組織にとって前向きな貢献を誘発するために横の信頼が欠かせないという視点も示されています。しかし、そのような好ましい人間関係を築く上で、同僚の陰謀が深刻な妨げになるとの結論が導かれています。こうした帰結は、人間関係が密接な職場ほど、ちょっとした陰口や足の引っ張りでも長く尾を引く可能性を指摘しているように思えます。
社会的陰謀は信頼厚い有能者に最も害を及ぼす
次に見ておきたいのは、優秀で自己評価が高く、しかもマネジメントの仕組みを信頼している従業員ほど、上司からの陰謀に強く傷つくという報告です。アメリカやイギリスで働く人々を対象に医療関係者などからデータを収集し、上司の振る舞いが部下のストレスや退職への意向をどれほど左右するかを調べた研究があります[3]。
そこでは、高い能力を持ち、自信を持って仕事に向かう従業員こそ、上司のいびつな行為に直面すると「なぜ自分だけがこんな扱いを受けるのか」といっそう深刻なダメージを受けるのです。
評価尺度には、上司からどのくらい意図的な嫌がらせを受けたかを問う項目や、自己評価(自分が成功をつかめる人間だと思う度合いなど)を測る設問、さらに組織の管理全般への信頼感の度合いなどが含まれていました。
解析の結果、自分に対して肯定的な感覚をもつ人のほうが、上司の陰謀による精神的負荷を大きく感じ、その後に離職を考えたり、仕事場面でストレスを抱え込んだりしやすいと示されています。これは「自分は有能であるはずなのに、なぜこんな扱いをされるのか」といった混乱が一層の苦悩を呼ぶ、という自己認知理論の視点に合致しています。
さらにマネジメントへの信頼が高いほど、その落差が人を苦しめるという結果が出ています。全体的には良好な環境だと思っていたのに、直属の上司から陰謀を受けてしまうと「組織を信じていたのに裏切られた」と感じやすいのです。職場自体への肯定的なイメージが強い人ほど、裏切られた感覚が一気に増し、結果的に離職意向が高まります。
能力も意欲も十分な人材が、最悪のショックを味わってしまう場合がある点は見逃せません。組織としては有能で自信にあふれる人を歓迎するはずですが、その人たちが上司の悪意に遭遇すると、「こんなはずではない」という気持ちがより強く働くため、深い苦しみにつながるのです。
こうした結論は、いわゆる「中核的自己評価」という観点を軸に検討されており、自分の能力に誇りを持つ人ほど、否定的なフィードバックに脅かされてしまいます。このねじれは長期的な視点で見ると組織にとって痛手になるはずです。
社会的陰謀が倫理的リーダーシップの効果を弱める
最後に見ていくのは、倫理を大切にするリーダーがいても、同僚同士で妨害が行われていると従業員の満足感やエンゲージメントが失われる、という視点です。教育関連の職場を対象に、大勢の従業員から横断的にデータを集めて分析を進めた報告があります[4]。
そこでは「倫理に配慮したリーダーが示す模範」が組織に良い働きかけをしても、同僚同士の冷淡なやりとりや意地の悪い行為が見られると、そのポジティブな作用がかき消されてしまうという現象です。
具体的には、倫理を意識してメンバーと接するリーダーのもとでは、従業員が仕事への情緒的・認知的なやる気を持ちやすくなるという好ましい図式が想定されています。しかし、そこに横やりを入れる形で同僚からの嫌がらせがあると、人は周囲の信頼度や公正さを疑い始め、結果として満足度が伸びなくなります。どれだけ上に立つ人が正義を貫こうとしていても、隣にいる仲間の攻撃的な態度が強いと、従業員の心が冷めてしまうことが示されました。
研究の流れとしては、倫理観に支えられたリーダーの振る舞いが従業員のやる気や幸福感に良い成果をもたらすかを調べ、その間に同僚による妨害が入り込むことで一気に満足度が損なわれる仕組みを検討したものです。
統計分析では、大規模な質問票調査によって「リーダーの公正な言動→従業員の認知的・感情的エンゲージメント→仕事に対する満足」の道筋がある程度立証された反面、同僚間の陰謀の水準が高まると、せっかくのリーダーの好影響が薄れていくパターンが明らかになりました。
「行動的なエンゲージメント」については有意な媒介を確認できなかったという点もあり、すべてが単純にまとまるわけではないものの、同僚による妨害がコミュニティ感覚を弱める一因となっていると考えられます。
特にリーダー側が倫理面をしっかり重んじている環境であれば、なおのこと同僚同士の不和や足の引っ張りは際立つのかもしれません。思いがけないところで冷たい言葉をかけられたり、仕事の進捗を邪魔されたりすると、組織全体として掲げる公平・誠実な雰囲気に反する現実を目にするため、当事者のやる気が大いに削がれます。
このように、リーダー側の立派な姿勢があったとしても、周囲にいる仲間の態度次第で最終的な満足度が大きく下がってしまう点は、多くの職場で看過できない課題と言えるでしょう。
職場の信頼関係を再考する
ここまで、4つの異なる視点から社会的陰謀がもたらす弊害を見てきました。職場のマネジメントを考える際には、誰がどのような目にあい、それがどれほど深い疲弊や不信を生むかを冷静に見つめることが欠かせないでしょう。
一部の人は周囲からの妨害に直面して仕事を先延ばしにしてしまい、別の場面では信用を失った従業員が悪意にも近い行動に走る可能性があるかもしれません。また、自信や実力のある人こそ裏切りを強く感じ、離職を真剣に考える展開になることもあります。さらに、リーダーの高い倫理観が存在していても、同僚の陰謀が激しいと満足感や意欲がしぼんでしまうことも示唆されています。
こうした一連の知見が職場のマネジメントに与える意味合いは深いと言えます。従業員同士の小さな妨害が連鎖すると、人材が出しうる力が十分に発揮されず、ひとたび信頼の土台が崩れると、自発的な貢献も停滞する恐れがあるのです。
しかも有能さを備えた人ほど強い傷を負い、チームの要となるはずの人材が退職を考える状況が生じかねない点は看過できません。職場に広がる空気がどういうものであれ、仲間からの陰謀がはびこると大いに問題が生じる可能性があります。
適切な組織運営のためには、このような社会的陰謀の存在を軽んじない姿勢が求められます。そうした認識を育むこと自体が、今後のマネジメントにとって大事な一歩だと考えられます。
脚注
[1] Jung, H. S., and Yoon, H. H. (2022). The Effect of Social undermining on employees’ emotional exhaustion and procrastination behavior in deluxe hotels: Moderating role of positive psychological capital. Sustainability, 14(2), 931.
[2] Lin, D. O., and Angeline, T. (2019). The Effects of co-workers’ social undermining behaviour on employees’ work behaviours, Istanbul International Academic Conference Proceedings.
[3] Booth, J. E., Shantz, A., Glomb, T. M., Duffy, M. K., and Stillwell, E. E. (2020). Bad bosses and self‐verification: The moderating role of core self-evaluations with trust in workplace management. Human Resource Management, 59(2), 135-152.
[4] Ali, R., Shehzadi, M., and Mirza, S. (2023). Connecting the dots of ethical leadership and job satisfaction: Moderated mediation effect of co-worker undermining and employee engagement. Academic Journal of Social Sciences, 7(2), 107-125.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。