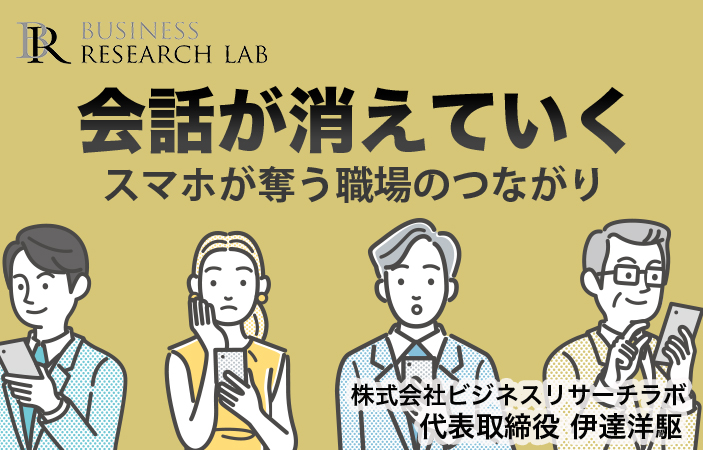2025年4月15日
会話が消えていく:スマホが奪う職場のつながり
職場や家庭の至る所でスマートフォンが使われるようになり、対話の最中でも画面に目を奪われる場面が少なくありません。二人以上が集まっているのに、一方は相手よりもスマートフォンを優先する行為を目撃すると、多くの人が気まずさや戸惑いを覚えます。
このような場面でみられる行動は「ファビング」と呼ばれます。ファビングは、対話の相手を置き去りにする形でスマートフォンを操作するため、コミュニケーションの質を損ない、人間関係に思わしくない帰結をもたらす可能性があります。
ファビングが目の前の人と向き合う姿勢を弱める点は、働く人々にとって見過ごせない問題です。これまでの研究では、ファビングを行う当事者の心理や、その周囲でのコミュニケーションの様子が取り上げられてきましたが、どのような要因がこの行動を引き起こすのか、まだ十分に整理されていない部分があります。
本コラムでは、職場の休憩時間や自宅での夫婦間のやりとりなど、さまざまな場面で観察されたファビングの生まれ方を見つめることで、どのような雰囲気や考え方がこの行動の裏に潜んでいるのかを考察していきます。
大事なのは、ファビングをただやみくもに否定するのではなく、その背景にある人々の感情や行動原理を把握することです。近年の研究は、人と交わるときにどの程度つながりを重視するのかや、自分のスマートフォン利用に対してどれほど肯定的かなどが、ファビングの発生率と結びついていることを明らかにしています。
中には、相手よりスマートフォンに没頭することで得られる心理的な安らぎや、オンライン情報の取りこぼしを恐れる気持ちなどが、ファビングの背後で作用している場合もあります。
休憩中のファビングが関係悪化を招く
職場の仲間と休憩を取るとき、日常的な雑談や情報交換は仲間意識を育むうえで欠かせないと感じる方が多いのではないでしょうか。ところが、その和やかなひとときで片方がスマートフォンに没頭し始めると、相手側は微妙な気まずさや取り残されたような思いをすることがあります。
実際に電気工事業や医療業界の人々へインタビューを行い、休憩時間中のファビングに焦点を当てた質的研究があります[1]。対象者は合計25名ほどで、それぞれの職場環境で日々どのようにスマートフォンを使い、休憩を過ごしているのかを聞き取ったところ、ファビング行動にまつわる生々しい経験や考え方が浮かび上がりました。
まず、大半の参加者が「同僚がスマートフォンに没頭していると会話が途切れる」「周りと交流しにくくなる」など、居心地の悪さを語っています。それと同時に、自らも同じことをしていると自覚しているケースが少なくありませんでした。会話の中断によって相互理解が浅くなり、休憩時間の和やかさが損なわれるという指摘もあったのです。
一方で、自分がスマートフォンを触る理由を尋ねると、多くはストレス発散や外部との連絡、あるいは気まずい沈黙を紛らわす手段として挙げられました。そのため、やめようと思っても、つい手に取ってしまうという声が聞かれます。
インタビューでは職種ごとに微妙な違いも見られました。電気工事の現場にいる人々は比較的若年層が多く、休憩中のスマートフォン使用頻度が高いと語られました。それに対して、医療現場で働く人々は対面でのやりとりを大事にする慣習があるためか、休憩中にスマートフォンを操作することに抵抗を覚える意見もいくつかありました。ただし、いずれの業種でも、ファビングが人間関係の円滑さを妨げる要因になり得ることに注目されていました。
周囲の人がファビングをするのを見ても、直接注意したり咎めたりすることはあまりありません。その理由を尋ねると、波風を立てたくない、余計な軋轢を生みたくないと考えるためだと言います。仮に何らかの不満があっても、相手の気分を害しそうで怖いというのです。ファビングは知らないうちに人々の間に壁を作り、自分自身のストレス対処行動とも絡み合っている姿が浮かび上がります。
もう一点特徴的なのは、休憩時間のファビングが同僚の結束感を希薄にしかねないと考えている電気工事業の参加者が多かった点です。孤立感を深めるきっかけとしてスマートフォン使用が意識されることがあり、休憩中なのに誰とも視線を合わせないまま時間を過ごす場面が生じやすいと言います。
一方、医療業界の参加者も同じ問題を挙げはするものの、職場での対面コミュニケーションが根強く求められるため、ファビングが生じにくい雰囲気が一部に存在しているとも語られていました。
全体として、スマートフォンに触れる行動が休憩中の気軽な対話を奪い、人間関係をぎくしゃくさせるおそれがあることが示されています。外から見れば些細な行為にも思えますが、当事者たちは「話す相手がいない寂しさ」や「会話をやめてしまった後ろめたさ」を感じています。
このように、休憩時間という本来のリラックスシーンが、思いがけず断絶を生む場面へ転じてしまうことは避けたいと考える人が多いという点が、この調査結果からうかがえます。
しかも、スマートフォンは個人的な空間へ逃げ込む手段として見なされます。やり取りに疲れを感じているときに、小さな画面を眺めることで一人だけの世界に没頭できるからです。そのため、居合わせた同僚たちと直接交流しなくとも、SNSや動画視聴に浸ることで息抜きになると捉える人が一定数いました。ファビングは対人コミュニケーションを薄れさせるばかりか、自ら能動的に人間関係を回避する結果にもつながりやすいことが示唆されます。
休憩中のファビングは、一見取るに足りない習慣にも見えますが、そこで抱えられる感情や思いは多様でした。続いては、職場でのファビングと仕事の熱意との関連を中心に論じていきます。
職場におけるファビングで仕事の熱意が低下
働く場でのやりとりは、業務そのものの効率だけでなく、人間関係の充実感を左右する点で欠かせない要素です。そのため、同僚や上司との対話中にスマートフォンへ意識を移すファビングは、当人たちの仕事への向き合い方にどのような影響をもたらすのかが注目されています。
インドネシアの若手から中堅までを含む従業員221名を対象とした調査では、ファビングの度合いと仕事への熱意(ワーク・エンゲージメント)を測り、その関連性を解析しました[2]。結果としては、ファビングが上昇すると仕事への意欲が下がる傾向が明白となりました。日々の業務に前向きさを維持するには、対人コミュニケーションの質が不可欠であると考える人が多い一方、その対話を断ち切るようなファビングがあるとモチベーションを落とす要因になるわけです。
研究では、対象者に対して「職場にいるとき、会話の途中でもスマートフォンを見てしまうか」「対面で話しているのに端末に注意を向ける場面が頻発していないか」といった質問を投げかけ、それと仕事のエネルギーや没頭感を結びつけて調べています。スマートフォンに気を取られる回数が多い従業員ほど、仕事中の活力や集中度が低くなることが確認されました。
調査においては、ファビングがただ面と向かっている相手との関係を損なうだけでなく、仕事そのものへの情熱にも悪い結果を与えることが浮き彫りになっています。例えば、同僚とアイデアを話し合う時間が少なくなり、自分の業務に意義を感じにくくなるような連鎖があり得ます。従業員が主体的に行動を起こそうとするときには、人間関係や職場での良好なやり取りが支えとなるからです。
ただし、職場であってもスマートフォンが役立つ場面があります。とはいえ、対話の最中に画面へ集中することによるデメリットが無視できないため、そのような利用法とファビングとの違いを整理する必要があるでしょう。
いずれにしても、同僚同士が互いを尊重し合う関係を築くには、意図せずとも行ってしまうファビングの存在を見過ごすわけにはいきません。次は、家庭内で起こるファビングが想像力や創造性にどのように関係しているのかを、調査結果から眺めていきましょう。
家庭のファビングが創造性を阻害する
家で過ごす時間は、職場と異なる心の安らぎをもたらし、それが仕事への意欲やアイデアにも結びつくことがあります。家庭内でのやりとりについて調べ、夫婦間のファビングがどのように仕事上の創造性に影響しうるのかを探究した調査があります[3]。
結果の中には面白い一面が含まれており、家庭でスマートフォンに意識が向いていると、パートナー同士の支援が十分に機能しにくくなる可能性が指摘されています。
研究の方法は、共働きカップル65組を対象に15日間のデイリーレポートを記録してもらうというものでした。夫婦それぞれが、1日の終わりに「今日はパートナーがどれだけ自分を助けてくれたと思うか」「家庭でスマートフォンを操作している様子を気にしたか」「自分の仕事に関する発想が広がったか」などを数値化して報告する形式です。そのデータをマルチレベル分析にかけることで、家庭内のサポートと創造性の関係がどのように日ごとに変動するかを追いかけました。
なぜ夫婦の間で生まれるサポートが創造性とつながるのでしょうか。家庭での相互理解や協力が本人の心理的な余裕や自己効力感を高め、それが仕事場面に波及して新しいアイデアを生む原動力になると考えられています。
しかし、このプロセスを大きく妨げるもののひとつとして、家庭内のファビングが浮かび上がりました。端末ばかり見ている姿勢が「相手に関心を払っていない」という空気を生み、互いにサポートを与え合う流れを滞らせると推測されます。
研究では、ファビングが強い日には、パートナーからのワーク・ファミリー支援を受け取った感覚が下がると報告されています。その結果、職場でのジョブ・クラフティング(仕事を自分に合った形へ再構築する試み)をする意欲が小さくなり、創造性発揮が抑えられるというメカニズムが見いだされました。
これは特に女性側が顕著であったとされており、家庭内での態度が仕事上でのアイデア創出に波及するケースもあるのではないでしょうか。互いに理解し合うことで新たな発想が育まれる状況は、家庭が心身をリフレッシュするための大切な場であることを物語っています。
もう一つの示唆としては、家庭におけるファビングの有無が、夫婦が互いの努力をどれほど実感できるかに影響する点です。家庭という比較的リラックスした環境でこそ得られるポジティブな気持ちが、スマートフォンによって遮断されるのではないかという懸念が挙げられています。パートナーが近くにいるのに画面ばかり見ていると、感謝やいたわりを感じ取りにくくなり、本人の仕事への挑戦心やアイデアづくりまで下がってしまいます。
家庭は職場とは異なる枠組みを持っていますが、そこを安らぎの場として活用できるかどうかは、仕事にもつながる可能性があります。ファビングはその循環を断ち切る要因として、意外なほど作用しうることが示されています。
肯定的態度がファビングを誘発する
ファビングをする人たちの心理には、多様な思惑が潜んでいます。その中でも注目されるのは、「ファビングに対してポジティブに考えるほど、この行動を取りやすくなる」という指摘です。
ある調査では、ランチ後に2人組を対象にアンケートを実施し、お互いのスマートフォン使用に対する認識や姿勢を評価してもらいました[4]。その結果、ファビングを肯定的に捉えるほど実際にファビングへ至りやすい様相が浮かび上がりました。
64組の参加者に対して、昼食後に「スマートフォンを使って相手をないがしろにすることをどう思うか」「周囲の人はファビングをどの程度許容すると思うか」「相手とのやりとりをどれほど大事にしているか」などの項目を尋ね、実際のファビング頻度をそれぞれに報告させました。
それらのデータを分析したところ、最も顕著だったのは「ファビングに前向きな姿勢を持つ人が、食事中に相手を無視するようなスマートフォン使用を行いがち」という点です。つまり、自分自身の態度が行動を強力に後押ししているのです。
一方で、周囲がファビングをどのくらい受け入れるかという規範意識や、相手との交流をどれほど価値あるものと感じているかといった要因は、ファビングの発生にそれほど強い関連を示しませんでした。ファビングを評価する自分の見方こそが行動を形づくる核心に位置づけられるため、周りの目よりも「自分は気にしないから別にいいじゃないか」という意識が優先されるのではないでしょうか。
この研究ではスマートフォンを共有して使う場面(画面を一緒に見るなど)は、会話そのものを深める可能性もあるとして区別されています。ファビングと異なるのは「同じコンテンツを共有する行為」だからです。
しかし、そこから個々で別々に端末を操作し始めると状況が一変し、相手の存在を脇に置いてしまうファビングへ発展する危険性があります。このように、「スマートフォンを触る行為」自体が一概に悪いわけではないものの、相手と向き合う姿勢を削ぎ落としてしまう使い方へ移行しやすい点に注意が必要です。
少人数の集まりでは、誰かが最初にスマートフォンを触り始めると、連鎖的に周囲の人も同じ行動をとりやすくなります。いわゆる伝染のような現象が起き、最終的に食事や会話をしているはずの場が、画面をのぞき込む人だらけになってしまいます。
そうした状況を嫌う人がいないわけではありませんが、否定的意見を言いにくい雰囲気のため、どこかでブレーキをかけるのが難しい場合があります。本人が「ファビングなんてたいしたことない」と思っていれば、なおさら自制に働きかける動機を得にくいのです。
ファビングを軽く見る態度を持つことが、行動のスイッチを押すきっかけとなりやすいという結論が得られたと言えます。最後に、ファビングを抑制するかどうかに関わるとされる「スマートフォン使用規範」について確認された研究を紹介します。
規制強化でファビングが減る
スマートフォンに関する意識や規範は、多くの人々の行動を左右する可能性があります。ある研究では、モバイルフォン使用に関して厳格なルールやマナー意識が強いほど、ファビングが少なくなることが報告されました[5]。ここでいう規範は、公的な罰則ではなく、周囲からの「対面で会話しているときは端末を触るべきではない」という暗黙の了解や雰囲気を指しています。
調査では、参加者に対して昼食時に実際にファビングをどれほど行ったかを尋ねると同時に、スマートフォン使用を控えることを当然だと考える度合い(MPN)を評価しました。そして、FOMO(見逃しを恐れる気持ち)や、POPC(常にオンラインでつながっている感覚)なども測定し、それらがファビングとどのように関わるかを検討しました。
その結果、MPNが強いほどファビングは減少し、逆にFOMOやPOPCが高い人ほどファビングを多く報告する様子が確認されました。
MPNが強い個人は「友人や知人と実際に顔を合わせているときにスマートフォンを見るのは良くない」という認識をはっきり持っており、それを理由に対面の相手を無視する行動を控えがちです。
一方、FOMOが強い人はオンラインでの出来事を逃したくない気持ちが先立ち、リアルの会話よりスマートフォンへ視線を落としやすくなります。POPCについては、いつでもメッセージが来る可能性を感じるため、目の前のやりとりより端末を優先する素地があります。
研究では、FOMOやPOPCとMPNの相互作用も調べられていますが、MPNの働きを緩和するほどの力は確認されませんでした。FOMOやPOPCがいくら高くても、本人がしっかりとしたマナー意識を抱いていればファビングに走る可能性は低くなるということです。
ただ、FOMOやPOPCがファビングそのものを後押しする面は裏づけられており、オンライン接続を強く意識する人ほど、対面相手をないがしろにするリスクは高まります。
年齢差の分析では年長者ほどファビングが少ないことも確認されました。性別による際立った違いはなかったものの、社会的マナーを強く意識するほどファビングをしにくいという線が見えてきます。
研究者の見立てによれば、社会的に「対面中にスマホを使うのは失礼」と感じる人たちが、無意識にでも行動を制御しているからではないかと推測されています。強いモバイル規範に従う人は、スマートフォンを見る前に「やめておこう」と思いとどまるのです。
脚注
[1] Martinsson, P., and Thomee, S. (2025). Co-worker phubbing: A qualitative exploration of smartphone use during work breaks. Scandinavian Journal of Psychology, 66(1), 158-173.
[2] Nanda, G. N., and Prihatsanti, U. (2023). Phubbing in workplace: The effect to employees’ work engagement. Proceedings of International Conference on Psychological Studies (ICPsyche), 4(1), 308-315.
[3] Wang, S., Rofcanin, Y., Las Heras, M., and Yalabik, Z. (2024). The more you connect, the less you connect: An examination of the role of phubbing at home and job crafting in the crossover and spillover effects of work?family spousal support on employee creativity. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 97(3), 1100-1128.
[4] Buttner, C. M., Gloster, A. T., and Greifeneder, R. (2022). Your phone ruins our lunch: Attitudes, norms, and valuing the interaction predict phone use and phubbing in dyadic social interactions. Mobile Media & Communication, 10(3), 387-405.
[5] Schneider, F. M., and Hitzfeld, S. (2021). I ought to put down that phone but I phub nevertheless: Examining the predictors of phubbing behavior. Social Science Computer Review, 39(6), 1075-1088.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。