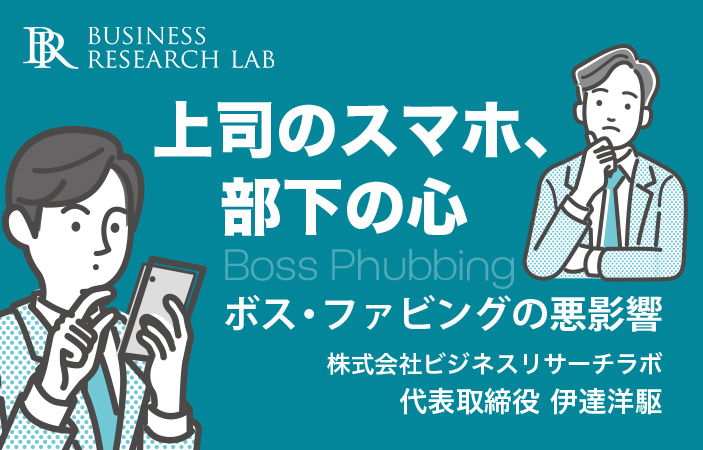2025年4月14日
上司のスマホ、部下の心:ボス・ファビングの悪影響
スマートフォンの普及によって仕事の進め方やコミュニケーションの様式が変化しています。いつでもどこでも連絡が取りやすい一方で、対面でのやり取りが分断されるケースも増えています。
そのような状況の中で注目を集めているのが「ファビング」という概念です。これは、本来なら目の前にいる相手と向き合うべき場面で、スマートフォンを操作してしまい、相手をないがしろにしているように感じさせる行動を指します。
この行動が職場で上司と部下の間で発生すると、部下にとっては心理的に不安になり、さまざまな否定的感情をもたらす要因になるという議論がいくつかの研究から報告されています。
日々の職務の中で部下が必要としているのは、話を聞いてもらえる安心感や敬意の共有であり、仮にその真逆の光景が繰り返されると、職務における思い入れが減少したり、ストレスが増大したりする可能性があります。
こうした「上司によるファビング(ボス・ファビング)」という行動は、上司が部下とのやりとりの最中にスマートフォンへ意識を奪われることにより、部下が自分の存在を軽視されているかのように感じる状況を生み出します。
その結果、部下が職場で孤独感を味わったり、自分への評価が低いのではないかと疑念を抱いたりすることもあり得ます。これらの懸念は学術研究でも指摘されており、実証的なデータに基づいて考察が進められてきました。
本コラムでは、ボス・ファビングが部下にどのような心理的プロセスを引き起こし、どのような形で仕事への向き合い方に影響をもたらすかを、多角的な視点から読み解きます。
ボス・ファビングが部下の疎外や離脱を促す
まず視点をあてるのは、ボス・ファビングによって部下が経験する疎外感や心理的離脱行動についてです。
ある研究では、職場の従業員302名を対象として、上司のスマートフォン利用が会話中にどれほど多いかを問うアンケート調査を実施し、部下が抱える感情面や行動面の変化を測定しました[1]。このとき、調査の回答者には「会議の途中で上司が端末を触っていることに気づく頻度」などが問われ、回答結果と併せて心理的状態を関連づけました。
研究はストレスと感情の相互作用に着目し、ボス・ファビングが繰り返されると部下が自分の意見が軽んじられていると感じ、疑心暗鬼になることを捉えました。個々の従業員が、こうした不満や不安を誰にも打ち明けられないまま内面に抱え込むと、職場に対して気持ちが離れる「心理的離脱行動」へとつながる可能性が高まります。
調査結果によると、上司がコミュニケーションの最中にスマートフォンをいじる頻度が高いほど、部下の疎外感スコアや仕事に興味を失う指標が上昇していました。
加えて、研究では「対人感受性」に注目しています。これは、周囲からの評価や言動に敏感になりやすい特性を指し、同僚の目線や上司の何気ない行動に大きく反応してしまう性質を表しています。
対人感受性が高い人ほど、自分が置かれている環境を否定的に捉えやすいため、上司がスマートフォンを操作しているのを見かけると強い不快感を抱き、疎外感から逃れるために意図的に職務への集中を弱めてしまいます。そして、その状態が長引くと、最終的には心身の健康を損なう方向へ傾きます。
上司のスマートフォン使用による「話を聞いてくれない」感覚は、部下にとっては職場への信頼を後退させる発火点となります。とりわけ対面で指示を受ける場面で、上司が画面に集中していると、「いま、この場ですら自分は重要な存在ではないのか」という思いが生じやすいのです。そうした悪循環が続けば、仕事への意欲を次第に失う部下が増え、人間関係が気まずくなる契機になります。
ボス・ファビングが孤立と怠業を呼ぶ
次に、ボス・ファビングの存在が職場での孤立感や「サイバーローフィング」と呼ばれる現象を加速させるという研究を紹介します。インドの267名の従業員を対象に実施された分析で、上司のファビング行動と従業員が仕事中に私的なオンライン活動へ逸れてしまう行動との間に有意な関連があると報告されています[2]。
調査では、ボス・ファビングの頻度をアンケートで測定したうえで、対象者の「職場での排斥感」を数値化しています。会話をしているのに上司が画面を見ている、ミーティング中に急にメッセージ確認をしている、といった報告が高いほど、部下が孤立感を訴える割合も上昇するという結果が得られました。
孤立感が高まると、従業員は内面的に落ち着きを失い、仕事への注意力が散漫になる様子が見られます。仕事への集中が低下した従業員はサイバーローフィング、すなわち、職務に直接関係のないインターネット利用やSNS閲覧に時間を使うケースが増えるのです。
この研究では「心理的デタッチメント」と呼ばれる要素も測定されています。ここでいう心理的デタッチメントとは、仕事上のストレスや不快感をオフタイムにうまく切り離し、別の活動に目を向けてリフレッシュするような力を表します。
サイバーローフィングに陥る人は、仕事から頭を切り替えられずに職場で抱いた負の感情を抱え込む一方、その対処策として業務時間内にネットに逃避するというパターンを取りがちになります。
データ分析の結果からは、心理的デタッチメントの能力が低い人ほど、孤立感を発端にサイバーローフィングへ流れ込みやすい可能性があります。別の言い方をすると、ボス・ファビングによる孤立感が生じても、オフタイムにきちんと気分転換できる人は、ネットへの逃避に陥りにくいという解釈があり得ます。
職場でのやり取りが円滑にいかず、上司が部下に目を向けない場面がしばしば重なると、当事者たちは互いの存在を距離のあるものとして認識してしまいます。その結果、正式なミーティングの場でも共有や意見交換がうまく進まず、一部の従業員は仕事とは無関係のオンライン活動をはさむ怠業状態を生み出してしまうということです。こうした状態が放置されると、作業効率が下がるだけでなく、チーム全体の雰囲気がギクシャクする恐れもあります。
承認欲求が高い部下はパフォーマンスが低下
続いては、ボス・ファビングによるマイナス要因が「社会的承認欲求」の高い部下にはどのように影響するかを扱った研究を取り上げます[3]。上司のファビング行動が部下の仕事成績を弱める要因になると想定され、特に周囲からの賞賛を望む度合いが大きい場合、その打撃がいっそう顕在化することが調べられました。
従業員の「仕事パフォーマンス」をアンケートで測定し、その上で上司が普段どれほどスマートフォンに気を取られているかを部下側から報告してもらっています。
あわせて「社会的承認欲求」の強さも数値化されました。社会的承認欲求は、自分が評価されたい、認められたいという思いを測る指標であり、人によっては自尊感情の多くを他者からのフィードバックに依存することもあります。
調査対象者を細かく区分すると、承認欲求が大きい人ほど、上司から目を向けてもらえないと感じたときのストレスが高まるという結果が判明しています。
ここでの分析では、ファビング行動が部下に生じさせる「社会的距離」や「上司への信頼の低下」が成績を下げる間に入る要素になると説明されています。上司が部下をまったく顧みず、スマートフォンへ気を奪われているように映った場合、承認欲求の高い部下は深く傷つき、「仕事に打ち込んでも評価してもらえないかもしれない」と考えます。
そして、作業への取り組みが消極化したり、メンタル面に負担がかかることで仕事の質が低下したりするという流れがあります。社会的距離が広がることで信頼感が弱まり、仕事に対する前向きな姿勢が後退すると、部下が本来発揮できるはずの能力が十分に生かされなくなります。
研究の中では、多数の項目を用いた質問票で部下の心理状態を測定したうえで、パフォーマンスの客観指標との関連を確かめる試みも行われています。上司が頻繁にスマートフォンを操作していると感じるほど部下のパフォーマンスが下がり、そのマイナス度合いは承認欲求が強い人に顕著でした。
これは「人に認められたい」と強く思う従業員ほど、上司の冷淡にみえる振る舞いに敏感であり、行動面や結果面にもその影が投げかけられることを示唆する例といえます。
ボス・ファビングで部下の熱意が下がる
部下の仕事への熱意やエンゲージメントがいかにして下がっていくかを中心に検討してみましょう。ボス・ファビングは、従業員の心理的条件(意味のある仕事かどうか、自分が行動できる心的リソースが残されているかどうかなど)を経由してエンゲージメントが損なわれるのか、その可能性を検証しています[4]。
研究デザインとしては、アンケート調査と実験的手法が組み合わされています。アンケート調査では、従業員数百名に対し、上司のスマートフォン利用頻度と自分の仕事観(仕事を価値ある活動と感じる度合いや、上司に対する信頼感)、さらにエンゲージメントを数値化してもらいました。
その結果、上司のファビング頻度が高いほど上司への信頼が低くなり、心理的に「この仕事は自分の成長にとって有意義だ」という認識が下がっているパターンが見いだされました。そうした心理状態の変化は、エンゲージメントの低下に結びつき、最終的には職務への取り組み意識が弱まる形で表面化していました。
対して、実験パートでは、被験者を複数のグループに分け、一方のグループには「上司が会話中にしきりに端末を操作している映像」を見せ、もう一方には「上司が部下の話に集中している映像」を提示しました。その後、被験者には上司への信頼感や仕事の重要性評価を尋ねました。
その比較から、ファビング映像を見たグループは、上司をあまり信用できないという傾向を回答しやすく、結果的に「自分の仕事は意義あるものだ」と思いにくくなる結果が得られました。こうした知見は、ボス・ファビングが部下のエンゲージメントを下げるメカニズムを裏付ける材料となります。
このように、上司が部下と向き合うべきタイミングでスマートフォンに意識を奪われていると、部下は「自分の仕事は上司から軽んじられているのかもしれない」と感じます。そのような認識が高まると業務への熱意がそがれ、ひいては生産性に悪い余波が出ます。信頼の低下が起点となり、心理的な下支えが弱まることで仕事へのエネルギーが減退するのは、どのような職種や組織であっても起こりうることでしょう。
ボス・ファビングで信頼が損失し、意欲も下落
ボス・ファビングが部下の信頼を失墜させ、仕事への意欲を損ねる流れを整理した系統的レビューも存在します[5]。2013年から約10年間に出版された複数の英文論文を集約し、共通点や相違点を掘り下げたうえで、上司がスマホを利用して部下を無視する場面がさまざまな領域に波及しうることを報告しています。
レビューでは、データを抽出した論文のほとんどがアンケート手法を用いており、職場で上司が端末を触っている姿が部下の信頼や満足度、仕事への姿勢にどのように結びついているかを検討していることを紹介しています。
そのうちの一部では、面白いほど一致したパターンとして、上司のファビングを強く感じているグループが部下のパフォーマンス評価やエンゲージメントの数値で低い値となることが示されています。
また、レビューで言及された研究のいくつかは、ファビングに直面した従業員がストレスや虚無感を覚え、その感情を周囲の同僚へ伝えにくい状況が重なることで気力を失う状態を引き起こすと論じています。
スマートフォンを介したコミュニケーションが進む時代でも、直接顔を合わせた会話で重視されるのは目線のやり取りや相槌などの非言語的サインとされています。そうしたサインが遮断されると、部下は「自分の存在を尊重してくれない」という解釈を抱きやすくなり、上司への信頼感を失っていきます。
その結果、意欲面がしぼんでいき、新しい提案をする気になれない、職務の効率が落ちる、といったマイナス面が見過ごせなくなります。
レビューの結論では、今後の研究課題として、スマホが業務上のコミュニケーションツールとして欠かせない一方で、ファビングによる摩擦をどのように回避するかという議論が挙げられています。
心理的資本の損失でパフォーマンスが悪化
最後に、ボス・ファビングが従業員の心理的資本を削ぎ、成果に関わる働きが低下するというモデルについて述べた研究を確認します[6]。心理的資本とは、希望や楽観、自信(自己効力感)などを含む前向きな状態を指す概念で、こうした資源が豊富であれば仕事の困難に直面しても踏ん張れます。一方、上司の不適切な振る舞いが原因で心理的資本が枯渇すると、業務パフォーマンスそのものが弱まる恐れがあります。
研究では、中国の従業員215名を調査対象に、まず上司のスマホに意識を奪われている場面をどれほど頻繁に目撃するかを数値化し、その後、部下が自分の心理的資本をどの程度保っているかを問いました。
さらに、ボス・ファビングの程度と、最終的なパフォーマンス評価を結びつけて統計解析を行ったところ、両者のあいだに負の相関が見出されました。メカニズムとしては、スマホにのめりこむ上司の姿が部下の期待を裏切り、やる気をそぐ行動として認識されることで心理的資本が徐々に失われ、結果、仕事の成果が落ち込むという流れが想定されています。
加えて、ワーク・ファミリー・エンリッチメントという概念も検討され、家庭生活や個人的な支えがどれほど対抗手段になりうるかが分析されています。家族やプライベートでの活動によって精神的に潤う機会が多いほど、ボス・ファビングの負荷を軽減できるかもしれないという見通しがありました。
しかし、家族からの支援が多い人でもボス・ファビングによって心理的資本が損なわれるパターンは残り、完全な防波堤になるわけではありませんでした。これに関しては、ボス・ファビングというものが職場内での人間関係に直結するため、いくら家庭側で支えられていても、当事者が受ける失望感がそれほど簡単には消えないという解釈が可能です。
上司が部下とのやり取り中にスマートフォンに意識を向ける行動は、その部下の肯定的なエネルギーを弱め、職務の成果を下げる要因として作用し得るのです。このように、心理的資本がじわじわと失われてしまうと、長いスパンで生産性やモチベーションにダメージを受けるでしょう。
脚注
[1] Yao, S., and Nie, T. (2023). Boss, can’t you hear me? The impact mechanism of supervisor phone snubbing (phubbing) on employee psychological withdrawal behavior. Healthcare, 11(24), 3167.
[2] Saxena, A., & Srivastava, S. (2023). Is cyberloafing an outcome of supervisor phubbing: Examining the roles of workplace ostracism and psychological detachment. International Journal of Business Communication. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/23294884231172194
[3] Xu, T., Wang, T., and Duan, J. (2022). Leader phubbing and employee job performance: The effect of need for social approval. Psychology Research and Behavior Management, 15, 2303-2314.
[4] Roberts, J. A., and David, M. E. (2017). Put down your phone and listen to me: How boss phubbing undermines the psychological conditions necessary for employee engagement. Computers in Human Behavior, 75, 206-217.
[5] Yuda, I. H., and Suyono, J. (2024). Systematic literature review of Boss Phubbing from 2013?2023. Jurnal Syntax Transformation, 5(2), 406-415.
[6] Zhen, Y., and Wen, C. Y. (2022, November). The Impact of Boss Phubbing on Employees’ Job Performance: A Mediation Model with Moderation. In 2022 7th International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE) (pp. 384-387). IEEE.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。