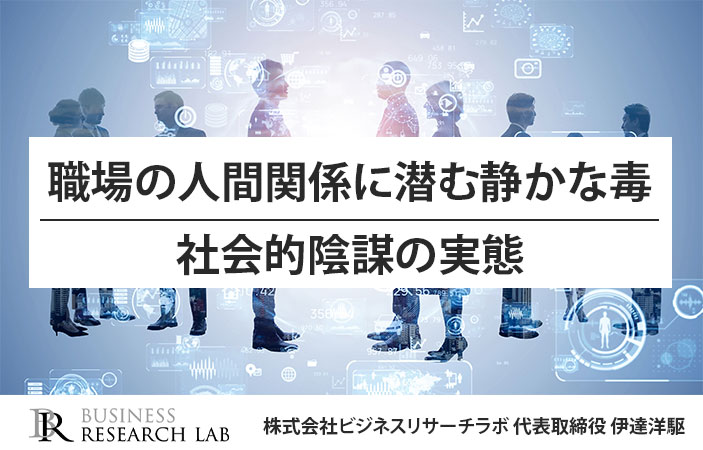2025年4月11日
職場の人間関係に潜む静かな毒:社会的陰謀の実態
人間関係が豊かだとされる職場でも、人を陥れようとする行為が密かに進行している場合があります。仕事そのものには熱意を持っていても、周囲の同僚や上司からささやかな悪意を向けられると、自己防衛のために感情を閉ざしてしまうこともあるかもしれません。
そうした微妙な攻撃は、ときに表立って見えにくいのが特徴です。あからさまないじめではなく、うわさを流したり、仲間外れの空気を醸成したりといった巧妙な手法が取られることがあるからです。それは行動の背後にある意図が見えにくいため、被害を受ける側もどのように対応すれば良いか悩むことになります。心身の不調やモチベーションの低下へつながりやすいため、組織で働く個人にとって深刻な問題といえるでしょう。
こうした隠れた攻撃性に注目が集まる背景には、人間の心理が組織の活力や創造性に関係するという考え方が広がってきたことがあるのかもしれません。仕事の成果を高めるためには、人間関係がスムーズに進むことが望まれますが、実際には邪魔をする動きも少なからず存在します。
相手の評判をこっそり下げようとしたり、仕事上の助け合いをわざと行わず、個人の達成を損ねようとしたりするなど、表向きにはわかりにくいさまざまな行為が見受けられます。
ここでは、そうした行為を「社会的陰謀」と呼び、その広がりや特徴について、研究で得られた知見をたどりながら考えてみましょう。人間関係の闇を掘り下げることで、社会的陰謀がどのように発生し、広がり、どんな流れで職場を揺るがすのかを読み解いていきます。
社会的陰謀の研究は拡大し続ける
社会的陰謀は、職場や組織において他者の成功や評判を故意に妨げる行為を指します。以前は、あからさまないじめや口汚い暴言などが中心的な研究対象とされてきましたが、徐々に「人間同士の水面下での妨害」に焦点を当てた研究が増えてきました。
ある大規模な文献調査によれば、2000年代の初期には研究数が限られていたものの、その後は急増し、近年は学会誌でも頻繁に発表されるようになっています[1]。
この急拡大の背景には、経営学や組織行動論だけでなく、社会心理学の枠組みを参照する論文が増えていることが挙げられます。ひとくちに社会的陰謀といっても、組織構造や職場の人間関係、文化的要因など、さまざまな視点で捉えられるようになっているわけです。さらに、調査手法もアンケートを用いた定量的研究だけでなく、長期的な追跡や質的なインタビューを取り入れる試みがなされています。
過去の研究をまとめたレビューによると、多くの論文が「社会的陰謀は他者の仕事の進行をさりげなく遅らせたり、誤情報を与えたり、陰口を広めたりする行為を含む」と論じています。
調査では、自分が受けたこうした行為を報告する形式がよく用いられ、その頻度や被害の度合いが分析の軸となっています。一方で、加害を行う動機や背景を明らかにしようとする研究も存在し、職場内で生じる不和や競争心理などが複雑に絡んでいることがうかがえます。
研究の射程は広く、個人レベルの心理特性に関する分析や、組織文化全体からの視点まで扱われるため、複数の学問領域が交差する形となっています。ある論考では、社会的陰謀がどのように発生するかを説明するための概念的フレームワークが提示されており、人間同士の比較意識が引き金となっている可能性が示されています。
上司の評価を奪い合う場面でネガティブな感情が強まり、そのはけ口として陰謀が働くという仕組みを想定しているのです。このように、背景には組織内の権力構造やコミュニケーションの習慣、個人の性格特性など、多くの要素が同居していると考えられます。
社会的陰謀は職場攻撃性の一形態
社会的陰謀は、いわゆる職場での攻撃性の一つとみなされています。職場攻撃性という概念自体は、上司による暴言から無礼な対応まで幅広く扱われてきましたが、社会的陰謀の場合はあからさまに相手を傷つけるというより、陰での情報操作や人間関係をゆがめるといった特徴があります。
理論的には、暴言や物理的攻撃のような強度の高い行為と必ずしも区別できるわけではないのですが、測定項目を見ると、対象者に気づかれないレベルでの加害行為に焦点が当てられています。
ある論文では、パワハラやいじめ、無礼な言動など職場での加害行為が多数報告されており、それらを分類するための検討が行われています[2]。その報告によると、行動の強度、加害者の地位、意図の有無などをもとに区分は試みられてきましたが、実際の測定ではそれらを厳密に見分けることが難しいものです。例えば、業務連絡で嘘を伝える行為と、直接怒鳴り散らす行為とでは様子が異なるはずですが、被害感を抱く側が感じる苦痛には必ずしも大きな違いがないことがあります。
このように概念の整理が難航する一方で、社会的陰謀ならではの性質として、相手の評判を落とし、仕事上の信頼を失わせる点が繰り返し言及されています。例えば、同僚の客先対応に粗を探して否定的なうわさを流す、チームでの意見交換から特定の人だけ排除するなど、どこか冷たさや陰湿さを感じさせる事例が報告されています。暴言や身体的接触といったわかりやすい攻撃がなくても、相手を精神的に追い込むことがありうるのです。
職場攻撃性という大きなくくりの中で、社会的陰謀は、最初は軽度に見えても、長期にわたって続くほどに苦痛を与える可能性があると論じられています。攻撃として認識しにくいからこそ、被害を受ける側にとって「自分が過剰反応しているだけではないか」と疑心暗鬼を呼びやすく、そのまま放置されるケースもあるとされます。
これは仕事への熱意や健康状態を揺るがしかねず、個人だけでなく組織全体に波紋が広がることが少なくありません。研究の統合を試みたメタ分析では、無礼さやいじめが仕事の満足感や離職意図と強く結びついている傾向が示されていますが、社会的陰謀も同様に組織生活を揺るがす要因になりうると考えられます。
社会的陰謀は連鎖し加害を生む
社会的陰謀の恐ろしさの一つとして、「被害に遭った側が新たに加害側に回る」という連鎖が指摘されています。ある銀行の従業員を対象とした研究では、他人から妨害されて精神的に消耗した人が、後日、自分も同僚に対して似たような陰謀行為に手を染める事例が認められました[3]。
この研究は、被害経験による対人関係への不公正感や、自己コントロール資源の枯渇が重要だと説明しています。人は周囲から攻撃を受けると、公正感が崩れ、加えて強いストレスによって理性的な判断がしにくくなります。
それが高じると「やり返してもかまわない」という心理的ハードルが低くなるというのです。そのような心の状態は道徳的な観点を忘れやすくし、結果的に自分も加害行動に移る可能性を高めるのだと考えられています。
さらに、この過程には個人の道徳観も関わっているとされています。道徳観を強く意識する人は、不公正を受けても相手と同じような攻撃行動に及びにくいことが確認されています。一方、職場に対する公正な環境への期待が裏切られると、「正しく振る舞うだけでは馬鹿をみる」と感じるようになり、倫理観の自動ブレーキが働きにくくなります。
こうした連鎖は厄介なものです。自分が受けた不当な扱いを糸口にして、別の相手を攻撃してしまうようになると、人間関係はさらに悪循環へ陥ります。周囲で見ている人も疑心暗鬼になり、職場全体の人間関係がギクシャクすることがあるため、当事者だけの問題にはとどまらなくなります。その悪循環が長く続くと、集団全体の協調や安心感が損なわれ、ひそやかにライバル意識をかき立てあうような風土が生まれるかもしれません。
この連鎖に関する調査では、質問票を複数の時点で配布するという手法が用いられ、時間の経過によって被害者がどのように心理状態を変化させ、それが行動に結びつくのかを確認する形がとられています。自己コントロールを支える心理的資源が弱まるタイミングや、公正感の喪失と攻撃行動の間を結ぶプロセスを分析することで、職場の衝突はどのように再生産されていくのかを掘り下げています。そこからうかがえるのは、被害者が翌日に加害者へ転じるという、否定的な連鎖が生じうる現実です。
社会的陰謀が創造性を奪う
社会的陰謀には、ただ個人を傷つけるだけでなく、組織内のイノベーションや創造的思考を奪ってしまう危険があります。広告代理店で働く従業員を調査した研究では、社会的陰謀を強く感じる職場ほど、一人ひとりが新しいアイデアを生み出す力が阻害されるという結果が得られました[4]。
その研究で詳しく取り上げられているメカニズムとして、周囲への不信感と知識を隠す行動が挙げられています。社会的陰謀にさらされると、自分のノウハウや斬新なアイデアを開示することに疑念を持つため、発想や情報が共有されにくくなります。そうなると、互いに刺激し合ったり協力したりしながら新しいアイデアを形にしていくような職場環境が望めなくなり、最終的にチーム全体の想像力や意欲が低下していきます。
調査では時間差のある自己記入式アンケートが活用され、まず社会的陰謀を被っていると感じるかどうか、次に周囲への不信が高まっているか、さらに知識を隠す行動に及ぶことがあるか、という順序で質問がなされました。分析の結果、社会的陰謀が先に存在し、それが対人不信につながり、そこから知識を隠すという習慣が生まれることが見えてきました。
知識を隠す姿勢は、仕事に必要なやりとりだけでなく、自由な発想やひらめきを共有する場面にも影響を及ぼす可能性があります。対人不信に陥った状態では、ひらめきを披露することの心的ハードルが高くなってしまうからです。
周りの反応を怖れて意見を飲み込む場面が増えれば、組織の創造力はしぼんでいきます。一度そのような心理状態に陥ると、日頃のコミュニケーションがめっきり減り、組織の革新を支えるはずの発想の火種も失われます。
社会的陰謀が組織愛着を歪める
社会的陰謀は、職場に対する愛着感にも作用します。ある研究では、感情面の愛着、義務感としての愛着、損得に基づく愛着の三つの次元を測定し、社会的陰謀の被害がそれぞれにどう関係するかを探っています[5]。結果は興味深いもので、感情面と義務感の愛着は下がる一方、経済面での損得勘定にもとづく愛着は高まる傾向が見受けられました。
組織になんとなく好感を抱いていたり、「お世話になっているから責任を感じる」という状態だと、社会的陰謀に直面すると愛着が失われていきます。しかし、同時に「ここを辞めると収入面などで困る」といった計算が強まって、しがみつくかたちで組織にとどまることがあります。一口に愛着といっても、その根底にある思考や感情によって方向は変わってきます。
その研究では個人の愛着スタイルにも着目しています。人は対人関係に不安を感じやすいタイプや、回避するタイプなど、もともとの愛着スタイルが異なります。職場においても同じように、不安型の人は人間関係のちょっとした変化に敏感になる一方、回避型の人は深く踏み込んだコミュニケーションを敬遠しがちです。
そして社会的陰謀が発生したとき、不安型の人はなんとか関係を維持したい気持ちが強く、意外にも感情面の愛着が残りやすいとされています。回避型の人は、そもそも組織に対して深い情緒的結びつきを抱きにくいため、義務感の愛着も低下しやすくなります。
これらの結果からわかるのは、社会的陰謀にさらされると組織と個人のつながり方がゆがむことがある点です。人によっては、職場を心から敬愛する気持ちを失いつつも「ここを去るわけにはいかない」といった矛盾を抱えたまま働くかもしれません。そのような状態だと、どこかしら息苦しい思いを抱えながらの仕事となり、心の健康や生産性に影を落とす懸念があります。
社会的陰謀が組織に及ぼす影響
職場のマネジメントを考えるうえで、社会的陰謀という存在が持つ意味は正面から考慮する必要があるでしょう。周囲からの悪意のような行為が目立ち始めると、人は自分自身を守りたい気持ちから不信感を高め、他者との関わりを減らしていきます。そして、その余波として創造的な発想が生まれにくくなり、組織に対する愛着が損なわれ、残留の動機が経済的な打算に偏るケースも出てくるのです。
職場で相手を妨害する行為が続くと、加害の連鎖まで引き起こされる可能性が否定できません。かつて被害を受けた従業員が、自分も同じように他者を妨害してしまう流れが生まれると、人間関係全体の雰囲気が悪化するかもしれません。
気付かぬうちに「誰もがいがみ合い、疑い合う」風土が根を張っていくと、働く人々が落ち着いて力を発揮できなくなります。それは心身の健康はもちろん、業務の成果にも関わる問題となり得ます。このように、社会的陰謀の知見は、職場環境における人間関係の奥深さを考えるうえで欠かせない視点をもたらしています。
脚注
[1] Haider, B., Khizar, H. M. U., Kallmuenzer, A., and Hilal, O. A. (2024). Unraveling social undermining at the workplace: A systematic review of past achievements and future promises. Strategic Change, 33(1), 45-67.
[2] Hershcovis, M. S. (2011). “Incivility, social undermining, bullying… oh my!”: A call to reconcile constructs within workplace aggression research. Journal of Organizational Behavior, 32(3), 499-519.
[3] Lee, K. Y., Kim, E., Bhave, D. P., and Duffy, M. K. (2016). Why victims of undermining at work become perpetrators of undermining: An integrative model. Journal of Applied Psychology, 101(6), 915-924.
[4] Khan, M. A., Malik, O. F., and Shahzad, A. (2022). Social undermining and employee creativity: The mediating role of interpersonal distrust and knowledge hiding. Behavioral Sciences, 12(2), 25.
[5] Jing, E. L., Gellatly, I. R., Feeney, J. R., and Inness, M. (2023). Social undermining and three forms of organizational commitment: The moderating role of employees’ attachment style. Journal of Personnel Psychology, 22(1), 31-42.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。