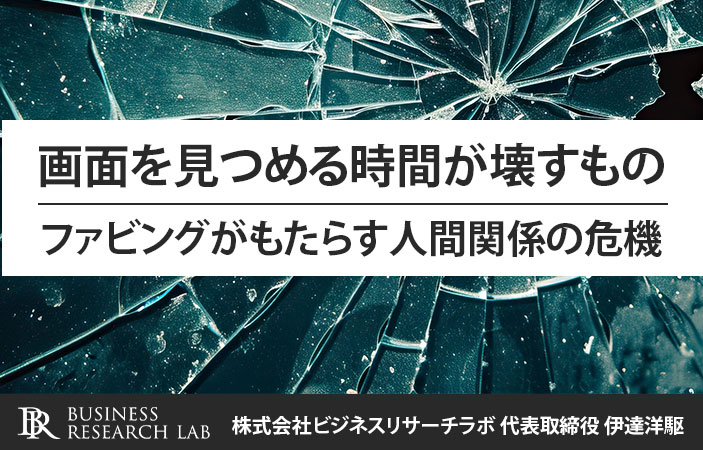2025年4月9日
画面を見つめる時間が壊すもの:ファビングがもたらす人間関係の危機
人と会話をしている最中、そちらには目もくれずにスマートフォンを操作してしまう行為を、「ファビング」と呼びます。日常生活や職場で、誰かが隣にいるにもかかわらず画面を見つめ続けてしまう場面は珍しくありません。
離れた相手との連絡が容易になった反面、いま目の前にいる人との交流がおろそかになるケースが増えています。こうした行動は、ただ礼儀を欠くという話ではなく、人間同士のやりとりが本来もたらす作用を弱める要因として警戒されるようにもなっています。
ある研究ではファビングを、周囲への冷淡さや対人距離の拡大に関わる要素としてとらえています。対面のやりとりが減少し、発言する側も受け手も、「相手はどのように感じているだろうか」という想像をしにくくなるかもしれません。実際、他者を思いやる行動や協力行為が少なくなることが観察されており、ファビングがコミュニケーションの本質を損なうという指摘がなされています。
本コラムでは、複数の調査や実験に基づく知見を踏まえつつ、ファビングが引き起こす問題を概観していきます。相手の言葉に耳を傾けながら、互いに感情を通わせることで信頼関係が育まれていくプロセスを、ファビングがどのように妨げてしまうのか。心の動きや身体の健康、人間関係の安定、そして対面でのやりとりがもたらす満足感がどのように脅かされるのか。その点を考えていきます。
共感を損ねて、善意を削ぐ
ファビングが人間同士の交流にどのような結果をもたらすかを扱った研究のうち、特に共感や親切心の低下に関する報告は興味深いものです。ここでは、ある相関研究と実験研究が組み合わされたものを見ていきましょう[1]。
まず相関研究では、日常的にスマートフォンを使って対面する相手をそっちのけにしてしまう場面が多い人を集め、その人々に対して他者への思いやりや向社会的行動の意図をどの程度持っているのかを尋ねました。同時に、その参加者が自分自身をどれほど制御できていると感じているか、すなわち衝動に流されずに行動できるかどうかについても尋ねています。
すると、ファビングをよく行う層においては、そうした自己制御感が低く、その一方で相手に手を差し伸べようという意欲も下がるという結果が得られました。自己制御が高い人ほど共感力が強く、相手の気持ちを思いやる発想が芽生えやすいという分析がなされています。
ここで注目したいのは、自己制御が高い人ほど善意を発揮しやすいという流れに、ファビングという行動が乱れを引き起こすかもしれない点です。
日々スマートフォンを操作する習慣のなかで、相手を置き去りにしてしまうやり方が当たり前になっていくと、心のブレーキがかかりにくくなり、他者の感情に思いを寄せにくくなるという指摘があります。これは、相手に関心を向けず、自分の画面を見る快適さを優先してしまううちに、自然と他者の状況への想像力が小さくなってしまうというメカニズムと考えられています。
続いて行われた実験研究では、仮想の状況を想定した上で、スマートフォン使用によって相手を無視している場面を提示しました。すると、そのような場面を多く体験するほど、相手への共感が弱まり、助けたいと行動に移す気持ちまでもが薄れることが確認されました。
先ほどの相関研究では自己制御が媒介的な要因として作用していたのに対し、実験の条件下ではその媒介がはっきりとは立証されませんでした。ただし、長期的には、ファビングを繰り返す人ほど自己制御が損なわれ、その結果、他者への優しさが育ちにくくなる可能性があるという見解が示唆されています。
共感は、周囲の苦しみや困難に心を痛め、なんとか助けになりたいという方向へ人を動かす感情です。顔と顔を合わせているとき、相手の表情や声のトーンから読み取るものは多く、自然な気づかいにつながりやすいとも考えられます。
しかし、スマートフォンにのめり込むファビングが続くと、言葉や表情の微妙な変化を見逃し、助け合いの種が芽吹かなくなるかもしれません。その点で、ファビングは他者への善意を薄れさせる要因となりうるわけです。
親切心を支える仕組みを支点にして、ファビングがいかに共感を失わせるかを中心に見てきました。ファビングによる負担は心の動きだけでなく、親子間や仕事の場などさまざまなところへ派生していきます。以降、精神的健康と社会的関係の広い範囲に及ぶ弊害について、複数の研究をつなぎながら考察していきます。
心身にも対人関係にも悪影響
ファビングに関する複数の文献を総合し、対面を無視したスマートフォン使用が広範な困りごとにつながりうるというレビューが公開されています[2]。
そこにおいては、大人だけでなく子どもや青年に関しても、ストレス反応、家族関係のこじれ、学業や仕事の能率低下など、多種多様な事例が挙げられています。とりわけ長期的なスマートフォン依存が絡むとき、うつ症状や強い孤独感、インターネットへの過度な接触といった状態を抱えやすくなるとの報告が重なっています。
ある調査では、親自身がファビングを積み重ねることで、子どものスマートフォン依存が高まる可能性を示唆する結果が得られています。親が食卓や家庭内で何度も子どもを無視して画面に向かうと、子どもは自然とインターネットやゲームに熱中し始め、家族との会話が減っていく兆しが見られました。
親子のコミュニケーションがぎくしゃくし、孤立感を覚えた子どもが情緒をうまく扱えなくなることも言われています。親から無視されていると感じた子どもが攻撃的になったり、学校での人間関係に溶け込めず落ち込んだりする可能性も指摘されます。
別の研究では、親によるファビングが高じた際、教師との良好なつながりが子どもの心を救済する緩衝材として機能するのではないかという仮説を検証するため、親子関係の質や子どもの心理状態、さらに教師とのコミュニケーション状況などを調べています。
もし家庭内で親がスマートフォンを離さず、子どもが自分の話を聞いてもらえないと感じていても、学校で安心できる大人と会話できる環境があれば、子どもの不安や閉塞感がいくぶん軽減される兆候が確認されました。
もちろん、親とのコミュニケーションが本質的に壊れてしまうと完全に回復するのは難しいですが、それでも学校現場が一定の下支えになるという示唆が得られました。
こうした家庭内の実情は、成人同士の関係にも当てはまります。ファビングにのめり込んだ人は、結果的に、スマホを介するあらゆる交流に時間を費やし、現実の世界で向かい合う相手への意識が後回しになります。
その帰結として、仕事場では協調性に悪い影響を及ぼし、チームのまとまりが崩れやすくなります。ただし、この問題が本当にどれほど大きいかは職場の制度や業種によって異なり、組織文化によっては人々が積極的に対面の時間を確保しようとする場合もあります。
子どもや青年にとっては親のファビング、大人同士であれば同僚や友人のファビングが、互いのコミュニケーションを阻害し得る、と複数の論文が報告しています。心が落ち着かない状態が長引けば、うつ状態や怒りが膨らむリスクが高まりますし、家族や仕事仲間と接する時間がそもそも減少し、人と協力し合う感覚も薄れていくかもしれません。
ここまでで、ファビングという行動が無作法を超えた広範な弊害を持ちうる要素だという論調がわかってきたのではないでしょうか。
次は、ファビングが生み出すそのような弊害の一端として、信頼感がどう蝕まれていくのかという側面に焦点を当てます。人が他者を信頼できなくなる過程は、一瞬の無視が繰り返されるなかでどのように進行するのか。その問いに迫ります。
ファビングは信頼を蝕む
会話をしている途中で、相手がスマートフォンの画面に集中する様子を何度も目にすると、そこにはちょっとした疎外感が生まれます。
先ほどまで言葉を交わしていたはずなのに、突然無視されたような気持ちになり、「この人は私と話すよりも、オンライン上で見える何かのほうが大事なのだろうか」と疑ってしまうわけです。こうした場面が慢性的に繰り返されると、仲間やパートナー、上司や部下に向けて抱いていた信頼感が薄れていく危険性があります。
ある調査では、短時間のうちにファビングが起きたことを想定させ、参加者の退屈感や見逃したくないという意識がその行動をどれほど高めるかを測定しました[3]。ここで、退屈感が強い人ほど、その埋め合わせにスマートフォンを触りたくなりやすいという傾向があることがわかりました。
さらに、その背景に「取り残されたくない」という不安を抱えているとき、ちょっとした会話中であってもすぐに画面を確認しがちであることも示されています。言いかえれば、ファビングが生じる事情として、退屈をまぎらわす意図と、周囲の動きをいつでも追いかけたい気持ちが、複合的に絡んでいると推察されます。
その上で問題となるのは、見逃し不安と退屈がファビングを繰り返す行為を後押ししてしまうことにより、周囲に対して「この人は会話の途中で平気で私を放置する」という印象を与える点です。
いったんそうした印象が根づいてしまうと、「どうせすぐにスマホを見始めるのだろう」と考えられ、相手への信頼が芽生えにくくなるメカニズムがあります。「この場で話をしていても、無駄だ」という心理が働けば、対面でのやり取りを諦めてしまうことにもつながります。
別の実験手法を用いた事例では、ファビングによって被験者がコミュニケーションの場そのものを否定的に捉えることが確認されました。
例えば、パートナーが終始スマートフォンをいじるアニメーション映像を見せられた参加者は、自分が会話に参加していると想像したとき、交流のなかで感じる安心感が減り、共に過ごす時間を充実とは思えないと回答する割合が増えました。その後の質問では、「もう一度、同じ相手と話を続けたいと思うか」と問われた際に否定的な意見が強まっていました。
こうした一連の結果は、仲間や恋人、職場の相手など問わず、目の前にいる人を置き去りにするファビングが信頼感を徐々に削いでいくリスクを示唆しています。とりわけ対話というのは、言葉を交わすだけでなく、うなずきや視線を通じて「あなたの存在を認めている」というメッセージを発する場面でもあります。そこが断ち切られれば、お互いに安心して心情を打ち明けたり、協力を頼んだりする土台が崩れるのです。
ファビングは退屈感や見逃したくない気持ちを抱えた人にとっては一時的な行動かもしれませんが、周囲からは「信頼しにくい人物だ」という評価を受ける一因になる危うさがあります。そうした姿勢が積み重なって会話の質や満足度がどう下がっていくのか、実験的な操作による検証を踏まえて論じたいと思います。
交流の質と満足度が著しく低下
ある大規模な実験的検証では、対面で話す相手がどの程度スマートフォンに目を落としているかを段階的に操作し、被験者の感じる交流の質と満足感を測定しました[4]。例えば、まったくスマホに触れない条件、少しだけ触る条件、頻繁に触る条件の三つを作り、いずれの状態が相手に対する印象や会話への評価を下げるのかを比べています。
結果的に、頻繁にファビングをされるほど会話を「充実していない」と感じ、相手との親密さを生み出す余地がかなり少ないと回答する人が多くなりました。それだけでなく、自己尊重感や所属意識のような心理的欲求が脅かされたと報告する度合いも高まりました。
一方で、「少しだけ触る」程度でも不快感を訴える参加者は存在しており、人によってはわずかなスマートフォン使用でも排除された気分になることが示されました。
別の測定では、心理的な痛みや悲しみを感じたかどうか、さらにコミュニケーション相手に抱く好意のレベルなどを点数化しています。分析結果によれば、ファビングが激しいほど、ポジティブな感情が感じにくくなり、対話を楽しいとは思えないという応答が増える傾向がありました。
これを媒介する要素としては、相手から「無視された」「自分のことを大事に思っていない」と捉える認知的プロセスが作用しています。こうした心理的プロセスを経ると、もう一度同じ相手と話し合ったり何かを相談したりしようという意欲が萎えてしまいます。
さらに、交流の質が落ち込むと、その相手との関係を続ける意味づけも弱まります。対面で話すことが無価値に感じれば、「どうせ通じ合えない」とあきらめが生じ、それが関係満足度の低下を呼び込みます。
愛情や友情、あるいはビジネスパートナーシップなど、場面はいろいろあり得ますが、いずれの場合もファビングが頻発するほど「一緒にいる意義が感じられない」と考える人が増えるのです。
興味深い点として、こうした落ち込みを経験すると、ただちに会話に復帰しようという気力さえ失われてしまう例があります。何度ファビングを見せられても、それを乗り越えようとがんばれる人もいれば、一度不信感を抱いたら簡単には気持ちを取り戻せない人もいます。短期間の実験デザインであっても、その差が顕著に現れます。
これらの検討から、ファビングによって対面のコミュニケーションの質と満足度が大幅に損なわれる可能性があることが明らかになりました。
その背景には「無視されている」と感じたときの心理的痛みや自己価値の下落があります。顔を合わせることで得られる安心感や、相手に認められているという実感がファビングによって妨げられ、会話に充実感を見いだせなくなるということです。
脚注
[1] Schmidt-Barad, T., and Chernyak-Hai, L. (2024). Phubbing Makes the Heart Grow Callous: Effects of Phubbing on Pro-social Behavioral Intentions, Empathy and Self-Control. Psychological Reports, 00332941241284917.
[2] Field, T. (2024). Phubbing: a narrative review. Journal of Psychology & Clinical Psychiatry, 15(5), 274-280.
[3] Al-Saggaf, Y. (2021). Phubbing, fear of missing out and boredom. Journal of Technology in Behavioral Science, 6(2), 352-357.
[4] Chotpitayasunondh, V., and Douglas, K. M. (2018). The effects of “phubbing” on social interaction. Journal of applied social psychology, 48(6), 304-316.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。