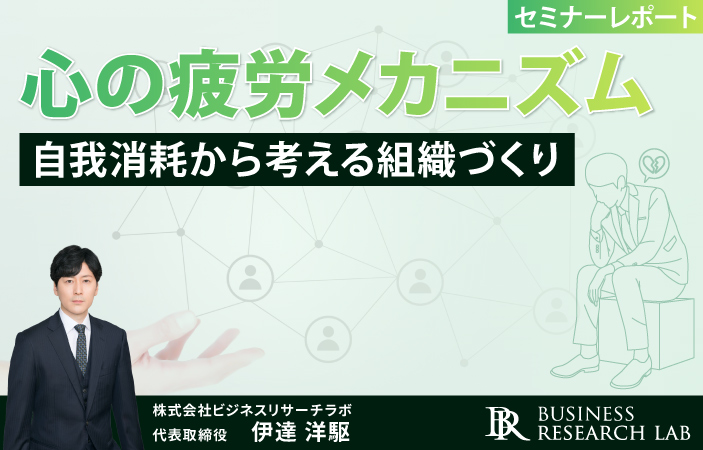2025年4月3日
心の疲労メカニズム:自我消耗から考える組織づくり(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年3月にセミナー「心の疲労メカニズム:自我消耗から考える組織づくり」を開催しました。
従業員の心の健康が、かつてないほど重要性を増しています。そのような中で近年、注目を集めているのが「自我消耗」という現象です。
感情をコントロールし、締切に追われ、人間関係に気を配る。そうした日々の業務の中で、私たちの心は確実に疲れています。
なぜ優秀な社員ほど突然パフォーマンスが低下するのか。なぜ完璧主義的な従業員は周囲との関係を損ないやすいのか。そして、どうすれば組織としてこの問題に効果的に対応できるのか。学術研究は、これらの問いに対する興味深い答えを示しています。
セミナーでは、職場における自我消耗の実態と対策について解説しました。組織の生産性向上と従業員のウェルビーイングの両立を目指す上で、新たな視点をお届けします。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
日々の業務で、朝は冷静に対応できていたのに、夕方になると些細なことでイライラしてしまうことはありませんか。顧客対応に終始笑顔で接していたのに、終業間際にはちょっとしたミスを繰り返してしまう。重要な会議で冷静に議論していたのに、帰り際に思わず本音が漏れてしまう。こうした経験は「自我消耗」という現象かもしれません。
本講演では、職場における自我消耗のメカニズムと影響について研究知見をもとに解説します。自我消耗がなぜ起こるのか、どのような悪影響をもたらすのか、そしてどのように対処すべきかについて考えていきます。
自我消耗とは
自我消耗とは、自分の感情や行動をコントロールするための心理的エネルギーが徐々に減少していく状態を指します。職場では、イライラを抑えたり、注意を集中させたり、誘惑に負けないようにしたりと、様々な場面で自己統制を働かせています。このような自己統制を長時間続けることで、次第に制御する力が弱まり、衝動的な行動や感情的な反応を抑えられなくなってしまいます。
自我消耗が起こることを検証した研究の一つに、ストループ課題を用いた実験があります[1]。ストループ課題とは、例えば「赤」という文字が青色で表示されたときに、文字の意味ではなく色を答える課題です。この課題では、自然と文字を読もうとする反応を抑制し、色に注目するという認知的な葛藤が生じます。
研究では、ストループ課題を行った後、参加者にアンチサッカード課題(視覚的な刺激が表示された方向とは反対の方向を見る課題)に取り組んでもらいました。その結果、ストループ課題で自己統制を使った参加者は、アンチサッカード課題での正確性が顕著に低下しました。
自我消耗状態にある人は、挑発を受けた際に攻撃性を示しやすくなることが明らかになっています。ある実験では、自我消耗群と非消耗群に分け、架空のパートナーとのチケット交換というタスクを通じて、参加者がどの程度攻撃的な行動を取るかを測定しました[2]。
興味深いことに、自我消耗状態の人でも、最初の試行ではまだ攻撃的な反応を抑制できることがわかっています。しかし、試行を重ねるごとに攻撃性の差が開いていきます。最初はまだ認知資源がある程度残っているため衝動を抑えられますが、課題を繰り返すうちに自我消耗の影響が強まり、挑発への衝動を抑えきれなくなっていくためです。
一見すると自我消耗は単純な疲労のように見えますが、実は両者は異なる性質を持っています。ある実験では、24時間の睡眠不足による疲労と、感情抑制による自我消耗が、人の行動にどのような違いをもたらすのかを検証しました[3]。
この実験の結果、感情抑制による自我消耗を経験した参加者は攻撃的な反応が増加する一方、24時間の睡眠不足を経験した参加者では攻撃性の顕著な増加は見られませんでした。これは、単純な疲労が必ずしも自己統制の低下には直結しないことを示しています。
組織における悪影響
多くの企業では、「組織市民行動」と呼ばれる思いやり行動が推奨されています。新入社員の指導や、困っている同僚の手助け、会社行事への積極的な参加などです。しかし、こうした行動には意外な落とし穴があることがわかってきました。
ある調査では、組織市民行動を多く行う従業員ほど自我消耗が進みやすく、その結果として顧客に対して不適切な対応をしてしまうことが明らかになっています[4]。組織市民行動に伴う自我消耗は、顧客の要望を無視したり、冷たい態度をとったり、必要な説明を省略したりするといった行動増加につながります。自我消耗によって感情をコントロールする力が低下し、本来なら抑制できるはずの不適切な行動が表出してしまうからです。
組織における自我消耗の影響は、これにとどまりません。心が疲れると、思わぬ行動に走ってしまうことがあります。その一つが不正行為です。研究では、不正行為を「多くの人が強く非難する行為」と「それほど非難されない行為」に分けて調査が行われました[5]。
その結果、自我消耗が進むと、それほど非難されない不正は増える傾向にあることがわかりました。例えば、実験では参加者に難しい制約のある文章作成課題を与えることで自我消耗を引き起こし、その後の行動を観察しました。自我消耗状態の参加者は、周囲があまり問題視しないような軽微な不正には手を出しやすくなりました。
他方で、多くの人が強く非難するような不正行為は、自我消耗状態ではむしろ減少しました。この一見矛盾する結果には、説得力のある説明があります。自我消耗状態では行動を抑制する力が弱まるため、「まあ、これくらいなら」という軽い気持ちで小さな不正に手を出しやすくなります。
しかし、大きな不正を働くには相応の「覚悟」や「エネルギー」が必要です。疲れ切った状態では、そこまでの行動に出る余力がないのです。税理士を対象にした調査でも、繁忙期の睡眠不足による自我消耗が進むと、比較的軽微な会計操作は増える一方、重大な虚偽報告は減少する傾向が見られました。
残念ながら、自我消耗の問題は職場だけにとどまりません。職場での心の疲れは、そのまま家庭に持ち込まれることがわかっています。ある研究では、仕事中に感情をコントロールする必要が多かった従業員は、帰宅後も心の疲れが続き、家庭での生活に支障が出ることが報告されています[6]。
職場での自己統制要求が高い日ほど、家庭でも自我消耗が強く表れました。例えば、仕事中にイライラを抑えたり、注意散漫を防いだりする必要が多かった日は、家に帰っても疲れが抜けにくく、家事や育児に集中できない状態が続きやすくなります。これは、職場で使い果たした自己統制の力が、十分に回復されないまま家庭生活に持ち込まれるためです。
そもそも、なぜ自我消耗がこれほど多くの悪影響をもたらすのでしょうか。有力な仮説の一つは、自我消耗によって自己効力感(自分にはできるという信念)が低下するというものです。一連の実験では、認知的な作業で意思の力を使った後、人々の自己効力感がどのように変化するかが調べられました[7]。
例えば、ある実験では、文章を読む際に特定の文字を使わないように書き写すという課題が与えられました。これは意識的な制御を必要とする作業で、自我を消耗させる操作として用いられます。この課題の後、健康的な食事に関する自己効力感を測定すると、自我を消耗させる作業を行ったグループは、そうでないグループと比べて、健康的な食事を続けられる自信が低下していました。
別の実験では、最初に自己統制を必要とする課題を行ったグループは、計算課題に対する自己効力感が低下し、実際の成績も下がることがわかりました。統計分析によって、自己効力感の低下が自我消耗状態とパフォーマンス低下の間を媒介していることが確認されました。要するに、自我消耗による自己効力感の低下が、次の課題での成績低下を引き起こすという関係が示されたのです。
自我消耗の生じやすい仕事
勤務環境が自我消耗に及ぼす影響も研究されています。ある研究では、異なる部署で働く医療従事者の自我消耗度を比較分析しました[8]。その結果、勤務する部署によって自我消耗の程度に違いが見られることがわかりました。
特に緊急性の高い処置が多い部署や、患者との密なコミュニケーションが必要な部署では、自我消耗が進みやすい傾向にありました。これらの部署では、緊張状態を強いられ、感情のコントロールや注意力の維持に多くの心理的エネルギーを必要とします。突発的な事態への対応や迅速な判断が求められるため、高い集中力を維持する必要があり、患者や家族との感情的なやり取りも多いため、自己統制の機会が頻繁に生じます。
また、同じ部署内でも、業務負担の分布によって自我消耗の程度は異なります。一部の職員に業務が集中する環境では、その職員の自我消耗が著しく進みます。複雑な意思決定が求められる業務や、感情労働の要素が強い業務が特定の職員に偏ると、心理的エネルギーの消耗が顕著になります。
この研究は、自我消耗を個人の問題として捉えるのではなく、組織や環境の問題として考える必要性を示しています。個人の努力だけでは解決できない構造的な課題が存在することが明らかになりました。自社の中でどのような仕事が自我消耗を引き起こしやすいのかを検討することは、組織マネジメントにおいて重要でしょう。
自我消耗への対処
職場には様々なストレスがありますが、全てのストレスが自我消耗につながるわけではありません。研究によれば、ストレスには大きく分けて二つのタイプがあることがわかっています[9]。
一つは「挑戦ストレス」と呼ばれるものです。これは、仕事量が多かったり、締め切りに追われたりするような、一見ストレスフルに見える状況です。もう一つは「妨害ストレス」です。これは、職場の対立や無駄な手続き、曖昧な指示など、仕事の達成を妨げるような要因から生まれるストレスです。
これら二つのストレスは、自我消耗に対して正反対の影響を及ぼすことが明らかになっています。挑戦ストレスは、むしろ自我消耗を減少させる傾向にあります。チャレンジングな仕事に取り組むことで自己効力感が高まり、ポジティブな感情が生まれるため、心理的なエネルギーが維持されやすくなります。
一方、妨害ストレスは自我消耗を増加させます。無駄な手続きや曖昧な指示に対処するためには、余計な心理的負担やエネルギーが必要となります。職場の対立に巻き込まれることで、感情をコントロールする力が大きく消耗してしまいます。
先ほどの結果は別の研究でも裏付けられています。チャレンジングな仕事には、自我消耗を減らす効果があることが明らかになっています[10]。一見すると、難しい仕事や責任の重い業務は心を疲れさせそうに思えますが、実際にはその反対の効果をもたらすのです。
中国で行われた調査では、責任の重い仕事や挑戦的な課題に取り組む従業員は、自我消耗が少なくなる傾向が見られました。この理由として、挑戦的な仕事には「自己効力感」や「達成感」を高める効果があることが指摘されています。
難しい課題に挑戦することで、「自分ならできる」という自信が芽生え、それが内発的な動機づけを高めます。課題を一つ一つ乗り越えていく過程で、ポジティブな感情が生まれやすくなります。このように、やりがいのある仕事は心理的なエネルギーを維持し、時には増加させる効果があるのです。
挑戦的な仕事が自我消耗を減少させるという知見は、職場のマネジメントにとって重要な示唆を与えています。単に業務量を減らしたり、責任を軽くしたりするのではなく、むしろ適切な挑戦を提供することが従業員の心理的エネルギーを保つ上で効果的だということです。
個々の従業員のスキルレベルに合った、やや高めの目標設定や、成長につながる新しい業務の割り当てが良いでしょう。また、達成感を得られるように、小さな成功体験を積み重ねられる環境づくりも求められます。
さて、自我消耗の研究で興味深い発見の一つは、意志力が実際に減少するわけではなく、意志力が減ると思い込むことで生じる可能性が高いということです。この点を検証するため、複数の実験が実施されました。
ある実験では、「意志力は有限である」と強く信じている参加者は、意志力を使う課題を行った後にパフォーマンスが低下しましたが、「意志力はそう簡単には減らない」と考えている参加者は、同じように意志力を使う課題を行ってもパフォーマンスはほとんど低下しませんでした[11]。
別の実験では、参加者を二つのグループに分け、一方のグループには「意志力は有限で使えば使うほど減っていく」という内容の説明文を読んでもらい、もう一方のグループには「意志力は無限に近く、使えば使うほど強くなる可能性がある」という内容の説明文を読んでもらいました。
その後、自己統制を必要とする課題を行ってもらったところ、意志力が有限だと説明された参加者は課題後のパフォーマンスが顕著に低下しましたが、意志力が無限に近いと説明された参加者はパフォーマンスの低下が見られず、一部の参加者では向上する傾向さえ見られました。
これらの研究結果から、自我消耗を防ぐためには、意志力に関する考え方を変えることが効果的だと言えます。「使えば使うほど減っていく」という考え方から、「適切に使うことで強くなり得る」という考え方へのシフトです。
組織においては、この知見を活かした研修やコーチングを導入することで、従業員の自己統制能力を強化できる可能性があります。また、成功体験を積み重ねることで「できる」という感覚を育み、意志力に関する前向きな信念を形成することも一案です。
自我消耗の良い点
自我消耗に関する研究では、意外な発見もあります。これまでの研究では、自我消耗は多くの場合、パフォーマンスの低下をもたらすと考えられてきましたが、ある種の問題解決場面では、むしろ有利に働く可能性があることがわかってきました。
ある実験では、自我消耗状態にある人とそうでない人に、固定観念を打破する必要がある問題を解かせました[12]。具体的には、マッチ棒を使った算数問題など、従来の思考パターンにとらわれていると解決が困難な課題が用いられました。
その結果、自我消耗状態にある参加者のほうが、柔軟な発想で問題を解決できることが明らかになりました。参加者の多くは、課題に取り組む過程で「インパス」と呼ばれる行き詰まりを経験しました。これは、従来の思考パターンでは解決できないことに気づく段階です。
自我消耗群と非消耗群の両方で、このインパスを経験する割合に大きな違いはありませんでしたが、インパスから抜け出し、新しい解決策を見出す過程で違いが現れました。自我消耗状態にある参加者のほうが、固定観念から解放され、斬新なアプローチを試みる傾向が強かったのです。
この結果は、自我消耗が必ずしもあらゆる意味でパフォーマンスの低下をもたらすわけではないことを示しています。通常の状態では、私たちは既存の思考パターンや固定観念に縛られています。しかし、自我が消耗した状態では、そうした思考の枠組みが緩み、新しい発想が生まれやすくなるのです。
参加者の主観的な疲労感についても考えさせられる結果が得られました。自我消耗群と非消耗群の間で、課題に対する認知的な負担感に大きな違いは見られませんでした。創造的な問題解決において、主観的な疲労感と実際のパフォーマンスが必ずしも一致しないことを示唆しています。
おわりに
本講演では、職場における自我消耗について多角的に考察してきました。自我消耗は単純な疲労とは異なり、感情や行動のコントロールが難しくなる状態です。組織市民行動のような良かれと思ってする行動が自我消耗を引き起こし、顧客サービスの質の低下や不適切な行動の増加、さらには家庭生活にまで悪影響を及ぼす可能性があることがわかりました。
しかし、全てのストレスが自我消耗につながるわけではありません。挑戦的な仕事は自己効力感や達成感を高め、むしろ自我消耗を減らす効果があります。また、意志力に関する考え方を変えることで、自我消耗の影響を軽減できる可能性も示されました。さらに、自我消耗が創造的な問題解決を促進するという意外な効果も見出されています。
組織のマネジメントにおいては、これらの知見を活かした取り組みが求められるでしょう。適切な挑戦の提供、不必要な妨害要因の削減、意志力に関する前向きな考え方の育成など、自我消耗を予防し、あるいは有効活用するための施策を検討することが重要です。そして何より、自我消耗を個人の問題としてではなく、組織や環境の問題として捉える視点が求められます。
Q&A
Q:組織市民行動をとって自我消耗が起こった人が顧客に冷たくなる件ですが、なぜ自組織の従業員に対してではなく、顧客に矛先が向いてしまうのでしょうか。
一つの仮説として考えられるのは、顧客に対しての方が、普段から感情や行動をより強くコントロールしなければならない状況があるからではないでしょうか。一緒に働く仲間よりもお客さんに対しての方が、自分の本来の感情をコントロールすることが求められる度合いが大きいと思われます。顧客対応ではより高いレベルの自己統制力が必要とされるため、組織市民行動によって弱ってしまった自己統制力、すなわち自我消耗が生じた状態では、より強く自分をコントロールしなければならない顧客とのやり取りにおいて、ほころびが生じやすくなるのだと思います。
Q:自我消耗と一般的な疲労の違いを詳しく知りたいです。業務の中でどのように見分けることができますか?
自我消耗というのは、感情や行動といった自分自身のコントロールが難しくなってしまう状態を指します。一般的な疲労とは異なる点があり、その見分け方としては、例えば肉体的には元気であるにもかかわらず、感情的な反応が普段より強くなってしまうことがあります。ちょっとしたことで怒ってしまったり、機嫌を損ねてしまったりするような場合、「全然疲れていないはずなのに」という状況では、まさに自我消耗が起きている可能性があります。また、些細なミスが増えてしまうことも兆候として認められます。
Q:挑戦ストレスと妨害ストレスの違いについて例を教えていただきたいです。弊社ではプロジェクトの難易度が高く、どこからが挑戦でどこからが妨害になるのか線引きが難しいと感じています。
挑戦ストレスと妨害ストレス、確かにこれは自我消耗にとって重要な違いですので、もう少し掘り下げて説明します。振り返っておくと、挑戦ストレスの方が自我消耗に対してはそれを減らす効果がある一方で、妨害ストレスについては自我消耗を増やしてしまう効果があることがわかっています。
挑戦ストレスとは、達成可能ではあるけれども努力が必要な目標や、それを担うことによって成長につながっていくような課題やプロジェクトから発生する負荷のことを指します。例えば、新しい市場に参入するための計画を立てることや、技術的には難しいけれども努力すれば実現可能なプロダクトの開発などが挑戦ストレスの例として挙げられます。
一方、妨害ストレスは目標達成を阻む要因です。仕事の遂行を妨害するストレスと言えます。例えば、意味のない会議があったり、指示が曖昧であったり、要求されていることが矛盾していたり、社内政治が申告であったり、業務プロセスが非効率であったりする場合です。こういったことは自分の仕事が妨害されている状態であり、目標達成を妨げるようなストレスにあたります。
挑戦ストレスの方は乗り越えるとポジティブな感情が芽生えてきます。達成感や成長といったポジティブな状態になることができますが、妨害ストレスについては消耗するばかりというところが違いだと思います。
Q:自我消耗が創造的な問題解決を促進するという効果は興味深いと思いました。これをどのように応用できるでしょうか。例えばイノベーションが求められる部署で、この考え方をうまく取り入れるような方法はありますか。
取扱注意ではありますが、例えば創造的なタスクで行き詰まっているような状況において、あえて自我消耗の状態を活用していくという方法はあり得るのではないかと思います。例えば、集中力が必要となるようなタスクに取り組んだ上で、創造性が求められる議論を行っていくというやり方が一つあるかもしれません。また、1日が進んでいくとだんだん自我消耗は起こってくるものです。そうすると、夕方ぐらいの時間帯にブレインストーミングを行った方が固定観念を打破できる可能性があるかもしれません。
ただし、本来であれば必要のない形で自我消耗を発生させるというのはあまり健全ではありませんし、自我消耗によるパフォーマンスの低下という悪影響も考えられます。したがって、自然と起こる自我消耗をうまく活用していく方法が良いでしょう。
脚注
[1] Dang, J., Liu, Y., Liu, X., and Mao, L. (2017). The ego could be depleted, providing initial exertion is depleting: A preregistered experiment of the ego depletion effect. Social Psychology, 48(4), 242-245.
[2] Barlett, C., Oliphant, H., Gregory, W., and Jones, D. (2016). Ego‐depletion and aggressive behavior. Aggressive Behavior, 42(6), 533-541.
[3] Vohs, K. D., Glass, B. D., Maddox, W. T., and Markman, A. B. (2011). Ego depletion is not just fatigue: Evidence from a total sleep deprivation experiment. Social Psychological and Personality Science, 2(2), 166-173.
[4] Hongbo, L., Waqas, M., Tariq, H., Yahya, F., Marfoh, J., Ali, A., and Ali, S. M. (2021). Cost of serving others: A moderated mediation model of OCB, ego depletion, and service sabotage. Frontiers in Psychology, 12, 595995.
[5] Yam, K. C., Chen, X. P., and Reynolds, S. J. (2014). Ego depletion and its paradoxical effects on ethical decision making. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 124(2), 204-214.
[6] Germeys, L., and De Gieter, S. (2018). A diary study on the role of psychological detachment in the spillover of self-control demands to employees’ ego depletion and the crossover to their partner. European Journal of Work and Organizational Psychology, 27(1), 140-152.
[7] Chow, J. T., Hui, C. M., and Lau, S. (2015). A depleted mind feels inefficacious: Ego-depletion reduces self-efficacy to exert further self-control. European Journal of Social Psychology, 45(6), 754-768.
[8] Cui, Y., Yang, T., Gao, H., Ren, L., Liu, N., Liu, X., and Zhang, Y. (2022). The relationship between ego depletion and work alienation in Chinese nurses: A network analysis. Frontiers in Psychology, 13, 915959.
[9] Kang, F., Zhang, Y., and Zhang, H. (2022). Hindrance stressors, ego depletion and knowledge sharing. Organization Management Journal, 19(1), 22-33.
[10] Xia, Y., Schyns, B., and Zhang, L. (2020). Why and when job stressors impact voice behaviour: An ego depletion perspective. Journal of Business Research, 109, 200-209.
[11] Job, V., Dweck, C. S., and Walton, G. M. (2010). Ego depletion – Is it all in your head? Implicit theories about willpower affect self-regulation. Psychological Science, 21(11), 1686-1693.
[12] DeCaro, M. S., and Van Stockum Jr, C. A. (2018). Ego depletion improves insight. Thinking & Reasoning, 24(3), 315-343.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。