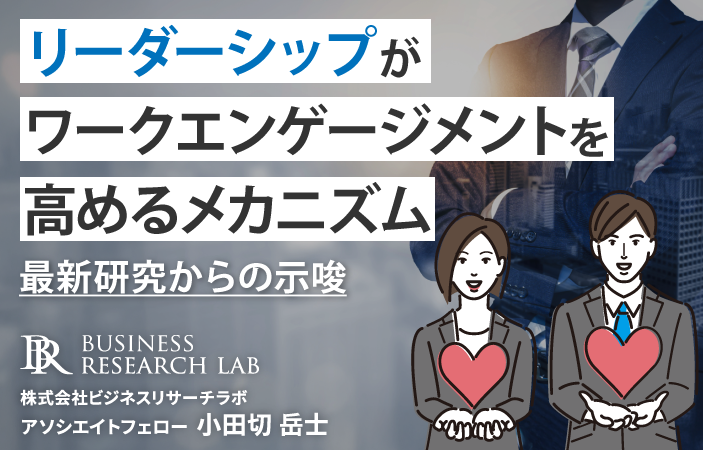2025年4月2日
リーダーシップがワークエンゲージメントを高めるメカニズム:最新研究からの示唆
組織が成功する要因の一つとして、従業員の「ワークエンゲージメント」に注目が集まってから、長い時間が経過しました。ワークエンゲージメントとは、前向きで充実した仕事に関連した心の状態を表します[1]。
具体的には、ワークエンゲージメントの高い従業員は、エネルギーに満ちあふれており、ハードルの高い課題にも挑戦的で、没頭して仕事に取り組みます。その結果として、高いパフォーマンスを発揮する[2]など、多くのポジティブな成果をもたらすことが明らかとなっています。一方、ワークエンゲージメントが低い従業員は、組織から退職しようとする意志が高くなる傾向にあることもわかっています[3]。
このように、ワークエンゲージメントを高めることは、組織の成功や成長にとって重要といえます。そのような社会の関心が広まる中で、学術領域においてもワークエンゲージメントに影響を与える要因について様々な研究が行われてきました。その中でも特に近年の研究で注目されているのが「リーダーシップ」です。
本コラムではリーダーシップとワークエンゲージメントの関係性を概観しつつ、近年の研究知見にもとづき、リーダーシップがワークエンゲージメントを高めるメカニズムについて解説します。
リーダーシップとエンゲージメントの関係性
一言にリーダーシップといえども、そのスタイルは多種多様です。複数の研究結果を統合して再分析した論文では、下記5つのリーダーシップスタイルが、部下のワークエンゲージメントを高める傾向にあることが明らかになっています[4]。
- 変革型リーダーシップ:影響力・動機づけ・個別配慮などを特徴とするスタイルです。カリスマ性を持ち、未来を見据え、フォロワー一人ひとりの関心に合わせてモチベーションを上げることのできるリーダーです。
- オーセンティックリーダーシップ:オーセンティック(Authentic)は「真正(本物)の」などと和訳されます。リーダーの自己認識・本音の提示・道徳的視点などを特徴とするスタイルです。自らの考えや本音を提示しつつ、自らの弱みも周囲に見せながら、日々の業務に取り組んでいるリーダーです。
- サーバントリーダーシップ:リーダー自身の誠実さ・他者への奉仕を特徴とするスタイルです。このスタイルを持つリーダーは、基本的に自分ではなく部下のニーズに焦点を当てるべきと考えており、フォロワーの成長を支援しようとします。
- 倫理的リーダーシップ[5]:リーダーの倫理性・規範性を特徴とするスタイルです。周囲に対して倫理的に適切な行動を示し、フォロワーに同じような行動を促そうとします。
- エンパワーメントリーダーシップ:権限の委譲・情報共有・コーチングなどを特徴とするスタイルです。フォロワーが自ら仕事を進められるように必要な情報を提供し、励まします。
結論として、この研究では上記5つのスタイルに共通する要素を次のようにまとめています。
- 道徳的である
- フォロワーのモデルとなるような役割・行動をとる
- フォロワーが自分で物事を決められるよう支援する
- フォロワーとの前向きな関係性を育むことに重点を置いている
つまり、部下のお手本となる道徳的な行動をとり、部下と仕事を進めるうえで有益な関係性を築き、部下が自分で仕事を進められるように支援する。このようなリーダーシップを発揮する上司のもとでは、部下のワークエンゲージメントが高まりやすくなるといえます。
なぜリーダーシップがワークエンゲージメントを高めるのか
それでは、なぜ前述のような特徴を持つリーダーシップが、ワークエンゲージメントを高めるのでしょうか。そのメカニズムの一端を明らかにした研究が2024年に発表されました[6]。この研究では、特にエンパワーメントリーダーシップとワークエンゲージメントの関係性に着目し、両者を結びつける要素として「組織同一視」「職場ウェルビーイング」が存在することを明らかにしました。
具体的には、エンパワーメントリーダーシップがワークエンゲージメントを高める経路には2つあることが示されています。一つは、エンパワーメントリーダーシップが組織同一視を高めることでワークエンゲージメントを高めるという経路です。もう一つは、エンパワーメントリーダーシップが職場ウェルビーイングを高めることでワークエンゲージメントを高めるという経路です。
組織同一視(Organizational Identification)とは、組織との一体感や組織への帰属意識を個人が持っている状態を表します。組織同一視が進んでいる従業員は、自分の組織に対して好意的になり、組織に起こった問題を自分の身に起きた出来事のようにとらえやすいといえます。また、職場ウェルビーイング(Workplace Well-being)は、仕事に関連したポジティブな心理状態であり、仕事の意義深さを感じており、満足している状態を表します[7]。
つまり、エンパワーメントリーダーシップを実践する上司の下では、部下の組織に対する愛着が高まると同時に、仕事に対する肯定的な感情も高まるため、結果としてワークエンゲージメントが促されます。それぞれの関係性について、学術的な理論をもとに詳しく説明していきます。
リーダーシップが組織同一視を高めるプロセス
社会的アイデンティティ理論は、集団における個人のアイデンティティに関する理論です。この理論では(1)個人が組織の特徴を好ましいと判断すると、組織の特徴を自らに取り込もうとする(2)組織の特徴を自らに取り込んだ個人は、組織に対する帰属意識や愛着が高まるとされています[8]。
例えば、倫理的なルールが順守されている組織を好ましいと思った従業員は、「自分も倫理的な人間だ(倫理的な人間になりたい)」と考えて倫理的なふるまいを行うようになります。また「組織で倫理的な問題が起きないよう努めなければ」と組織への帰属意識や貢献意欲がより高まりやすくなります。
一般的に、多くの従業員は「自分の力で仕事が進められるようになりたい」という願望を持っていると考えられます。エンパワーメントリーダーシップを持つ上司は、部下に仕事の裁量や役立つ情報、コーチングを提供します。それらの支援を受け取った部下は、自らのニーズが満たされたため、上司を好ましいと感じます。
さらに部下にとって上司とは組織を代表する人物であるため、「このような支援を与えてくれる組織は素晴らしい」「自分もこの組織の一員として誇れる人間になりたい」とポジティブな同一視を進めるようになります。
組織同一視が進んだ従業員は、組織の成功が自分の成功であり、組織に起きた問題は自分に起きた問題と捉えるようになります。よって、仕事に対してエネルギッシュに、真摯に取り組もうとするため、ワークエンゲージメントが高まりやすくなります。
リーダーシップが職場ウェルビーイングを高めるプロセス
モチベーションについて説明する自己決定理論では、人は働くうえで、自律性(自分の判断で物事を進められること)・有能性(他人よりも自分の能力が高いこと)・関係性(人と関わるいること)という3つの欲求を持っているとされています[9]。
エンパワーメントリーダーシップを持つ上司は、部下に権限を与え、成長の支援のため積極的に関わります。これらの支援が部下の欲求を満たすため、部下は仕事を肯定的に捉えるようになり、職場ウェルビーイングが高まるのです。
さらに、自己決定理論は、仕事の意義を感じていたり、仕事に満足したりしている従業員は、仕事に対するモチベーションが刺激されるとしています[10]。よって、仕事に対して熱心に取り組むようになり、ワークエンゲージメントが高まるといえます。
実践に向けたポイント
以上のように、近年の研究から、どのようなリーダーシップスタイルがワークエンゲージメントを高めやすいのかと、リーダーシップがワークエンゲージメントを高めるメカニズムが明らかとなってきました。研究知見に基づくと、実践に向けた代表的なポイントは以下の通りです。
現状のリーダーシップの把握
具体的な実践に先立って、各上司が現状どのようなリーダーシップをどの程度実践しているかを把握しましょう。例えば本コラムで挙げた5つのリーダーシップスタイルや、それらのスタイルに共通する4要素についてアンケートで測定することが考えられます。また、
この場合のアンケートは基本的に部下側が自分の上司について回答するものですが、できれば上司本人にも回答を求め、本人の認識と周囲との認識の差異をフィードバックすることも一案です。
適切なリーダーシップの実践
リーダー本人にできることとして、現状のリーダーシップの実践度が把握できたら、どの要素が足りていないかを確認し、それらを意識的に実践するよう心がけましょう。
例えば「部下が自分で物事を決められるような支援」が少ない上司は、マイクロマネジメントで指示が多くなりがちかもしれません。まずは失敗してもリスクの少ない業務から、期限を短く設定して、情報は提供しつつもいったん任せ、終了後にフィードバックするといった手段が考えられます。
リーダー選抜時の工夫
組織・人事側がリーダーを選抜する際にできる工夫をご紹介します。例えばエンパワーメントリーダーシップを発揮できるかどうかには、リーダーの性格や価値観(権力を追い求める志向や、あいまいな状況を回避したがる性格)が影響する可能性が指摘されています[11]。従業員サーベイでそれら性格や価値観に関する項目を把握することで、適切なリーダーシップを発揮しやすい人物に当たりをつけることが可能です。
また、リーダー選抜後には新任リーダー向け説明会や研修を実施することが多いでしょう。その中で、組織としてワークエンゲージメントの向上を重視していることや、そのためのリーダーシップの必要性や実践方法について、本コラムに記載されている内容などを用いながら十分に説明し、教育する機会を設けましょう。
フォロワーとしての振る舞いを見直す
リーダーシップは、上司やリーダー自身が独力で発揮しなければならないものだと考えられがちです。しかし、リーダーシップの発揮には、部下自身の有能さや積極性も影響することが指摘されています[12]。よって、部下側にも自身の振る舞いを見直す必要があるといえます。
上司が適切に関わってくれることをただ待っているだけになっていないか、今任せられている仕事で成果をさらに上げるためにはどうすればいいかを、改めて考えてみることも必要でしょう。
リーダーシップが影響を与える各要素の測定
リーダーシップを促進する施策に合わせて、組織同一視・職場ウェルビーイング・ワークエンゲージメントについても従業員サーベイで測定しましょう。そうすることによって、実施している施策が、リーダーシップの要素にどのような影響を与え、実際に良い成果をもたらしているかどうかを確認することができます。
仮にリーダーシップが高まっていても、組織同一視・職場ウェルビーイングが高まっていない場合、その2つの要素を直接的に下げてしまう別の要因が存在する可能性があります。それらに改善の余地がないかも併せて検討します。
リーダーシップがワークエンゲージメントを高めるメカニズムを理解し、適切なリーダーシップを実践することは、組織の成長と従業員の満足度向上に繋がります。経営層・人事・上司・部下のいずれもが、ワークエンゲージメント向上の重要性を認識し、自分たちのできることを実行することが、結果的に組織としての成果につながるといえます。
脚注
[1] Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2010). Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the concept. Work engagement: A handbook of essential theory and research, 12, 10-24.
[2] Christian, M. S., Garza, A. S., & Slaughter, J. E. (2011). Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance. Personnel psychology, 64(1), 89-136.
[3] Yalabik, Z. Y., Popaitoon, P., Chowne, J. A., & Rayton, B. A. (2013). Work engagement as a mediator between employee attitudes and outcomes. The International Journal of Human Resource Management, 24(14), 2799-2823.
[4] Decuypere, A., & Schaufeli, W. (2021). Exploring the leadership–engagement nexus: A moderated meta-analysis and review of explaining mechanisms. International journal of environmental research and public health, 18(16), 8592.
[5] 倫理的リーダーシップの詳細は当社コラムをご覧ください。
[6] Liu, S., Han, X., Du, L., Zhu, H., Shi, R., & Lan, J. (2024). How Does Empowering Leadership Relate to Work Engagement? The Roles of Organisational Identification and Workplace Well-Being. Psychological Reports, 00332941241259370.
[7] Zheng, X., Zhu, W., Zhao, H., & Zhang, C. (2015). Employee well‐being in organizations: Theoretical model, scale development, and cross‐cultural validation. Journal of Organizational Behavior, 36(5), 621-644.
[8] Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of management review, 14(1), 20-39.
[9] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Self-determination theory. Handbook of theories of social psychology, 1(20), 416-436.
[10] Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self‐determination theory and work motivation. Journal of Organizational behavior, 26(4), 331-362.
[11] Sharma, P. N., & Kirkman, B. L. (2015). Leveraging leaders: A literature review and future lines of inquiry for empowering leadership research. Group & Organization Management, 40(2), 193-237.
[12] 脚注11 (Sharma & Kirkman, 2015)と同じ
執筆者
 小田切 岳士 アソシエイトフェロー
小田切 岳士 アソシエイトフェロー
同志社大学心理学部卒業、京都文教大学大学院臨床心理学研究科博士課程(前期)修了。修士(臨床心理学)。公認心理師。働く個人を対象にカウンセラーとしてのキャリアをスタート。その後、企業人事として制度・施策の設計・運用などに携わる。現在は主な対象を企業や組織とし、臨床心理学や産業・組織心理学の知見をベースに経営学の観点を加えた「個人が健康に働き組織が活性化する」ための実践を行っている。特に、改正労働安全衛生法による「ストレスチェック」の集団分析結果に基づく職場環境改善コンサルティングや、職場活性化ワークショップの企画・ファシリテーションなどを多数実施している。