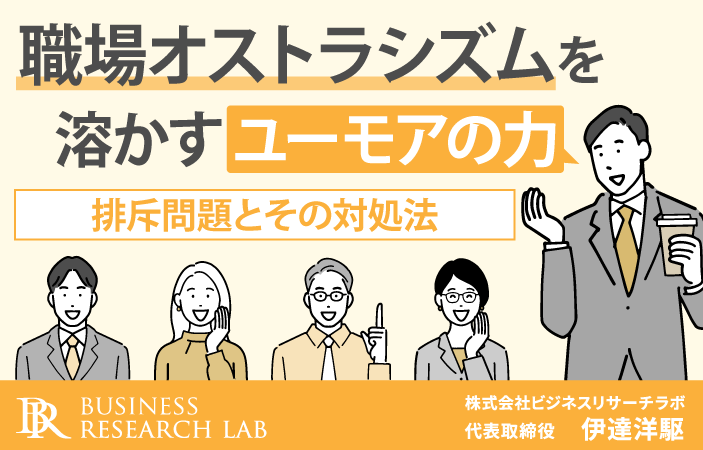2025年4月1日
職場オストラシズムを溶かすユーモアの力:排斥問題とその対処法
コミュニケーションツールの発達により、職場における情報共有や連絡は、かつてないほど容易になりました。オンラインチャットやビデオ会議システムを通じて、いつでもどこでも同僚とつながることができます。しかし、こうしたコミュニケーションの「しやすさ」は、時として人々を孤立させる原因にもなり得ます。
例えば、グループチャットから外される、オンライン会議に招待されない、メールの返信がない。デジタルツールを介した排除は、オフィスでの直接的な無視と同じく、従業員を傷つける可能性があります。
もちろん、職場のオストラシズム(社会的排斥)は、決して現代特有の問題ではありません。むしろ、人類が集団で働き始めて以来、存在してきた課題だと言えます。ただし、働き方が多様化し、職場のコミュニケーション手段が複雑化する中で、その形態や影響は変化し続けています。
本コラムでは、職場オストラシズムについて多角的な考察を試みます。排斥がなぜ発生し、どのような影響をもたらすのか、そしてそれにどう対処できるのかについて知見を紹介します。
侮辱的管理とオストラシズムの関係をユーモアが緩和
職場のオストラシズムは、上司のマネジメントスタイルと関連することが分かっています。ポルトガルの研究グループが、40社の上司と部下を対象に実施した調査では、上司の侮辱的管理が部下への排斥を引き起こすことが判明しました[1]。
調査では、上司による虐待的な指導(罵倒、侮辱、無視など)を受けている従業員は、同僚からも排斥されやすいことが分かりました。同僚たちが上司との良好な関係を守るために、問題のある従業員との距離を置くためです。上司から否定的な評価を受ける従業員に近づくことで、自分も同様の扱いを受けることを恐れ、その従業員を避けようとするのです。
この状況がさらに悪化するのは、排斥された従業員が同僚に対して非生産的な行動(例えば、ゴシップや非建設的な競争)を取るようになる場合です。これによって、職場の人間関係はさらに悪化し、排斥の連鎖が生まれることがあります。
しかし、この研究では、職場でのユーモアの存在が、こうした負の連鎖を断ち切る可能性を秘めていることが示されています。同僚間でユーモアが頻繁に使われる職場では、上司の侮辱的管理と排斥の関係が弱まることが判明しました。
職場でのユーモアは、ポジティブな感情を生み出す社会的資源として機能します。同僚間でユーモアが交わされると、心理的な距離が縮まり、仲間意識が高まります。その結果、侮辱的管理を受けている従業員に対しても共感を示しやすくなり、排斥する必要性が低下するのです。
ユーモアは上司の虐待的行動というネガティブな要因を「職場環境の外側の問題」として切り離す効果があります。これによって、集団内での上司の否定的な影響力が最小化されます。逆に、ユーモアが少ない職場では、ネガティブな環境がそのまま維持され、同僚間の排斥行動が助長されるということです。
許しの雰囲気が職場オストラシズムの悪影響を緩和
中国の企業を対象とした調査では、職場のオストラシズムが従業員の幸福感に及ぼす影響と、それを緩和する要因について分析が行われました。研究では、多数の従業員とその上司を対象に、3か月間にわたるデータ収集が実施されました[2]。
調査の結果、職場での排斥は従業員の幸福感に直接的な負の影響を与えることが確認されました。排斥された従業員は自己否定や孤立感を抱き、精神的なリソースを消耗させていきます。この消耗が回復されないまま続くと、ストレスが蓄積され、最終的に幸福感が大きく損なわれることになります。
排斥は「情緒的消耗」という状態を引き起こすことも判明しました。情緒的消耗とは、物事に対する興味や活力を失い、心理的・身体的に消耗した状態を指します。この状態に陥ると、周囲の人々や仕事に対する意欲が低下し、さらなる幸福感の低下につながります。
しかし、「許しの雰囲気」が排斥による悪影響を緩和する可能性を持っています。許しの雰囲気とは、チームメンバー間の過失や失敗を寛容に受け入れる風土のことを指します。
実際に、許しの雰囲気が強いチームでは、排斥による情緒的消耗の影響が弱まることが分かりました。チーム内の信頼感と協力が、情緒的消耗を回復するリソースとして機能するためです。許しの雰囲気は否定的な感情を軽減し、従業員への支援を増加させることで、心理的な負担を和らげます。
これらの結果は、職場環境における「許し」という要素が、排斥のネガティブな影響を緩和する上で役割を果たすことを示唆しています。心理的なストレスを軽減し、従業員の幸福感を維持するためには、寛容で支援的な職場文化を育むことが有効です。
自己効力感と職位が職場オストラシズムの悪影響を緩和
パキスタンの組織を対象とした研究では、職場での排斥が従業員の仕事の成果に与える影響と、それを緩和する要因について分析が行われました。調査では、銀行、通信、繊維産業などの従業員とその上司を対象に、3段階のアンケート調査が実施されました[3]。
調査の結果、排斥を受けた従業員の仕事の成果は有意に低下することが確認されました。排斥によるストレスやエネルギーの枯渇が、タスク遂行能力を損なうためです。排斥は基本的な「帰属欲求」を満たさず、心理的なストレスを引き起こし、エネルギーの消耗を進行させます。
しかし、「自己効力感」と「職位」という二つの要因が、排斥の悪影響を緩和する可能性を持つということも明らかになりました。
自己効力感が高い従業員は、排斥による負の影響を受けにくいのです。自己効力感が高い人は、困難な状況に直面してもそれを乗り越えるための創造的な解決策を考え出します。例えば、他の情報源を活用したり、別のネットワークを頼ったりして、不足する知識を補うことができます。
この自己効力感の緩和効果は、職位が高い場合に特に強く現れます。職位が高い従業員は、組織内の重要な情報や知識へのアクセスが容易です。排斥により一部の会話から除外されたとしても、他のルートを通じて情報を得る手段を持っているのです。
職位が高い従業員は、組織の全体像や人間関係を理解しているため、排斥の理由を冷静に分析し、それに応じた対応策を講じることもできます。組織内で築いてきたネットワークやリソースを活用して、排斥を受けても必要な情報やサポートを得られる可能性が高くなります。
対照的に、職位が低い従業員は、排斥を受けた際に対応策を見つけにくく、さらなる孤立に陥る可能性があります。加えて、職位が低い場合、自己効力感が高すぎると「過信」に陥る危険性があります。例えば、「自分一人で問題を解決できる」と誤解し、実際には問題を悪化させるかもしれません。
系統的レビューで職場オストラシズムの対策を列挙
2010年から2022年までの職場オストラシズムに関する研究を系統的にレビューした論文では、複数の国際的なデータベースから多数の研究が検討されています[4]。この論文の目的は、職場での排斥が従業員に与える影響と、その影響を軽減するための実践的な方法を整理することなどです。
論文では、様々な対策が11のテーマに分類されています。
- 「トレーニングと開発」では、ストレス対処や心理的耐性を高めるためのセミナーや研修が有効とされています。レジリエンス訓練やマインドフルネス介入などが、具体例として挙げられています。
- 「職場文化」では、開放的で公平な職場文化を構築することが、排斥のリスクを減少させる方法として提案されています。包摂的で互いに関与する職場環境を促進することが、その中心的な考え方です。
- 「正式・非正式な会議」では、イベントや非公式な交流を通じて孤立感を軽減する方法が示されています。
- 「採用と選考」では、排斥を受けにくい、または対処能力の高い人材を選定することの重要性が指摘されています。
- 「対人関係」のテーマでは、同僚間の友好的な関係を構築し、孤立感を防ぐことの重要性が強調されています。
- 「タスク依存性」では、チームワークを奨励し、排斥を減少させるタスク設計の有効性が示されています。
- 「モニタリング」のテーマでは、サーベイなどで職場環境を定期的に評価することの必要性が指摘されています。
- 「信頼と透明性」では、信頼を築き、排斥を防ぐマネジャーの行動が重要視されています。
- 「適切なコミュニケーションチャネル」では、排斥された従業員が意見を述べるためのルートを提供することの必要性が示されています。
- 「個人特性」では、従業員の特性に応じたサポートの必要性が指摘されています。
- 「職務の自律性」では、従業員が自己決定をしやすい環境を整備することの重要性が強調されています。
これらのテーマは、それぞれ職場排斥の防止や影響緩和において役割を果たします。各テーマに基づく施策は、排斥の原因や影響に基づいた対策として機能することが期待されています。
職場オストラシズムへの対処方法を整理
職場での排斥に対する対処方法について、研究者たちは個人レベルでの対応策を検討しています[5]。排斥による「目に見えない痛み」への対処に焦点を当てた研究では、資源保存理論に基づいて、排斥がもたらす職務遂行の低下や離職意図の増加、ストレスの増加などへの対応策が検討されています。
研究によると、排斥された従業員は、まず「怒りのコントロール」が重要だとされています。排斥により生じる怒りや攻撃性を制御することが、状況の悪化を防ぐ第一歩となります。攻撃的な行動はさらなる排斥を招く可能性があります。
次に「取り入れ戦略」が挙げられています。他者に好意的な印象を与える行動を取ることで、社会的グループに再び参加しやすくする方法です。例えば、積極的に挨拶をしたり、共通の趣味を共有したりすることが、この戦略の一環となります。
「政治的スキル」の活用も、有効な対処法の一つとされています。職場内の状況を読み取り、効果的にコミュニケーションを取るスキルを指します。適切な言葉や態度を選ぶことで、他者からの受容感を高めることができます。
「自己効力感の向上」も対処法として挙げられています。自己効力感を高めることで、排斥の影響を乗り越える力を得られます。自己効力感が高い従業員は、自信を持って問題解決に取り組めます。
「プロフェッショナリズムの維持」も対処法です。他者からの排斥を無視し、業務に集中することで心理的負担を軽減することができます。排斥の影響を受けにくい小規模な人間関係を築くことも有効です。
最後に、「カウンセリングや相談」の活用が推奨されています。人事部門や専門家に相談することで、問題を客観的に分析し、対処法を見つけるサポートを受けられます。第三者の視点を取り入れることで、感情的な負担が軽減されるだけでなく、対処法を学ぶことができます。
排斥のない職場づくりに向けた指針
職場オストラシズムの研究から得られた知見は、人材マネジメントにおける実践的な含意を持っています。まず、上司のマネジメントスタイルが組織の人間関係に影響を及ぼすことが判明しました。侮辱的管理は、対象となった従業員を直接傷つけるだけでなく、その従業員の職場での孤立を招く可能性があります。
一方で、職場環境における「ユーモア」や「許しの雰囲気」といった要素が、オストラシズムの悪影響を緩和する可能性も明らかになりました。特に、同僚間でユーモアが交わされる職場では、排斥の連鎖が断ち切られやすいことが分かっています。
個人特性の観点からは、自己効力感の高さが排斥への耐性を高めることが判明しました。ただし、この効果は職位によって異なり、高い職位にある従業員の方が、自己効力感を活かして排斥に対処しやすいことも分かりました。
職場オストラシズムへの対処には、個人レベルと組織レベルの両方からのアプローチが必要です。個人レベルでは、怒りのコントロールや政治的スキルの活用、プロフェッショナリズムの維持などが有効でしょう。組織レベルでは、トレーニングと開発、職場文化の醸成、コミュニケーションチャネルの確保などが求められます。
これらの知見は、組織における人材育成や職場環境の整備に新たな視点を提供します。排斥の問題に対しては、個人の努力だけでなく、組織全体での取り組みが必要とされます。職場の雰囲気づくりから、従業員の心理的サポートまで、包括的なアプローチが有効であることが示唆されています。
脚注
[1] Neves, P., and Pina e Cunha, M. (2017). Exploring a model of workplace ostracism: The value of coworker humor. International Journal of Stress Management, 25(4), 330-347.
[2] Wang, L.-m., Lu, L., Wu, W.-l., and Luo, Z.-w. (2023). Workplace ostracism and employee wellbeing: A conservation of resource perspective. Frontiers in Public Health, 10, 1075682.
[3] De Clercq, D., Haq, I. U., and Azeem, M. U. (2019). Workplace ostracism and job performance: Roles of self-efficacy and job level. Personnel Review, 48(2), 400-422.
[4] Mohammad, S. S., and Nazir, N. A. (2023). Practical implications of workplace ostracism: A systematic literature review. Business Analyst Journal, 44(1), 15-33.
[5] Oberai, H. (2021). Exploring the invisible pain of workplace ostracism: Its outcomes & coping mechanism. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(5), 791-796.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。