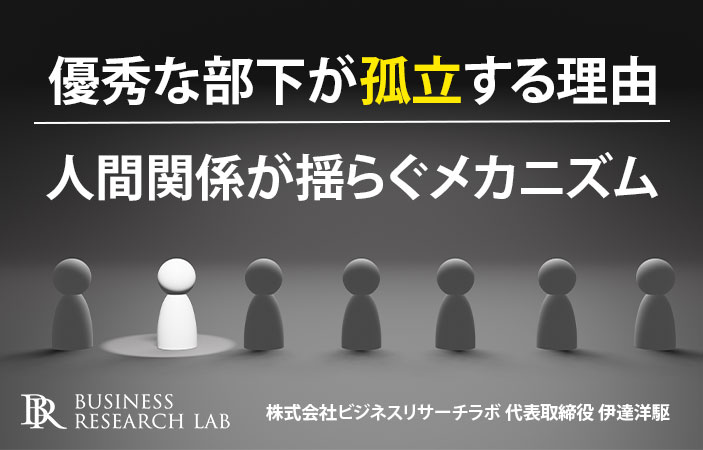2025年3月31日
優秀な部下が孤立する理由:人間関係が揺らぐメカニズム
「今日は昼食、一緒にどう?」「お疲れさま。この件について意見を聞かせてもらえる?」「あとで、みんなでお茶しない?」
こうした何気ない声かけや誘いかけは、私たちの職場生活の中で日常的に交わされています。これらは一見、ささやかな出来事に思えるかもしれません。しかし、こうした交流から継続的に除外されることは、その人の職業人生を変えてしまう可能性があります。
学術研究は、職場における人間関係の質が、従業員の創造性や生産性、そして心の健康に関係があることを明らかにしています。職場での人間関係から排除されることは、個人の能力発揮を妨げるだけでなく、組織全体の活力も低下させる原因となります。
本コラムでは、職場における人間関係から排除されること(オストラシズム)がなぜ起こり、どのような結果をもたらすのかについて考えていきます。働く私たち一人一人にとって、自分自身や周囲の人々との関係を見つめ直す機会となるでしょう。
職場オストラシズムの深刻な代償
職場オストラシズムは、個人と組織の双方に深刻な代償をもたらします[1]。
心理的な影響として、排斥された人は不安やストレス、抑うつ状態に陥りやすくなります。自尊心や職場への所属感が低下し、自分をコントロールできているという感覚も失われていきます。例外的に、性格特性によって抑うつに陥りにくい人もいますが、それは珍しいケースです。実際の調査では、排斥を経験した人の多くが、自分には価値がないという感覚や、周囲から否定されているという感覚を報告しています。
身体的な反応も見逃せません。排斥された人の多くは睡眠の質が低下し、夜中に何度も目が覚めるといった睡眠の断片化に悩まされます。排斥によるストレスが脳の覚醒システムを刺激し続け、リラックスして眠ることを妨げるためです。排斥された出来事を何度も思い返してしまい、心理的に仕事から離れられなくなることも、睡眠障害の原因となります。こうした睡眠の質の低下は、翌日の業務パフォーマンスにも影響を及ぼすことが分かっています。
この影響は職場の枠を超えて、家庭にまで及びます。排斥されることで生じたストレスは、配偶者や子どもとの関係にも悪影響を及ぼします。家族との感情的な摩擦が増え、家庭生活の質が低下することがあります。職場での排斥によって感情的なエネルギーが消耗し、家庭で使える心理的な余裕が減ってしまうためです。研究者たちは、このような仕事から家庭へのストレスの伝播が、家族全体の精神的健康にも影響を及ぼす可能性を指摘しています。
職場における人間関係も変質します。排斥された人は同僚や上司に対する満足感や信頼感を失い、情報共有や助け合いの行動が減少します。チームワークの基盤が損なわれることで、組織全体の機能が低下する可能性があります。排斥された人は他者への情報提供を控えるようになり、それが組織内のコミュニケーションの質を低下させます。
組織への影響は広範囲に及びます。排斥を受けた従業員は離職や欠勤を考えるようになり、生産性が低下します。組織への忠誠心や満足感も失われ、顧客対応や業務パフォーマンスの質が落ちていきます。排斥された従業員が組織に害を及ぼす行動を取るリスクもあります。データの隠蔽や設備の破壊といった行為から、消極的な抵抗(必要最小限の仕事しかしない)まで、様々な形態があります。
悪循環を緩和する要因も、研究によって明らかになっています。個人レベルでは、レジリエンスやポジティブな性格、自己効力感といった特性が、排斥の影響を和らげます。組織レベルでは、上司との良好な関係や社会的なサポート体制が欠かせません。宗教心や伝統的な価値観といった文化的要素も、排斥の影響を軽減する助けとなることが示されています。
排斥によるストレスを軽減する手法として、マインドフルネスの効果も注目されています。定期的にマインドフルネスを実践する人は、排斥による心理的・身体的な影響を受けにくいことが示されています。マインドフルネスが感情制御能力を高め、ストレスへの耐性を強化する効果を持つためと考えられています。
優秀な部下が排斥される理由
職場オストラシズムの発生には、意外な要因が隠れています。部下の能力の高さです[2]。
一般的に、高い能力を持つ従業員は組織にとって価値ある存在とされます。しかし、部下の優れた能力が上司の不安を引き起こし、その結果として排斥につながることがあります。
台湾の様々な業界(製造業、IT、サービス業など)で実施された調査で明らかになりました。上司と部下のペアを対象とした研究では、能力の高い部下を持つ上司が不安を感じ、その不安が排斥行動を引き起こすという関係が確認されています。
上司はなぜ優秀な部下に不安を感じるのでしょうか。社会比較理論が関係しています。人は他者との比較を通じて自己評価を行う生き物です。上司は部下と自分を比較する際、部下の能力が自分を上回っていると感じると、自身の役割や地位が脅かされるのではないかという不安を抱くのです。
この不安は、上司を排斥行動へと駆り立てます。部下との接触を避け、意図的に情報共有を控えたり、会議での発言機会を制限したりするといった行動が見られます。不安を感じる対象を遠ざけることで、心理的な安定を得ようとする自己防衛の現れと言えます。このような排斥行動は、上司の不安が強いほど顕著に表れることが示されています。
排斥された部下は、さまざまな形で反応を示します。職場でのゴシップが増加し、上司へのコミットメントが低下する傾向があります。自分の能力に対する自信も失われていきます。排斥によって心理的な資源(安全感、承認、関係性)が失われ、そのストレスを発散する方法としてゴシップなどの行動が選択されるためです。
研究者たちは、部下の反応にも段階的な変化があることを発見しています。初期段階では、部下は状況を改善しようと建設的な行動を取ることがありますが、排斥が継続すると次第に諦めや抵抗の姿勢を見せるようになります。排斥という経験が、部下の職場における存在意義や自己価値感を徐々に損なっていくためと考えられています。
部下の能力の高さが引き金となって起こる排斥の連鎖は、組織全体に波及します。部下は職場でのネットワークや支援を失い、それがさらなるストレスとなって、職場の人間関係を悪化させていきます。このような状況が長期化すると、組織全体の雰囲気にも影響を及ぼし、他の従業員の働き方やモチベーションにも悪影響を与えるでしょう。
こうした排斥は組織の革新性や創造性を損なう可能性もあります。能力の高い部下が排斥されることで、その知識や技術が組織内で十分に活用されなくなります。他の従業員も自身の能力を発揮することを躊躇するようになり、組織全体の成長が妨げられるかもしれません。
職場オストラシズムを引き起こす要因
職場オストラシズムの発生には、個人の性格、上司のリーダーシップ、職場環境など、様々な要因が関係しています[3]。それぞれの要因について見ていきましょう。
個人の性格特性は、排斥のリスクと関連します。外向的で社交的な人、協調性が高く対立を避ける人、誠実で責任感の強い人は、排斥されにくい傾向にあります。こうした特性を持つ人が積極的に他者とつながり、グループ内での信頼を築きやすいためです。
一方で、神経質で感情が不安定な人は、排斥のリスクが高まります。ネガティブな感情(怒り、嫉妬、罪悪感など)を表出することで、周囲に不快感を与えてしまうからです。自分が排斥されていると過剰に感じやすい認知バイアスも、疎外感を強める要因となります。このような性格特性を持つ人々は、実際の排斥経験がなくても、主観的な排斥感を感じる傾向があります。
学歴や性別といった属性も、排斥のリスクに影響を与えます。学歴が低い人は排斥されるリスクが高く、また男性は女性よりも排斥される傾向があることが分かっています。学歴による排斥は、能力不足や職務への貢献度が低いと見なされることが原因とされます。一方、男性が排斥されやすい背景には、男性特有の競争的・攻撃的な行動パターンが、職場での軋轢を生みやすいことが関係していると考えられています。
上司の存在も大きな意味を持ちます。部下に敵対的な態度を取る上司のもとでは、その部下が職場で孤立するリスクが高まります。上司が自身の権威を保つために部下を排斥し、周囲にも「従うべき態度」を示すことがあるためです。上司の排斥行動を他の従業員が模倣することで、排斥がエスカレートしていく場合もあります。上司の行動は、職場全体の雰囲気や規範に影響を与え、排斥を容認する文化を形成する可能性があります。
反対に、上司との良好な関係は、排斥を防ぐ効果があります。上司が部下を守る姿勢を見せることで、他の従業員もその部下を大切にするようになるのです。上司と部下の良好な関係(LMX:Leader-Member Exchange)が、職場での社会的なサポートを増加させ、排斥のリスクを低減することが明らかになっています。
職場環境、特に社会的なサポート体制の有無も重要です。職場内での支援ネットワーク(友人や協力者)が弱い人は、排斥のリスクが高まります。支援が少ない人は他者との関係を維持する力が弱く、排斥が成功しやすいのです。社会的ネットワークが弱いと、助けを得られず孤立するリスクが増大します。職場での社会的サポートは、排斥による心理的ダメージを緩和する「バッファー」として機能します。
こうした排斥は、被害者の性質によっても異なる形で現れます。「従属的な被害者」は自分を責めやすく、排斥に対抗しないため、加害者にとって低リスクの標的となります。このタイプの被害者が排斥を受けた際、自己非難の傾向が強まり、それが抑うつ症状を悪化させる可能性が指摘されています。
一方、「挑発的な被害者」は行動が集団規範に反するとみなされ、罰として排斥されることがあります。このタイプの被害者は、職場の規範や慣習に従わない独特の行動パターンを示すことがあり、それが他のメンバーの反感を買う原因となります。こうした行動パターンが、職場での人間関係を徐々に悪化させ、最終的に排斥につながるプロセスがあります。
文化的背景も排斥の発生や影響に関係することが分かってきました。例えば、集団主義的な文化では、個人主義的な文化に比べて排斥の心理的影響が強く表れる傾向があります。集団への所属が個人のアイデンティティにとって重要な意味を持つためでしょう。文化的な価値観や規範が、排斥の受け止め方や対処方法に影響を与えます。
職場オストラシズムのメカニズムと影響
職場オストラシズムがどのように発生し、人々の行動に影響を及ぼすのか。そのメカニズムについて、研究者たちはいくつかの理論的枠組みを用いて説明を試みています[4]。
中心となるのが「ニーズ脅威モデル」です。このモデルによると、排斥は人間の基本的な心理的ニーズを脅かすことで、その後の行動や感情に影響を与えます。所属の欲求、自尊心、存在意義の感覚、そして状況をコントロールする感覚という四つの基本的なニーズが関係しています。
排斥を受けた人は、所属の欲求が満たされないことで、積極的に他者とのつながりを求める行動を取ることがあります。失われた所属感を取り戻そうとする自然な反応です。排斥された直後に、人々が他者からの承認を得ようと協調的な行動を増加させることが確認されています。
一方で、コントロール感が脅かされると、攻撃的な行動が増加する可能性があります。失われたコントロール感を取り戻すための一つの手段として、攻撃性が表出されるためです。排斥された人は、無関係な第三者に対しても攻撃的な態度を示すことが分かっています。
感情的な反応も重要です。排斥は即座に強い感情的反応を引き起こします。怒りや悲しみといった感情反応に始まり、その後、不安や恐れといった感情が続きます。これらの感情は、排除された状況を改善しようとする動機づけとなる一方で、過度な感情的反応は建設的な問題解決を妨げます。
認知的な側面も見逃せません。排斥は人々の認知資源を消耗させます。排斥された人は、その経験を繰り返し考え続けることで、他の課題に向ける認知的な余裕を失っていきます。その結果、仕事上のパフォーマンスが低下したり、倫理的な判断が鈍ったりします。
長期的には、排斥は人々の社会的な学習にも影響を与えます。排斥を繰り返し経験することで、人は対人関係に対して防衛的になり、新しい関係を築くことを躊躇するようになります。将来の排斥を予防するための適応的な反応とも言えますが、それによって社会的なサポートを得る機会も失われてしまいます。
職場の人間関係を見つめ直す
職場オストラシズムは、見えにくい形で個人と組織に深刻な影響を及ぼします。本コラムでは、その発生メカニズムを多角的に検討してきました。
興味深いのは、部下の優れた能力が上司の不安を通じて排斥を引き起こすという発見です。組織内の人材育成や評価システムを考える上で示唆を提供します。
また、個人の性格特性や上司のリーダーシップ、職場環境といった多層的な要因が排斥の発生に関与していることも分かりました。これらの要因は相互に影響し合い、複雑な社会的プロセスを形成します。
職場オストラシズムの問題は、表面的な対処だけでは解決できません。組織全体で問題の本質を理解し、適切な対応を考えていく必要があります。それは結果として、生産性の向上だけでなく、従業員一人一人の幸福にもつながるはずです。
脚注
[1] Sharma, N., and Dhar, R. L. (2022). From curse to cure of workplace ostracism: A systematic review and future research agenda. Human Resource Management Review, 32(1), 100836.
[2] Chang, K., Kuo, C.-C., Quinton, S., Lee, I., Cheng, T.-C., and Huang, S.-K. (2019). Subordinates’ competence: A potential trigger for workplace ostracism. The International Journal of Human Resource Management, 32(8), 1793-1817.
[3] Howard, M. C., Cogswell, J. E., and Smith, M. B. (2020). The antecedents and outcomes of workplace ostracism: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 105(6), 583-596.
[4] Mao, Y., Liu, Y., Jiang, C., and Zhang, I. D. (2018). Why am I ostracized and how would I react? A review of workplace ostracism research. Asia Pacific Journal of Management, 35(3), 745-767.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。