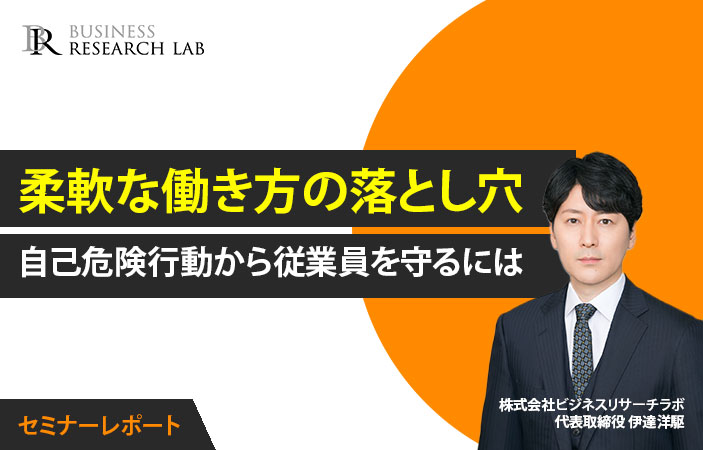2025年3月27日
柔軟な働き方の落とし穴:自己危険行動から従業員を守るには(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年3月にセミナー「柔軟な働き方の落とし穴:自己危険行動から従業員を守るには」を開催しました。
働き方改革が進む中、皮肉にも従業員の健康を脅かす新たな問題が密かに広がっています。それが「自己危険行動」です。
体調不良でも休めない、際限なく残業を続ける、休憩時間を削って仕事をする。一見「仕事熱心」に見えるこれらの行動が、従業員の心身を蝕み、組織の生産性低下やリテンション悪化を引き起こしています。
セミナーでは、自己危険行動の実態とその影響について解説しました。在宅勤務やフレックスタイム制など、柔軟な働き方の広がりが、予期せぬ形で従業員の自己危険行動を助長しています。
従業員の自律性を重視する現代の働き方において、どのように健康リスクを低減し、持続可能な職場環境を築いていけば良いのでしょうか。この機会に、これからの時代に求められるマネジメントのあり方を共に考えましょう。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
近年、私たちの働き方は変化しています。在宅勤務やフレックスタイム制の導入により、多くの人が以前よりも柔軟に仕事を進められるようになりました。時間や場所の制約から部分的に解放され、自分のペースで仕事ができる環境は、一見すると理想的に思えます。
しかし、この柔軟性の高まりは、思わぬ形で私たちの健康に影響を及ぼしているのではないでしょうか。「体調が優れないのに仕事をする」「遅くまで仕事を続ける」「早朝出勤が増える」といった経験をする人がいます。
こうした現象は、研究の中で「自己危険行動」と呼ばれ、一見すると個人の選択のように見えます。ところが、その背景には、柔軟な働き方がもたらす予期せぬ影響が潜んでいます。自由度の高まりは、皮肉にも私たちの健康を損なうリスクを生み出しているのです。
本講演では、研究知見をもとに、自己危険行動が生じる仕組みと、それが私たちの心身に及ぼす影響について探っていきます。また、柔軟な働き方が進む中で、どのように健康を守っていけばよいのか、その方向性についても考えていきます。
私たちは働くために生きているのではなく、生きるために働いているはずです。しかし、時に仕事への責任感や周囲からの期待に応えようとするあまり、この本質を見失ってしまうことがあります。健康的な働き方を実現するためには、自己危険行動の実態を知り、うまく対処することが求められます。
柔軟な勤務形態の副作用
自己危険行動とは、高い業務要求に応えるために、自分の健康を二の次にして働く行動を指します。具体的には、個人的な時間を削って長時間働くことや、休憩を取らずに仕事を続けること、そして体調が悪くても出勤することなどが挙げられます[1]。
例えば、夜遅くまで仕事を続けることで家族との時間や趣味の時間を犠牲にしたり、昼食時間を短縮して仕事のメールに対応し続けたり、発熱や体調不良があっても「仕事が溜まる」「同僚に迷惑をかけられない」と無理をして出勤したりする行動です。さらに、疲労を紛らわすために過度にカフェインを摂取したり、睡眠時間を削って仕事を優先したりするのも自己危険行動に含まれます。
自己危険行動の研究は、柔軟な勤務形態がもたらす予期せぬ副作用を浮き彫りにしています。表面上は働きやすさを促進するはずの制度が、皮肉にも従業員の健康リスクを高める結果につながっているのです。
ここにおける柔軟な勤務形態とは、従業員が仕事の時間や場所を自由に選択できる働き方です。在宅勤務では通勤の必要がなく、自宅という慣れ親しんだ環境で仕事ができます。通勤によるストレスや時間的な制約から解放され、自分のペースで仕事に取り組めるメリットがあります。
フレックスタイム制では、コアタイムを除いて出退勤時間を自由に決められるため、自分のライフスタイルに合わせた働き方が可能になります。朝型の人は早めに出勤して早く帰宅できますし、子育てや介護などの事情に合わせて勤務時間を調整することもできます。
また、ワーケーションのように、リゾート地などで仕事と休暇を組み合わせる働き方も出てきています。これらの柔軟な勤務形態は、従業員の働きやすさやワークライフバランスを向上させる可能性を持っています。
ある研究において、柔軟な勤務形態で働く従業員は、固定的な勤務形態の従業員と比較して、仕事に対する熱意が高いことがわかりました[2]。これは、従業員が仕事に対して強い意欲と責任感を持っていることを表しています。自分の裁量で働ける環境では、仕事への主体性や当事者意識が高まり、仕事への熱意につながっています。
しかし、同時に注目すべき結果も明らかになりました。柔軟な勤務形態で働く従業員は、固定的な勤務形態の従業員と比較して、疲労感や自己危険行動の発生率も高いのです。この一見矛盾する結果は、柔軟な働き方の裏に潜む課題を示しています。仕事に対する熱意の高さは、一方では過度な取り組みへとつながり、その結果、自己危険行動が増加してしまいます。
労働時間の自律性に関する研究からは、興味深い事実が明らかになっています。労働時間の自律性が高い従業員ほど、仕事の過負荷による悪影響が顕著に表れることがわかりました[3]。これは、働く時間を自由に決められる環境が、皮肉にも予想以上の負担をもたらす可能性を示唆しています。
柔軟な働き方は、従業員に自由度を与える一方で、過度な責任感をもたらす要因にもなっています。「自分で時間を決められるのだから、きちんと結果を出さなければ」という意識が働き、必要以上に仕事を抱え込んでしまうのでしょう。
例えば、在宅勤務で通勤時間が不要になった分、仕事時間が延びてしまったり、フレックスタイム制で好きな時間に働けるはずが、夜遅くまで仕事を続けてしまったりする事例があり得ます。また、「自分の裁量で働けるのだから」と周囲からの期待も高まり、それに応えようとしてさらに無理をすることもあります。
固定化される自己危険行動
医療現場の看護師に関する研究は、自己危険行動の特性を理解する上で特に示唆に富んでいます。「患者のため」という意識が強く、自分よりも他者のニーズを優先する看護師は、患者の生命と健康を預かる専門職として、点滴の管理やバイタルサインのチェック、投薬管理などの重要な業務を確実に実施するために、自分の休息を後回しにする傾向があります[4]。
例えば、同僚が急に休んだ場合、自分の休憩時間を削ってでもその同僚の担当患者のケアを引き受けようとします。勤務時間が終わっても、次の勤務者への申し送りが十分でないと感じれば、時間外でも残って情報共有を行おうとするのです。
こうした行動の背景には、強い使命感や同僚からの期待に応えたいという気持ち、そして「自分が頑張らなければ」という責任感があります。看護師たちは、セルフケアの重要性を理解しているにもかかわらず、業務の中でそれを実践することが困難な状況に置かれています。夜勤と日勤の交代制勤務による不規則な生活リズム、急な呼び出し、患者の状態変化への常時の注意など、様々な要因によって十分な休息を取ることが難しいのです。
さらに、利他的な動機が強い人ほど、自己危険行動をとる傾向にあることも複数の研究から明らかになっています[5]。患者の容態が急変した際に休憩時間を返上して対応したり、夜勤明けでも申し送りが不十分と感じれば残って情報共有を行ったりと、他者への思いやりの強さが自己犠牲につながるのです。研究者たちはこの現象を「利他的自己危険行動」と呼び、特に医療や福祉、教育などの対人援助職において顕著に見られると指摘しています。
自己肯定感の問題も、この状況をより複雑にしています。看護師の中には、自分自身の価値や能力に対して自信が持てない人もいます。自己肯定感の低さは、独特な行動パターンを生み出します。他者からの評価や承認を得ることで、自己価値を確認しようとするのです。
例えば、「この人なら頼りになる」と患者や同僚から認められることで、自己価値を感じようとします。「誰よりも患者さんのことを考えている」と評価されることで、自己肯定感を保とうとします。このため、「助けを求められたら断れない」「自分が犠牲になってでも他者のニーズに応えなければならない」という気持ちが形成されます。そして、この気持ちが自己犠牲的な行動をさらに強化していきます。
こうした自己危険行動の背景には、「困っている人を助けたい」「人の役に立ちたい」という使命感があります。医療現場では、このような利他的な価値観が重視され、称賛されます。そのため、利他主義の強い看護師は、この職業的な価値観に共鳴し、時には自分の健康状態や疲労度を無視してでも、患者や同僚のニーズに応えようとするのです。
自己危険行動が問題となるもう一つの理由は、それが組織の中で積極的な対処とみなされることにあります[6]。多くの職場では、締め切りに間に合わせるために残業する、体調不良でも出勤する、休憩時間を削って仕事を進めるといった行動が、「問題解決のための積極的な取り組み」として評価される傾向にあります。
そのため、従業員自身もこうした行動を「望ましい行動」として内面化してしまい、それを継続・強化してしまう悪循環に陥りやすいのです。実際、自己危険行動を繰り返す従業員は、短期的には高い成果を出すことが多いため、管理職からも高く評価されます。しかし長期的に見れば、そうした働き方は持続困難であり、やがて疲弊や健康問題へとつながっていきます。
自己危険行動との付き合い方
自主性と自己危険行動の関係について、ドイツの大学生を対象とした調査では、両者の間にはU字型の関係が存在することが明らかになっています[7]。自主性が低い場合と高い場合の両方で、自己危険行動が高まることが確認されました。
この結果は、自主性は低すぎても高すぎても良くないことを示しています。自主性が低すぎると、自分の意思や判断で行動できず、外部からの圧力や期待に応えようとするあまり、無理をしてしまいます。例えば、教授や上司からの厳しい要求に対して「断れない」と感じ、睡眠時間を削ってでも課題を完成させようとします。
他方で、自主性が高すぎると、責任感から自分にプレッシャーをかけすぎて、健康を犠牲にする選択をしてしまうのです。自分で高い目標を設定し、それを達成するために無理な計画を立て、結果として健康を損なうことになります。
では、ほどほどの自主性とは、どの程度を指すのでしょうか。自分の仕事に関して、ある程度の裁量権を持ちながらも、枠組みやガイドラインが存在する状態が良いでしょう。例えば、仕事の進め方や時間配分について自分で決められる一方で、業務量や期限については組織側が管理しているような環境です。また、自主性を発揮できる範囲が明確で、責任の所在も適切に分散されている状態が望ましいと言えます。
ほどほどの自主性を保つためには、いくつかの方法があります。まず、自分自身の限界を認識し、それを尊重することです。無理な目標や計画を立てず、実現可能な範囲で行動することを心がけましょう。「完璧にこなさなければならない」という考えから離れ、「十分に良い状態」を受け入れる柔軟性も必要です。
また、定期的に自分の状態を振り返り、疲労やストレスのサインを見逃さないようにします。身体の疲れやイライラ、集中力の低下などは、無理をしている証拠かもしれません。そして、必要に応じて周囲に協力を求めることも、健全な自主性の発揮につながります。一人で抱え込まず、上司や同僚、友人や家族に助けを求めましょう。
なお、柔軟な勤務形態において従業員がとる対処行動は、大きく分けて3つのパターンがあることが研究で明らかになっています[8]。
- 1つ目は「問題解決型の対処行動」で、業務上の課題に直面した際に建設的なアプローチを心がけ、上司や同僚に相談したり、仕事の進め方を見直したり、タイムマネジメントを工夫したりします。
- 2つ目は「回避型の対処行動」で、問題から目を背け、締め切りの迫った仕事を後回しにしたり、困難な課題を無視したり、問題の存在自体を否定したりするなど、その場しのぎの対応をとります。
- 3つ目が「自己犠牲型の対処行動」で、これまで説明してきた自己危険行動に該当します。
このうち自己危険行動は、情緒的な疲弊に直結することが実証されています。教師を対象とした研究では、高い労働負荷が自己危険行動を引き起こし、それが情緒的消耗につながるという連鎖が確認されました[9]。
教師たちは増加した労働負荷に対処するために休息時間を削って仕事に充てるようになり、その結果、十分な休息が取れなくなって心身の回復が妨げられます。そして疲労が蓄積され、情緒的消耗が悪化していきます。「労働負荷→自己危険行動→休息不足→心身の疲労蓄積→情緒的消耗の悪化」という連鎖の存在が確認されています。
こうした悪循環を断ち切るためには、問題解決型の対処行動を増やしていくことが重要です。問題解決型の対処行動をとる人々は、心身ともに良好な状態を保ちやすいことが判明しています。その理由として、問題に対して前向きに取り組むことで、ストレスの蓄積を防げることが挙げられます。
では、自己危険行動ではなく問題解決型の対処行動を増やすには、どうすれば良いのでしょうか。業務上の課題や問題を早期に発見し、それに対して具体的な解決策を考える習慣をつけることが大切です。問題が小さいうちに対処することで、後々の大きな負担を防ぐことができます。
一人で抱え込まず、周囲の力を借りることも重要です。上司や同僚に相談することで、新たな視点や解決策が得られることがあります。「助けを求めることは弱さの表れではなく、問題解決のための賢明な選択である」という認識を持ちましょう。
うまく減らすための工夫
他者を助けることは確かに大切な価値観ですが、それを自分の健康を犠牲にしないで行うことが肝心です。自分が健康でなければ、長期的には他者を助け続けることもできません。例えば、医療従事者が自分の体調管理を疎かにして病気になれば、より多くの患者に迷惑がかかってしまいます。自分の健康を守ることは、他者への責任を果たすための前提条件なのです。
チーム全体で「適度に助け合う」文化を築くようにしましょう。特定の人に負担が集中しないよう、皆が互いにサポートし合える環境を整えます。例えば、一人が常に残業して仕事を引き受けるのではなく、チームメンバー全員が状況に応じて柔軟に役割を分担します。誰かが体調不良の時には、他のメンバーがカバーする体制を整えておくことで、無理をして出勤する必要がなくなります。
「休まず働く=責任感がある」という基準を改め、「適切に休むことも仕事」とする価値観の転換も必要です。休息は怠慢ではなく、持続可能な働き方のために必要です。適切に休むことで、集中力や創造性が高まり、生産性の向上につながります。
仕事の合間に短時間の休憩を挟むこともおすすめです。長時間集中し続けることは、脳の疲労を招き、効率の低下につながります。短い休憩時間に、席を立って軽く体を動かしたり、窓の外を眺めたり、深呼吸をしたりすることで、リフレッシュ効果が得られます。たとえわずかな時間であっても、「マイクロブレイク」には大きな効果があります。
おわりに
変化する働き方の中で、私たちは「自己危険行動」という新たな課題に直面しています。柔軟な勤務形態の広がりは、多くの可能性をもたらす一方で、私たちの健康を脅かす隠れた危険も内包しているのです。
自己危険行動は、短期的には「熱心さ」や「責任感」の表れとして評価されることがあります。しかし長い目で見れば、それは心身の健康を蝕み、バーンアウトや離職といった深刻な結果を招きかねません。「休まず働く」「体調不良でも出勤する」といった行動が美徳とされる文化そのものを、私たちは見直す時期に来ているのです。
健康と仕事のバランスを保つためには、個人の意識改革と組織の取り組みの両方が必要です。自分の限界を認識し、休息を取ること。チーム全体で協力し合い、特定の人に負担が集中しない文化を築くこと。これらの取り組みが、健全な職場環境への第一歩となります。
Q&A
Q:自己危険行動のリスクを従業員に伝えていきたいのですが、「頑張りすぎないで」という言い方をすると「頑張らなくていい」というメッセージに誤解されそうです。どのように伝えれば、自己危険行動を効果的に抑制できるでしょうか。
確かに「頑張りすぎると良くない」と言うと、場合によっては、「頑張らなくていいのか」という解釈をされる可能性があります。一つの考え方としては「成果を持続可能な形で出していくために、どう働けば良いか」という問いを提示するのが有効だと思います。短期的な成果だけを重視すると、自己犠牲的な働き方(自己危険行動)でも問題なく成果を出せるかもしれませんが、長期的に継続して成果を生み出すには限界が出てきます。
例えば「短期的に頑張ることは必要だけれど、長く貢献してほしいからこそ、頑張りすぎないでほしい」というメッセージを伝えるということです。会社として長期的に活躍できる働き方を評価したい、という姿勢を打ち出すと「頑張りすぎないで」と言われても「サボっていい」という意味だとは受け取りにくくなると思います。要するに「頑張らない」わけではなく、「長い目で見て効率的かつ効果的に働く」という方向性を示すことが大切です。
Q:自己危険行動は、業種によって発生頻度に差があるものでしょうか。例えば営業職と事務職ではどうでしょうか。
今回ご紹介した研究の範囲で言えば、医療・福祉・教育など、いわゆる対人援助職において、利他的な動機から生じる自己危険行動が見られると言えます。対人援助職は特に注意が必要でしょう。
ただし、発生頻度だけでなく、自己危険行動の「現れ方」が職種によって異なる可能性があります。例えば営業職において成果が比較的明確であれば、残業や休日出勤をしてでも成果を出そうとする行動が起きるかもしれません。事務職の場合、締め切りに間に合わせるために休憩を取らない、あるいは食事を抜いてしまうなど、健康面にリスクを伴う行動が起こるかもしれません。
いずれも本来必要な休息を削ってまで仕事を優先してしまう点では同じ「自己危険行動」ですが、その具体的な形は職種や業界によって異なると考えられます。
Q:利他的な価値観が自己危険行動につながるというのは意外でした。利他的な動機を持ちながらも、健全な働き方を促すにはどうしたらいいですか。
利他的な動機自体は基本的に良いことでしょう。誰かの役に立ちたいという思いを否定する必要はありません。ただし、そこに「持続可能性」という時間軸を導入する視点が重要ではないでしょうか。短期的には無理がきくかもしれませんが、燃え尽きてしまえば長期的に誰も助けられなくなり、利他的な行動を続けることができなくなってしまいます。
例えば、医療従事者が十分に休息を取ってこそ、安全で質の高いケアを継続的に提供できるといった例があります。休みを取らなかったり、過度に無理をしたりすると、長い目で見れば自分も周りも助けられなくなります。「利他的でありたいからこそ、休息を確保して持続可能な働き方をしよう」というメッセージが有効だと思います。
Q:部下が自己危険行動をとっているとき、管理職はどのようにアプローチすべきでしょうか。「心配している」と伝えても「大丈夫です」と言われてしまうことが多いのですが。
部下の側からすれば、「大丈夫です」と言ってしまうのは自然な反応かもしれません。「あなたのことが心配だ」と個人的に伝えるだけでは、相手にとっては具体的にどうすればいいかわからず、逆に気を遣わせてしまう場合もあるでしょう。そこで考えられるアプローチとしては、「個人」ではなく「チーム」の視点を導入することです。
例えば、「チームとしてパフォーマンスを高めるために、お互いが持続的に働ける仕組みや休息の取り方を一緒に考えませんか」という呼びかけ方をすると、本人も前向きに捉えやすくなるかもしれません。また、管理職自身が休息を重視した健全な働き方を実践し、その経験を率直に共有するのも大切だと思います。「実際に休みをきちんと取るようにしてから、パフォーマンスが上がりました」という具体例があれば、部下も納得しやすいでしょう。
脚注
[1] Dettmers, J., Deci, N., Baeriswyl, S., Berset, M., and Krause, A. (2016). Self-endangering work behavior. In M. Wiencke, S. Fischer, & M. Cacace (Eds.), Healthy at Work: Interdisciplinary Perspectives (pp. 37-51). Springer International Publishing.
[2] Yokoyama, K., Nakata, A., Kannari, Y., Nickel, F., Deci, N., Krause, A., and Dettmers, J. (2022). Burnout and poor perceived health in flexible working time in Japanese employees: the role of self-endangering behavior in relation to workaholism, work engagement, and job stressors. Industrial health, 60(4), 295-306.
[3] Mander, R., and Antoni, C. H. (2022). Work overload and self-endangering work behavior: The amplifying and buffering role of work autonomy and self-leadership. Zeitschrift fur Arbeits- und Organisationspsychologie A&O, 66(3), 123-135.
[4] Eder, L. L., and Meyer, B. (2022). Self-endangering: A qualitative study on psychological mechanisms underlying nurses’ burnout in long-term care. International Journal of Nursing Sciences, 9(1), 36-48.
[5] Eder, L. L., and Meyer, B. (2023). The role of self-endangering cognitions between long-term care nurses’ altruistic job motives and exhaustion. Frontiers in Health Services, 3.
[6] Dettmers, J., Deci, N., Baeriswyl, S., Berset, M., and Krause, A. (2016). Self-endangering work behavior. In M. Wiencke, S. Fischer, & M. Cacace (Eds.), Healthy at Work: Interdisciplinary Perspectives (pp. 37-51). Springer International Publishing.
[7] Mulder, L. M., Deci, N., Werner, A. M., Reichel, J. L., Tibubos, A. N., Heller, S., … & Rigotti, T. (2021). Antecedents and moderation effects of maladaptive coping behaviors among German university students. Frontiers in Psychology, 12, 645087.
[8] Deci, N., Dettmers, J., Krause, A., and Berset, M. (2016). Coping in flexible working conditions? Engagement, disengagement and self-endangering strategies. Psychology of Everyday Activity, 9(2), 49-65.
[9] Baeriswyl, S., Krause, A., and Mustafic, M. (2021). Teacher’s emotional exhaustion: Self-endangering work behavior as novel concept and explanatory mechanism. Clinical Psychiatry, 7(3), 96.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。