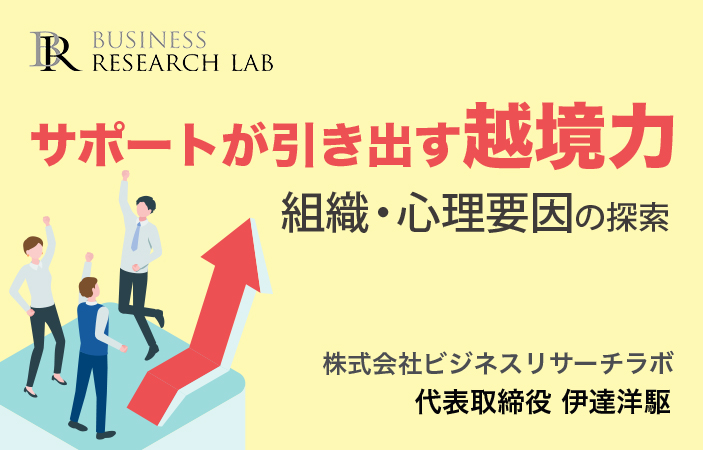2025年3月27日
サポートが引き出す越境力:組織・心理要因の探索
境界を越える力の重要性は高まるばかりです。環境が急速に変化し、不確実性が増大する現代において、組織やチームの境界を超えて外部と関係を構築し、情報やリソースを交換する「バウンダリー・スパニング」は、これまで以上に求められています。
例えば、医療現場では、患者の多様なニーズに応えるため、看護師が診療科を越えて連携を図る必要があります。企業の新製品開発では、研究開発、製造、マーケティングなど、異なる部門の知識を統合することが不可欠です。大学は地域社会と協働し、研究成果を社会に還元することが期待されています。このように、バウンダリー・スパニングは、様々な組織で日々実践されています。
しかし、組織の壁を越えることは容易ではありません。異なる価値観や文化を持つ相手と関係を築き、時には対立を乗り越えて協力を実現しなければなりません。個人にとって、この活動は挑戦となり得ます。心理的な不安や抵抗を感じることもあるでしょう。
本コラムでは、バウンダリー・スパニングを促進する要因と阻害する要因について考察します。組織の境界を越える行動について、個人の特性や組織の環境がどのように関係しているのか、そして実際の職場でどのように活用できるのかを探っていきます。日々の業務に追われる中で、私たちはどのようにして境界を越える力を発揮できるのでしょうか。
組織・同僚・上司からのサポートが大事
医療現場における実証研究から、組織や上司、同僚からのサポートがバウンダリー・スパニングを促進することが明らかになっています。ベルギーの病院で実施された調査では、看護師を対象に、サポートと境界を越える行動の関係を分析しました[1]。
この調査では、看護師の行動を3つの側面から検討しています。
- 1つ目は、組織のイメージやサービスを外部に広める「外部代表性」です。病院の理念や取り組みを患者やその家族に伝え、信頼関係を築く活動が含まれます。
- 2つ目は、職場内でのサービス改善提案などの「内部からの働きかけ」です。患者ケアの質を高めるため、部門を越えて新しいアイデアを提案し、実現に向けて調整を行います。
- 3つ目は、柔軟で丁寧な患者対応を行う「サービス提供」です。患者一人ひとりの状況に応じて、通常の業務範囲を超えた対応を行うことも含まれます。
分析の結果、組織からのサポートは、看護師の組織への感情的なつながりを強めることで、境界を越える行動を引き出すことが分かりました。組織が看護師の貢献を認め、福利厚生を充実させることで、看護師は「この組織のためにもっと貢献したい」という気持ちを抱くようになります。感情的なつながりが、業務の枠を超えた積極的な行動につながるのです。
同僚からのサポートは、二つの経路で行動を促進します。一つは、チームへの帰属意識を高める経路です。同僚との良好な関係を通じて、「このチームの一員である」という意識が強まり、チームの目標達成に向けて行動するようになります。もう一つは、心理的な安心感を与える経路です。同僚からの支援があると、困難な場面でも自信を持って行動できるようになります。
上司からのサポートは、感情的なつながりを介さず、直接的に行動を促進する効果があります。上司の支援が日々の業務において即効性のある助けとして認識されるためです。上司からのポジティブなフィードバックや助言は、看護師の行動意欲を高めます。
これらの結果は、サポートの提供者によって、異なるメカニズムで行動が促されることを表しています。組織からのサポートは長期的な関係性を築き、看護師の自発的な行動を引き出します。同僚からのサポートは、チームの一体感と心理的な安全性を高めます。上司からのサポートは、直接的な指導や支援を通じて、具体的な行動を促します。
病院という特殊な環境で得られたこれらの知見は、他の組織にも応用可能でしょう。組織、同僚、上司という三つのレベルでのサポートを適切に組み合わせることで、より効果的にバウンダリー・スパニングを促進できると考えられます。
タスクや組織の不確実性が自ずと促す
米国の農業関連バイオテクノロジー企業で実施された調査からは、タスクの性質や組織の状況が、バウンダリー・スパニングを促すことが明らかになりました。この調査では、研究チームメンバーにインタビューを行い、チーム間の連携がどのように生まれるのかを分析しています[2]。
調査では、タスク特性、チームレベルの要因、組織的な文脈という三つの視点から分析が行われました。まず、タスク特性として、チーム間の依存度が高い場合に、情報共有や連携が活発になることが分かりました。例えば、製品開発チームが法律の専門家チームから規制情報を得る必要がある場合、自然と両者の間で連携が生まれます。また、製品の安全性評価には、毒性試験チームと臨床試験チームの協力が不可欠です。このように、タスクの相互依存性が高まると、チームは否応なく連携を深めることになります。
タスクの不確実性も連携を促します。答えが一つではなく、状況に応じた柔軟な対応が求められる場合、外部の知識やリソースを求める機会が増加します。新規市場向けの製品開発では、その市場の規制や消費者ニーズの把握が必要となり、外部との連携が不可欠になります。また、新しい技術を用いた製品開発では、予期せぬ技術的課題が発生する可能性があり、様々な専門家の知見を統合する必要があります。
チームの発展段階も、外部との連携に影響を及ぼします。プロジェクトの初期段階では、目標設定や計画立案のために幅広い情報収集が必要です。実行段階では、具体的な課題解決のために専門家の協力を仰ぐことになります。評価段階では、成果の検証や改善点の特定のために、外部の視点を取り入れることが求められます。
チームレベルの要因として、リーダーの活動が重要な役割を果たします。リーダーは組織内でチームの活動を可視化し、必要なリソースを確保します。経営陣への報告やプレゼンテーションを通じて、チームの成果や課題を共有し、支援を取り付けます。また、他のチームとの調整や交渉を行い、スムーズな協力関係を築きます。
チームの多様性も、外部との連携を促進します。メンバーが異なる分野のバックグラウンドを持っている場合、知識の幅が広がり、他チームとの交流やコラボレーションが容易になります。製造業務とマーケティングの経験者が同じチームにいることで、多方面の外部関係を構築しやすくなります。異なる視点を持つメンバーがいることで、チーム内で活発な議論が生まれ、より創造的な解決策を見出すことができます。
組織的な文脈も、バウンダリー・スパニングに影響を及ぼします。組織内のリソース不足や不確実性は、外部との連携を促進します。リソースが限られている場合、チームは上層部と交渉し、必要なリソースを確保しようとします。例えば、予算が削減される中で、研究チームがトップマネジメントに直接アピールして追加予算を得るような状況です。市場環境の変化が激しい場合、他部門との情報共有や協力が不可欠になります。
組織内の協力文化や競争の度合いも、チーム間の関係性に影響を与えます。協力的な文化が根付いている組織では、部門間の壁が低く、自然と情報やリソースの共有が行われます。一方、競争が激しい文化では、部門間の対立や情報の囲い込みが起こりやすく、連携が妨げられることがあります。
これらの知見は、バウンダリー・スパニングが個人やチームの意思だけでなく、タスクや組織の特性によっても促進されることを示しています。特に、不確実性や相互依存性が高い状況では、外部との連携は避けられない必要条件となります。組織はこうした状況を認識し、適切な支援体制を整えることが求められます。
アタッチメント不安が阻害要因になる
個人の心理特性、特にアタッチメント(愛着)の特徴が、バウンダリー・スパニングを妨げる可能性があることが、中国の新製品開発プロジェクトを対象とした調査で明らかになりました。この調査では、多くのチームを対象に、個人の心理特性と境界を越える行動の関係を分析しています[3]。
アタッチメント不安とは、他者に拒絶されることや受け入れられないことを過剰に心配する傾向を指します。この特性を持つ個人は、外部との関わりを伴う活動に対して「失敗したらどうしよう」「評価されないかもしれない」といった恐怖心を抱きやすく、行動が抑制されます。新しい関係を築くことや、不確実な状況に身を置くことに強い不安を感じるため、境界を越える活動に消極的になってしまいます。
調査では、アタッチメント不安と行動の関係を検討しました。その結果、アタッチメント不安が強い個人は、他者からの承認を過度に求める傾向があり、それが逆効果となることが分かりました。承認欲求が強すぎるために、失敗を恐れて挑戦的な行動を避けるのです。他者の反応に過敏になり、わずかな否定的な反応でも打撃を受けてしまいます。
アタッチメント回避も、バウンダリー・スパニングを妨げます。これは、他者やチームへの不信感が強く、他人に頼ることや連携することを避ける傾向です。この特性を持つ個人は、外部との関係を築く行動に消極的になります。他者との深い関係を避けようとするため、表面的なコミュニケーションに終始し、実質的な協力関係を築くことができません。
調査では、これらの特性が自己効力感(自分には能力があるという自信)を低下させ、それが境界を越える行動の減少につながることも分かりました。アタッチメント不安の人は、過度に他者からの承認を求めるあまり、自己評価を下げがちです。「自分にはできない」という否定的な思い込みが、新しい挑戦を妨げます。アタッチメント回避の人は、他者との関係を信頼せず孤立的に振る舞うため、外部との連携を必要とするタスクへの自信を持てません。
組織の支援的な環境は、アタッチメント不安による行動の抑制を和らげる効果があります。支援的な環境では、失敗を恐れず挑戦できる雰囲気が醸成され、個人の心理的な安全性が確保されます。上司や同僚からの励ましや支援は、不安を抱える個人の自信を高め、行動を促進します。
しかし、アタッチメント回避に対しては、支援環境の効果はほとんど見られません。これは、アタッチメント回避の人が組織の支援を価値あるものとして受け取れないためと考えられます。他者との関係性を避ける傾向が強いため、どんなに支援的な環境が整っていても、その価値を認識できないのです。むしろ、過度な支援は彼らの独立性を脅かすものとして認識され、より強い回避行動を引き起こす可能性があります。
これらの知見は、個人の心理特性に応じた異なるアプローチの必要性を示唆しています。アタッチメント不安の高い個人に対しては、段階的な挑戦の機会を提供し、小さな成功体験を積み重ねることが効果的です。失敗しても受け入れられる環境を整え、自己効力感を高めていく支援が求められます。
一方、アタッチメント回避の高い個人に対しては、まず信頼関係の構築から始める必要があります。押しつけがましい支援は逆効果となるため、個人の自律性を尊重しながら、徐々に協力関係を築いていくアプローチが望ましいでしょう。
コミュニティの文脈でどう測定するか
バウンダリー・スパニングは、大学と地域社会の連携においても重要な役割を果たしています。米国の調査では、大学とコミュニティをつなぐ役割の人々の行動を測定する手法が開発されました[4]。この研究は、目に見えにくい境界を越える活動を、具体的な指標として可視化することを目指しています。
この研究では、4つの行動特性に注目しています。1つ目は、プロジェクト管理や課題解決などの「技術的・実務的志向」です。これには、具体的な成果物の創出やプロセスの設計、問題解決のための方法の開発などが含まれます。担当者は、限られた資源を効果的に活用し、具体的な成果を生み出すことが求められます。
2つ目は、他者の成長や信頼関係の構築を重視する「社会・感情的志向」です。この特性は、人々の潜在能力を引き出し、互いの信頼関係を深める活動を指します。メンバーの成長を支援し、チームワークを促進する役割が含まれます。また、コミュニケーションの障害を特定し、解決することも重要な任務です。
3つ目は、地域社会のニーズを理解し対応する「コミュニティ志向」です。この特性を持つ人は、地域社会の声に耳を傾け、その期待や要望を理解することに長けています。単なる理解にとどまらず、解決策を提案し、実行に移す能力も求められます。また、コミュニティの利益を代表して、組織内外で発言する役割も担います。
4つ目は、組織の目標や利益を優先する「組織志向」です。この特性は、所属する組織のミッションや戦略を理解し、それに沿った行動を取ることを意味します。組織のリソースを活用してコミュニティに貢献する方法を考案したり、組織の専門知識を外部パートナーと共有したりする活動が含まれます。
調査票の開発では、194の質問項目から、最も関連性が高く重複のない32項目が選ばれました。この過程では、各項目の意味が明確で、測定したい特性を適切に反映しているかが慎重に検討されました。また、回答者の負担を考慮し、できるだけ簡潔な表現が用いられています。
これらの項目は、行動がどの程度頻繁に行われるかを測定します。たとえば、「コミュニティのニーズを理解し、それを満たす方法を模索する」「組織の利益を促進するための施策を提言する」といった行動の頻度を評価します。このように、抽象的な概念を具体的な行動レベルで測定することで、より正確な評価が可能になりました。
調査ではまた、回答者の属性や役割による回答パターンの違いも分析されました。大学教員、行政職員、地域活動家など、異なる立場の人々が、それぞれどのような行動特性を持つのかが明らかになりました。これによって、役割に応じた効果的な支援策を検討することができます。
調査の結果、この測定手法は高い信頼性を持つことが確認されました。各特性を測定する項目群の内部一貫性が高いことが分かりました。これは、この測定手法が科学的な分析ツールとして使用できることを意味します。
ただし、「コミュニティ」の定義に混乱が見られることも分かりました。コミュニティが地理的な地域を指すのか、特定の興味や関心で結びついたグループを指すのかが不明確だったためです。この課題に対応するため、調査実施時には「コミュニティ」の定義を明確に示す必要があります。
この測定手法の特徴は、その柔軟性にあります。大学教員や地域リーダー、ボランティアなど、異なる文脈での測定が可能です。また、測定結果を基に、個人やチームの強みと弱みを特定し、対象に合わせた支援を提供することができます。
脚注
[1] De Regge, M., Van Baelen, F., Aerens, S., Deweer, T., and Trybou, J. (2020). The boundary-spanning behavior of nurses: The role of support and affective organizational commitment. Health Care Management Review, 45(2), 130-140.
[2] Joshi, A., Pandey, N., and Han, G. H. (2009). Bracketing team boundary spanning: An examination of task-based, team-level, and contextual antecedents. Journal of Organizational Behavior, 30(6), 731-759.
[3] Li, F., Liang, X., and Liu, Q. (2022). Applying attachment theory to explain boundary-spanning behavior: The role of organizational support climate. Journal of Work and Organizational Psychology, 38(3), 213-222.
[4] Sandmann, L. R., Jordan, J. W., Mull, C. D., & Valentine, T. (2014). Measuring boundary-spanning behaviors in community engagement. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 18(3), 83-104.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。