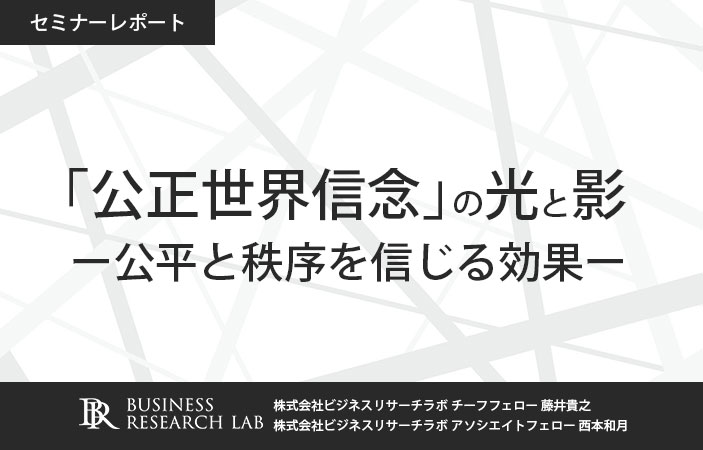2025年3月26日
「公正世界信念」の光と影:公平と秩序を信じる効果(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年2月にセミナー「公正世界信念の光と影:公平と秩序を信じる効果」を開催しました。
近年のビジネス環境は、仕事もそれに関わる人間も多様化し、変化のスピードが加速しています。創造性や進歩の可能性が広がる一方で、予測が難しい状況も増えてきています。
業界や会社がどのような方向に進むのかが不確実な状況は、従業員にとってストレスの原因となることがあります。しかし、不確実性が高い中でも秩序や予測可能性を感じられることで、希望や安心感を持って仕事に取り組むことが可能になります。
その鍵の一つとなるのが、「公正世界信念」です。これは、世界は公平であり、人は自分の行動に応じた結果を手に入れることができるという考え方を示す概念です。
本セミナーでは、「公正世界信念」が個人や組織にもたらす影響について研究知見をもとに解説しました。公正世界信念を持つことで、人は秩序や安定感を感じやすくなり、予測が難しい環境においても自信を持って行動できるようになります。
一方で、公正世界信念は差別などのネガティブな側面との関係も指摘されています。この概念が持つ潜在的なリスクとその対策についてもご紹介しています。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
公正世界信念とはどのような考え方か
[西本]
公正世界信念とは、「世界は基本的に公正であり、人々は自分の行動に対して当然の報いを受ける」という考え方です。公正世界信念が高い人は、さまざまな出来事は偶然に起こるのではなく、世界には秩序があって、出来事には意味があると信じます。
努力すれば報われると信じる傾向があるため、仕事や人生において、誠実に努力すれば良い結果が得られ、手を抜けば失敗すると考えるのです。
公正世界信念が信念をもつ個人に与えるポジティブな影響
公正世界信念が個人にもたらすポジティブな影響の一つとして、キャリアの先行きが不安な状況に直面しても、前向きでいられるということが研究で示されています。
教員養成課程の学生に対して、少子化とそれに伴う教職のキャリア見通しの悪化に関する文章を読んでもらい、その後に気分を測定した研究[1]があります。予測できない状況に耐える力が弱い人は、「怒り」や「絶望感」というネガティブな感情が高くなってしまうのですが、公正世界信念が高い場合には、怒りや絶望的な気分が少なく、ポジティブな気分を経験しやすくなるという結果が出ています。
この結果は、公正世界信念はネガティブな状況が、感情に与えるネガティブな影響を緩和する緩衝材としての役目を果たすということを意味します。同じ研究で、悪い状況にいる場合だけでなく、予測できない状況に強い人が明るいキャリアの見通しがあるというストレスのない良い状況についても検討されています。公正世界信念が高い人はよりポジティブな気分が促進されるという結果が示され、公正世界信念は悪い状態を緩和するだけのものではなく、良い状態の効果をさらに大きくするための資源にもなるといえます。
また、公正世界信念が高い人は、身体の健康面にも良い影響を受けることが示されています。理不尽な出来事(犯罪被害や不当な解雇など)に直面した際、公正世界信念が高い人ほど、身体の炎症レベルや代謝リスク、睡眠リスクが低いという結果が得られています[2]。
公正世界信念が高い人は、出来事に意味があると考えます。理不尽で嫌な出来事も、ただストレスなものとして終わりにしてしまうのではなく、意味を見出す傾向があるのです。
「嫌な出来事ではあったけれど、自分の人生にとって意味のある必要なことだった」などと、適応的な考えや行動につなげていけることが、身体的な健康と関連してくると考えられます。
公正世界信念が周囲に与えるポジティブな影響
公正世界信念が周囲に与えるポジティブな影響として、組織市民行動を促進することが挙げられます。組織市民行動とは、正式な就業規則で義務付けられていなくても、組織にとって有益であり、組織の発展を促すような職場環境を作り出すための行動です。困っている同僚がいたら自発的に手伝ったり、求められている以上に丁寧に仕事をこなすといった行動が組織市民行動にあたります。
公正世界信念の高さと組織市民行動を行う意欲との関係を調べた研究では、公正世界信念が高いと組織市民行動への意欲も高くなるという結果が示されました[3]。正式な就業規則で義務付けられていなくても、組織にとって有益であり、組織の発展を促すような職場環境を作り出すための行動が、仕事においてより多くのサポートを受けたり、仕事の質や効率を向上させ高い評価を受けたりするといった、良い結果につながると公正世界信念が高い人は考え、組織市民行動への意欲が高くなるのです。
公正世界信念には他にも、本人に責任がない問題で苦しんでいる人への援助行動を促進するというポジティブな影響があります。病気になった人を援助するかどうかということを調べた研究では、公正世界信念が高い人は低い人に比べ、本人の行動には問題がないのに、遺伝子の異常が原因で病気になってしまった人を援助しようという傾向がより強いということが示されています[4]。
本人が健康に悪い行動をとっていないのに病気になってしまうという状況は、世界は公正で、人は自分の行動の報いを受けるという信念を脅かす状況です。公正さを回復するために、ボランティア活動や寄付など、無実の人への援助行動が促進されると考えられます。
公正世界信念が高い人は、ただ親切なだけでなく、自分ではどうしようもなく、切実に他者の助けを必要としている人に手を差し伸べることができると考えられます。
公正世界信念は、この信念を高くもつ人自身の精神的・身体的健康にも、周囲の人と助けあって良好な職場環境をつくることにもつながる信念であると言えます。
公正世界の信念が生み出す歪み
[藤井]
このパートでは、公正世界信念が強い場合に、組織や職場ではどのような問題が生じる可能性があるのかを解説します。
一つ目の問題として、信念に基づく正当化が行われることに注目します。例えば、他者に責任を押し付ける形で原因を帰属したり、自分自身の問題行動を正当化したりすることがあります。こうした行動は職場でのコミュニケーションやチームワークに悪影響を及ぼす可能性があります。
二つ目の問題として、改善行動が妨げられる可能性に注目します。職場や組織の改善を進めようとする際に、変革に対して抵抗を示したり、プロジェクトや計画の変更・改善に消極的になったりすることがあります。
信念に基づく正当化
ここでは「信念に基づく正当化」について解説します。
まず、公正世界信念とは「世界は公正である」という思考ですが、この信念の強さは、認知バイアスとも関連していることが示唆されています。
例えば、「ハロー効果」と呼ばれる認知バイアスがあります。これは、ある対象の目立つ特徴や印象が、他の評価にも影響を及ぼす現象を指します。公正世界信念にも似た傾向があり、「良い人には良いことが起こるはずだ」といった考え方につながります。ただし、学術的には、公正世界信念と認知バイアスは区別されています。
公正世界信念の特徴として、比較的安定しており、個人の価値観に近い点が挙げられます。一方、原因帰属のバイアスは特定の状況判断に影響を与え、状況や文脈によって変わりやすいものです。公正世界信念は、個別の事象ではなく、より広範囲の世界観に関わるため、影響範囲が大きいと考えられます。
続いて、公正世界信念が強い場合、否定的な出来事をどのように解釈するかについて考えてみます。公正世界信念に限らず、信念に基づいて思考を進めると事実に基づかない思考が生じることがあり、これが他者との間で見解の相違を引き起こす可能性があります。
ここで、公正世界信念が強い人々が不公正な状況に直面した際の反応について、研究結果を紹介します。特に注目すべきは、「他者への原因帰属」という視点です。
他者への原因帰属
研究によると、公正世界信念が強い人ほど、不当に被害を受けた人に責任を帰属する傾向があることが示されています[5]。これは、認知的不協和の解消が関係していると考えられます。認知的不協和とは、自分の価値観と現実が矛盾したときに生じる不快感のことで、この不快感を解消するために正当化が行われる可能性があります。
例えば、公正な世界を信じる人にとって、不当な被害を受けている人の存在は、その信念を揺るがすものになります。この矛盾を解消するために、「被害者にも何らかの落ち度があったのではないか」と考えてしまうのです。このような正当化の過程には、差別や偏見を助長する懸念があります。
特にマイノリティに対する偏見を強化する可能性があります。例えば、差別を受けている人に対して「そのような扱いを受ける理由がある」と考えたり、「社会はすでに公正だから、差別は存在しない」と認識することで、問題が見過ごされたり無視される危険性があります。それが職場や組織においては、風土や文化の形で差別や偏見を容認する雰囲気を生み出し、改善されなければ定着してしまう可能性があります。
自分の問題行動の正当化
また、公正世界信念が強いことで、自分の問題行動を正当化する傾向も示唆されています。例えば、ハラスメントの加害者が「被害者にも問題がある」と自らの行動を正当化することが考えられます。このような考えが広がると、職場の心理的安全性が低下し、問題提起がしにくくなるという懸念もあります。
こうしたリスクを踏まえ、公正世界信念の強さが他責的な考え方や行動に結びつく場合には、適切な対策が必要になります。
公正世界信念には、自分の置かれた状況を受け入れやすくなり、ストレスを軽減するといったポジティブな側面があります。しかし、その信念が他者への責任転嫁や問題行動の正当化につながる場合には、注意が必要ということです。
対策の一例として、事実に目を向けることが重要です。主観的な認識に対し、客観的なデータを示すことで、誤った認識を修正する一助となります。また、評価に関する偏りを防ぐために、成果だけでなく、努力やプロセスを可視化し、評価の対象とすることも対策の一つです。さらに、ダイバーシティ施策への反感に関しては、「社会はすでに平等である」といった思い込みを正すために、昇格率の違いなどのデータを提示することで、現実の状況を正しく理解してもらうことが有効です。
以上の点を踏まえ、公正世界信念の影響を適切に理解し、職場や組織における問題を防ぐための対策を検討することが重要です。
改善行動を妨げる
ここからは、「改善行動を妨げる要因」について解説します。改善行動は組織に変革をもたらすものですが、公正世界信念が強いことで抵抗につながる場合があります。
変革への抵抗
公正世界信念が変革への抵抗につながる理由として、「既に公平に運用されているはずだから、変える必要がない」という思考が指摘されています[6]。公正世界信念が強いと、現状を正当なものと見なす傾向が強くなります。これはシステム正当化とも密接に関連し、特に、伝統的な手法や既存のやり方を維持しようとする心理が働くことが知られています。その背景には、「安心できる現状を維持したい」という心理があると考えられます。
まず、システム正当化について説明します。システム正当化とは、「現状の制度やシステムは正当である」と合理化する傾向のことを指します。これは、現状を肯定することで心理的な安心感を得るという側面があります。また、この傾向が強い人は幸福感が高いという研究結果もあります。つまり、安心できる環境にあることで幸福感が高まるため、変革の動きがあると、その安心感を手放すことへの抵抗が生じる可能性があります。
例えば、多様性に配慮する制度を導入しようとする際に、「現状はすでに公平なのだから、特別な支援を設けることは不公平なのではないか」という考えが生じることがあります。このような思考が改善行動を妨げる可能性があります。
改善を妨げる正当化の一例として、「システムに問題はない」と前提することで、個人の努力不足に原因を求めるケースが挙げられます。例えば、プロジェクトの失敗に対して「プロジェクトを進めた本人の努力不足が原因だ」と考えてしまい、システムの問題点には目を向けないといった事例です。このように、個人の責任に帰属させることで、組織の改善の機会が損なわれる可能性があります。
また、ハラスメントの被害者に対しても、「被害者に何らかの落ち度があったのではないか」という思考が働くことがあります。これは、現状が正当であると考えるあまり、加害者の行動を問題視せず、被害者側に原因を求める傾向です。このような思考が、差別や格差の是正に対する抵抗につながる可能性があります。
ただし、公正世界信念が高いからといって、必ずしも不平等や格差を正当化するわけではありません。例えば、所属する組織に対して「この組織は問題を改善できる」と認識している場合、不平等を正当化する傾向が低くなるという研究結果もあります[7]。つまり、改善が期待できる環境では、公正世界信念が必ずしも変革の妨げにならないということです。
低いリスク認識
また、計画の見直しに対する抵抗も、公正世界信念が影響を及ぼすことがあります。例えば、「ここまで投資したのだから成功するはずだ」と考えてしまうサンクコスト効果と関連がある可能性があります。この考え方は、「努力すれば報われる」という信念と結びつきやすく、不合理な意思決定につながることがあります。
例えば、すでに多くの資金や時間を投じたプロジェクトがうまくいっていない場合でも、「ここまでやったのだから、このまま続ければ良い結果が得られるはずだ」と考え、改善策を検討せずに継続してしまうといったケースが考えられます。
このような判断の非合理性については、研究知見からも示唆されています[8]。例えば、公正世界信念が高い人は、バイアスの影響を受けやすいことが指摘されており、論理的な情報処理を行う傾向のある人ほど、公正世界信念が低いという研究結果もあります。このことから、公正世界信念に基づく判断には、非合理な側面が含まれることが示唆されます。
リスクマネジメントの観点から考えると、公正世界信念に基づく意思決定は、事実ではなく信念に基づくため、リスクを過小評価する可能性があります。例えば、「頑張っている私に悪いことが起こるはずがない」や「当社は優良企業だから不祥事など起こるはずがない」といった思考が、潜在的なリスクを軽視する要因となり得るのです。このようなリスクを防ぐためには、データや客観的な指標を用いてリスクを可視化し、合理的な判断を促すことが重要です。
最後に、対策の例を挙げます。一つ目のパートとも共通する点として、客観的な評価や視点を取り入れることが重要です。例えば、システムの改善を拒む際に「うまくいっていないのは本人のミスが原因だから、システムには問題がない」と考えてしまうケースでは、客観的なデータを活用し、システムに本当に問題がないのかを評価することが必要です。
また、失敗が見えている計画を途中で中止できないといった事態に陥らないように、事前に数値基準を設定し、一定の基準を満たさない場合には撤退するといった仕組みを導入することが有効です。感情的な判断ではなく、データや事実に基づいた合理的な意思決定を促すことで、リスクを低減することができます。
さらに、差別的な慣習が問題視されない環境では、組織の内外で価値観をアップデートするための施策が求められます。例えば、「この業界では昔からこのやり方だから平等だ」と考える人に対して、コンプライアンス教育を実施し、現代の価値観に沿った考え方を取り入れる機会を提供することが有効です。
Q&A
Q:公正世界信念はポジティブ心理学とは関係があるのでしょうか?
[藤井]
ポジティブ心理学においても、公正世界信念と関連するテーマがよく扱われています。特に、「努力すれば報われる」といった考え方はポジティブ心理学と親和性が高いです。
公正世界信念が強い人は、逆境を乗り越える意欲を持ちやすく、前向きな姿勢を維持しやすい傾向があるため、この観点に注目した研究がポジティブ心理学の領域で取り上げられていると考えられます。
Q:公正世界信念の強さには、男女差や年代差などの傾向があるのでしょうか?
[西本]
現在の研究では、明確な性差や年代差は示されていません。ただし、個人の経験や社会的背景によって、公正世界信念の強さが異なる可能性があります。今まで自分がある行動をとったときに、どのような結果を得てきたか、また周囲の人はどうだったのか。今まで身を置いてきた組織のあり方がどのようだったのかということの影響が大きいと考えられます。
Q:公正世界信念が強い人は、偶然の理由で病気や災害に見舞われた人には積極的にサポートする一方で、被害者に対して「あなたにも責任がある」と非難することもあります。このように、同じ信念を持ちながらも支援と非難という二面性を生み出す要因は何でしょうか?
[西本]
この違いは、状況や情報の提示のされ方によって変化すると考えられます。悪い結果だけが示されると、きっと被害者に何か原因があったのだろうと非難する方に傾いてしまいますが、悪い結果になってしまった人が、今までどのような行動をとってきたかという情報を得ている場合には、サポートというポジティブな行動につながると考えられます。公正世界信念が高い人は、結果だけを見るのではなく、広い視点で多くの材料をもとに物事を判断することが特に重要です。
脚注
[1] Nudelman, G., Otto, K., & Dalbert, C. (2016). Can belief in a just world buffer mood and career prospects of people in need of risk protection? First experimental evidence. Risk analysis, 36(12), 2247-2257.
[2] Levine, C. S., Basu, D., & Chen, E. (2017). Just world beliefs are associated with lower levels of metabolic risk and inflammation and better sleep after an unfair event. Journal of personality, 85(2), 232-243.
[3] Han, L., Zhou, H., & Wang, C. (2022). Employees’ Belief in a Just World and Sustainable Organizational Citizenship Behaviors: The Moderating Effect of Interpersonal Intelligence. Sustainability, 14(5), 2943.
[4] DePalma, M. T., Madey, S. F., Tillman, T. C., & Wheeler, J. (1999). Perceived patient responsibility and belief in a just world affect helping. Basic and Applied Social Psychology, 21(2), 131-137.
[5] CubelaAdoric, V. (2005). Belief in a just world and justifications of negative outcomes. Personality and Individual Differences, 39(3), 717-727.
[6] Silva, C., Pedrero, V., Barrientos, J., Manzi, J., & Reynaldos, K. (2024). Just-World Beliefs, System Justification, and Their Relationship with People’s Health-Related Well-Being: A Narrative Review. Behavioral Sciences, 14(10), 941.
[7] Beierlein, C., Werner, C. S., Preiser, S., & Wermuth, S. (2011). Are just-world beliefs compatible with justifying inequality Collective political efficacy as a moderator. Social Justice Research, 24, 278-296.
[8] Cheng, Y., Nudelman, G., Otto, K., & Ma, J. (2020). Belief in a just world and employee voice behavior: The mediating roles of perceived efficacy and risk. The Journal of psychology, 154(2), 129-143.
登壇者
 藤井 貴之 株式会社ビジネスリサーチラボ チーフフェロー
藤井 貴之 株式会社ビジネスリサーチラボ チーフフェロー
関西福祉科学大学社会福祉学部卒業、大阪教育大学大学院教育学研究科修士課程修了、玉川大学大学院脳情報研究科博士後期課程修了。修士(教育学)、博士(学術)。社会性の発達・個人差に関心をもち、向社会的行動の心理・生理学的基盤に関して、発達心理学、社会心理学、生理・神経科学などを含む学際的な研究を実施。組織・人事の課題に対して学際的な視点によるアプローチを探求している。
 西本 和月 株式会社ビジネスリサーチラボ アソシエイトフェロー
西本 和月 株式会社ビジネスリサーチラボ アソシエイトフェロー
早稲田大学第一文学部卒業、日本大学大学院文学研究科博士前期課程修了、日本大学大学院文学研究科博士後期課程修了。修士(心理学)、博士(心理学)。暗い場所や狭い空間などのネガティブに評価されがちな環境の価値を探ることに関心があり、環境の性質と、利用者が感じるプライバシーと環境刺激の調整のしやすさとの関係を検討している。環境評価における個人差の影響に関する研究も行っている。