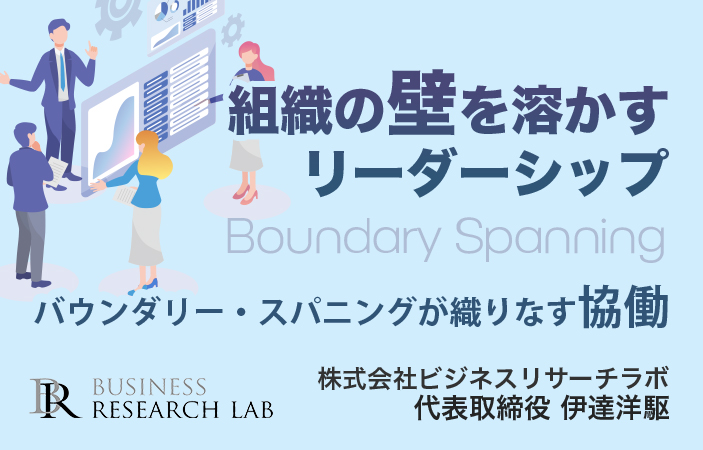2025年3月26日
組織の壁を溶かすリーダーシップ:バウンダリー・スパニングが織りなす協働
デジタル化とグローバル化が加速する現代社会において、組織の成功は部門や企業の壁を越えた協働にかかっています。優れた製品やサービスを生み出すには、異なる専門性や視点を持つ人々の知恵を結集する必要があるからです。しかし、この協働を実現することは容易ではありません。部門間の対立、組織文化の違い、専門用語の壁など、さまざまな障壁が立ちはだかります。
そこで注目を集めているのが、バウンダリー・スパニング(境界を越えた連携)を促進するリーダーシップです。これは、組織の内外における多様な関係者をつなぎ、効果的な協働を実現します。従来のリーダーシップ研究が組織内部の指揮・統制に焦点を当てていたのに対し、このアプローチは組織の境界を越えた関係構築や調整に光を当てます。
本コラムでは、バウンダリー・スパニングを促進するリーダーの特性や行動について解説します。とりわけ、メンバーの自主性を尊重し、心理的安全性を高めるリーダーシップの意義に着目します。組織の壁を越えた協働が不可欠となる中、これらの知見はマネジメントに新たな視座を提供するはずです。
リーダーシップを高く評価される
バウンダリー・スパニングに優れたリーダーは、なぜ高い評価を得るのでしょうか。米国の研究開発チームを対象とした調査は、外部との関係構築やチーム外からの情報収集に長けたメンバーが、他のメンバーから高いリーダーシップ評価を受けることを明らかにしました[1]。
この結果の背景には、外部との関係構築がチームの成功に欠かせない要素となっている現実があります。例えば、研究開発チームでは、クライアントや外部の専門家との連携が成果を左右します。クライアントのニーズを的確に把握し、それを製品開発に反映させる能力は、プロジェクトの成否を決定づけます。また、最新の技術動向や市場情報を収集し、チーム内で共有することも、製品の競争力を高める上で不可欠です。このため、外部との調整やリソース獲得に長けたメンバーは、チーム内で影響力を持つようになります。
ただし、全ての外部連携が同じように評価されるわけではありません。調査では、アドバイザーとの連携は、リーダーシップ評価にほとんど影響を及ぼしませんでした。これは、アドバイザーがチームの技術的な支援者としてよりも、コーチやファシリテーターとして認識されているためです。アドバイザーとの連携は、チームの日常的な業務遂行や問題解決に直接的な貢献をもたらすものではないと考えられているのです。
個人特性もバウンダリー・スパニングに関係します。セルフモニタリング能力の高い人、すなわち状況に応じて自分の行動を調整できる人は、外部との関係構築に優れています。異なる文化や価値観を持つ組織との連携において、柔軟な対応が求められるためでしょう。相手の立場や考え方を理解し、それに応じたコミュニケーションを取れる能力が、外部連携を成功に導くのです。
プロアクティブな性格も、バウンダリー・スパニングを促進します。自ら主体的に行動を起こす傾向がある人は、外部の専門家や情報源に積極的にアプローチし、プロジェクトに有用な情報を収集します。このスカウティング・スキャニング活動は、チームの視野を広げ、イノベーションの機会を見出すことにつながります。
一方で、クライアント対応には個人特性はあまり影響しませんでした。これは、クライアント担当という役割が明確に定められており、担当者の行動が役割によって規定されているからです。クライアントとの関係は組織にとって重要であるため、個人の裁量よりも、組織として定められた手順や方針に従って対応することが求められるのでしょう。
動機づけの観点からは、境界管理の自己効力感が要因となることが分かりました。自分が外部関係をうまく構築できると確信している人は、クライアントや外部専門家との連携を積極的に行います。この自己効力感は、失敗を恐れず、新しい関係構築に挑戦する姿勢を支えます。
リーダーの支援的コーチングが重要
リーダーの支援的なコーチング行動は、メンバーのバウンダリー・スパニングを引き出します。製造業のエンジニアを対象とした研究では、リーダーの支援的コーチングがメンバーの自己効力感を高め、それが外部との連携行動を促進することが明らかになりました[2]。
支援的コーチングとは、メンバーの能力を信頼し、自主的な行動を奨励するリーダーシップスタイルです。このスタイルを取るリーダーは、メンバーに外部との連携に関する権限を与え、その行動を支持します。例えば「この課題は、外部の専門家と相談して解決する権限があなたにある」と述べることで、メンバーは自信を持って行動できるようになります。
このような支援的コーチングが効果を発揮する背景には、メンバーの心理的なメカニズムが関係しています。リーダーから信頼され、権限を委譲されることで、メンバーは自分の判断や行動に自信を持てるようになります。この自己効力感の向上が、実際の行動変容につながるのです。
支援的コーチングは外部連携に関する自己効力感を高めます。外部との連携には、未知の相手との交渉や、予期せぬ問題への対応など、不確実性を伴う要素が多く含まれます。このような状況において、リーダーの支持があることは、メンバーの心理的な支えとなります。
自己効力感が高い人は、困難な状況を脅威としてではなく、成長の機会として捉えます。これは外部連携においても同様です。自己効力感の高いメンバーは、新しい関係構築や複雑な調整業務を、自己成長の機会として前向きに受け止めることができます。
支援的コーチングは、メンバーの問題解決能力の向上にも貢献します。リーダーが直接的な指示を出すのではなく、メンバー自身に考えさせ、決断を委ねることで、メンバーは自律的に問題に対処することができます。こうした経験は、外部との連携場面で直面する様々な課題に対応する上で、貴重な学びとなります。
この行動変容は、メンバーの仕事満足度にも好ましい結果をもたらします。外部との連携を通じて必要なリソースを確保し、目標を達成することで、自身の仕事に価値を見出せるようになります。これは、自己決定理論で説明される「達成感」や「承認欲求の充足」につながります。
支援的コーチングの効果は時間の経過とともに強まり得ます。メンバーが外部連携の経験を積み重ねることで、自己効力感がさらに向上し、それが新たな行動を生む好循環が生まれるのです。
謙虚なリーダーシップが促進する
中国の研究開発チームを対象とした調査は、リーダーの謙虚さがバウンダリー・スパニングを促進することを発見しました[3]。この研究では、リーダーの謙虚な態度が、チームの心理的安全性を高め、それがメンバーの外部連携行動を引き出すというメカニズムが見えてきました。
謙虚なリーダーシップの第一の特徴は、自己認識の深さです。自らの欠点や限界を客観的に受け入れられる態度は、チーム全体に現実的で健全な文化をもたらします。リーダーが自身の不完全さを認めることで、メンバーも失敗を恐れず、新しい挑戦に向かうことができます。
この自己認識は、外部連携の文脈で意味を持ちます。組織の境界を越えた活動には、未知の要素や予期せぬ困難が伴います。謙虚なリーダーは、自分たちの知識や能力の限界を認識しているからこそ、外部との協力の必要性を理解し、それを積極的に推進することができます。
第二の特徴は、他者への感謝の念です。チームメンバーの能力や貢献を認め、その価値を評価する姿勢は、メンバーの自尊心と帰属意識を高めます。この心理的な基盤があるからこそ、メンバーは安心して外部との関係構築に挑戦できます。
他者への感謝は、組織の境界を越えた関係構築においても意味を持ちます。外部の協力者の貢献を心から評価し、感謝の意を表すことで、持続的な協力関係を築くことができます。表面的な関係を超えた、深い信頼関係の構築につながるでしょう。
第三の特徴は、学びへの献身的な姿勢です。新しい知識やアプローチを柔軟に取り入れる態度は、組織の革新性を高めます。謙虚なリーダーは、自分が全てを知っているわけではないことを認識し、他者から学ぶ機会を求めます。
こうした学習志向は、外部との協働を通じた組織学習を促進します。異なる専門性や経験を持つ外部の関係者との交流は、新しい知識や視点を獲得する機会となります。謙虚なリーダーは、これらの学びをチーム全体で共有し、組織の能力向上につなげることができます。
謙虚なリーダーの下では、チームの心理的安全性が高まります。心理的安全性とは、チーム内で自分の意見を自由に言える、失敗や批判を恐れずに行動できるという感覚です。謙虚なリーダーは、メンバーを平等に扱い、適切なフィードバックを与えることで、チーム全体の心理的な雰囲気を穏やかなものにします。
心理的安全性は、外部連携における不確実性やリスクへの不安を和らげる効果があります。例えば、新しい取引先との交渉や、他部門との調整にはリスクが伴います。しかし、心理的安全性が確保された環境では、メンバーはこれらのリスクを恐れず、挑戦する意欲を持てるようになります。
研究では、謙虚なリーダーシップがチームの心理的安全性を介して、境界を越えた行動を促進することが実証されました。この結果は、謙虚さという一見控えめな特性が、組織の革新性と成果に貢献することを示しています。
促進的プロジェクトマネジメントが有効
オランダの都市開発プロジェクトに関する研究は、促進的なプロジェクトマネジメントがバウンダリー・スパニングを活性化することを見出しました[4]。促進的プロジェクトマネジメントとは、関係者間の対話や参加を促すマネジメントスタイルを指します。このアプローチは、従来の指示命令型のマネジメントとは異なり、多様な関係者の自発的な協力を引き出すことに主眼を置いています。
この研究では、非公式な会議や関係構築の場の重要性に着目しています。ネットワークミーティングやワークショップ、懇親会といった非公式な場は、参加者が自由に意見交換を行い、信頼を築く機会となります。公式な会議では見えにくい本音や課題が共有され、それが問題解決のヒントになることも少なくありません。
非公式な場が機能する理由の一つは、心理的な障壁の低さにあります。公式な場では、組織の立場や役職の違いが対話を制約することがあります。一方、非公式な場では、そうした制約から解放され、より自由な発想や率直な意見交換が可能になります。これは、組織の境界を越えた創造的な解決策を生み出す上で意味を持ちます。
非公式な場は、関係者間の人間的な理解を深める機会にもなります。仕事上の役割を超えて、個人としての価値観や考え方を知ることで、相互理解が進みます。この理解は、その後の公式な場面での協力関係を円滑にします。
促進的プロジェクトマネジメントのもう一つの特徴は、関係者の参加意識を高める工夫です。各関係者が自分の役割や貢献を実感できるよう、意思決定プロセスへの関与を促します。参加型のアプローチにより、関係者は情報の受け手ではなく、プロジェクトの共同創造者として関わるようになります。
例えば、ワークショップでは、関係者が自身の専門知識や経験を活かして問題解決に貢献する機会が設けられます。それぞれの組織が持つ独自の強みや資源が明らかになり、それらを組み合わせることで新たな価値を生み出すことができます。
エグゼクティブ層のサポートも見逃せません。上層部がプロジェクトマネージャーに必要な資源や裁量を与えることで、マネージャーは関係者との自由な協働や関係構築に時間とエネルギーを振り向けられます。エグゼクティブ層の支援は、プロジェクトの成功に不可欠な要素となります。
エグゼクティブサポートの具体的な形態としては、予算や人材の配分、意思決定の権限委譲などが挙げられます。組織の方針や優先順位を明確にし、プロジェクトの正当性を保証することも重要な支援となります。これによって、プロジェクトマネージャーは外部との調整においても、確信を持って行動することができます。
ただし、研究ではエグゼクティブサポートは直接的にバウンダリー・スパニングを促進するのではなく、促進的マネジメントを通じて間接的に影響を及ぼすことが明らかになりました。実際の協働や関係構築は、現場レベルでの日常的な相互作用を通じて実現されることを示唆しています。
調査では、バウンダリー・スパニングがネットワークの信頼形成に寄与することも確認されました。境界を越えた協働の経験を重ねることで、関係者間の相互理解が深まり、将来的な協力関係の基盤が形成されるのです。このような信頼関係は、長期的なプロジェクトの成功に寄与することでしょう。
しかし、興味深いことに、信頼そのものがネットワークのパフォーマンスを直接的に高めるわけではありませんでした。信頼は短期的な成果よりも、長期的な協力関係の維持に貢献することを示唆しています。信頼は、円滑な協働のための必要条件ではありますが、それだけでは十分ではないということです。
脚注
[1] Marrone, J. A. (2004). Cutting across team boundaries: Antecedents and implications of individual boundary spanning behavior within consulting teams (Doctoral dissertation). University of Maryland, College Park.
[2] Marrone, J. A., Quigley, N. R., Prussia, G. E., and Dienhart, J. (2021). Can supportive coaching behaviors facilitate boundary spanning and raise job satisfaction? An indirect-effects model. Journal of Management, 48(5), 1131-1159.
[3] Lv, J., and Deng, Z. (2020). Impact of humble leadership on the boundary spanning behavior. Proceedings of the International Conference on Big Data Application & Economic Management, 280-284.
[4] van Meerkerk, I., and Edelenbos, J. (2018). Facilitating conditions for boundary-spanning behaviour in governance networks. Public Management Review, 20(4), 503-524.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。