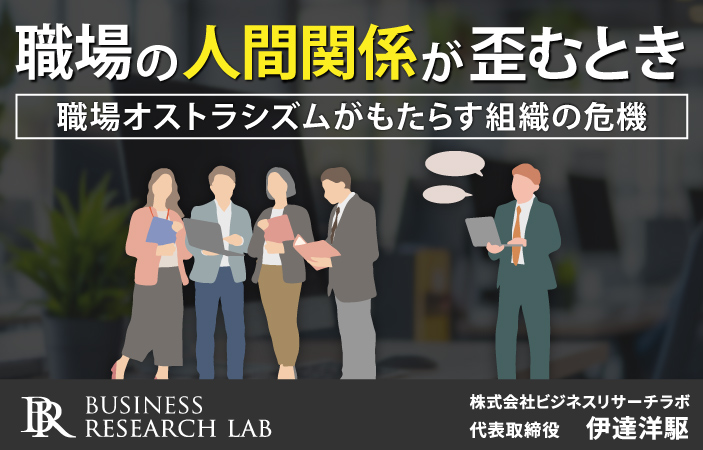2025年3月25日
職場の人間関係が歪むとき:職場オストラシズムがもたらす組織の危機
職場における人間関係は、私たちの日々の生活に大きな意味を持ちます。毎日のように顔を合わせ、共に仕事をする同僚たち。その関係が良好であれば、仕事の楽しさは倍増し、生産性も向上するでしょう。しかし、その反対に、誰かが周囲から無視されたり、排斥されたりする状況に置かれたらどうでしょうか。
「おはよう」と挨拶しても返事がない。会議で発言しても誰も反応してくれない。休憩時間になっても誰も声をかけてくれない。こうした排斥行為は、深刻な問題となり得ます。この「職場オストラシズム」と呼ばれる現象は、どこかの職場において起きているにもかかわらず、その深刻さが見過ごされがちです。
なぜなら、排斥は他者への攻撃や暴言と異なり、「何もしない」という形で表れるからです。目に見える形での非難や攻撃がないため、周囲も気づきにくく、対応が遅れることもあります。しかし、排斥された人の心には、傷が刻まれます。その痛みは、身体的な痛みと同じような反応を引き起こします。
本コラムでは、職場オストラシズムが従業員の行動にどのような負の波及をもたらすのかを解説します。排斥が従業員の心理と行動を変化させる過程を見ていきましょう。一人一人が相手の立場に立って考え、行動することの価値を、あらためて考える機会となれば幸いです。
組織市民行動の低下と逸脱行動の増加
職場オストラシズムを経験した従業員は、組織市民行動を控えめにし、逸脱行動を増やす傾向にあります[1]。組織市民行動とは、職務として定められていない自発的な協力や貢献のことです。他の従業員を手助けしたり、職場の雰囲気を良くしようと努力したりする行動が含まれます。
職場で排斥を経験すると、このような自発的な協力行動が減少します。特に排斥する側が上司である場合、その傾向は顕著になります。これは、上司からの排斥が従業員の自尊心や職場での価値を脅かすためです。上司は評価や昇進、情報へのアクセスをコントロールする立場にあるため、その人からの排斥は従業員に心理的ダメージを与えます。
同時に、他者への逸脱行動も増加します。例えば、同僚の失敗を喜んだり、悪口を言ったりするような行動です。排斥によって失われた力を取り戻そうとする心理が働くためです。自分が無力だと感じる状況を補うために、他者への攻撃的な態度を示します。
外部からの社会的支援の有無によって、この関係性は変化します。家族や友人など、職場以外からの支援が少ない従業員は、排斥による行動の変化が一層顕著になります。職場外での支援が心理的な負担を軽減する役割を果たしているためと考えられます。支援が少ない従業員は、ストレスを軽減する代替手段を持たないため、職場内で攻撃的な行動を取ることで内的な不満を解消しようとします。
他方で、外部からの支援が多い従業員は、排斥を経験すると離職意図が高まる傾向にあります。家族や友人からの支援が心理的な余裕を生み出し、他の職場で働く選択肢を考える余地を与えます。支援が少ない従業員は、現在の職場に留まらざるを得ず、どうにか現状を改善しようと試みます。
このように、職場オストラシズムは従業員の基本的な行動パターンを変化させます。組織にとって望ましい自発的な協力行動が減少し、望ましくない逸脱行動が増加するという負の連鎖が生じるのです。
道徳的無関与を通じた自己保身的行動の発生
職場オストラシズムは、従業員の道徳観にも変化をもたらします。排斥された従業員は、道徳的無関与と呼ばれる心理状態に陥りやすくなります。道徳的無関与とは、本来は倫理的に問題のある行動であっても、それを正当化して受け入れてしまう心理状態です。
中国の企業で実施された調査では、職場排斥を経験した従業員が、自分の仕事や立場を守るために不道徳な行動を取る傾向が確認されました[2]。例えば、他者の業績を故意に低く評価したり、チームの一員としてふさわしくない行動を取ったりするケースが報告されています。
このプロセスにおいて、まず排斥によって従業員は心理的なストレスや不安を感じます。その負担を軽減するために、道徳的な判断基準を一時的に停止させ、不道徳な行動を正当化するのです。「この行動は職務のためだから仕方がない」といった考えが生じ、本来なら避けるべき行動を受け入れてしまいます。
この傾向は、対人感受性が高い従業員において顕著です。対人感受性とは、他者からの反応に敏感な性格特性を指します。感受性が高い従業員は、排斥による心理的ストレスを強く感じ、それを和らげるために道徳的な判断を一時的に停止させやすいのです。他人からの無視や孤立を強く感じるため、心理的ストレスや不安が高まり、認知リソースが消耗されます。その結果、倫理的判断を下す能力が低下してしまいます。
自己利益的な政治意図が強い従業員も、道徳的無関与を介して不道徳行動を起こしやすくなります。自己利益的な政治意図とは、自分の地位や目標を達成するために他者を操る傾向のことです。このような従業員は、排斥を受けると、自己防衛的に不道徳な行動を正当化する可能性が高まります。
職場オストラシズムは従業員の道徳的判断を歪め、自己保身的な不道徳行動を引き起こします。個人の性格特性によってその程度は異なりますが、組織全体の倫理観にも悪影響を及ぼす可能性があります。
仕事の緊張感を経由した知識隠蔽行動
職場オストラシズムは、従業員の知識共有行動にも大きな変化をもたらします。パキスタンの繊維産業で行われた調査によると、職場で排斥を経験した従業員は、仕事の緊張感が高まり、その結果として知識隠蔽行動を取るようになります[3]。
知識隠蔽には、いくつかの形態があります。「回避的隠蔽」は、知識の共有を先延ばしにしたり、意図的に誤った情報を提供したりする行動です。「無知のふり」は、知識を持っているにもかかわらず知らないと装う行動を指します。「合理的隠蔽」は、正当な理由を用いて知識共有を拒否する行動です。
調査の結果、排斥された従業員は特に「回避的隠蔽」と「無知のふり」を増やすことが分かりました。これらの行動は、相手との直接的な対立を避けながら、自分の知識という資源を守ることができる方法だからです。従業員は排斥によってストレスを感じ、自分の持つ知識を貴重な資源として守ろうとする防衛的な姿勢を強めます。
この背景には、資源保存理論が説明する心理メカニズムが存在します。この理論によれば、人は心理的・社会的なリソースを失うと、残されたリソースを守ろうとする行動を取ります。職場で排斥された従業員は、人間関係という重要なリソースを失った状態にあります。そのため、自分の知識という別のリソースを守ることで、心理的なバランスを保とうとするのです。
高い忠誠心を持つ従業員は、排斥による仕事の緊張感を強く感じ、知識隠蔽行動を取りやすくなります。組織への強い感情的なつながりを持つ従業員ほど、排斥による心理的なダメージが大きいからです。期待を裏切られたという感情が、防衛的な行動を引き起こします。
組織への強い愛着があるにもかかわらず排斥されることで、従業員は矛盾を感じ、心理的な葛藤が、知識隠蔽という形で表出します。忠誠心の高い従業員は組織を離れたくないため、排斥を受けても職場に留まります。しかし、排斥によるストレスから防御的行動を取る傾向が強まり、知識隠蔽を選択するということです。
職場オストラシズムは組織内の知識共有を阻害する要因となります。これは個人レベルの問題ではなく、組織全体の学習能力や革新性にも影響を与えます。
エンゲージメント低下を介した役割行動の減少
職場オストラシズムは、従業員のエンゲージメント(仕事への没頭)を低下させ、それを通じて役割内・外の行動にも影響を及ぼします。台湾の五つ星ホテルで行われた調査では、排斥を受けた従業員の行動変化が、直接的ではなく、エンゲージメントの低下を介して生じることが明らかになりました[4]。
役割内行動とは、職務記述書や組織の規範に基づいて従業員が行う基本的な行動を指します。例えば、顧客への丁寧な対応や、定められた業務手順の遵守などです。一方、役割外行動は、職務要件を超えて行う任意の行動です。顧客に対する追加の配慮や、同僚への自発的な支援などが含まれます。
職場で排斥を経験すると、従業員は仕事に対する熱意や献身性を失っていきます。排斥による心理的なダメージが、仕事への集中力や意欲を低下させるのです。エネルギーが枯渇し、業務に没頭できなくなることで、基本的な職務行動にも支障が出始めます。
この影響は役割外行動にも波及します。エンゲージメントが低下した従業員は、顧客満足を追求するような追加的な行動を控えめにします。他の従業員との協力行動も減少します。職場環境への一体感が薄れ、他者を助ける意欲が低下するということです。
アジアの文化的背景を持つ従業員の場合、このプロセスには独特の特徴が見られます。調和を重視する文化的傾向から、排斥に対して表立った反発を示すことは少ないものの、エンゲージメントの低下という形で反応が表れます。表面的には平静を保ちながらも、内面では仕事への意欲が徐々に失われていくという現象があります。
職場オストラシズムの影響は、エンゲージメントの低下を介して、従業員の基本的な職務行動から発展的な行動まで幅広く影響を及ぼします。外的評価への意識から最低限の行動は維持されるものの、エンゲージメントの低下によって、組織や顧客に対する自発的な貢献は確実に減少していきます。
サービスパフォーマンスの低下
サービス業における職場オストラシズムは、従業員のサービスパフォーマンスを低下させます。中国南部のホテルで行われた調査によると、神経症傾向の強い従業員は、排斥による悪影響を特に受けやすいことが判明しました[5]。
神経症傾向とは、不安や怒り、悲しみといったネガティブな感情を抱きやすい性格特性です。このような傾向が強い従業員は、職場排斥をストレスフルな出来事として受け止め、精神的なリソースを大きく消耗してしまいます。その結果、サービスパフォーマンスが著しく低下するわけです。
排斥を受けた従業員は、業務に対する精神的なエネルギーや忍耐力を失っていきます。職場での人間関係が損なわれることで、仕事に意義や挑戦を感じられなくなります。さらに、業務に没頭する能力も低下し、顧客対応の質が下がってしまいます。これらの変化は、サービス品質の全般的な低下につながります。
神経症傾向の強い従業員は、他者からの否定的な態度や無視を過度に意識する傾向があります。そのため、職場排斥をより深刻な出来事として受け止め、それによる心理的ダメージも大きくなります。このような従業員は、排斥を受けると自分の価値や存在意義に疑問を持ち始め、それがサービスパフォーマンスの低下を加速させます。
職場排斥は従業員の心理的資源を奪うだけでなく、職場での支援や関係性も減少させます。これによって、業務上の困難に直面した際のサポートも得られにくくなり、サービスの質を維持することがますます難しくなります。特に感受性の高い従業員は、このような支援の欠如をより強く感じ取り、サービスパフォーマンスに深刻な影響が出やすいのです。
このような変化は、最終的に顧客満足度の低下をもたらす可能性があります。サービス業において、従業員の心理状態とパフォーマンスは密接に結びついています。職場オストラシズムは、個々の従業員の行動変化を通じて、組織全体のサービス品質に影響を及ぼす要因となり得ます。
排斥がつくりだす負の連鎖
職場オストラシズムは、従業員の行動に広範な負の波及をもたらします。組織市民行動の減少、逸脱行動の増加、道徳的判断の低下、知識隠蔽行動の促進、そしてサービスパフォーマンスの低下など、その影響は多岐にわたります。
これらの変化は、従業員個人の性格特性や、組織への忠誠心、外部からの社会的支援の有無によって、その度合いは異なります。神経症傾向や対人感受性が高い従業員、組織への忠誠心が強い従業員は、排斥による心理的ダメージをより深刻に受けやすいことが分かっています。
職場オストラシズムは、単純に人間関係の問題に見えるかもしれません。しかし、その影響は個人の心理状態や行動を大きく変え、最終的には組織全体のパフォーマンスにまで広がる可能性があります。良好な人間関係を築き、従業員が安心して働ける環境を整えることは、組織の生産性と持続可能性を支えるのです。
脚注
[1] Fiset, J., Al Hajj, R., and Vongas, J. G. (2017). Workplace ostracism seen through the lens of power. Frontiers in Psychology, 8, 1528.
[2] Liu, X., Zhang, H., and Yu, X. (2023). Effects of workplace ostracism on pro-job unethical behavior: The role of moral disengagement, interpersonal sensitivity and self-serving political will. Psychological Reports.
[3] Riaz, S., Xu, Y., and Hussain, S. (2019). Workplace ostracism and knowledge hiding: The mediating role of job tension. Sustainability, 11, 5547.
[4] Yuan, C.-Y., Chen, C.-Y., Fei, Y.-M., and Yan, C.-H. (2022). Workplace ostracism and prosocial service behaviours: The role of work engagement. Current Issues in Tourism, 25(16), 2665-2678.
[5] Leung, A. S. M., Wu, L. Z., Chen, Y. Y., and Young, M. N. (2011). The impact of workplace ostracism in service organizations. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 836-844.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。