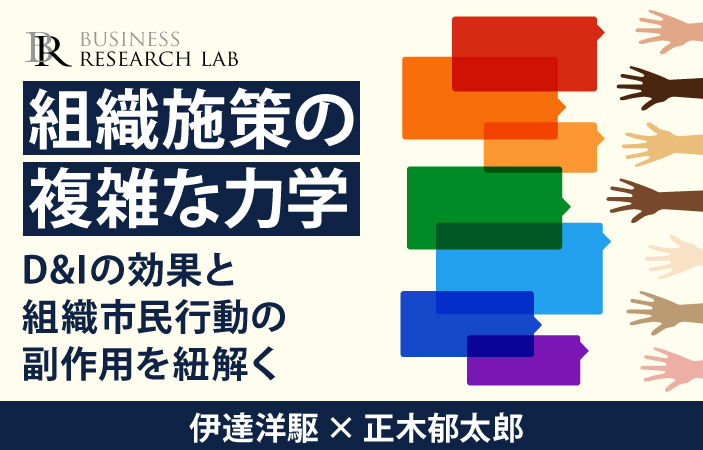2025年3月21日
組織施策の複雑な力学:D&Iの効果と組織市民行動の副作用を紐解く
企業の経営課題として注目を集めるダイバーシティ&インクルージョン(D&I)。多くの企業が取り組みを進める一方で、その成果には大きな差が生まれています。なぜ、ある企業では成功し、別の企業では期待した効果が得られないのでしょうか。本対談では、ビジネスリサーチラボ 代表取締役の伊達洋駆とテクニカルフェローの正木郁太郎が、D&Iの取り組みが企業によって異なる成果をもたらす理由について、議論を展開します。
特に注目されるのは、施策の導入から組織の成果に至るまでの「ブラックボックス」の解明です。D&I施策が従業員一人ひとりの認知や行動にどのような変化をもたらし、それが組織全体のパフォーマンスにどうつながっていくのか。その複雑なメカニズムに迫る必要性について議論します。
さらに対談では、組織における「望ましい行動」の意外な副作用についても掘り下げていきます。例えば、同僚への援助などを含む組織市民行動が、時として予期せぬマイナスの影響を及ぼす可能性があることなど、組織行動の両義性についても検討します。
理論と実践の架け橋となることを目指す二人による本対談は、D&Iをはじめとする組織施策の「効果」を考える上で、示唆に富む新たな視座を提供します。
ダイバーシティ施策が抱える問題
正木:
今回、私が初めに取り上げたいのは、ダイバーシティやインクルージョン(D&I)に関する施策の成果が、企業によってなぜこんなに違うのかという問題です。
D&Iを推進すると、「組織がイノベーティブになる」「社員の心理的安全性が高まる」など、いろいろポジティブな話が出ますが、「本当に成果が出ている会社」と「うまくいっていない会社」が分かれています。その差はどこから生じるのか、そこに興味を持って様々な研究を調べています。
具体的には、2019年に発表された論文がそうしたアプローチを取っていて、わかりやすかったですね。そこでは「企業が何らかのダイバーシティ施策を取ったとき、従業員はそれをどう解釈するのか」という部分が効果を分けているのではないかと指摘されています。
D&I施策というと、一見すると「公平な制度を整えて差別をなくすこと」が主な目的のように思えますが、それだけでなく、その施策が社員一人ひとりに「これは会社がこういう価値観を持っているというシグナルなんだ」というメッセージを与える働きもする。例えば、公平性を重視する会社だ、と解釈されるのか、特定の属性の人たちだけを優遇する会社だ、と解釈されるのか。その認知プロセスで様々な行動が変わり、結果的に企業全体のD&Iやパフォーマンスに影響を与えるというわけです。
この論文自体が言っていることは、社会心理学や組織行動論で伝統的に言われてきたシグナリング理論や原因帰属、ステレオタイプの話を整理し直したようなもので、「新しい主張」というよりは「既存の理論を踏まえて大きな流れを再確認した」ものだと感じました。
ただ、このような理論的整理がしっかりとあるだけでも、企業が「D&I施策を導入すれば必ず組織成果が上がるはず」と思いこんでしまうことに対して、「いや、実際には会社の狙いや姿勢を従業員がどのように理解しているかが重要なんです」「だから経営層の一貫したメッセージや、他の施策との組み合わせこそが大事です」という指摘ができるようになります。ここは、社会心理学の基礎研究と社会応用をつなぐうえで、大事な点だと思っています。
企業の経営者やマネージャーに「ダイバーシティ施策が成果に結びつくのかどうか」を説明するとき、単純に「多様な人材を受け入れればイノベーションが生まれます」とか「女性やマイノリティが活躍すれば業績が伸びます」という話では、「なぜ」という点が欠けていて説得力が弱いと感じます。
その中間にあるメカニズム、つまり「施策による認知変化が社員の行動を変え、それが集団・組織レベルのアウトカムに影響していく道筋」を解明しなければいけない。ここが私の中で問題意識になっていて、社会心理学的な知見をもっと取り入れて、企業を含めた実社会の出来事をしっかりと研究する必要があると思っています。
伊達:
企業としても、いざ導入するとなると投資や制度変更が必要ですし、経営者も「本当にプラスになるのか」と確認したくなる。けれども、その因果がぼやけているから納得しきれない面もあるというのはよく聞きます。
正木:
そうなんです。私も社会心理学を学んできたという背景があるからかもしれませんが、「D&Iを進めるとシナジーが起こる」という説明だけでは納得しきれないんですね。
実際に「なぜシナジーが起こるのか」「そのシナジーはどんな心理プロセスや集団プロセスを通じて機能するのか」を丁寧に分析して示す研究が少なく、議論が飛躍しているように見えます。だからこそ、1人1人の行動変化が集団全体に集積して企業成果に影響を及ぼす、というミクロとマクロをつなぐ視点が重要になると思うのです。
ただ、そのミクロとマクロをつなぐ研究は大変でして、企業が施策を導入したとしても、それが個人の行動変化につながるのかを確かめるのは難しく、さらにそれが組織全体の利益や文化変容につながるかどうかを追うのはもっと難しい。
データの取得方法も含めて、企業と研究者が同じ目的のもとで協働したり、様々なテクノロジーを活かしたりしないと実証しきれません。結果、単純化した話にとどまってしまいがちですが、本当はそこにはもっと複雑なプロセスがあると感じています。
ミクロ・マクロ・リンクの意義と難しさ
伊達:
正木さんのお話を聞いて、経営学にも同じような流れがあると思いました。例えば、「ミクロ・ファンデーション」という概念が注目されています。企業の戦略が成功するのはなぜかを考えたとき、「トップ・マネジメントがどんな考え方や意思決定をするのか」といったミクロな要素を無視できないという話です。これもマクロとミクロをつなげようという試みといえます。
しかし現状において、経営学のコミュニティは「マクロ寄りの人」と「ミクロ寄りの人」で学会が分かれていて、アプローチの違いも小さくありません。一例を挙げれば、戦略論は企業全体や産業全体を見ようとしますが、組織行動論は個々の従業員や小集団の行動を検討する。実際の企業では両方が同時に起こっているわけですから、それを橋渡しして説明できるかが鍵になっていると思います。
D&Iという現象についても同様で、例えば、トップ・マネジメントの強いメッセージが出されても、それが社員の心にどう響いて行動を変えるか、変わった行動がさらに組織の慣習や文化にどう反映されていくのかを追うのは簡単ではありません。
しかも、文化が形成されるまでには時間がかかるので、長期的な観測も必要になる。だからこそD&Iの話は「すぐに成果が出る」「一瞬で変わる」という誤解を生みやすいのかもしれません。
正木:
企業側が「投資したら半年後にこういう成果が出ます」と知りたくなる気持ちは理解できますが、厳密には一年や二年では捉えきれない中長期の変化があるかもしれません。そこを丁寧に追おうと思うと、例えば社会心理学のフィールド調査や経営学のケーススタディなど、様々な手法を駆使する必要が出てくるわけです。
伊達:
エージェントベースモデルなどのシミュレーションも、ミクロとマクロをつなげようとする手法の一つですよね。
正木:
確かに、ミクロのエージェントがどう行動するかのルールを設定して、その相互作用がマクロの動きを生む過程をシミュレーションしようとする手法ですよね。理論的には面白いのですが、シミュレーションで得た仮説を実際に検証するのはまた別の山があります。
いずれにしても、企業単位でデータをとるとなると自社を相手にする経営層や人事の方だけでなく、コンサルタントの方々などの実務家との連携が不可欠です。そうした連携の中で測定指標をどう設定するのか、さらにそこにどんな条件が加わると成果が高まるか、といった検討は複雑になりがちで、腰を据えた長期研究が必要です。
伊達:
大規模かつ長期的な研究のためには、研究資金やチームのメンバーの多様な専門性が求められます。ミクロとマクロをつなぎたいという意識はあっても、想像以上に労力が大きく、なかなか簡単にはいかないのかもしれません。
正木:
これだけ難易度が高いからこそ、それを少しでも前に進める研究には大きな価値があると思っています。何より、現場の方々もこのテーマには興味を持っているので、うまく共同研究を組めれば企業側のニーズにも応えられますし、学術面でも貢献しやすい領域だと思います。
モラル・ライセンシングと組織行動論における副作用
伊達:
続いて、私のテーマについてお話しします。私が特に注目しているのは「モラル・ライセンシング」という概念です。これは、「ある人が道徳的な行動をしたあと、その善行を理由に、後の非倫理的行為を正当化してしまう」という心理プロセスを指します。具体例を挙げるなら、「今日は環境に良いことをしたから、夜は多少無駄遣いしてもいいや」といった具合ですね。
古くから哲学者や倫理学者が「人は善行を積んでも油断すると悪行に走りがちだ」という議論をしていましたが、それが本格的に実証研究のターゲットになったのは2000年代になってからです。
一方で、再現性の危機が話題になったとき、モラル・ライセンシングの効果も「果たしてどれだけ確かなのか」と疑問視されました。複数のメタ分析を見ると、効果サイズはそこまで大きくはないものの、確かに存在するという結果が示されているようです。
私がなぜこれを、自分の専門とする組織行動論の文脈で注目しているかというと、「組織市民行動」という概念と組み合わせた研究が出てきたからです。組織市民行動とは同僚の手助けをするなど、会社にとってプラスになる行動を指します。一見すると望ましい行動ですが、最近の研究では「組織市民行動をした人が、その後、別の場面で悪影響をもたらすケースがある」ことが指摘されています。
例えば、周りをサポートしたり、親切な振る舞いをしたりした社員が、後で「これだけ尽くしたんだから多少失礼な対応をしても仕方ない」や「自分はもう十分に貢献したから次はサボっても許されるだろう」と思ってしまうということです。興味深いのは、こうした副作用は、内発的に組織市民行動を行った人ほど出やすいという研究もあって、人間の心理は単純にはいかないと痛感します。
正木:
内発的なモチベーションが高い人ほど、モラル・ライセンシングが強く出るというのは興味深いですね。普通は「自発的にいいことをする人は、その後も連続していい行いをしそうだ」と考えがちですから、これは意外に映ります。
ただ、認知的不協和など他の理論と絡めて考えると、「一度いい行いをしたからもう十分」と思う人もいれば、「過去の善行と一貫性を保ちたいからさらに善行を積む」という人もいそうで、その境界条件が気になります。
伊達:
モラル・ライセンシングは条件の違いで効果が変わります。それがメタ分析による効果の小ささの一つの要因と考えることもできます。
ところで、私が組織市民行動の「副作用」という視点にこだわるのは、人や組織に関する概念は、良いところが強調されがちだからです。D&Iもそうですし、エンゲージメントやリーダーシップなども、ポジティブな面ばかり語られます。しかし実際にはネガティブな側面や、特定の条件下では悪影響があることもあります。
副作用を知っておくことで、実務におけるリスクマネジメントがしやすくなるはずです。薬にたとえれば、効能だけでなく副作用も理解したうえで使い方を工夫しないと大変なことになる。同様に、組織市民行動やエンゲージメントを高める施策を導入するときも、「こういう状況で逆の影響が出るかもしれない」とわかっていれば手を打てるかもしれません。
その視点が十分に広まっていないので、私はモラル・ライセンシングの研究に注目しています。モラル・ライセンシングは、副作用のメカニズムを説明する理論の一つですから。
正木:
企業も成果を急いで導入しては「期待した成果が出ない」と嘆くケースがあります。そもそも導入時に、「こういうデメリットが起こり得るから気をつけましょう」という話があれば、計画段階で対処できたかもしれませんから、副作用は事前に周知されるべきですよね。
研究と実務をつなぐ今後の展望
伊達:
私が最近考えているのは、副作用研究をもっと体系的にまとめて、学術的にも実務的にも参照しやすい形にすることです。組織市民行動の副作用だけでなく、様々な組織行動論の概念について「こういう場合に、こんな悪影響が起こる可能性があります」と整理した「裏ハンドブック」のようなものがあれば便利かなと。実際の執筆は大変ですが、ここ何年かでしっかり取り組もうと思っています。
正木:
それこそ誰もやっていない貢献になりそうですし、「概念の負の側面」を掘り起こす作業は、現場のリスクマネジメントや研究者自身の視野拡張にもつながります。お話を聞いていると、伊達さんは学術的な厳密さを踏まえたうえで、実務にも活かしたいという両面の思考があるように思いますが、そこはご苦労も多いのではないでしょうか。
伊達:
私のように理論を深めたい一方で実務家の人にも使えるアウトプットを出そうとすると、「どちらの世界からも異端扱いされやすい」という悩みはあります。ただ、実践領域の現場に出入りしてきた中で、「メカニズムを解明したい」という研究者の視点の必要性も痛感しますし、一方で「理論だけで終わると社会的なインパクトが限定的」というもどかしさも感じてきました。だから両方を目指したくなってしまいます。
正木:
私もよく似た道を通っています。学術書を出すと「難しすぎる、一般の現場には響きにくい」と言われ、逆に一般向けにレポートなどの文章書くと「エビデンスが薄い、もっと理論的背景をしっかり示して」と研究者から言われる。そこを埋めるために、結局2種類の本や論文、レポートを書かなくてはいけないなど、なかなか大変です。
伊達:
そういう研究や実務の橋渡しをする人が、今後ますます必要になると思います。D&Iや組織市民行動の副作用など、なかなか一筋縄ではいかないテーマだからこそ、両方の言語を使える人が地道に実証して、企業や社会に還元していく活動が求められるのではないでしょうか。
正木:
私もこれから企業との共同研究などを通して、ミクロとマクロをつなぐ視点でより説得力のあるデータを集めたいと考えています。もちろん時間はかかりますが、一歩ずつ進めていきたいですね。
伊達:
ぜひそうしていきましょう。
対談者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。
 正木郁太郎 株式会社ビジネスリサーチラボ テクニカルフェロー
正木郁太郎 株式会社ビジネスリサーチラボ テクニカルフェロー
東京女子大学現代教養学部心理・コミュニケーション学科心理学専攻専任講師。株式会社ビジネスリサーチラボ テクニカルフェロー。東京大学大学院人文社会系研究科博士後期課程修了。博士(社会心理学:東京大学)。組織のダイバーシティに関する研究を中心に、社会心理学や産業・組織心理学を主たる研究領域としており、企業や学校現場の問題関心と学術研究の橋渡しとなることを目指している。著書に『職場における性別ダイバーシティの心理的影響』(東京大学出版会)がある。