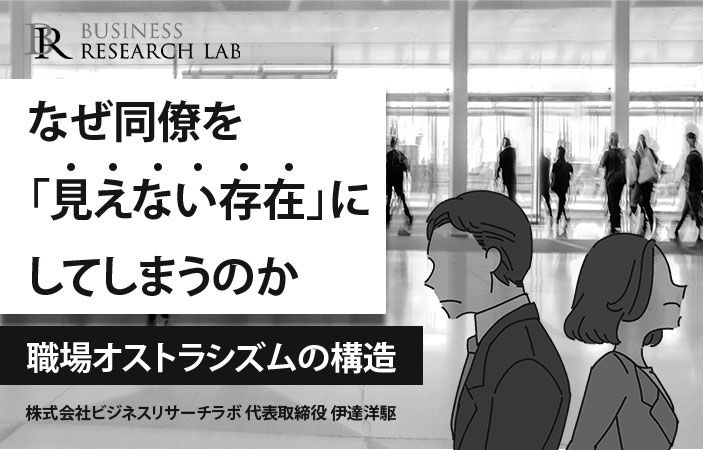2025年3月19日
なぜ同僚を「見えない存在」にしてしまうのか:職場オストラシズムの構造
職場において、私たちは日々様々な人々と関わりを持ちながら働いています。しかし時として、その関係性に歪みが生じ、特定の個人が周囲から無視されたり、疎外されたりする状況が発生します。「職場オストラシズム」と呼ばれる現象です。
職場オストラシズムは、表立った暴力や嫌がらせというより、「冷たい暴力」とも表現される事象です。例えば、挨拶を返さない、目を合わせない、会話に入れない、といった形で表れます。些細な行為に思える人もいるかもしれませんが、従業員の心理状態や仕事へのモチベーション、さらにはパフォーマンスにまで深刻な結果をもたらすことが分かってきました。
本コラムでは、職場オストラシズムについて、その実態と影響を見ていきます。どのような状況で発生し、人々にどのような心理的・行動的な変化をもたらすのか。さらに、文化的な背景がどのように関係するのかについても考えていきましょう。
職場オストラシズム研究の広がり
職場オストラシズムに関する研究は、2014年以降に急速な広がりを見せています。この分野の文献を体系的に分析した論文によると、特に2018年と2019年には、前例のない数の研究論文が発表されました[1]。職場における人間関係の課題が世界的に注目を集めていることの表れです。
研究の増加には、いくつかの要因が関係しています。一つは、職場環境の改善やメンタルヘルス問題への社会的関心の高まりです。働く人々の心理的な健康が組織のパフォーマンスに影響を与えることが広く認識されるようになりました。もう一つは、職場のダイバーシティが進む中で、異なる背景を持つ人々の間での軋轢や排除の問題が顕在化してきたことです。
研究は地理的に広がりを見せています。中国の研究機関、特に上海財経大学や香港バプテスト大学が、この分野で多くの研究成果を発表しています。これらの研究機関がこのテーマに力を入れているのは、急速な経済発展に伴う職場環境の変化が、人々の心理や行動にもたらす影響を解明する必要性が高まっているためです。
職場オストラシズムの研究では、文献計量学や内容分析などの手法を用いて、様々な側面からの検討が行われています。職場の無礼行動や社会的支援の欠如が従業員の行動に与える影響が注目されています。また、人間の動機づけや社会的排除に関する基礎理論の検証も進められています。
この分野の研究では、測定方法の確立も進展の一つです。職場オストラシズムを客観的に評価するための尺度が開発され、それが多くの研究で活用されています。これによって、排斥が従業員に及ぼす影響を定量的に分析することが可能になりました。
心理学、組織行動学、経営学など、様々な分野の研究者がこのテーマに取り組んでいます。そこでは、社会的絆理論や資源保存理論など、多様な理論的アプローチが用いられ、職場オストラシズムの理解が深められています。このように、学際的な視点から研究が進められることで、この問題の複雑な性質が徐々に解明されつつあります。
加害者の意図と被害者の認識のずれ
職場オストラシズムを考える上で、加害者の行動と被害者の認識との間にずれが生じることが分かっています。中国の製造業企業を対象とした調査では、同僚による排斥行動が必ずしも被害者の排斥認識に直接的には結びつかないことが判明しました[2]。
そこには「帰属欲求」という個人特性が関係しています。帰属欲求とは、他者とのつながりや受容を求める心理的な欲求の強さを表します。この欲求が強い人は、他者からの些細な行動にも敏感に反応し、それを排斥として認識する可能性が高くなります。一方で、帰属欲求が低い人は、同じような状況でも、それを排斥として受け止めにくい傾向にあります。
この研究では、従業員の行動を2回に分けて調査し、排斥行動と排斥認識の関係を分析しています。1回目の調査では、排斥行動や帰属欲求、政治的スキルなどを測定しました。そして3か月後の2回目の調査で、反生産的行動を測定しています。この時間差を設けた調査設計により、排斥の影響が時間の経過とともにどのように変化するかを捉えることができました。
調査ではソーシャルネットワーク分析も用いられ、排斥行動を具体的な行動として詳しく計測しました。例えば、挨拶を返さない、目を合わせないといった行動が、どのような頻度で、誰から誰に対して行われているのかが分析されました。
人は、周囲の行動をどのように解釈するかによって、異なる反応を示します。同じ行動であっても、それを意図的な排斥と捉えるか、偶然と捉えるかで、心理的な影響は異なってきます。この認識の差異は、職場のコミュニケーションを考える上で示唆を含んでいます。
「政治的スキル」の役割は興味深いものです。これは、職場における人間関係を上手く処理する能力を指します。政治的スキルが高い従業員は、排斥を受けても、それに対して建設的な対応を取ることができます。このスキルは、排斥認識が反生産的行動につながるのを防ぐ緩衝材として機能します。
調査結果から、排斥による心理的な影響は、個人特性によって異なることも判明しました。職場での人間関係の改善を考える上で重要な発見でしょう。一律な対策ではなく、個人の特性に応じたきめ細かな対応が必要とされることを示唆しているからです。
加害者の動機の二面性
職場オストラシズムにおいて、加害者の動機は主に二つに分類できることが分かってきました[3]。懲罰的動機と防御的動機です。これらの動機は、職場での人間関係の複雑さを反映しています。
懲罰的動機による排斥は、グループの秩序や効率を維持するために行われます。例えば、職場のルールを守らない人や、チームの目標達成に貢献しない人が排斥の対象となることがあります。この場合、排斥は一種の警告として機能し、他のメンバーに対して「規範を守らなければ同じ扱いを受ける」というメッセージを送ることにもなります。
この懲罰的動機には、集団の規範を維持するという側面があります。グループのメンバーが共有する価値観や行動規範から逸脱する人物を排斥することで、グループの一体感や効率性を保とうとするのです。時には、特定の人物を排斥することで、他のメンバーに対する見せしめとする意図も含まれています。
一方、防御的動機による排斥は、自己防衛の手段として行われます。他者との比較で劣等感を感じたり、自分の地位が脅かされると感じたりした時に、その対象となる人を排斥するのです。例えば、創造性の高い同僚が上司から高く評価されている場合、それを脅威と感じた人がその同僚を排斥することがあります。
防御的動機による排斥には、いくつかの典型的なパターンがあります。一つは、自分より優れた能力や実績を持つ人を排斥するケースです。このような場合、排斥者は自己イメージを守るために、優れた同僚との接触を避けようとします。もう一つは、上司との関係が良好な同僚を排斥するケースです。これは、その同僚との関係が自分の立場を脅かすと感じることから生じます。
研究では、これらの動機が「評価理論」の枠組みで説明できることも分かってきました。排斥者は、まず状況を「脅威」として認知し、それに対してネガティブな感情を抱き、最終的に排斥行動を選択するというプロセスを経ます。この理論的な理解は、職場での排斥行動を予防するための手がかりを提供しています。
これらの動機は、職場における人々の心理的な反応を理解する上で価値ある知見を提供します。排斥は感情的な行動というより、組織内のダイナミズムや個人の心理的防衛機制が複雑に絡み合った結果として生じるのです。
さらに、この研究はマネジャーに対して示唆を与えています。排斥行動の背後にある動機を理解することで、効果的な予防策や対応策を講じることが可能になります。例えば、防御的動機による排斥に対しては、個人の安全感や自尊心を高める取り組みが求められるでしょう。
組織とのつながりや個人的価値への打撃
職場オストラシズムが従業員に及ぼす影響について、調査が行われました。多くの従業員のデータを分析したこの研究では、排斥が組織や個人に深刻なダメージを与えることが明らかになっています[4]。
排斥を受けた従業員は、組織への帰属意識が低下します。自分が組織の一員であるという感覚が弱まり、職場での存在意義を見失いがちになります。それに伴い、仕事に対する満足度も減少します。職場環境を否定的に捉えるようになり、日々の業務に喜びを見出せなくなるのです。
この研究では、職場排斥の影響を態度、幸福感、行動の3つの側面から分析しています。態度面では、組織コミットメントや仕事満足度の低下が見られます。幸福感の面では、感情的な消耗や心理的ストレスの増加が観察されています。行動面では、組織市民行動の減少や離職意図の上昇が確認されました。
「組織内自尊心」に注目している点は興味深いでしょう。これは、組織の一員としての自己評価を表します。排斥を受けると、組織内自尊心が低下することが分かっています。組織内自尊心の低下は、さらなる悪影響の連鎖を引き起こします。自己評価が下がることで、仕事への意欲が失われ、パフォーマンスも低下するのです。
これらの影響は文化的背景によって異なります。個人主義的な文化圏では、排斥による所属感や仕事満足度への打撃が顕著です。一方、集団主義的な文化圏では、組織との一体感や協力行動への影響が強く表れます。文化によって人々が重視する価値観が異なることを反映しています。
さらに、この研究は排斥の影響が時間とともに拡大することも示唆しています。最初は小さな心理的ストレスとして始まった問題が、次第に行動面での変化を引き起こし、最終的には組織全体のパフォーマンスにまで波及するのです。
このように、職場オストラシズムは、従業員の心理面だけでなく、行動面にも変化をもたらします。組織の一員として活躍したいという意欲が損なわれ、結果として組織全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼすのです。
この研究結果は、職場における人間関係の質が、組織の健全性にとって重要であることを示しています。排斥という見えにくい形の暴力が、組織に予想以上の損失をもたらす可能性があります。そのため、早期発見と適切な対応が不可欠となります。
義務感の低下とエンゲージメントの喪失
職場オストラシズムが従業員に与える影響の中でも、深刻なのが義務感とエンゲージメントの低下です。中国のサービス業企業での調査では、排斥された従業員が組織に対する義務感を失い、それが仕事への関与度の低下につながることが分かりました[5]。
義務感とは、組織や同僚に対して貢献したいという気持ちです。排斥を受けると、「自分は組織から支持されていない」という認識が強まり、この義務感が低下します。その結果、仕事に真剣に取り組む動機が失われ、エンゲージメントの低下につながるのです。
研究では、4か月にわたる2段階の調査が実施されました。第1段階では職場での排斥と集団主義の度合いを測定し、第2段階では義務感と仕事への関与度を測定しています。時間差を設けた調査設計により、排斥が及ぼす影響の時間的な変化を追跡することができました。
排斥が仕事への関与に与える影響のプロセスは注目に値します。排斥を受けた従業員は、まず組織に対する義務感を失います。これは、社会的交換理論で説明できる現象です。組織から支持されていないと感じることで、組織に貢献しようとする意欲が失われるのです。そして、義務感の低下が、仕事への関与度の低下につながっていきます。
ここでも文化的な要因が役割を果たしています。集団主義的な価値観を持つ従業員は、排斥による義務感の低下がより顕著です。人間関係やグループへの所属感を重視する文化的背景が、排斥の心理的影響を増幅させるためでしょう。
この研究は、職場での人間関係が従業員のモチベーションにいかに影響を与えるかを示しています。排斥は、組織と従業員の間の心理的な契約を損ない、それが仕事への取り組み方を変えてしまうのです。従業員の心理的安全性を確保することが、組織のパフォーマンスを維持する上で不可欠であることが、改めて確認されました。
この研究は排斥の影響が個人の特性によって異なることも明らかにしています。同じ排斥行動を受けても、その受け止め方や反応は、個人の価値観や文化的背景によって異なります。このことは、職場での人間関係の改善を考える上で重要です。
脚注
[1] Kaushal, N., Kaushik, N., and Sivathanu, B. (2021). Workplace ostracism in various organizations: A systematic review and bibliometric analysis. Management Review Quarterly, 71(4), 783-818.
[2] Yang, J., and Treadway, D. C. (2018). A social influence interpretation of workplace ostracism and counterproductive work behavior. Journal of Business Ethics, 148(4), 879-891.
[3] Henle, C. A., Shore, L. M., Morton, J. W., and Conroy, S. A. (2023). Putting a spotlight on the ostracizer: Intentional workplace ostracism motives. Group & Organization Management, 48(4), 1014-1057.
[4] Li, M., Xu, X., and Kwan, H. K. (2021). Consequences of workplace ostracism: A meta-analytic review. Frontiers in Psychology, 12, 641302.
[5] Xu, X., Kwan, H. K., and Li, M. (2020). Experiencing workplace ostracism with loss of engagement. Journal of Managerial Psychology, 35(7/8), 617-630.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。