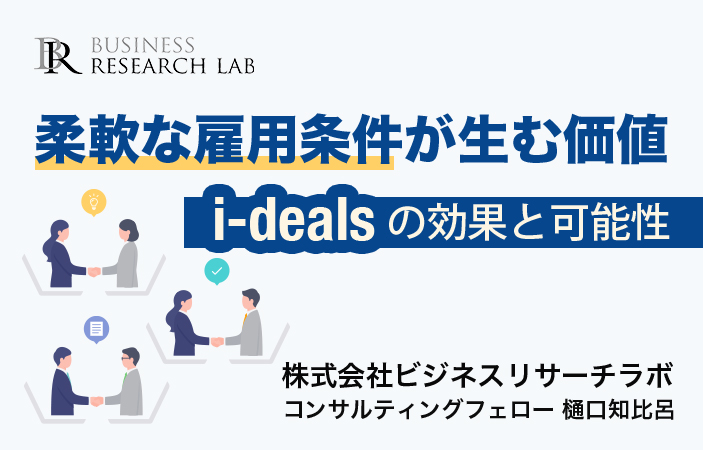2025年3月18日
柔軟な雇用条件が生む価値:i-dealsの効果と可能性
近年、多様な人材を「個別扱い」することで確保しようという動きが注目されています。学術的には、これを「i-deals」と呼びます。この概念は、「idiosyncratic(特異な)」と「ideal(理想)」を組み合わせた造語であり、「各当事者に利益をもたらす条件について、個々の従業員と雇用主との間で交渉される、非標準的な性質を持つ自発的で個別化された合意」を意味します 。簡潔に言えば、従業員が自身のニーズに応じて仕事条件を雇用主と交渉し、個別にカスタマイズした特別な取り決めです。
多様性推進や働き方改革の一環として注目されているi-dealsは、単なる雇用条件の調整にとどまらず、従業員と雇用主の関係性や動機づけを深く理解するための重要な枠組みとされています。本コラムでは、i-dealsが職場に与える影響についてメタ分析を基に解説します。また、これに関連するポジティブな影響やネガティブな側面を明らかにした研究知見を紹介します。これらの研究結果を通じて、i-dealsの本質を深く理解し、ビジネス現場で実践に役立つヒントを提供します。働き方や人材管理の多様化が求められる現代において、i-dealsがもたらす可能性にぜひ注目してください。
職務満足度向上や離職意図低下、エンゲージメント向上に影響
まず最初に、i-dealsの研究動向をレビューします。過去23件の実証研究を基にしたメタ分析では、i-dealsが文化的文脈においてどのように機能し、組織や従業員にどのような影響を及ぼすのかが探求されました[1]。メタ分析とは、独立して実施された複数の研究結果を統合し、それらを解析する方法です。
研究の結果、i-dealsが従業員の職務満足度や組織的な支援、リーダーメンバー交換関係(Leader Member Exchange:LMX)といった職務態度や行動に肯定的な影響をもたらすことが明らかになりました。
ただし、その効果は文化的背景によって異なります。東洋文化では集団的努力や関係性の重視が影響を与える一方、西洋文化では個人の特性や主体性が効果を左右することが示唆されています。
また、メタ分析により、i-dealsの具体的なタイプや内容が従業員の行動に与える影響が異なることも確認されました。例えば、スケジュールの柔軟性を重視するi-dealsは職務満足度の向上や離職意図の低下に寄与し、能力開発を目的としたi-dealsは建設的な発言や組織へのエンゲージメントを強化することが示されています。
実践的な示唆として、i-dealsは従業員のニーズに応じた柔軟な職務設計を実現するための有効なツールです。しかし、i-dealsの効果を最大化するためには、交渉プロセスや適用において透明性と公平性を確保することが重要です。また、文化的背景や個人特性に応じたi-dealsの設計も求められます。
例えば、集団主義が強い文化圏では、チーム全体の利益を考慮した「we-deals(個人ではなく集団として取り決め)」の導入が効果的です。一方で、個人主義が強い文化圏では、従業員個人のニーズに特化したi-dealsがより効果を発揮します。
マネジメントへの応用としては、まず、i-dealsを通じて人材マネジメントの柔軟性を強化することが挙げられます。例えば、働く時間や場所を調整できることで、従業員の満足度やエンゲージメントを高めることが期待されます。
また、i-dealsの交渉では、従業員個人のニーズを正確に把握し、組織全体の目標と調和させることが重要です。さらに、i-deals導入に伴う公平性の問題について、従業員間の認識を調整するためのコミュニケーション戦略を構築することも求められます。
個人の成長や貢献意欲を高める
i-dealsが従業員の行動や業績にどのように影響するかを探求した研究があります[2]。イタリア国内の多様な業種にわたる400名以上の社会人を対象に、i-dealsの効果とその個人差について分析が行われました。調査では、従業員が目指す達成、地位向上、精神的な結びつきの3つの動機づけ目標が、同僚がに与える影響に焦点を当て、これらの目標がi-dealsと業務評価の関係をどのように取り持つかということについて検討されました。
研究の結果、特に達成と地位の向上を強く求める従業員ほどi-dealsを交渉しやすく、i-dealsを得た従業員は、上司からの業務遂行能力や対人市民行動に関する評価が高まる傾向があることが明らかになりました。対人市民行動とは、他人を助ける、他人のために便宜を図る、欠席した同僚をカバーするなどのことです。
さらに、同僚がi-dealsを得ていると認識すると、従業員も自らのi-dealsを積極的に求めるようになる傾向が確認されました。これは、他者の待遇が従業員に対して「自分も同様の待遇を受けるべき」との認識を促し、個々の動機づけが強化されるためです。
この研究からは、を得ることが個人の成長や貢献意欲を高めるだけでなく、職場全体にポジティブな影響をもたらし得ることが示唆されます。一方で、i-dealsが特定の従業員にのみ提供されると、他の従業員が不公平感を抱く可能性もあるため、注意が必要です。
管理職にとっては、従業員の目標に応じて適切なi-dealsを提供することが、職場全体の業務遂行能力の向上につながると考えられます。例えば、達成志向が強い従業員にはスキル開発機会を、地位向上意欲が高い従業員にはリーダーシップの研修機会を提供するなど、各個人の動機に応じたi-dealsを活用することが推奨されます。
従業員の能力拡大や長期的な雇用可能性の向上につながる
戦略的人事ツールとしてのi-dealsが、従業員のエンプロイアビリティ(雇用可能性)向上にどのように寄与するかを探る研究を紹介します[3]。本研究では、オランダの複数の企業で実施されたエンプロイアビリティに関する取り組みを例に挙げつつ、i-dealsの実践的活用方法について議論しました。
調査の結果、i-dealsは従業員と組織の双方に利益をもたらすWin-Winの関係を形成できることが示されました。特に、キャリア開発やスキル向上に焦点を当てたi-dealsは、従業員の能力拡大や長期的な雇用可能性の向上につながる可能性が高いことが明らかになりました。
一方で、i-dealsの種類によっては効果が異なり、例えば柔軟な労働条件に関する取り決めは従業員に快適さを提供する一方、長期的にはエンプロイアビリティを低下させるリスクがあることも示唆されました。このため、i-dealsを活用する際には、従業員の個別ニーズとキャリアの持続可能性を慎重に考慮する必要があります。
実践的な含意として、組織はi-dealsを積極的に活用するための環境を整備すべきです。具体的には、i-deals交渉を奨励する方針を労働協約や人事ハンドブックに明記し、従業員が安心して交渉を開始できる文化を醸成することが求められます。
また、エンプロイアビリティ・コーチ(従業員が特定の仕事やキャリアの課題についての支援を求めることができる専門家)やグループディスカッション形式のワールドカフェといった支援体制を導入することで、従業員が自分に適したi-dealsを見つけ、交渉を成功させるための具体的な助言を得る機会を提供できます。
マネジメントへの応用としては、上司がi-deals交渉の中心的役割を果たすことが重要です。上司は従業員のニーズを理解し、個別の取り決めを実現するために必要な支援を提供することが望まれます。
管理職の肯定・否定感情が交渉実現の鍵となる
従業員と管理職との間で交渉されるi-dealsにおいて、交渉がどのように実現に結びつくか、特に管理職の感情が果たす役割に焦点を当てた研究があります[4]。
本研究では、トルコの社会人MBA学生とその管理職を対象に、データ収集を行い、従業員の行動と管理職の感情がに与える影響を分析しました。
調査の結果、i-dealsの交渉後、管理職が従業員の交渉プロセスに対して肯定的な感情を抱けば、に結びつく可能性が高くなる一方で、否定的な感情を抱く場合にはその可能性が低下することが明らかになりました。
また、従業員がi-dealsの交渉後、他者との社会的つながりを強化する行動を取ると、管理職はそのプロセスに対して肯定的に感じやすくなります。逆に、従業員が社会的に孤立する行動を取ると、管理職の否定的感情を引き起こしやすいことも示されました。
これらの結果から、i-dealsの交渉後の交渉条件の実現をするためには、交渉後の従業員の行動が重要であることが示唆されます。従業員がi-dealsを自分だけの利益のためでなく、チーム全体の利益にも資するものとして行動することが、管理職の肯定的感情を引き出し、鍵となります。
マネジメントへの応用としては、まずi-dealsの交渉過程において透明性を確保することが重要です。管理職には、交渉の背景や期待される成果を明確に説明するトレーニングを提供し、従業員との建設的な対話を促進するスキルを養うことが求められます。
また、i-dealsがチーム全体に利益をもたらすよう設計されていることを従業員に理解させるためのメンタリングやコーチングの導入も効果的です。さらに、職場での孤立を防ぐため、チームビルディングやコミュニケーション能力向上のためのトレーニングを導入することが効果的です。
家庭生活の質の向上と仕事スキル拡大に影響
仕事と家庭の充実(Work Family Enrichment)におけるi-dealsの役割を調査した研究があります[5]。中国における子育てをしながら働く人々179名を対象にアンケート調査を実施し、データを解析しました。
その結果、i-dealsをうまく交渉するためには、従業員が自発的に行動することと、家庭から仕事へのポジティブなサポートが重要であることが示されました。また、柔軟な働き方に関するi-dealsは、仕事と家庭の時間や場所の調整を可能にし、スキルやキャリア開発を支援する取り決めは、仕事に対する意欲ややりがいを高める効果があることがわかりました。
調査からは、i-dealsが従業員の仕事と家庭の双方に影響を及ぼし、それらをうまくつなげる2つの重要なポイントが明らかになりました。柔軟性i-dealsは、仕事のタイミングや場所に柔軟性をもたらすことで家庭生活の質を向上させる一方、開発i-dealsは仕事の役割の充実を通じて家庭へのポジティブなエネルギーの波及をもたらします。このように、i-dealsは従業員が仕事と家庭の役割を調和させ、より良いバランスを実現するための重要な手段となり得ることが示唆されます。
マネジメントにおける示唆としては、従業員の家庭生活を考慮した人事管理の重要性が挙げられます。特に、従業員が仕事を通じて家庭の幸福を向上させる可能性を理解し、これを支援する柔軟性のある労働条件を提供することが推奨されます。
たとえば、柔軟な勤務時間や勤務地の調整を可能にするi-dealsは、家庭生活の質を向上させ、従業員のモチベーションを高める効果があります。また、開発i-dealsを通じて、従業員が自らのスキルや役割を拡大し、家庭へのポジティブな影響を広げる仕組みを構築することも重要です。
さらに、i-dealsの交渉と実現に際して、従業員と雇用者の間の透明なコミュニケーションが欠かせません。従業員がi-dealsの恩恵を受けると同時に、組織全体や家庭生活にポジティブな波及効果をもたらす行動を取ることを促進する仕組みづくりが必要です。
ワークライフバランスの向上、成長機会の拡大に寄与
が、従業員の働き方や組織との関係にどのような影響を及ぼすかについての研究を紹介します[6]。本研究は、ドイツの税務行政機関で働く887人の職員を対象に、パートタイム労働や在宅勤務などの柔軟な勤務形態が、職員の労働環境や感情的コミットメントにどのように影響するかを調査しました。柔軟性と能力開発に関連するi-dealsが注目されました。
調査の結果、柔軟な労働条件をは、仕事と家庭のバランスをうまく取れており、無報酬残業も少ないことが示されました。特にパートタイム労働や在宅勤務といった柔軟性i-dealsが、従業員の仕事と家庭の葛藤を減らし、ワークライフバランスの向上に寄与することが明らかになりました。
一方、能力開発に関するi-dealsでは、従業員の成長機会が広がる一方で、上司からの業績期待が高まる傾向があり、感情的コミットメントの向上にも関連が見られました。
この研究は、i-dealsが公的機関のような規則の厳格な環境でも可能であり、従業員の主体性と交渉力がその効果を引き出す重要な要素であることを示唆しています。
この研究の実践的な含意として、組織はi-dealsを導入することで、従業員が職務環境に柔軟に適応し、ワークライフバランスを向上させられることが挙げられます。特に、柔軟性i-dealsは家庭と仕事のバランスを支援する効果が高く、育児や介護と仕事の両立を成し遂げに対して有効です。また、能力開発i-dealsは、従業員の成長と組織へのコミットメントを高めるための有効な施策となるでしょう。
能力開発の機会に関しては、i-dealsを通じて成長の場を提供し、成長意欲の高い従業員のパフォーマンス向上を支援することで、組織全体の成果向上につなげることが可能です。
チームメンバー間の公平性に注意が必要
これまではi-dealsのポジティブな影響を中心に概説してきましたが、ポジティブとネガティブの両面に作用した研究を紹介します[7]。本研究は、40の組織、166チーム、合計1016人の従業員を対象に実施され、チーム内のi-dealsの普及率がチームの結束力や組織市民行動(Organizational Citizenship Behavior: OCB)にどのような影響を与えるかを分析しました。
組織市民行動とは、従業員が自発的に行う、チームや会社をより良くするための協力的な行動やサポートのことです。この研究のユニークな点は、i-dealsがチーム全体に広がるとき、結果がポジティブにもネガティブにも作用する可能性を示唆したことです。
調査の結果、チーム内のi-dealsの普及率が高いと、特定の条件下でチームの結束力やOCBが向上することが明らかになりました。具体的には、組織がi-dealsを多く提供する場合、チームにおいてもi-dealsが普及し、特に不平等な権力構造を持つチームでは、チームの結束力とOCBの向上が見られました。
一方で、低下する傾向が観察されました。
この結果から、組織やマネージャーがi-dealsを管理する際の重要なポイントが見えてきます。i-dealsの普及が組織と従業員にとって利益をもたらすためには、いくつかの条件が必要です。
まず、チーム内での権力構造の影響に注目する必要があります。権力がバランスよく配分されているチームでは、メンバー間で互いにサポートし合う文化が育まれ、i-dealsが結束力とOCBを促進する傾向があります。したがって、マネージャーはチーム内での権力のバランスを見極め、必要に応じて調整することが推奨されます。
さらに、組織全体としてi-dealsを提供する余力や資源が限られている場合には、i-dealsの提供に慎重になることが求められます。i-dealsの提供が希少であれば、特定のメンバーにだけi-dealsが適用されることがチーム内で不公平感を生む可能性があるためです。そのため、こうした状況ではi-dealsを提供する対象や基準を明確にし、透明性を保つことで、チームメンバー間の不満や競争意識の高まりを抑えることが重要です。
この研究は、組織がi-dealsを用いて柔軟な人材管理を行う際の指針を提供しています。例えば、i-dealsの対象を適切に設定し、チーム全体に好意的に受け入れられるようにすることが、組織全体のパフォーマンス向上につながる可能性を示唆しています。
また、i-dealsがもたらす相乗効果を引き出すためには、組織のリーダーシップがメンバー間の公平性を意識しながら、組織内の資源の配分とチーム内の力関係を慎重に調整する必要があります。
競争的な風土では離職率が高まる
i-dealsのネガティブ側面に着目した研究があります。開発的i-dealsが、若手高学歴従業員の離職や職場環境に及ぼす影響を検討しました[8]。香港における190名の大卒従業員を対象に、開発的i-dealsを提供された従業員とその周囲の反応に関する調査が行われました。
研究の結果、開発的i-dealsを受け取った従業員は、同僚から妬みの対象となり、職場の競争的風土を強く感じるようになることが明らかになりました。また、同僚がi-dealsを受けるのを目撃することも、羨望の感情を引き起こし、同様に競争的な風土認識を促進します。こうした競争的な職場風土の中で、従業員は次第に疎外感を抱き、その結果として離職率が高まることが示されました。
本研究の実践的含意として、i-dealsを適切に提供することの重要性が挙げられます。特に、キャリア形成への強い期待を持つ若年層に対しては、i-dealsが他者との比較意識を高め、否定的な感情を誘発するリスクがあるため、管理職や人事担当者は慎重な対応が求められます。i-dealsの提供が特権的なものではなく、組織内で公平かつ透明性をもって行われることで、同僚間の公平感を保つことが期待されます。
さらに、マネジメントにおいては、i-dealsの運用方法について再考が必要です。本研究は、開発的i-dealsが従業員のモチベーションを高める一方で、競争的風土を助長し、疎外感や離職率上昇につながる可能性があると指摘しています。
このため、i-dealsが組織内で一部の特権とみなされないようにし、適切なフィードバック体制を整えることが重要です。また、i-dealsの提供基準を明示し、従業員が自らのキャリア目標と結びつけた成長計画を共有する機会を増やすことが、同僚間の不公平感を軽減する方策として有効です。
本研究が示唆するもう一つのポイントは、職場の競争的風土のコントロールが、若手従業員の離職防止に寄与する可能性です。i-dealsを通じた公平性の維持が図られることで、従業員の仲間はずれ感や妬まれに対する不安を低減し、組織内の結束力や協力関係を維持することができます。
したがって、マネージャーはi-dealsを提供する際、受け取った従業員が他者に影響を及ぼさないような配慮を行い、必要に応じてi-dealsの恩恵を広く組織全体に浸透させる施策が求められます。
可能性と慎重な運用の重要性
i-dealsは、従業員一人ひとりのニーズや目標に応じた柔軟な職務設計を可能にし、組織と従業員の双方に利益をもたらす強力なツールです。これまでの研究からは、i-dealsが従業員の職務満足度やエンゲージメントを高めるだけでなく、離職意図の低下やキャリア形成の支援といったポジティブな影響をもたらすことが示されています。
一方で、ネガティブな側面として、i-dealsのと、不公平感や職場内の競争を助長し、逆効果となるリスクも明らかになっています。
このような特性を踏まえると、i-dealsを効果的に活用するためには、設計と運用における慎重な配慮が不可欠です。まず、従業員との透明なコミュニケーションを通じて、i-dealsの目的や期待される成果を共有することが重要です。
また、全ての従業員が公平な機会を持てるよう、i-dealsの提供基準を明確にし、透明性を確保する必要があります。例えば、交渉可能な条件を事前に提示し、各従業員が自分のニーズや目標に基づいて交渉を行える環境を整備することが効果的です。
さらに、組織は文化的背景やチームの特性を考慮し、i-dealsがもたらす影響を適切に管理することが求められます。集団主義が強い文化ではチーム全体を考慮した設計が必要であり、個人主義が重視される文化では個人に特化した柔軟性が効果を発揮します。
また、リーダーや管理職には、i-dealsの公平性を保ちながら従業員の成長を支援する役割が期待されます。これには、リーダーシップトレーニングやコミュニケーションスキルの向上が有効です。
最終的に、i-dealsは多様な働き方やキャリア志向に対応する手段として、組織の柔軟性と持続可能性を高める可能性を秘めています。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、従業員の声に耳を傾け、公平性と透明性を重視した戦略的な運用が求められます。これにより、i-dealsは従業員エンゲージメントと生産性の向上を促進し、組織全体の成功を支える基盤となるでしょう。
脚注
[1] Liao, C., Wayne, S. J., & Rousseau, D. M. (2016). Idiosyncratic deals in contemporary organizations: A qualitative and meta‐analytical review. Journal of organizational behavior, 37, S9-S29.
[2] Ng, T. W., & Lucianetti, L. (2016). Goal striving, idiosyncratic deals, and job behavior. Journal of Organizational Behavior, 37(1), 41-60.
[3] Van der Heijden, B., Nauta, A., Fugate, M., De Vos, A., & Bozionelos, N. (2021). Ticket to ride: I-deals as a strategic HR tool for an employable work force. Frontiers in psychology, 12, 769867.
[4] Rofcanin, Y., Kiefer, T., & Strauss, K. (2017). What seals the I‐deal? Exploring the role of employees’ behaviours and managers’ emotions. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 90(2), 203-224.
[5] Tang, Y., & Hornung, S. (2015). Work-family enrichment through I-Deals: evidence from Chinese employees. Journal of Managerial Psychology, 30(8), 940-954.
[6] Hornung, S., Rousseau, D. M., & Glaser, J. (2008). Creating flexible work arrangements through idiosyncratic deals. Journal of applied psychology, 93(3), 655.
[7] Vossaert, L., Anseel, F., & Ho, V. (2023). Do multiple I-deals in a team help or hinder team outcomes? A resource scarcity perspective. Group & Organization Management, 48(1), 156-191.
[8] Ng, T. W. (2017). Can idiosyncratic deals promote perceptions of competitive climate, felt ostracism, and turnover?. Journal of Vocational Behavior, 99, 118-131.
執筆者
 樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
早稲田大学政治経済学部卒業、カリフォルニア州立大学MBA修了、UCLA HR Certificate取得、立命館大学大学院博士課程修了。博士(人間科学)。国家資格キャリアコンサルタント。ビジネスの第一線で30年間、組織と人に関する実務経験、専門知識で、経営理論を実践してきた人事のプロフェッショナル。通信会社で人事担当者としての経験を積み、その後、コンサルティングファームで人事コンサルタントやシニアマネージャーを務め、さらに銀行で人事部長などの役職を歴任した後、現在はFWD生命にて執行役員兼CHROを務める。ビジネスと学術研究をつなぐ架け橋となることを目指し、実践で役立つアプローチを探求している。