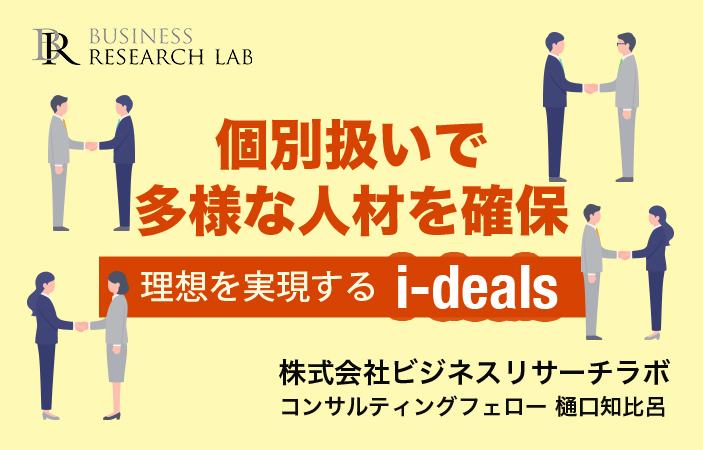2025年3月17日
個別扱いで多様な人材を確保:理想を実現するi-deals
令和六年の「労働経済の分析[1]」では、「人手不足への対応」を副題に掲げ、長期的な労働力不足の背景やその緩和に向けた取り組みを多角的に検討しています。この白書では、潜在的な労働力の労働参画促進と、一人当たりのアウトプットである労働生産性の向上が鍵であると強調されています。
潜在的な労働力とは、具体的には女性、高齢者、外国人などを指し、それぞれのニーズに応じた柔軟な雇用条件が必要です。例えば、時短勤務、週3日勤務、残業なしといった働き方の選択肢が挙げられます。また、労働生産性向上のためには優秀な人材の確保が欠かせません。
こうした状況を背景に、多様な人材を「個別扱い」することで確保しようという動きが注目されています。学術的には、これを「i-deals」と呼びます。この概念は、「idiosyncratic(特異な)」と「ideal(理想)」を組み合わせた造語であり、「各当事者に利益をもたらす条件について、個々の従業員と雇用主との間で交渉される、非標準的な性質を持つ自発的で個別化された合意」を意味します[2]。簡潔に言えば、従業員が自身のニーズに応じて仕事条件を雇用主と交渉し、個別にカスタマイズした特別な取り決めです。
i-dealsは、従業員と雇用主の関係性や動機づけを深く理解するための枠組みとして注目されています。これまでの研究では、社会的交換理論をはじめとする多様な学術理論の中で、i-dealsの形成過程やその効果について考察されてきました。本コラムでは、理論的な背景や研究知見を紹介するとともに、実践的な示唆やマネジメントへの応用を探求します。これらの研究知見を通じて、i-dealsについての理解を深め、ビジネス現場で活用可能なヒントを提供します。
社会交換理論においては公平性、透明性が重要
最初に、社会交換理論の観点から、i-dealsが組織内で与える影響について検討した研究を紹介します[3]。社会交換理論とは、人と人、または人と組織の関係が、互いに与え合う価値(例えば、信頼や支援、報酬)によって成り立つと考える理論です。特に、i-dealsに対する同僚の受容(他者の意見や行動、状況を前向きに理解し受け入れる姿勢)が、組織内の関係性や将来の期待にどのように影響を与えるかを調査しました。米国東部にあるハイテク研究開発企業の従業員65名を対象に、調査が実施されました。同僚がi-dealsを受け入れる意思が、交渉した従業員との友好関係や雇用関係の性質(社会的交換または経済的交換)によってどのように影響を受けるかを分析しています。
調査の結果、同僚がi-dealsを受け入れる傾向は以下の要因に依存することが分かりました。第一に、i-dealsを交渉した従業員が親しい友人である場合、同僚はそのi-dealsを受け入れる可能性が高まりました。第二に、親しい友人ではない同僚の場合、同僚が雇用関係を社会的交換とみなすと、他者のi-dealsを受け入れる傾向が強くなる一方で、経済的交換としてみなすと、その傾向が弱まりました。さらに、同僚が「将来自分も同様のi-dealsを得られる」という期待を抱くことで、受容に正の影響を与えることも明らかになりました。これらの結果から、i-dealsは組織内の社会的ダイナミクスに依存して調整されることが示唆されています。
実践的な含意として、i-dealsを活用する際には、組織内の公平感を維持することが不可欠です。雇用主は、i-dealsが特定の従業員だけでなく、同僚やチーム全体にとって肯定的な影響を持つように設計する必要があります。そのためには、職場での社会的交流を促進し、i-dealsが個人の特権ではなく組織全体の利益に資するものであるという認識を広めることが重要です。
また、i-dealsは「他の従業員にも将来的に開かれている」という透明性を持たせることで、同僚が状況を理解し、前向きに受け入れる姿勢や態度を高めることが可能です。
マネジメントへの応用として、i-dealsの交渉プロセスを透明化し、その基準や適用範囲を明確にすることで、公平性を確保する手法が考えられます。また、従業員間の社会的交流を促進し、チーム全体で協力的な関係を構築することで、i-dealsが引き起こす潜在的な対立を回避することが重要です。さらに、i-dealsを実験的に導入し、成功例を他の従業員にも展開することで、職場全体で受容を高めることができます。
帰属意識、積極的行動、成果向上に効果あり
i-dealsは従業員の成果向上に大きな役割を果たすことが示されています。社会的交換理論と自己高揚理論という二つの視点から、i-dealsが従業員の成果に与える影響を分析した研究があります[4]。自己高揚理論とは、人が自分の価値や能力を肯定的に捉え、周囲からもそう評価されたいと望む心理を説明する理論です。中国の2社で働く従業員230名とその上司102名を対象に、3段階の時系列データ収集を実施し、柔軟性や能力開発に関するi-dealsの効果を検証しました。
調査の結果、i-dealsが従業員の知覚された組織支援(Perceived Organizational Support: POS)を高め、それが感情的コミットメント(従業員が組織に対して感じる愛着や帰属意識)や積極的行動(変革や状況改善を目指した自発的な行動)を促進することが確認されました。また、組織内自尊感情(Organization-Based Self-Esteem: OBSE、従業員が自身を組織内で重要で価値ある存在と認識する程度)が、i-dealsと従業員成果の関係を一層強化する役割を果たすことも明らかになっています。
個人主義の程度もi-dealsの効果に影響を与える重要な要素です。個人主義の高い従業員は、i-dealsを通じて自己高揚効果を強く感じ、個人の達成感を重視する傾向があります。一方、個人主義が低い従業員は、i-dealsを職場での人間関係や支援の強化に役立てる傾向が見られます。
これらの知見を踏まえ、i-dealsを設計・運用する際には、従業員の個別ニーズや文化的背景を考慮することが重要です。特に、能力開発に関するi-dealsは、従業員の成長を支援し、自己高揚と社会的交換の双方を促進する可能性があります。
さらに、文化的背景や個人の価値観を考慮した柔軟なアプローチが必要です。例えば、個人主義の強い文化圏では、個別のキャリア形成やスキル向上を重視したi-dealsが効果的です。一方、集団主義が強い文化圏では、チーム全体の利益を考慮したi-dealsが、従業員間の信頼や協力を促進するために有効と考えられます。
マネジメントへの応用としては、i-dealsを導入した後もその効果を定期的に評価し、組織内でのポジティブな影響を継続的に促進するための仕組みを整えることが重要です。具体的な施策としては、従業員の自己評価や組織支援の認識を向上させるトレーニングやフィードバックの実施が挙げられます。
従業員の建設的で積極的な発言を促進する鍵
i-dealsが従業員のボイス行動(voice behavior)に与える影響を、社会的交換理論の視点から分析した研究があります[5]。ボイス行動とは、組織や業務の改善を目的として、従業員が建設的かつ積極的に意見や提案を表明する行動を指します。調査は、米国と中国の管理職および専門職466名を対象に、10カ月間で3つの時点にわたりデータを収集して実施されました。本研究では、i-dealsが従業員の行動にどのように影響を与えるのかを、柔軟な仕事役割志向(従業員が自身の仕事役割をどの程度広く定義しているか)、ソーシャルネットワーキング行動、組織的信頼という3つの変数を通じて検証しました。
調査の結果、i-dealsにはスケジュールの柔軟性(個々の従業員が交渉して得られる、働く時間や場所を柔軟に調整できる特別な勤務条件のこと)と専門能力開発の2つの要素があり、それぞれが異なる形でボイス行動に影響を与えていることが分かりました。スケジュール柔軟性に関するi-dealsは従業員の役割を柔軟に再定義する能力を高め、専門能力開発型i-dealsは組織的信頼を強化することでボイス行動を間接的に促進しました。特に、中国の調査対象では、組織的信頼がボイス行動の重要なつなぎ役であることが示されました。一方、米国では、ソーシャルネットワーキング行動が主なつなぎ役となりました。
これらの知見は、文化的背景がi-dealsの効果に与える影響を示しています。集団主義的な文化圏では組織的信頼が重要な役割を果たし、個人主義的な文化圏では、ネットワーキング行動が従業員行動の主要な要因となる傾向があるといえます。
実践的な含意として、i-dealsは従業員の建設的な意見表明を促進する有効なツールです。専門能力開発型のi-dealsは、特に従業員の組織的信頼を強化し、ボイス行動を引き出す効果が高いことが示唆されています。また、スケジュールの柔軟性に関するi-dealsは、従業員に主体性を持たせることで、積極的な働き方を実現します。
マネジメントへの応用としては、まずi-dealsを従業員の発言や提案を引き出すための戦略的ツールとして活用することが挙げられます。特に、文化的背景や職務特性に応じたi-dealsの設計が必要です。例えば、集団主義が強い文化圏では、従業員の信頼感を高める取り組みを通じて、ボイス行動を促進するi-dealsを導入することが効果的です。一方、個人主義的な文化圏では、ネットワーキング行動を支援するi-dealsを設計することで、従業員が積極的に意見を表明しやすい環境を整えることが求められます。
さらに、i-dealsの効果を持続的に高めるためには、定期的な評価と調整が欠かせません。組織内でのi-dealsの適用が公平であることを確認し、従業員が付与される条件に対して納得感を持てるようにすることで、ボイス行動をさらに強化することが可能です。このような取り組みを通じて、i-dealsは従業員と組織の両方にとっての価値を最大化する手段となるでしょう。
従業員間の公平感の維持が大事
社会的比較理論に基づき、i-dealsが職場における従業員の援助行動に与える影響を分析した研究があります[6]。社会的比較理論とは、人が自分の能力や状況を他者と比較することで、自身の価値や立ち位置を確認しようとする心理的なプロセスを指します。調査は、フランス南西部の工学系学校を卒業したエンジニアを対象に実施され、過去10年以内の卒業生471名にアンケートを配布し、そのうち182名から有効な回答を得ました。
分析の結果、i-dealsと援助行動の間には直接的な関係は見られないものの、組織内自尊感情(Organizational Based Self-Esteem: OBSE)がそのつなぎ役を果たすことが分かりました。具体的には、i-dealsを受けた従業員は、自身がチーム内で特権的な地位にあると感じることでOBSEが高まり、それが同僚への援助行動を促進する結果につながったのです。
i-dealがi-dealを受け取る側だけでなく、チームにとってもプラスの効果をもたらすことを示唆します。なぜなら、援助行動がチームの成功を促進する可能性があるからです。
さらに、この関係の強弱は、同僚がi-dealsを得る機会の多寡によって変化することも判明しました。同僚が自分のためにi-dealsを得る機会がないと考えている場合、この効果は強まります。なぜなら同僚を助けることはi-dealsのおかげで成長した肯定的な自己と一致するからです。
一方で、同僚にも同様の機会がある場合には社会的比較が働き、OBSEの影響が薄れて、i-dealsの付与による援助行動が行われなくなる可能性が高いことが示されています。
これらの結果は、職場におけるi-dealsの管理においてマネージャーは従業員にi-dealsの交渉を許可する前に、コストと便益のトレードオフを考慮することが極めて重要であることを示唆しています。適切に管理されたi-dealsは、従業員間のポジティブな行動を促進し、組織全体のパフォーマンス向上に寄与する可能性を秘めています。しかし、不適切な配分や過度な透明性は公平感を損ね、チームの士気や生産性に悪影響を与える可能性を及ぼすリスクも抱えています。
マネジメントへの応用として、i-dealsを効果的に活用するためには、まず従業員間の公平感を維持する仕組みを構築することが重要です。例えば、i-dealsを付与する基準を明確にし、対象者の貢献やスキル開発の観点から正当性を説明することで、他の従業員からの不公平感を軽減できます。
また、i-dealsが与えるポジティブな影響を最大化するために、その付与が従業員個人だけでなく、チーム全体にどのように貢献するかを明示することも有効です。さらに、i-dealsの付与によるコストと便益をバランスよく評価し、チーム全体の成功に寄与する戦略的な運用を目指すことが求められます。
従業員のモチベーションとパフォーマンス向上に影響
もう一つ社会的比較理論をベースとした研究を紹介します。i-dealsが従業員のパフォーマンスに与える影響を分析した研究があります[7]。ここでは、特に個人が受けるi-dealsがチーム内でどの程度「特別」なものであるかを示す「相対的i-deals」に焦点を当てています。また、チームの特性やリーダーとの関係がこの影響をどのように調整するのかについても検討されました。
調査はインドの大規模私立大学における46の学術チーム、合計321名の教職員を対象に実施され、時間差を設けたデータ収集が行われました。i-dealsの実施状況、リーダーメンバー交換社会的比較(Leader-Member Exchange Social Comparison: LMXSC)、上司による業績評価、チーム志向性、タスク相互依存性といった要素が含まれています。リーダーメンバー交換社会的比較とは、リーダーが部下との関係の質を他の部下との関係と比較し、部下間での公平感やモチベーションに影響を与えるプロセスのことです。
分析の結果、相対的i-dealsは従業員の職務遂行能力や組織市民行動(組織全体の利益を考えた自発的な行動)に対して正の影響を持つことが確認されました。この効果は、チーム志向性やタスク相互依存性が低いチームで特に顕著でした。
チーム志向性とは、グループメンバーが共に機能しようとする傾向のことで、チーム志向性の高いグループのメンバーは、仕事を達成するためにチームで働くことを好みます。タスク相互依存性は、メンバーが仕事の目的を達成するために、同僚の支援にどの程度依存しているかを表します。
一方、これらの属性が高い場合、相対的i-dealsの影響は抑えられる傾向が見られました。また、LMXSCは相対的i-dealsと業績の関係をつなぐ重要な役割を果たしており、この効果はチーム志向性が低い環境でより強く現れることが示されています。つまり、個別扱いが他のメンバーとの関係性や評価に与える影響が小さくなるため、個人の成果への影響がよりダイレクトに現れるからです。
本研究の知見は、i-dealsが適切に活用されれば、従業員のモチベーションと業績を向上させる有効な手段となることを示しています。ただし、i-dealsの設計と運用には注意が必要です。特に、チーム内の公平感や一体感を損なうことなくi-dealsを実施することが重要です。
マネジメントへの応用として、i-dealsを効果的に活用するためには、まず従業員間の公平感を維持する仕組みを構築することが重要です。例えば、i-dealsを付与する基準を明確にし、対象者の貢献やスキル開発の観点から正当性を説明することで、他の従業員からの不公平感を軽減できます。
また、i-dealsが与えるポジティブな影響を最大化するために、その付与が従業員個人だけでなく、チーム全体にどのように貢献するかを明示することも有効です。さらに、i-dealsの付与によるコストと便益をバランスよく評価し、チーム全体の成功に寄与する戦略的な運用を目指すことが求められます。
上司の感情的支援がスケジュールの柔軟性重視に影響
資源保存理論を基としたi-dealsの研究があります。資源保存理論とは、人がストレスを避けるために自分の持つ資源(時間、エネルギー、人間関係など)を守り、さらに増やそうとする行動や心理を説明する理論です。
上司の感情的支援がスケジュールの柔軟性を重視したi-dealsを通じて、従業員の家庭でのパフォーマンスを向上させ、仕事での逸脱行動(組織や他者に悪影響を与える行為)軽減にどのように影響を及ぼすかを検討しました[8]。この調査は、チリとコロンビアの企業で働く512名の従業員とその上司94名を対象に実施されました。
調査の結果、上司の感情的支援、つまり職場で同僚や上司が相手の感情に寄り添い共感や励ましを通じて心理的な安心感を与えるサポートは、従業員が柔軟にスケジュールを変更することを上司に交渉することを容易にし、それが家庭でのパフォーマンス向上をつなぐ役目を果たすことが示されました。
さらに、家族に十分配慮した職場環境が強く認識される場合、この効果がより顕著になることも明らかになりました。なぜならば、上司からの感情的支援により、従業員が心理的に安心感を得ることで、上司に対して個人的な要望やニーズを伝えやすくなるからです。
一方で、スケジュール柔軟性i-dealsと逸脱行動との間に直接的な関連性は見られませんでした。しかし、向社会的動機づけ(他者や組織の利益のために進んで貢献しようとする意欲や姿勢)の高い従業員においては、逆に逸脱行動が増加する可能性が示唆されました。これは、柔軟性i-dealsによって家庭活動が優先されすぎた結果、仕事に費やすリソースが不足することが原因と考えられます。
実践的な含意として、スケジュール柔軟性i-dealsが従業員のワーク・ライフ・バランスを改善し、全体的なパフォーマンス向上に寄与する可能性を示しています。特に、上司の感情的支援が重要な役割を果たすことが確認されており、従業員の多様なニーズを理解し、それに対応する柔軟な支援を提供する能力がマネージャーに求められます。
一方で、向社会的動機づけが高い従業員に対しては、仕事と家庭のリソース配分を適切に管理するサポートが必要です。例えば、自己管理ツールやリソース配分に関する研修を実施することで、家庭優先による職場でのリソース不足を防ぐことができます。
マネジメントへの応用として、マネージャーは従業員の個別ニーズを汲んでスケジュールの柔軟性を持たせることが求められます。スケジュールの柔軟性はワーク・ライフ・バランスを支援するために効果的であり、従業員の満足度とエンゲージメントを高める可能性があります。また、組織の全体的な家族支援に関する方針を見直し、職場全体のリソース管理を強化することで、従業員のパフォーマンス向上と職場環境の改善が期待されます。
職務遂行能力と自己効力感の向上、仕事過負荷軽減に影響
理論編の最後に、職務設計理論を基盤に、タスク、キャリア、柔軟性に関するi-dealsが従業員のパフォーマンスや心理的ウェルビーングにどのような影響を与えるかを探った研究を紹介します[9]。
- タスクideals: 個々の従業員が交渉して得る、自分のスキルや興味に合った特別な仕事の内容や役割を調整する制度
- キャリアi-deals:従業員が自らのキャリア成長やスキル開発のために交渉して得る、個別に設計された研修や成長機会
- 柔軟性i-deals:従業員が交渉して得られる、働く時間や場所、勤務形態を柔軟に調整できる個別な取り決め
この調査は、ドイツの精神科・神経科病院に勤務する医療従事者187名を対象に実施されました。アンケートを通じて、i-dealsの有無と内容、職務特性、従業員の心理的ウェルビーング状態に関するデータを収集し、これらの関係性を分析しました。
調査の結果、3つのi-dealsは異なる仕事特性と成果に関係していることが明らかになりました。具体的には、タスクi-dealsは職務の自律性を高め、それが職務遂行能力の向上のつなぎ役となりました。
キャリアi-dealsは技能習得と正の相関を示し、これを通じて職業的自己効力感を向上させる一方で、感情的苛立ちを軽減する効果も確認されました。これが何を意味するかというと、個別にカスタマイズされたキャリア支援や学習の機会が与えられることで、従業員は自分の能力や役割に自信を持つようになり、仕事上のストレスや不安が減少し、より安定した精神状態で職務に取り組むことができるようになるということです。
柔軟性i-dealsは仕事の過負荷を軽減し、それが感情的および認知的苛立ちの低減をつなぐ役目を果たすことが示されました。これもまた何を意味するかというと、従業員が自分の仕事の進め方やスケジュールを柔軟に調整できる環境が整うことで、業務量や時間的制約に対するプレッシャーが軽減され、結果として心理的なストレスや集中力の低下が防がれるということです。
これらの成果は、i-dealsが従業員の動機づけ、学習、ストレス軽減プロセスにおいて重要な役割を果たすことを示唆しています。
本研究の実践的な含意として、i-dealsの効果的な活用には、従業員の個別ニーズを的確に把握し、それに応じた職務条件を提供する柔軟性が求められます。タスクi-dealsは、従業員のスキルや興味に応じた職務を調整することで、内発的動機づけとパフォーマンス向上を促進します。
また、キャリアi-dealsはスキル向上やキャリア形成を支援するため、長期的な従業員エンゲージメントの維持に寄与します。さらに、柔軟性i-dealsは、ワーク・ライフ・バランスの改善を通じて、従業員のストレス軽減と生産性向上を可能にします。
これをマネジメントに応用する際、リーダーは従業員の個別のニーズを理解し、それに応じたi-dealsを交渉・実現するスキルを持つことが求められます。さらに、i-dealsは従業員との信頼関係を強化する手段にもなり得ます。
例えば、リーダーメンバー交換関係(Leader-Member Exchange: LMX)が良好であるほど、i-dealsの交渉が成功しやすいことが確認されています。これに基づき、リーダーは公正で透明性のある交渉プロセスを構築し、組織の信頼性を高めることが重要です。
理論からの考察
i-dealsは、多様な人材確保や従業員のモチベーション向上、組織全体の成果改善に貢献する革新的なツールです。これまでの研究は、i-dealsが職場における職務満足度やエンゲージメントを高め、離職意図を低下させる効果を持つことを示してきました。
また、柔軟性、能力開発、タスク設計といったi-dealsの具体的なタイプごとに、その影響が異なることも明らかになっています。これらの成果を踏まえると、i-dealsを適切に活用することで、個々の従業員のニーズに応じた柔軟な雇用関係の構築が可能となり、結果的に組織の生産性向上や競争力強化に寄与することが期待されます。
しかし一方で、i-dealsの導入には慎重な計画と管理が必要です。特に、従業員間の公平感や透明性を確保しなければ、特別待遇への不満や組織内の対立を招く可能性があります。この課題に対処するためには、i-dealsの付与基準を明確化し、その意図や目的を従業員に周知徹底することが重要です。また、i-dealsの適用範囲や効果を定期的に評価し、必要に応じて修正を行う柔軟な体制を整えることも求められます。
さらに、文化的背景や従業員の特性を考慮したi-dealsの設計が不可欠です。個人主義的な文化圏では、スキル開発やキャリア形成を重視したi-dealsが効果的である一方、集団主義的な文化圏では、チーム全体の利益を考慮した取り決めが適しています。
加えて、リーダーシップの役割も重要です。リーダーは従業員との信頼関係を構築し、公正で透明な交渉を実施することで、i-dealsの付与が組織全体の目標にどのように寄与するかを示す必要があります。
i-dealsは単なる個別待遇ではなく、従業員と組織が相互に利益を得られる関係を構築するための戦略的な手段です。その成功には、公平性、透明性、適応性を備えたマネジメントの実践が不可欠です。組織がこれらの要素を適切に取り入れることで、i-dealsは単なる人材確保の手段を超え、持続可能な成長を支える基盤となるでしょう。
脚注
[1] 厚生労働省(2024). 労働経済の分析-人手不足への対応
[2] Rousseau, D. M., Ho, V. T., & Greenberg, J. (2006). I-deals: Idiosyncratic terms in employment relationships. Academy of management review, 31(4), 977-994.
[3] Lai, L., Rousseau, D. M., & Chang, K. T. T. (2009). Idiosyncratic deals: Coworkers as interested third parties. Journal of Applied Psychology, 94(2), 547.
[4] Liu, J., Lee, C., Hui, C., Kwan, H. K., & Wu, L. Z. (2013). Idiosyncratic deals and employee outcomes: The mediating roles of social exchange and self-enhancement and the moderating role of individualism. Journal of applied psychology, 98(5), 832.
[5] Ng, T. W., & Feldman, D. C. (2015). Idiosyncratic deals and voice behavior. Journal of Management, 41(3), 893-928.
[6] Guerrero, S., & Challiol-Jeanblanc, H. (2016). Idiosyncratic deals and helping behavior: The moderating role of i-deal opportunity for co-workers. Journal of Business and Psychology, 31, 433-443.
[7] Vidyarthi, P. R., Singh, S., Erdogan, B., Chaudhry, A., Posthuma, R., & Anand, S. (2016). Individual deals within teams: Investigating the role of relative i-deals for employee performance. Journal of Applied Psychology, 101(11), 1536.
[8] Kelly, C. M., Rofcanin, Y., Las Heras, M., Ogbonnaya, C., Marescaux, E., & Bosch, M. J. (2020). Seeking an “i-deal” balance: Schedule-flexibility i-deals as mediating mechanisms between supervisor emotional support and employee work and home performance. Journal of Vocational Behavior, 118, 103369.
[9] Hornung, S., Rousseau, D. M., Weigl, M., Müller, A., & Glaser, J. (2014). Redesigning work through idiosyncratic deals. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(4), 608-626.
執筆者
 樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
早稲田大学政治経済学部卒業、カリフォルニア州立大学MBA修了、UCLA HR Certificate取得、立命館大学大学院博士課程修了。博士(人間科学)。国家資格キャリアコンサルタント。ビジネスの第一線で30年間、組織と人に関する実務経験、専門知識で、経営理論を実践してきた人事のプロフェッショナル。通信会社で人事担当者としての経験を積み、その後、コンサルティングファームで人事コンサルタントやシニアマネージャーを務め、さらに銀行で人事部長などの役職を歴任した後、現在はFWD生命にて執行役員兼CHROを務める。ビジネスと学術研究をつなぐ架け橋となることを目指し、実践で役立つアプローチを探求している。