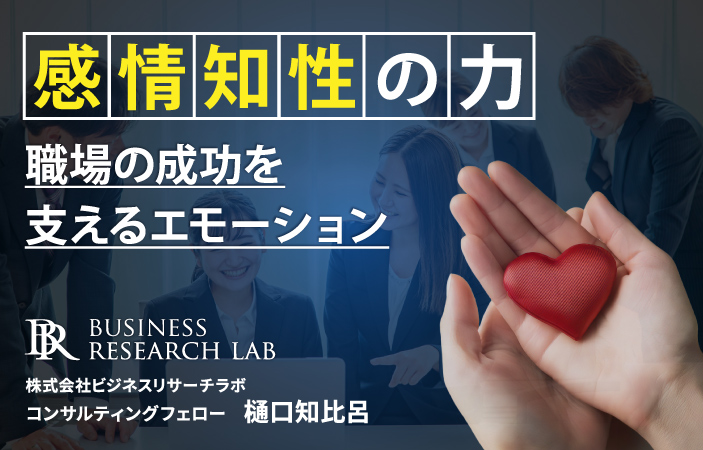2025年3月14日
感情知性の力:職場の成功を支えるエモーション
現代の職場環境では、個々のスキルだけでなく、感情や人間関係に対する適切な理解と対応がますます求められています。その中で、「感情知性(Emotional Intelligence: EI)」は、従業員やリーダーが自己や他者の感情を認識し、管理し、活用する能力として注目を集めています。このスキルは、単なる個人の特性を超え、組織全体の成功や持続可能な成長を支える重要な要素であることが、さまざまな研究を通じて明らかになってきました。
本コラムでは、感情知性が職場にどのような影響を及ぼし、どのように実践的に活用できるかを多角的に検証します。最新の研究結果を基に、感情知性が従業員のパフォーマンス向上やストレス軽減、チームの有効性向上に寄与する仕組みを解説するとともに、組織が感情知性を戦略的に活用するための具体的な方法を探ります。感情知性が持つ可能性を理解し、その恩恵を最大化するための知見を共有していきます。
パフォーマンス向上とストレス軽減に効果あり
最初に、感情知性が従業員の成果にどのように影響を与えるのかを包括的に分析したメタ分析を紹介します[1]。メタ分析とは、独立して実施された複数の研究結果を統合し、それらを解析する方法です。
研究では、感情知性の3つのアプローチ(能力EI、自己報告EI、混合EI)に基づき、組織コミットメント、組織市民行動、職務満足、職務遂行能力、職務ストレスとの関係を明らかにすることを目的としました。
感情知性の3つのアプローチ分類の特徴を簡単に説明します。
- 能力EI:感情知性を知能の一部として捉え、感情の知覚、理解、管理といったスキルを客観的に測定。例えば、他者の感情を正確に読み取り、それに基づいて適切に対応する能力が評価される。
- 自己報告EI:感情知性を自己評価に基づいて測定。感情を認識し管理する能力を、主観的な質問に回答する形で評価。例えば、「ストレスの多い状況でも冷静に対処できる」といった自己認識に関する設問に答えることで測定する。
- 混合EI:感情知性を「能力」と「特性」の混合として捉え、対人スキルや適応力、楽観性など幅広い要素を含む。例えば、リーダーシップや自己動機付けの高さなど、職場での成功に寄与する多面的な特性を評価される。
1990年から2020年初頭までの期間に発表された287の論文と118の未発表研究から得られた78,159人のデータを対象に、分析が行われました。
研究の結果、感情知性は、組織コミットメント、組織市民行動、職務満足、職務遂行能力に正の相関(一方が増えれば、もう一方も増える関係)があり、職務ストレスには負の相関(一方が増えると、もう一方は減る関係)を持つことが明らかになりました。特に、自己報告EIが他のアプローチと比べて、これらの成果に最も強い影響を与えることがわかりました。
たとえば、自己報告EIは職務満足や職務遂行能力において最も高い相関を示し、職務ストレスに対しても最も強い負の相関を持っていました。一方で、感情知性の影響は管理職と非管理職で異なり、非管理職の従業員において、職務満足や職務遂行能力などの成果により強く関連する傾向が見られました。
これらの知見には、実践的な示唆が含まれています。感情知性は、従業員のパフォーマンスを向上させるだけでなく、職場でのストレスを軽減するための重要な要素となります。これに基づき、組織は感情知性を高めるためのトレーニングや能力開発プログラムを導入することが有益と考えられます。
たとえば、従業員が自己や他者の感情を効果的に管理できるようにするワークショップや、自己報告EIを向上させるフィードバックセッションが挙げられます。さらに、感情知性が高い従業員は、職務遂行能力や職務満足度が向上するだけでなく、同僚との良好な関係を築く傾向があるため、チームの生産性や協力意識を高める可能性もあります。
マネジメントの視点からは、感情知性を評価基準に取り入れることが有用です。リーダーシップトレーニングでは、管理職が感情知性を実践できるスキルを磨くことが重要です。
また、従業員がストレスを感じる職場環境を改善するために、感情知性に基づいたコミュニケーション戦略を導入することが効果的でしょう。これにより、従業員一人ひとりが持つ潜在能力を最大限に引き出し、組織全体のパフォーマンスを向上させることが期待できます。
職務満足度やキャリア・コミットメントが向上
感情知性は、職場における管理職の成功において重要な役割を果たすスキルとされています。次に紹介する研究は、イスラエルの地方自治体で最高財務責任者として働く上級管理職を対象に、感情知性が仕事に対する態度や行動、成果にどのような影響を与えるかを調査しました[2]。
262名の上級管理職にアンケートを送付し、98名から得られた回答をもとに分析を行いました。この調査により、感情知性が仕事上のポジティブな要因を高めるだけでなく、仕事と家庭の葛藤に対処する能力とも関連していることが明らかになりました。
分析の結果、感情知性の高い管理職は、組織やキャリアへのコミットメントが強く、職務遂行能力や利他的行動といった成果にもポジティブな影響を及ぼすことが確認されました。特に、感情的知性が高いほど、職務満足度やキャリア・コミットメントが向上する傾向が見られました。
一方で、感情知性が高い管理職は、仕事と家庭の葛藤を効果的に管理し、この葛藤がキャリア・コミットメントに与える負の影響を緩和することが分かりました。一方で、仕事への関与(自分の仕事に対して積極的に関わり、その成功や成果に対して責任を感じる状態)に関しては、感情知性との関連性が統計的に有意な差は確認されませんでした。
これらの知見は、管理職の育成や組織運営において重要な示唆を提供します。まず、感情知性の高い上級管理職は、職務遂行能力や利他的行動において高いパフォーマンスを示し、組織の生産性や調和に寄与することが期待されます。そのため、組織は、感情知性を評価基準の一部として採用時や昇進時に活用することが有益です。
また、既存の管理職に対しては、感情知性を高めるためのトレーニングプログラムを導入することが効果的です。具体的には、自己の感情を認識し、適切に管理するスキルを向上させるワークショップや、チームメンバーの感情に寄り添うコミュニケーション能力の開発が挙げられます。
さらに、感情知性が仕事と家庭の葛藤を緩和する役割を持つことを踏まえ、職場におけるワークライフバランス支援策を強化することも重要です。たとえば、フレックスタイム制度や在宅勤務の導入により、管理職が家庭のニーズに柔軟に対応できる環境を整えることで、感情知性の高い管理職がその能力を最大限に発揮できるよう支援することが可能です。
職場における社会的支援に対する満足度の高さと、職場におけるパワーの認知度の高さが感情知性に影響
感情知性が職場での充実にどのように貢献するのかを検討した研究があります[3]。職場での充実とは、働く環境や仕事そのものが満たされており、従業員が心理的・感情的に豊かさを感じている状態で、指標には従業員の良好なメンタルヘルスと、従業員のワーク・エンゲイジメントにおける個人と組織の相互作用の質が用いられます。
オーストラリアの社会人319人を対象に調査を実施し、参加者は、オンライン形式で感情知性、メンタルヘルス、ワーク・エンゲイジメント、職場での社会的支援の満足度、自身の職場での力に関する認識について回答しました。この研究の目的は、感情知性が職場における良好な成果や充実を支える要因であるかどうかを明らかにすることでした。
調査の結果、感情知性が高い従業員ほど、メンタルヘルスが良好であり、ワーク・エンゲイジメントが高く、職場での社会的支援に満足しており、職場での自身の力をより強く認識していることが分かりました。さらに、社会的支援の満足度と職場の力の認識は、感情知性がメンタルヘルスやワーク・エンゲイジメントに及ぼす影響の橋渡しをしていることが示されました。
これらの結果から、感情知性が職場充実の基盤となり、職場環境で他者からの支援を受けやすくしたり、自身の役割や影響力をより強く感じさせることがわかります。
実践的な含意として、この研究は職場における感情知性の重要性を再確認するものです。従業員の感情知性を高めるためのトレーニングを導入することで、メンタルヘルスやワーク・エンゲイジメントが向上し、結果として職場全体のパフォーマンスが高まる可能性があります。たとえば、感情の認識と管理スキルを鍛える研修や、社会的支援を意識的に活用する方法を教えるセッションが有効です。
マネジメントの観点からは、感情知性が高い従業員が職場に与える影響を考慮し、人材採用や育成において感情知性を評価基準に組み込むことが考えられます。また、職場の社会的支援ネットワークを強化し、従業員が互いに支援し合える環境を整えることも重要です。具体的には、メンタルヘルスの促進やチームビルディングを目的としたワークショップを開催することで、組織全体の職場充実をサポートできます。
さらに、権力の認識に関連する施策も検討するとよいでしょう。感情知性が高い従業員は、自分の役割を正しく評価し、職場での存在感を高める傾向があります。これをサポートするために、リーダーシップ研修やキャリア開発プログラムを通じて、従業員が自信を持って職場に貢献できる仕組みを構築することが有益です。
感情知性が高い経営幹部は、リーダーシップの有効性が高い
感情知性がリーダーシップの有効性にどのように影響するのかを検討した研究を紹介します[4]。オーストラリアの公共サービス機関で働く41名の経営幹部を対象に行われ、参加者には、感情知性、性格、認知能力を測定するテストが実施されました。
リーダーシップの有効性は、直属の上司や部下149人による360度評価と、業績評価を通じて客観的に測定されました。この研究の目的は、感情知性が性格やIQでは説明できないリーダーシップの成果にどのように寄与するかを明らかにすることでした。
調査の結果、感情知性が高い経営幹部は、リーダーシップの有効性が高いと評価される傾向があることが分かりました。特に、感情を知覚する能力は、リーダーシップの「どのように」職務を遂行するかという具体的な行動やアプローチを予測する上で、特に重要であることが明らかになりました。
一方、リーダーシップの「何を」達成するかに関しては、性格が主な影響を与えることが明らかになりました。これらの結果は、感情知性が部下や同僚との関係性を円滑にし、より高い業績評価を得る要因となることを示唆しています。
この知見には、実践的な含意が多く含まれています。まず、感情知性を測定することで、リーダーとしてのポテンシャルを予測しやすくなるため、経営幹部の選抜や育成に活用することに役立ちます。特に、感情知性が高いリーダーは、部下との信頼関係を築きやすく、チーム全体の業績を向上させる可能性が高いです。
研修プログラムにおいても、感情を知覚し、適切に管理するスキルを向上させるセッションを組み込むことで、リーダーシップの効果を最大化することができます。
マネジメントへの応用としては、組織は感情知性を重要なリーダーシップスキルとして評価基準に組み込むとよいでしょう。感情知性の高さは、単に業績を出す能力だけでなく、部下のマネジメントや職場の雰囲気の改善にも寄与します。
さらに、感情知性を活用したフィードバックの仕組みを整えることで、リーダーが自己のスキルを客観的に把握し、継続的に成長できる環境を提供することが可能です。また、新たに採用された経営幹部が職務を開始する前に感情知性を測定し、そのスキルに基づいてリーダーシップ育成計画を立てることも有効です。
感情知性の高いチームが、信頼、グループアイデンティティ、グループ効力感を強化
グループの感情知性の向上が、チームの有効性にどのように寄与するかを探った研究を紹介します[5]。感情知性はこれまで個人の特性として議論されることが多かったものの、この研究は、現代の職場では多くの仕事がチームで行われることを踏まえて、グループ全体の感情知性の重要性に焦点を当てています。
この研究の主な成果は、感情知性の高いチームが、信頼、グループアイデンティティ(自分がユニークで価値のあるグループに属しているというメンバーの感覚)、グループ効力感(チームが良いパフォーマンスを発揮でき、グループのメンバーは離れて働くよりも一緒に働いた方が効果的であるという信念)を強化し、これらがタスクへの取り組みや協力の質を向上させることを示唆しています。
これを実現するためには、3つの相互作用レベル(個人、グループ、境界を越えたレベル)で感情に対処するための規範を構築することが重要です。例えば、メンバー間でお互いを深く理解し、肯定的な環境を育む行動や、対立を建設的に解消する規範が挙げられます。また、外部組織との良好な関係を築き、広範囲な組織目標に沿った行動を取ることも有益です。
この知見には、具体的な実践的含意があります。まず、チームリーダーは、感情知性を重視したチームビルディングを推進するとよいでしょう。例えば、チーム内の規範を定め、対話やプロセス評価を通じてグループの感情的課題に積極的に向き合うことが求められます。
また、チームの感情状態や課題を定期的に評価し、外部からのフィードバックを受け入れる仕組みを導入することも効果的です。このような取り組みは、メンバーのモチベーション向上や離職防止に繋がり、チーム全体の生産性を高めます。
マネジメントへの応用としては、感情知性の高いチームが持つ特性を基に、研修プログラムや選抜基準を設計することが考えられます。たとえば、リーダー候補の育成において、単に技術的能力を評価するだけでなく、感情を適切に管理し、他者を巻き込む能力を重視する選考プロセスを取り入れるとよいでしょう。
さらに、感情知性の向上を目的とした定期的なワークショップやロールプレイングを実施することで、メンバー間の信頼を深め、建設的な対話を促進する環境を構築できます。
メンバーとリーダーの感情知性は補完的な関係
グループレベルで検証する研究をもう一つ紹介します。この研究は、チーム内の平均的なメンバーの感情知性とリーダーの感情知性が、チーム内信頼(メンバーが互いの信頼性を信じ、他のメンバーがチームの利益を大切にしていると感じること)を通じてチームパフォーマンスにどのように影響を与えるかを探り、その関係性に新たな知見を提供しました[6]。
研究対象は、アメリカ西部の都市部で活動する91の職場チームで、業種や構成員の背景は多岐にわたっています。調査方法としては、訓練を受けた研究アシスタントが既存の人脈を活用して参加者を募集し、回答者の感情知性、チーム内信頼、パフォーマンスについてデータを収集しました。
分析の結果、メンバーの感情知性とリーダーの感情知性が、それぞれチーム内信頼と正の相関を持ち、それがチームパフォーマンスに影響を及ぼすことが明らかになりました。特に、感情評価(他者の感情を正確に認識し、理解する能力)、ソーシャルスキル(他者との効果的な相互作用を可能にする能力)という感情知性の次元が、パフォーマンスにおいて重要な役割を果たしていました。
一方で、興味深いことに、メンバーの感情知性とリーダーの感情知性は補完的な関係にあることも示されました。具体的には、メンバーの感情知性が低い場合はリーダーの感情知性が、リーダーの感情知性が低い場合はメンバーの感情知性が高パフォーマンスを達成する上で有効に働いていました。
つまり、必ずしも両者の感情知性が高い状態である必要はなく、一方が不足している場合でももう一方がそれを補うことで、よい成果を生む可能性があることを示唆しています。
これらの知見は、職場における感情知性の重要性を再確認させるものであり、実務的な含意も多岐にわたります。第一に、感情知性はチーム形成や人材採用時に考慮するとよい重要な属性となり得ます。特に、感情的な労働や相互依存が求められる業種、たとえば接客業・サービス業、医療・介護、教育や、販売・営業といった職種では、感情知性の高いメンバーがチームの成功に寄与する可能性が高いといえます。
第二に、リーダーは、メンバーの感情知性が低い場合には特に感情管理に注意を払う必要があります。また、感情知性を高めるトレーニングや研修を導入することも、チームのパフォーマンス向上に効果的であると考えられます。
マネジメントの観点からは、感情知性をリソースとして戦略的に活用する方法を検討する必要があります。研究の結果を踏まえると、チームの特性や状況に応じて、リーダーやメンバーのどちらの感情知性を重視するかを柔軟に調整することが求められます。
たとえば、リーダーが高い感情知性を発揮してチームの信頼を築く環境を提供する一方、メンバーの感情知性が高い場合には、リーダーが過度に介入せずに彼らの自律性を尊重することが重要です。
感情知性とスピリチュアリティに類似性あり
次に、感情知性とスピリチュアリティが職場のパフォーマンスに与える影響について検討した研究を紹介します[7]。スピリチュアリティとは、霊性、精神性を指し、例えば、宇宙や超越的な存在、神とのつながりを感じたり、光を見たり、内なる声や他の声を聞いたりする体験のことをいいます。
従来、組織研究において感情やスピリチュアリティは敬遠される傾向にありましたが、近年、それらが職場の成功や有効性に与える可能性に注目が集まっています。この研究では、感情知性とスピリチュアリティの両方が職場での成功にどのように寄与するかを明らかにするために、これらの概念を統合した理論モデルが提案されています。
研究では、感情知性とスピリチュアリティが共通して個人および社会的スキルの発展に寄与し、職場での有効性を高める要因であることが示されました。感情知性は、自己認識、感情管理、社会的認識、そしてソーシャルスキルの向上をもたらし、スピリチュアリティは自己実現や利他主義、共感など、職場における肯定的な態度を促進します。両者には類似性があり、互いに補完し合うことで、個人と組織の成功に寄与する可能性があります。
一方で、相違点は、感情知性が自己認識や感情管理、社会的スキルの向上を重視しているのに対し、スピリチュアリティは自己実現や利他主義、共感といった精神的・内面的な態度の促進に焦点を当てている点にあります。
実践的含意として、感情知性とスピリチュアリティの向上が職場における生産性や従業員満足度の向上につながることが挙げられます。例えば、感情知性トレーニングプログラムやスピリチュアルな実践(瞑想や感謝の共有など)を取り入れることで、従業員の感情的成熟や精神的健康が向上し、職場のコミュニケーションやチームの協力が円滑になるでしょう。
マネジメントへの応用としては、リーダーが従業員の感情知性とスピリチュアリティを育成するための具体的な施策を導入することが考えられます。感情知性の観点では、感情管理スキルの向上を目指した研修やフィードバックの機会を提供することで、職場環境の感情的知性を高めることが可能です。
ストレスに関連するうつ症状を軽減
対人サービス従事者を対象に、感情知性が職場におけるストレスの認知およびウェルビーイングに関連する結果にどのように影響するかを調査した研究があります[8]。対象は医師、看護師、教師、保護観察官、管理職の330名で、質問票による調査が行われました。
調査の結果、感情知性は職業性ストレスの緩衝材として働き、特にストレスに関連するうつ症状を軽減する効果があることが示されました。しかし、感情知性と職業性ストレスやウェルビーイング全体との関連は強くなく、その影響力は限定的でした。
感情知性が高い従業員は、ストレス要因を低く認識し、精神的ウェルビーイングを維持する傾向が見られましたが、身体的ウェルビーイングには顕著な影響は見られませんでした。また、性別による違いも指摘され、女性は感情知性が高い一方で、不安や不眠などの健康課題をより多く抱える傾向がありました。
この研究の実践的含意として、感情知性を向上させるトレーニングの導入が挙げられます。ストレス管理研修を通じて従業員が感情を効果的に認識し、管理するスキルを習得すれば、職業性ストレスの影響を軽減し、職場での心理的健康を保つことができます。
さらに、採用プロセスに感情知性を測定する質問票を導入することで、ストレス耐性の高い候補者を選抜することが可能となり、組織全体のパフォーマンス向上につながるでしょう。
マネジメントの観点からは、感情知性を活用したストレス対策の強化が重要です。例えば、従業員の感情的なニーズを把握し、共感をもって対応するマネジメントスタイルを促進することで、職場の信頼関係を築くことができます。また、感情的知性を基盤としたリーダーシップトレーニングを実施することで、従業員同士の相互理解が深まり、職場環境が改善される可能性があります。
感情知性はリーダーシップに必要か否か
感情知性の妥当性、測定法、職場での有効性に焦点を当てた意見交換を通じ、リーダーシップにおいて感情知性がどの程度必要とされるかを検討する研究があります[9]。リーダーシップにおける感情知性の役割を支持する研究者と批判する研究者がそれぞれの視点を述べ、将来の研究の方向性についても提案が行われました。
研究では、感情知性が効果的なリーダーシップに必要不可欠であるとする支持派が、近年のメタ分析や理論的進展を根拠に、感情知性の有効性を示す証拠を提示しました。感情知性は、リーダーが部下の感情を理解し管理する能力を高め、職場でのパフォーマンス向上や従業員の満足度向上に寄与する可能性があるとされています。
一方、批判派は、感情知性の測定法やその構成要素の曖昧さを指摘し、既存の研究における方法論的限界を問題視しました。例えば、感情知性の測定がビッグファイブなどの性格特性(外向性、神経症傾向、開放性、勤勉性、協調性)と重複しており、独自の指標として十分な説得力を持っていないという指摘があります。
この研究の実践的含意として、感情知性を活用したリーダーシップ開発プログラムの重要性が挙げられます。リーダーシップトレーニングに感情知性を組み込むことで、リーダーが自分自身と部下の感情をより効果的に管理し、職場のストレスを軽減できる可能性があります。
たとえば、感情知性トレーニングを通じてリーダーが部下との信頼関係を構築しやすくなり、職場のモチベーションが向上することが期待されます。また、感情知性の測定を採用プロセスに組み込むことで、感情的能力が高い候補者を特定する方法としても有用です。
マネジメントへの応用としては、感情知性の活用を組織文化の改善に取り入れることが考えられます。例えば、感情知性に基づいたフィードバックや対人関係のスキルを重視することで、チーム内のコミュニケーションを円滑にすることが可能です。また、感情知性の活用は、不確実性の高い状況で特に重要であり、感情を理解し、効果的に対処できるリーダーシップが組織の安定と成長を支える鍵となります。
この研究は、感情知性の支持派と批判派の双方の意見がある中で、感情知性がリーダーシップにおいて一定の役割を果たしうる可能性を示唆しています。一方で、その測定法や理論的基盤にはさらなる精査が必要であることを強調しています。この議論は、感情知性の適用範囲とその限界を深く理解し、より良い職場環境の構築に役立つ方向性を示唆するものです。
感情知性は重要な資源として組織全体の成功を導く
感情知性は、現代の職場環境において、従業員やリーダーのパフォーマンス向上、ストレス軽減、チームの有効性向上に寄与する重要な資源であることが多くの研究で示されています。これまでの調査結果は、感情知性が単なる個人特性ではなく、組織全体の成功や持続的成長を支える要因であることを明確にしています。
感情知性の高い従業員は職務満足度が高く、メンタルヘルスが良好で、職場の協力関係を築く能力に優れています。また、感情知性を持つリーダーは部下との信頼関係を深め、チームのパフォーマンス向上に大きく貢献することが期待されます。
さらに、チーム全体で感情知性を高める取り組みは、信頼やグループの一体感を促進し、複雑な課題に対する柔軟な対応を可能にします。特に、感情的な労働や高い相互依存が求められる職場では、感情知性の価値がさらに高まります。
実務的には、感情知性の向上を目的としたトレーニングや研修の導入、採用や昇進時の評価基準としての活用が推奨されます。さらに、感情知性に基づいたマネジメント手法を導入することで、組織全体のパフォーマンスを最大化することが可能です。感情的な課題に積極的に向き合い、それを効果的に管理するスキルを持つリーダーやチームが、未来の組織を支える基盤となるでしょう。
感情知性は職場の成功に欠かせない要素として、組織や個人の成長においてますます重要な役割を果たしていくと考えられます。この知見を実践に活かすことで、より良い職場環境と持続的な成功を築くことが期待されます。
脚注
[1] Doǧru, Ç. (2022). A meta-analysis of the relationships between emotional intelligence and employee outcomes. Frontiers in psychology, 13, 611348.
[2] Carmeli, A. (2003). The relationship between emotional intelligence and work attitudes, behavior and outcomes: An examination among senior managers. Journal of managerial Psychology, 18(8), 788-813.
[3] Schutte, N. S., & Loi, N. M. (2014). Connections between emotional intelligence and workplace flourishing. Personality and Individual Differences, 66, 134-139.
[4] Rosete, D., & Ciarrochi, J. (2005). Emotional intelligence and its relationship to workplace performance outcomes of leadership effectiveness. Leadership & Organization Development Journal, 26(5), 388-399.
[5] Druskat, V. U., & Wolff, S. B. (2001). Building the emotional intelligence of groups. Harvard business review, 79(3), 80-91.
[6] Chang, J. W., Sy, T., & Choi, J. N. (2012). Team emotional intelligence and performance Interactive dynamics between leaders and members. Small group research, 43(1), 75-104.
[7] Tischler, L., Biberman, J., & McKeage, R. (2002). Linking emotional intelligence, spirituality and workplace performance: Definitions, models and ideas for research. Journal of managerial psychology, 17(3), 203-218.
[8] Ogińska-Bulik, N. (2005). Emotional intelligence in the workplace: exploring its effects on occupational stress and health outcomes in human service workers. International Journal of Occupational Medicine & Environmental Health, 18(2).
[9] Dasborough, M. T., Ashkanasy, N. M., Humphrey, R. H., Harms, P. D., Credé, M., & Wood, D. (2022). Does leadership still not need emotional intelligence? Continuing “The Great EI Debate”. The Leadership Quarterly, 33(6), 101539.
執筆者
 樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
早稲田大学政治経済学部卒業、カリフォルニア州立大学MBA修了、UCLA HR Certificate取得、立命館大学大学院博士課程修了。博士(人間科学)。国家資格キャリアコンサルタント。ビジネスの第一線で30年間、組織と人に関する実務経験、専門知識で、経営理論を実践してきた人事のプロフェッショナル。通信会社で人事担当者としての経験を積み、その後、コンサルティングファームで人事コンサルタントやシニアマネージャーを務め、さらに銀行で人事部長などの役職を歴任した後、現在はFWD生命にて執行役員兼CHROを務める。ビジネスと学術研究をつなぐ架け橋となることを目指し、実践で役立つアプローチを探求している。