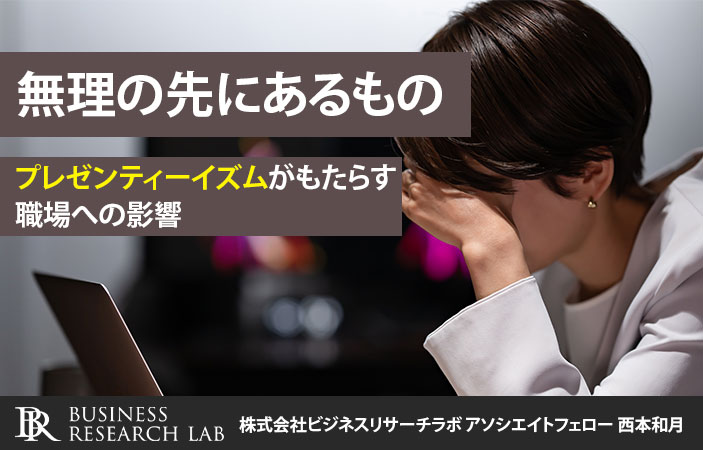2025年3月13日
無理の先にあるもの:プレゼンティーイズムがもたらす職場への影響
毎日健康で、元気に働くということは簡単なことではありません。インフルエンザなどの感染症やアレルギー疾患、腰痛などの筋・骨格系の不調、さまざまな原因から発生する頭痛など、私たちの身体の不調の原因は多岐にわたります。
しかも「健康」は身体のことだけではありません。世界保健機関(WHO)では、「健康とは、単に病気や虚弱がないというだけでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態である。」と健康を定義しています。
身体も心も社会的にもとなると、全く不調がないというのは難しく、すべての人が常に健康リスクと隣り合わせで働いていると考えることができます。実際に、風邪気味だから薬を飲んでマスクをして出勤というのはよくあることでしょう。
しかし、休む必要があるときにも無理をして働いているということはないでしょうか?
感染症だから同僚にうつしてしまうかもしれないとき、今休息をとらないともっと悪化することが予測されるとき、いつものように頭や身体がはたらかず成果があげられなさそうなとき、このような場合でも頑張って出勤する人はたくさんいます。
「体調不良で本来の能力が十分に発揮できない状態でも仕事を続ける」状態をプレゼンティーイズムと呼びます[1]。体調不良を押しても働こうとする意欲や、そうせざるを得ないときがあるということは理解できますが、無理をすることが様々な悪影響を生むことを実証した研究が数多く蓄積されているのです。
本コラムでは、研究知見をもとにプレゼンティーイズムが仕事や職場に与える影響や、組織はどのようにプレゼンティーイズムに対処していくべきかを解説します。個人と組織の両者にとって適した健康と仕事の両立を考えます。
プレゼンティーイズムの問題
多くの人が、実際の健康状態や機能に問題があったとしても、病気のまま働いていることが明らかにされています。不調があっても「休むほどではない」と頑張って出勤することは珍しいことではありませんが、実は多くの問題があることが分かっており、プレゼンティーイズムは欠勤よりコストが高いと考えられています。
生産性に及ぼす悪影響
病気の間は心身ともに機能が低下します。集中力も低下するため、状況を監視し迅速に対応する能力も低下し、エラーや判断ミスのリスクが高まる可能性もあります。
出勤はしていても、健康状態の影響で本来のパフォーマンスを発揮できないために、生産性で考えると欠勤したことと変わらなくなってしまう日がどれくらいあるのかを検討した研究があります[2]。
この研究では、回答者が自己報告した「健康状態に影響されながら出勤した日数」と「そのときの生産性の程度」から、プレゼンティーイズムによって失われる年間の労働日数を計算し、以下の結果が示されました。
ストレス:9.08日
睡眠障害:6.38日
首や背中の痛み:6.14日
アレルギー:6.12日
頭痛:5.97日
抑うつ気分:4.81日
風邪:4.47日
インフルエンザ:4.22日
健康に問題を抱えている本人は、つらい状況に耐えて頑張って出勤をしているのですが、成果としては休んだことと同じと言えてしまう日がこれだけあるのです。この状況は、従業員にとっても組織にとってももったいないことです。
同僚への悪影響
プレゼンティーイズムは他者に対しても悪影響を与える可能性があります。伝染性の疾患にり患しているにも関わらず出勤することは、職場の同僚の健康と安全にとってリスクとなります。
また、同僚のウェルビーイングに対する間接的なリスクも考えられます。病気の同僚に対応するためにより多くの労力を仕事に費やす必要があった結果、健康な同僚の仕事量が増え、ウェルビーイングの低下につながってしまうのです。
将来の健康問題や長期的な病気欠勤への悪影響
プレゼンティーイズムは現在だけでなく、将来にも悪影響となる可能性が指摘されています。プレゼンティーイズムは将来の欠勤を増加させることを示した研究があります[3]。
この研究では、韓国の一般健康診断を受けた非ホワイトカラー労働者を対象に、過去1年間のプレゼンティーイズムの経験について回答してもらい、翌年にまた過去1年間の傷病による欠勤の経験があるかどうかを回答してもらっています。
性別や年齢、健康指標、ライフスタイルの影響、職業の特徴の影響を除いたうえで、最初の1年間のプレゼンティーイズムと次の1年間の疾病による欠勤の関係を検討した結果、プレゼンティーイズムを経験した従業員は、プレゼンティーイズムがなかった従業員と比べて、翌年の病気による欠勤が4.90倍発生しやすいことが明らかにされました。
プレゼンティーイズムでは十分な休息がとれないため、初期の回復期を逃してしまい、病気を悪化させる可能性があると言えます。
プレゼンティーイズムを促進する仕事・職場の要因
プレゼンティーイズムの発生には、健康なのか、病気などによる体調不良があるかということが最初の要因にはなりますが、休まずに無理をして働くという状態を作ってしまう要因は実に多種多様であることが示されています[4]。
- 負荷の高い労働状況:過重労働、時間的プレッシャー、職務上の裁量が少ないなど
- 組織での立場:部下の手本となる必要があると感じること
- 非正規雇用や自営業:収入源が他にない、病気手当の欠如、自分が不可欠な存在であるという感覚
- 欠勤が評価に強く影響する厳格な勤怠管理方針:欠勤率が一定の基準に達すると、賃金カット、懲戒処分、解雇などの対象となる
- 職場での社会的環境:同僚間の協力、忠誠心
- 仕事に対するポジティブな志向:仕事をもっと頑張りたいというやる気、組織への献身、充実感や満足感
プレゼンティーイズムによって失われる年間の労働日数を示した先ほどの研究でも[5]、プレゼンティーイズムと関連する職場環境要因が検討されています。仕事と家庭の両立に問題がある、受けているリーダーシップに問題がある、能力開発の機会が乏しいといった経験がある従業員は、プレゼンティーイズムを経験する可能性が高いことが示されました。
ストレスがプレゼンティーイズムの大きな要因であることを示した研究もあります[6]。
危険でありながら国家の安全保障にとって重要な仕事を行っている、政府の警備複合施設の従業員を対象とした研究では、種類の異なるストレスがどれもプレゼンティーイズムと関連しているという結果が示されました。
職場でのストレス、家庭でのストレス、経済的ストレスという、3種類のストレスはどれもプレゼンティーイズムを引き起こす要因となることを示唆しています。
責任の重さもプレゼンティーイズムの要因であることが示されています。カナダの公務員の管理職を対象に、プレゼンティーイズムと欠勤の関係を調べている研究では[7]、責任の重さはプレゼンティーイズムとは正の関係を示しますが、欠勤とは負の関係を示すという結果が報告されました。
仕事の責任が重くなると、健康状態に関係なく出勤するという状態を引き起こしてしまうわけです。確かに責任の重い立場では無理をしてしまうことが増えてしまうことはありますが、病気が悪化し、長期的な休みを取らなければいけない状態になってしまったり、重大な局面でミスをしてしまうということになれば、他の人にも迷惑をかけてしまいます。重い責任を負っている人が、仕事と健康状態をうまく調整できる状況を整える必要があるでしょう。
組織の風土や職場の仲間関係の違いは、異なった方向からプレゼンティーイズムを促進するということも、ニュージーランドの小規模な私立病院と大規模な公立病院、小規模な工場という、3つの異なる職場の従業員へのインタビュー研究から報告されています[8]。
家族のような関係が職場で出来上がっている小規模な私立病院では、管理職によるプレッシャーはないものの、同僚を失望させたり、迷惑をかけたりしたくないという思いがプレゼンティーイズムを促進してしまいました。
関わる人の間で対立があったり、予測がつかない要素がある職場である大規模な公立病院では、その職務にある者として失望されたくない、プロフェッショナルとしての姿を保ちたいという思いがプレゼンティーイズムを促進していました。
危険な機械を扱ったり労働環境が劣悪な職場であった小規模な工場では、プレゼンティーイズムは管理職の圧力によって促進されていることが示されました。
プレゼンティーイズムはさまざまな要因が複雑に絡み合った結果起こる現象であることが、多くの研究から読み取ることができます。
職場の感謝がプレゼンティーイズムを減らす
多くの組織は欠勤を減らすための措置を講じていますが、プレゼンティーズムをうまく減らす効果的な要因は何でしょうか。
さまざまな企業や産業部門に所属するオーストリアの労働者を対象とした研究では、職場における「感謝」がプレゼンティーイズムの低下につながることを示しています[9]。
直属の上司の側から従業員の努力に気づき、その努力を認める「上司の感謝」と、社内の同僚やチームメンバーからの感謝である「一般的な感謝」の両方が、プレゼンティーイズムの低下につながることが示されました。
ただし、この結果は感謝とプレゼンティーイズムが直接つながるのではなく、感謝が仕事に関する資源(同僚からの支援や仕事の自律性など)を増加させ、そのことにより従業員のストレスが減少し、その結果としてプレゼンティーイズムが低下したというものでした。
プレゼンティーイズムを減らすことだけを考えるのではなく、先ほど紹介したようなプレゼンティーズムに関係する要因の改善が大切であると考えることができます。
適応的なプレゼンティーイズム
ここまでで紹介してきたように、プレゼンティーイズムには多くの問題が存在することは確かです。しかし、体調不良のなかでも頑張って仕事に励んでいる人たちの努力が完全に無駄かというと、そういうわけではありません。実際にプレゼンティーイズムは有害なだけのものというわけではなく、ポジティブな側面を持ちうることが研究で示されています。
仕事に従事できないほど衰弱している状態であることが比較的少ないのであれば、プレゼンティーイズムは病気中でも仕事で達成感を感じることができ、自己肯定感につながります。収入を保つことができれば経済的に困窮することも避けられますし、同僚に重い負担をかけてしまうことも避けられます。病気中に仕事が蓄積されることを防ぐことは、未来の自分の負担を減らすことにもなります。
プレゼンティーイズムを単純に減らすことだけを考えるのではなく、個人と組織の両方に利益をもたらす適応的なプレゼンティーイズムを考えていく重要さも示されています。
プレゼンティーイズムを「健康状態が悪化している中で、仕事への適応を促進することを目的とした、目的指向的な出席行動 」とみなしてプレゼンティーイズムを4つのタイプに分類し、職場環境の重要性について検討している研究があります[10]。
- 機能的プレゼンティーイズム(Functional Presenteeism) :不健康な状態であっても、健康にこれ以上負担をかけることなく仕事に従事し、要求されるパフォーマンスに応じている状態
- 機能不全プレゼンティーイズム(Dysfunctional Presenteeism):健康とパフォーマンスに悪影響を及ぼすプレゼンティーイズム行動であり、病気欠勤につながる可能性の高い持続不可能な状態
- 治療的プレゼンティーイズム(Therapeutic Presenteeism):健康により重点を置き、パフォーマンスにはあまり重点を置いていない状態
- 過剰達成型プレゼンティーイズム(Over-achieving Presenteeism):従業員が高水準の業績を維持できることを意味するが、病気からの回復を犠牲にしている状態
そのときの健康状態でできることの範囲を見定めて、可能なパフォーマンスを発揮することで、プレゼンティーズムを職場にとっても個人にとっても利益のあるものにすることが可能だと考えられます。
4つのプレゼンティーイズムはつながったものであり、個人の健康状態と職場の環境との関係によって、どのタイプになるかは変わっていくものになります。そして、健康とパフォーマンスが同時に達成される機能的プレゼンティーイズムは、プレゼンティーイズムからの出口となるものとも言えます。
したがって目標は機能的プレゼンティーイズムとなるのですが、健康状態に合わせて仕事を調整し、機能的プレゼンティーイズムに向かうことを可能にするのは、柔軟性と自律性を支援する職場環境であることが指摘されています。
臨機応変なスケジューリングやフレックスタイムなどの時間的な柔軟性と自律性、テレワークなどの空間的な柔軟性と自律性、パートタイムやジョブシェアなどの契約的な柔軟性と自律性は、どれも仕事の調整をしやすくしてくれます。同僚や上司から支援も仕事を自分の能力に合わせて調整するのに役立つものです。
ポジティブな職場環境は、機能的プレゼンティーイズムを説明する上で中心的な役割を果たすものとなります。
適切に管理され、適切な環境で支援されるのであれば、病気中の出勤は健康と業績に利益をもたらす可能性があるものとなります。個人と組織の両方から、個人の健康と組織の利益の両立を目指していくことが大切だと言えるでしょう。
脚注
[1] Kinman, G. (2019). Sickness presenteeism at work: prevalence, costs and management. British medical bulletin, 129(1), 69-78.
[2] McGregor, A., Ashbury, F., Caputi, P., & Iverson, D. (2018). A preliminary investigation of health and work-environment factors on presenteeism in the workplace. Journal of occupational and environmental medicine, 60(12), e671-e678.
[3] Won, Y., Kim, H. C., Kim, J., Kim, M., Yang, S. C., Park, S. G., & Leem, J. H. (2022). Impacts of presenteeism on work-related injury absence and disease absence. Annals of occupational and environmental medicine, 34.
[4] 脚注1(Kinman, 2019)と同じ
[5] 脚注2( McGregor et al., 2018)と同じ
[6] Callen, B. L., Lindley, L. C., & Niederhauser, V. P. (2013). Health risk factors associated with presenteeism in the workplace. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 55(11), 1312-1317.
[7] Gosselin, E., Lemyre, L., & Corneil, W. (2013). Presenteeism and absenteeism: differentiated understanding of related phenomena. Journal of occupational health psychology, 18(1), 75.
[8] Dew, K., Keefe, V., & Small, K. (2005). ‘Choosing’ to work when sick: workplace presenteeism. Social science & medicine, 60(10), 2273-2282.
[9] Bregenzer, A., Jiménez, P., & Milfelner, B. (2022). Appreciation at work and the effect on employees’ presenteeism. Work, 73(1), 109-120.
[10] Karanika-Murray, M., & Biron, C. (2020). The health-performance framework of presenteeism: Towards understanding an adaptive behaviour. Human Relations, 73(2), 242-261.
執筆者
 西本 和月 株式会社ビジネスリサーチラボ アソシエイトフェロー
西本 和月 株式会社ビジネスリサーチラボ アソシエイトフェロー
早稲田大学第一文学部卒業、日本大学大学院文学研究科博士前期課程修了、日本大学大学院文学研究科博士後期課程修了。修士(心理学)、博士(心理学)。暗い場所や狭い空間などのネガティブに評価されがちな環境の価値を探ることに関心があり、環境の性質と、利用者が感じるプライバシーと環境刺激の調整のしやすさとの関係を検討している。環境評価における個人差の影響に関する研究も行っている。