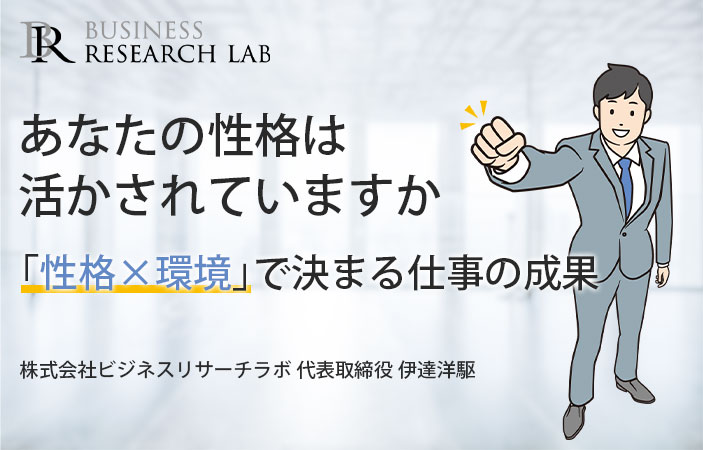2025年2月19日
あなたの性格は活かされていますか:「性格×環境」で決まる仕事の成果
職場における人々の振る舞いや成果は、その人の性格によって異なることがあります。例えば、外向的な人は営業職で成果を上げやすく、緻密で計画的な人は経理の仕事で実力を発揮しやすいかもしれません。しかし、これは本当でしょうか。また、仮にそうだとすれば、どのような状況でそれぞれの性格が活きるのでしょうか。
近年の研究では、性格特性が職場での行動に及ぼす作用は、置かれている状況によって変化することが分かってきました。性格は、それが活かされやすい状況で発揮されるのです。これを「特性活性化理論」と呼びます。
本コラムでは、性格特性が職場での成果にどのように作用するのかを、いくつかの実証研究をもとに解説します。特に、どのような状況でそれぞれの性格特性が活かされるのかに着目し、職場での人材活用について理解を深めていきます。
行動の状況特異性が見られる
人の性格は、時と場所を問わず一貫しているように思えます。しかし、実際の行動を詳しく観察すると、その場の状況に応じてかなり変化することが分かっています。この点を明らかにした古典的な研究では、特性理論に対する新しい視点が示されました[1]。
従来の人格理論では、性格特性が行動に一貫した作用を及ぼすと考えられてきました。しかし、子どもたちの遊び場での行動を観察した結果は、異なる見方を提示しています。
例えば、「優しい」と評価されている子どもでも、遊び場での具体的な行動は、一緒に遊ぶ相手や活動の内容によって大きく変わります。この子どもが常に優しい行動をとるわけではなく、相手や状況によって優しさの表れ方が異なるのです。
研究では、認知的社会学習の視点から、人格を形作る5つの要素が提案されました。それは、認知・行動構築能力、符号化戦略と個人的構成、行動–結果予測と刺激–結果予測、主観的刺激価値、そして自己制御システムと計画です。これらの要素が相互に作用しながら、状況に応じた行動の選択に関わっているのです。
この研究では、子どもたちの遅延満足に関する実験も行われました。将来的な報酬のために現在の欲求を抑制する能力は、報酬の提示方法や認知的な焦点の当て方によって変化することが分かりました。例えば、報酬を具体的にイメージさせると待機時間が短くなり、抽象的に考えさせると長くなる傾向が見られたのです。
子どもたちは過去の経験から学習することで、状況に適した行動を身につけていくことも明らかになりました。周囲からの反応を通じて、どのような場面でどのような行動が望ましいのかを学んでいくということです。
この観察からは、人の行動が認知的・社会的な要因によって動的に形作られていることが分かります。ある性格特性を持っているからといって、それが常に同じように表れるわけではありません。むしろ、その場の状況を認識し、過去の経験を活かしながら、適切な行動を選択しているわけです。
風土が積極的で社会的能力が高いと効果最大
職場の雰囲気や個人の社会的な能力によって、性格特性の効果は変化します。特に外向性が高い人の場合、どのような環境でその特性が活かされるのでしょうか。この点を明らかにするために、ドイツの介護施設で働く看護師を対象とした実証研究が行われました[2]。
実証研究では、247人の看護師とその上司から、仕事の様子について情報が集められました。研究チームは、オンライン調査を通じて外向性、社会的能力、職場の積極性風土を測定し、適応的パフォーマンスについては上司による評価を用いました。
その結果、外向性が高い看護師は、二つの条件がそろった時に最も高い成果を上げることが分かりました。一つ目は、職場に新しい取り組みを歓迎する積極的な雰囲気があることです。二つ目は、看護師本人が高い社会的能力を持っていることです。
この二つの条件がそろうと、なぜ外向性の高い看護師の成果が上がるのでしょうか。まず、積極的な職場の雰囲気は、外向的な人の行動を後押しします。例えば、患者への新しいケア方法を提案しやすい環境があれば、外向的な看護師は自分のアイデアを発信できます。このような環境では、外向性という特性が「活性化」され、行動として表れやすくなります。
対して、社会的能力は、外向的な行動が周囲に受け入れられやすくする働きをします。同じ提案でも、相手の立場や気持ちを理解したうえで伝えられれば、より建設的な議論につながります。外向性が高くても、社会的能力が低いと、周囲との関係がうまくいかない可能性があります。
研究では、三者の相互作用項(外向性×社会的能力×職場風土)が適応的パフォーマンスの変動を説明する要因であることが明らかになりました。外向性の高い看護師が置かれた状況によって、成果に大きな違いが出ることが示されたということです。職場の雰囲気が消極的だったり、社会的能力が十分でなかったりすると、外向性の効果はあまり見られませんでした。
看護師という実際の職務における詳細な分析は、性格特性が環境と個人の能力が合わさることで、初めて十分な効果を発揮することを実証的に示しています。これは、職場での人材育成や環境整備を考える上で、貴重な示唆を提供するものです。
組織の価値観と個人の知性が合えば高コミットメント
知的好奇心が強く、新しいことを学ぶのが好きな人は、どのような職場で力を発揮するのでしょうか。この疑問に答えるため、多様な職種で働く185名を対象とした実証研究が実施されました[3]。
研究では、個人の知的な志向性と仕事の成果、そして組織への愛着の関係が調べられました。個人の知的な志向性は、新しい知識を求める欲求、認識論的好奇心、一般的な知的関与という三つの指標から測定されました。
また、状況的要因として「仕事要求」「妨害要因」「制約」の三つの要素が、タスクレベル、社会レベル、組織レベルの三段階で評価されました。これによって、知性という特性がどのような状況で活かされるのかを多角的に分析することが可能になりました。
調査の結果、知的な志向性が高い人の仕事の成果は、仕事の内容によって変わることが分かりました。特に、タスクレベルでの状況的要因、とりわけ仕事要求の高さが、知性と職務遂行能力の関係を調整することが明らかになりました。
例えば、新しい知識の習得や複雑な問題解決が求められる仕事では、知的な志向性の高い人が良い成果を上げる傾向がありました。これは、そうした仕事が知的な刺激を求める人の興味と合致し、その能力を最大限に活かせるためです。一方で、妨害要因や制約が強い状況では、知性の効果が弱まることも分かりました。
さらに注目すべき点は、知的な志向性が高い人の組織コミットメントが、組織レベルの状況要因によって左右されることです。例えば、組織が学習や創造性を重視する文化を持っている場合、知的な志向性の高い人は強い愛着を感じやすいことが明らかになりました。
個人の特性と組織の価値観の一致が、組織コミットメントを高める要因であることを示す結果です。知的な活動や新しい試みを歓迎する組織文化は、知的好奇心の強い人々の満足度を高め, 組織への愛着を強めるのです。
逆に、組織が効率や慣習を重視し、新しい試みを歓迎しない場合は、知的な志向性の高い人の愛着が低くなりがちでした。このような環境では、個人の知的な欲求が満たされにくく、それが組織コミットメントの低下につながると考えられます。
研究では、組織の文化や価値観との不一致が、知的な志向性の高い人にとって大きなストレス要因となることも明らかになりました。自分の知的な興味や能力を活かせない環境では、仕事への意欲が低下し、組織を離れたいという気持ちが強まる傾向が見られました。
タスク/人間中心の状況かで性格特性の効果が変わる
性格特性がどのように仕事の成果に結びつくかは、その人が直面している状況の性質によって異なります。この点を明らかにするため、仕事の状況を「タスク中心」と「人間関係中心」に分類し、各状況での性格特性の効果を調べた実証研究が行われました[4]。
研究では、ビッグファイブとして知られる「誠実性」「情緒安定性」「協調性」「開放性」「外向性」に注目しました。研究チームは、これらの特性を持つ人が、異なる状況でどのような成果を上げるのかを分析しました。
データ収集では、ボランティア活動および人間工学分野の専門家から「有効」または「無効」とされる行動事例が集められました。これらの事例は、独立した研究助手によって「タスク中心の状況」と「人間関係中心の状況」に分類されました。分類の信頼性を確保するため、複数の評価者による相互評価が実施されています。
分析の結果、性格特性の効果は状況によって異なることが分かりました。誠実性と情緒安定性は、タスク中心の状況で特に強い効果を発揮しました。例えば、書類作成や締め切り管理といった具体的な作業が求められる場面では、計画的で落ち着いた性格の人が良い成果を上げました。
タスク中心の状況では、効率的な作業の進め方や期限の遵守が求められるためだと考えられます。誠実性の高い人は計画性と責任感を持って仕事に取り組み、情緒安定性の高い人はストレスの多い状況でも冷静に対応できるため、こうした場面で力を発揮しやすいのです。
他方で、協調性と開放性は、人間関係中心の状況で効果を発揮しました。顧客との交渉や同僚との協力が必要な場面では、他者への配慮や柔軟な発想を持つ人が高い評価を得ました。人との関わりが中心となる状況では、相手の立場を理解し、状況に応じて対応を変える能力が求められるためです。
特に人間工学分野の専門家を対象とした分析では、誠実性がタスク中心の状況で特に高い効果を示すことが明らかになりました。技術的な正確性やデータ分析が求められるこの職種では、計画的で綿密な作業が成果に直結するからでしょう。
興味深いことに、この「タスク中心」と「人間関係中心」という分類は、様々な職種で共通して見られました。技術職でも営業職でも、仕事の状況はこの二つに大きく分けられ、それぞれの状況で活きる性格特性が異なっていたのです。
これらの結果は、「暗黙の特性方針」という概念で説明することができます。これは、特定の状況において、ある性格特性を持つ人の行動が、その状況での要求に適合するかどうかを表す考え方です。状況の要求と性格特性が合致するとき、その人の行動は高い効果を発揮します。
成果が出る職種と性格の組み合わせ
数多くの職種と性格特性の組み合わせを分析した大規模な研究では、それぞれの職種で成果を上げやすい性格特性が明らかになりました。117の研究データを統合したメタ分析によって、性格特性と職種の相性について、いくつかの共通したパターンが見つかりました[5]。
研究では、職務遂行を訓練パフォーマンス、業務パフォーマンス、対人関係という3つの側面から評価し、ビッグファイブ(外向性、協調性、誠実性、情緒安定性、開放性)との関連を分析しました。
まず目立ったのは、誠実性の効果です。この性格特性は、職種を問わず職場での成果と結びつきました。誠実性の高い人は、計画的で責任感があり、仕事に対する真摯な姿勢を持つため、どのような仕事でも一定の成果を上げやすいことが分かりました。この傾向は、調査対象となったすべての職種で一貫して観察されています。
誠実性が広く効果を持つ理由として、系統立った行動がどの職場でも高い成果につながることが考えられます。計画性、責任感、自制心といった誠実性の特徴は、職務の内容に関わらず、効率的で安定した働き方を支える基盤となるのです。
外向性は、特に営業職や管理職といった対人コミュニケーションが多い職種で効果を発揮しました。外向的な人は、他者との関わりを好み、エネルギッシュに行動する傾向があるため、人と接する機会の多い仕事で成果を上げやすかったのでしょう。
外向性の特徴である社交性とリーダーシップ傾向が、これらの職種で求められる能力と直接的に結びつくためです。顧客との関係構築や部下の指導において、外向的な性格は大きな利点となります。
協調性と情緒安定性は、対人サービス業で特に良い結果をもたらしました。例えば、カスタマーサービスや看護職では、他者への配慮や感情のコントロールが求められます。そのため、協調的で感情が安定している人が高い評価を得る傾向がありました。
これらの特性が対人サービス業で効果を発揮するのは、この職種における業務の性質と関連しています。顧客や患者との関わりでは、相手の感情を理解し、適切に対応する必要があります。また、ストレスの多い状況でも冷静さを保つことが求められます。協調性と情緒安定性は、まさにこうした要求に応える性格特性なのです。
開放性は、創造性や革新性が求められる職種で価値を発揮しました。デザイナーや研究職など、新しいアイデアや解決策を生み出す必要がある仕事では、好奇心が強く、柔軟な思考ができる人が成果を上げやすいことが示されました。
ただし、開放性の効果は、他の性格特性と比べて一貫性が低いことも分かりました。創造性が全ての職務に必要とは限らないためです。定型的な業務が中心の職種では、むしろ既存の手順を正確に遂行する能力が求められ、開放性の効果は限定的となります。
この研究で特に注目すべき点は、性格特性と職種の相性が、職務遂行の異なる側面によって変化することです。例えば、訓練パフォーマンスと実際の業務パフォーマンスでは、性格特性の効果が異なります。職場での成功には、状況に応じて異なる性格特性が必要となることを示唆しています。
また、この研究は性格特性が職務遂行に及ぼす影響のメカニズムについても洞察を提供しています。例えば、誠実性が広く効果を持つのは、この特性が仕事への取り組み方自体を改善するためと考えられます。一方、外向性や協調性の効果は、特定の職務要件との適合度に依存することが明らかになりました。
脚注
[1] Mischel, W. (1973). Toward a cognitive social learning reconceptualization of personality. Psychological Review, 80(4), 252-283.
[2] Wihler, A., Meurs, J. A., Wiesmann, D., Troll, L., and Blickle, G. (2017). Extraversion and adaptive performance: Integrating trait activation and socioanalytic personality theories at work. Personality and Individual Differences.
[3] Mussel, P., and Spengler, M. (2015). Investigating intellect from a trait activation perspective: Identification of situational moderators for the correlation with work-related criteria. Journal of Research in Personality, 55, 51-60.
[4] Kell, H. J., Rittmayer, A. D., Crook, A. E., and Motowidlo, S. J. (2010). Situational content moderates the association between the Big Five personality traits and behavioral effectiveness. Human Performance, 23(3), 213-228.
[5] Barrick, M. R., and Mount, M. K. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. Personnel Psychology, 44(1), 1-26.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。