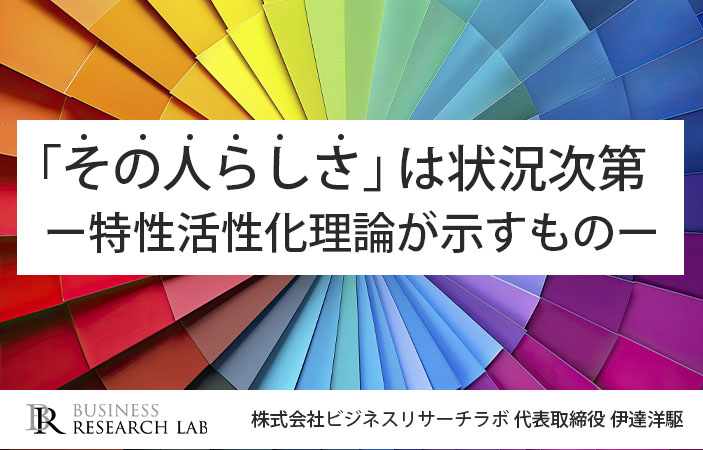2025年2月18日
「その人らしさ」は状況次第:特性活性化理論が示すもの
職場で自分らしさを発揮したいと願う人も多いでしょう。しかし、その「自分らしさ」は常に同じように表れるわけではありません。例えば、普段は社交的な人でも、集中して作業する必要がある時は黙々と仕事に取り組みます。几帳面な人でも、急いでいる時は細かいことにこだわらずに仕事を進めることもあります。
こうした状況に応じた性格特性の表れ方について、心理学では「特性活性化理論」という観点から説明を試みています。この理論は、私たちの特性が職場環境やその時々の状況に応じて、どのように引き出されるのかを考えるものです。
「特性活性化理論」を理解することは、職場における人々の行動パターンを理解する上で大切な視点を提供します。本コラムでは、この理論の基本的な考え方から、具体的な研究成果まで、解説していきます。読者の皆様が、自身や周囲の人々の行動をより深く理解するためのヒントとなると嬉しいです。
手がかりによって特性が活性化する
私たちの性格特性は、それを引き出す「手がかり」があって行動として表れます[1]。例えば、会議の場で発言を求められた時、社交的な性格の人は積極的に意見を述べるでしょう。この場合、「発言の機会」という手がかりが、その人の社交的な性格を引き出すきっかけとなっています。
職場における手がかりは多様です。デスクワークでは正確さが必要とされ、几帳面な性格の人がその特性を発揮できます。一方、チーム活動では協調性が必要とされ、思いやりのある人が活躍しやすくなります。このように、仕事の性質そのものが、特定の性格特性を引き出す手がかりになるのです。
特性活性化理論では、個人の特性が職場状況の中で「特性関連の手がかり」によって引き出され、行動として表れる過程を説明しています。この過程は、「課題レベル」「社会的レベル」「組織レベル」という3つのレベルに分類されます。課題レベルには日常の職務タスクや責任が含まれ、社会的レベルには同僚や上司との関係性が、組織レベルには組織全体の文化や方針が含まれます。
手がかりの働きは、実験的な研究からも確認されています。ある調査では、156名の大学生を対象に、様々な場面で人々がどのように行動するかを調べました。「冒険性」「複雑性」「共感性」「社交性」「組織性」という5つの特性について、それぞれ10個のシナリオを用意し、各シナリオでの行動意図を調べたのです。
その結果から見えてきたことは、手がかりの存在が性格特性の表れ方に差をもたらすということでした。例えば、冒険的な性格の人は、リスクを伴う状況(手がかり)に直面した時に、その特性を強く表現しました。冒険性の特性と行動意図の相関は、そうした手がかりが存在する場合に顕著に高まったのです。
また、特性と職務遂行の関連を理解するための「相互作用モデル」においても、手がかりの重要性が検討されています。このモデルでは、特性が職場で価値のある行動として評価されるメカニズムを分析しています。例えば、会計業務には「几帳面さ」が求められ、これが職務パフォーマンスの予測要因になることが示されています。
性格特性が行動に現れるには状況の特性関連性が重要
性格特性が行動として表れるためには、その特性と関連性の高い状況が必要です。これを「状況特性関連性」と呼びます。状況特性関連性とは、ある状況がどれだけ特定の性格特性を表現する機会を提供しているかを表します。
この点について、実証研究では26名の熟練評価者が、各シナリオと性格特性との関連性を評価しました[2]。評価は4段階で行われ、0(関連性なし)から3(非常に関連が高い)までの尺度が用いられました。シナリオは「スカイダイビングに誘われた時」「迷っている高齢者を見かけた時」など、様々な状況を想定したものでした。
調査結果は、特性と状況の関連性が行動の一貫性に関わることを明らかにしました。例えば、社交性の高い人は、その特性を発揮できる場面(会議やチーム活動など)で一貫した行動を示す一方、社交性とあまり関係のない場面(個人作業など)では、必ずしもその特性を表現しないことが分かりました。
このことは、性格特性と行動の関係が単純ではないことを教えています。同じ性格の人でも、状況によって全く異なる行動を取ることがあるのです。これは、その状況がその人の特性とどれだけ関連しているかによるものです。
さらに、複数の状況間での行動の一貫性も、特性関連性の類似性に依存することが確認されました。冒険性や社交性では、一貫性が特性関連性の類似性に強く依存することが示されました。これは、同じ特性が関与するシナリオ間では、行動の一貫性が高まることを意味します。
状況が弱いと性格特性がパフォーマンスに強く影響
職場における「状況の強さ」は、性格特性の発現に影響を及ぼします。「状況の強さ」とは、職務環境がどれだけ厳密にルールや手順を定めているかを意味します。
125の研究を分析した論文では、状況が「弱い」(自由度が高い)場合、性格特性が職務パフォーマンスにより強く反映されることが判明しました[3]。例えば、営業職では、顧客との対話方法に厳密なマニュアルがない場合が多く、これは「弱い状況」といえます。このような環境では、社交的な性格の人が自然とその特性を活かし、高いパフォーマンスを発揮できます。
調査では、「外向性」「協調性」「誠実性」「情緒安定性」「開放性」というビッグファイブが、職務パフォーマンスを予測する有効性について検討されました。その際、米国の職業情報ネットワーク(O*NET)のデータを用いて、各職務を「状況の強さ」や「特性活性化」の観点から分類しています。
分析では、職務状況を12の変数(自由裁量、競争性、創造性の要求など)に基づいて評価しました。回帰分析を使用し、状況の強さと特性活性化が性格特性と職務パフォーマンスの相関に与える影響を検討したところ、特に「外向性」と「協調性」が「弱い状況」で職務パフォーマンスに貢献することが明らかになりました。
一方、「強い状況」(ルールが厳格)では、個人の性格特性が発揮される余地が限られます。例えば、製造ラインでの品質管理など、手順が細かく規定された業務では、性格特性よりも定められたルールに従うことが求められます。このような環境では、個人の特性による行動の差異が小さくなります。
「誠実性」という特性については意外な発見もありました。細部への注意が必要な仕事では、誠実性の高い人の職務パフォーマンス予測力が低下したのです。これは、誠実性が「達成志向」と「義務感」という異なる側面を持つためだと考えられます。
達成志向が強い人は、細かい作業に不満を感じるかもしれません。例えば、野心的な営業職の人が、繰り返しのデータ入力を求められるとストレスを感じ、ミスが増える可能性があります。一方、義務感が強い人は、同じ作業でも丁寧に取り組むことができます。このように、同じ誠実性という特性でも、その内容によって職務パフォーマンスへの影響が異なることが分かりました。
状況要因をタスク、ソーシャル、組織に分ける
職場における状況要因は、大きく3つのレベルに分類できます。それぞれのレベルで、性格特性の発現のされ方が異なります。メタ分析によると、これらのレベルが相互に影響し合うことで、特性が発現する仕組みが説明できます[4]。
「タスクレベル」は、日常業務や職務上の責任に関する要因です。例えば、デスクワークでは正確さが求められ、これは几帳面な性格の人の特性を引き出します。プロジェクト管理では、期限を守る必要があり、計画性のある人が活躍できます。また、会計業務のような細かな作業では、慎重さが必要とされ、これが職務パフォーマンスの予測要因になります。
「ソーシャルレベル」は、同僚や上司、顧客との関係に関わる要因です。営業担当者は顧客との良好な関係を築く必要があり、社交的な性格の人が力を発揮します。チームリーダーには部下への配慮が求められ、思いやりのある人が向いています。例えば、指導的役割を持つ人は、チームの社会的期待に応えるために「外向性」や「社交性」といった特性を活かすことができます。
「組織レベル」は、企業文化や組織の価値観に関する要因です。革新を重視する企業では、新しいアイデアを積極的に提案する人が評価されます。一方、伝統を重んじる組織では、慎重で堅実な性格の人が活躍しやすいでしょう。例えば、革新を重視する組織では「開放性」が評価されやすく、これが個人のパフォーマンスに反映されます。
メタ分析によると、性格特性と職務パフォーマンスの関連性は、これら3つのレベルで異なることが分かっています。例えば、「協調性」が高い人は、チーム作業が多い環境で高いパフォーマンスを発揮します。しかし、競争的な文化の組織では、同じ特性が必ずしも評価されないかもしれません。
状況要因の影響は、「強い状況」と「弱い状況」でも異なります。強い状況では、各レベルでの規定や制約が強く働くため、個人の特性が発揮される余地が限られます。一方、弱い状況では、個人の特性がより自由に表現され、それぞれのレベルでの特性発現が促進されます。
実証研究では、これらの状況要因が性格特性の発現に複雑な影響を及ぼすことが確認されています。特に、タスクレベルでの手がかりが最も多く観察され、次いで社会的レベル、組織レベルの順となっています。
性格特性の活性化に関連する要因を整理
性格特性の活性化には、様々な要因が関係しています。2011年から2019年にわたる99本の論文を分析した研究では、これらの要因が特性の発現を促進したり抑制したりする仕組みを明らかにしています[5]。
「要求」は、達成が望ましい行動を引き出す要因です。詳細な分析が必要なタスクでは、慎重で几帳面な性格の人が活躍します。この場合、タスクの性質自体が特定の特性を要求していることになります。例えば、企業の予算管理では、細かな数字の確認が必要とされ、これが誠実性の高い人の特性を引き出すきっかけとなります。
「妨害」は、特性の発現を阻害する要因です。騒がしいオフィス環境は、集中力を必要とする業務の遂行を妨げる可能性があります。このような環境では、几帳面な性格の人が本来の力を発揮できないかもしれません。具体的には、オープンオフィスでの頻繁な会話や打ち合わせが、集中を要する分析業務の遂行を妨げることがあります。
「制約」は、特性の発現を制限する要因です。リモートワークでは、対面でのコミュニケーションが制限されます。そのため、社交的な性格の人が十分に特性を発揮できない可能性があります。また、厳格な業務マニュアルは、創造性や独自のアプローチを制限することで、開放性の高い人の特性発現を抑制することがあります。
「促進」は、特性の発現を後押しする要因です。創造性を奨励する職場環境は、新しいアイデアを生み出すことを促進します。こうした環境では、独創的な発想を持つ人が活躍できます。例えば、定期的なブレインストーミングの実施は、開放性の高い人がアイデアを提案しやすい場を提供します。
「裁量」は、特性を自発的に発揮する余地を提供する要因です。業務の進め方に自由度がある場合、個人は自分の特性に合った方法を選択できます。これによって、その人らしい働き方が実現できます。具体的には、プロジェクトの進め方を各チームに委ねることで、メンバーの特性を活かした独自の取り組みが可能になります。
研究では、これらの要因が複雑に絡み合って、性格特性の発現に影響を及ぼすことが確認されています。分析対象となった99本の論文において、タスクレベルでの影響が最も多く(60%)、次いで社会レベル(30%)、組織レベル(6%)という結果が得られました。
タスクレベルでの影響が大きい理由として、日々の業務活動が最も直接的に特性を引き出す機会を提供することが挙げられます。例えば、営業職における顧客との対話、エンジニアの問題解決、デザイナーの創作活動など、それぞれのタスクが特定の特性を必要とします。
社会レベルの影響は、主に対人関係を通じて特性を引き出します。チーム活動、上司との相互作用、顧客対応など、他者との関わりが特性発現の機会を作り出します。これは、職場が本質的に社会的な場であることを反映しています。
組織レベルの影響は比較的小さいものの、長期的には個人の特性発現に重要な役割を果たします。企業文化や価値観は、どのような特性が望ましいとされるかの基準を設定し、個人の行動選択に影響を与えるのです。
個人の強みを活かす職場づくり
特性活性化理論の理解は、職場のマネジメントに新たな視点をもたらします。この理論から得られる含意は、特に人材の配置や育成に有用でしょう。
人材配置においては、個人の性格特性と職務環境の適合性を考慮することが大切です。例えば、社交的な人を対人コミュニケーションが求められる部署に配置することで、その人の特性を活かせる可能性が高まります。
職場環境の設計も考え直す必要があります。特性の発現を促す「手がかり」を意図的に設けたり、不必要な制約を取り除いたりすることで、従業員が持てる力を発揮しやすくなります。
ただし、性格特性は状況によって変化することを忘れてはいけません。同じ人でも、異なる環境では異なる行動を取ることがあります。そのため、一時的な行動だけで人を評価するのではなく、長期的な視点で個人の特性を理解することが望ましいでしょう。
職場のマネジメントにおいて、この理論の知見を活用することで、個人と組織の双方にとって、より実りある関係を築くことができるはずです。
脚注
[1] Tett, R. P., and Burnett, D. D. (2003). A personality trait-based interactionist model of job performance. Journal of Applied Psychology, 88(3), 500-517.
[2] Tett, R. P., and Guterman, H. A. (2000). Situation trait relevance, trait expression, and cross-situational consistency: Testing a principle of trait activation. Journal of Research in Personality, 34(4), 397-423.
[3] Judge, T. A., and Zapata, C. P. (2015). The person-situation debate revisited: Effect of situation strength and trait activation on the validity of the Big Five personality traits in predicting job performance. Academy of Management Journal, 58(4), 1149-1179.
[4] Christiansen, N. D., and Tett, R. P. (2008). Toward a better understanding of the role of situations in linking personality, work behavior, and job performance. Industrial and Organizational Psychology, 1(3), 312-316.
[5] Tett, R. P., Toich, M. J., and Ozkum, S. B. (2021). Trait Activation Theory: A review of the literature and applications to five lines of personality dynamics research. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 8(1), 199-233.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。