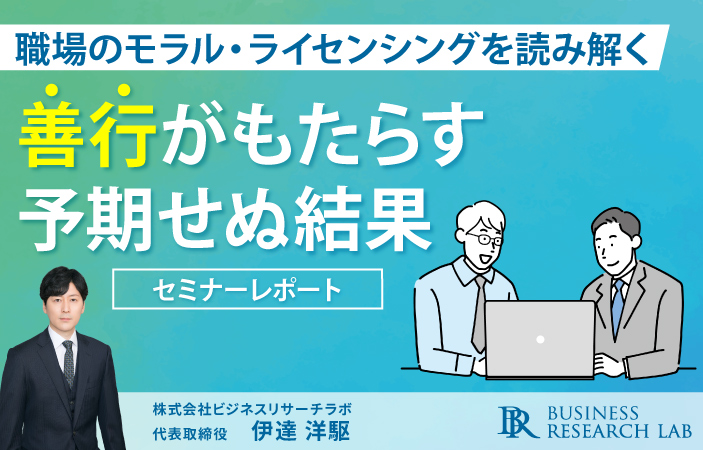2025年2月17日
善行がもたらす予期せぬ結果:職場のモラル・ライセンシングを読み解く(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年2月にセミナー「善行がもたらす予期せぬ結果:職場のモラル・ライセンシングを読み解く」を開催しました。
私たちの職場では日々、同僚への支援、環境保護活動、地域貢献など、数多くの善行が行われています。こうした道徳的な行動は組織を活性化し、職場の雰囲気を良くすると考えられています。しかし近年の研究では、善行を行うことで思わぬ副作用が生じる可能性が指摘されています。
本セミナーでは、「モラル・ライセンシング」という興味深い心理現象に注目しました。これは、道徳的な行動をした後に、その善行を根拠として不適切な行為を正当化してしまう傾向を指します。例えば、同僚への支援が、その後の規則違反や知識の隠蔽、無礼な態度を引き起こしてしまうのです。
組織における善行の意義を再考し、より健全な職場づくりのヒントを探ります。人事担当者、管理職の方々はもちろん、組織や人の心理に関心をお持ちの方にとって、新たな視点を提供する内容となっています。職場における道徳的な行動の両義性について、共に考えを深められると幸いです。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
私たちの心の中には、不思議な矛盾が潜んでいます。善良な行動が、思いもよらない悪い結果を招くことがあるのです。例えば、同僚のために残業した人が、翌日その同僚に厳しい言葉を投げかけたり、環境保護活動に熱心な企業が、内部統制をおろそかにしたりすることがあります。
こうした一見矛盾する行動の背景には、「モラル・ライセンシング」という心理メカニズムが存在します。これは、道徳的な行動をした後、その良い行いを理由に、道徳的に問題のある行動をとってしまう現象です。善行が「免罪符」となり、その後の非倫理的な行動を自分の中で許してしまいます。
興味深いことに、この現象は将来の善行の約束によっても、また他者の良い行いによっても引き起こされることがあります。私たちの道徳観は、予想以上に複雑で柔軟なのです。
本講演では、職場におけるモラル・ライセンシングについて解説していきます。善行が思いもよらない結果につながるメカニズムを理解することで、私たちの行動や組織のマネジメントに新しい視点を提供したいと思います。
組織市民行動の副作用
同僚への支援や業務改善の提案など、職務として定められていなくても組織のために自発的にとる行動を「組織市民行動」と呼びます。このような行動は組織の潤滑油として重要な役割を果たしますが、思いがけない副作用を引き起こすことがあります。
その一つが、同僚への無礼な態度です。サービス業の従業員を対象とした調査では、組織市民行動を行った従業員が、その後に同僚に対して無礼な行動をとるようになることが明らかになりました[1]。例えば、相手の話を遮ったり、会議で他者の意見を無視したり、メールや電話への返信を意図的に遅らせたりといった行動です。
このメカニズムにモラル・ライセンシングが関係しています。従業員は組織市民行動をとることで「道徳的なクレジット」を獲得します。このクレジットは心理的な「預金」のように機能し、その後の不適切な行動を正当化する根拠となります。「私はすでに十分な貢献をしている」という認識が、無礼な行動への心理的な抵抗を弱めてしまいます。
組織市民行動には、知識の隠蔽を引き起こす副作用もあります。同僚への自発的な支援を行った従業員が、その後に知識共有の要請を拒否したり、不完全な情報しか提供しなかったりする傾向が見られます[2]。例えば「自分も詳しくない」と装ったり、「時間がない」という理由で説明を避けたりします。
このような行動の背景にも、道徳的なクレジットの蓄積があります。従業員は自発的な支援行動によって「自分は十分に協力的だ」という自己認識を持ち、それを根拠に知識共有を拒否することを正当化します。特に、学習や成長を重視する文化が弱い職場では、この傾向が顕著になります。
また、内発的な動機で組織市民行動をとる場合、その後の行動が生産的ではなくなることがあります。これは一見すると直感に反する現象かもしれません。しかし、純粋な善意で行動する従業員ほど、その行動によって道徳的な自己イメージが高まり、その結果として不適切な行動への心理的な抵抗が弱まってしまいます。
すなわち、モラル・ライセンシングは、動機の違いによって異なる形で現れます。外部からの評価や報酬を期待して行動する従業員は、この傾向が弱いことが分かっています。行動の動機が外発的である場合、道徳的な自己イメージの向上につながりにくいためです。
他の行動への悪影響
仕事への熱心な取り組みもまた、予想外の結果をもたらすことがあります。ある調査は、仕事に熱心に取り組む従業員が、その後に組織のために不正を行う可能性が高まることを明らかにしました[3]。
従業員には「仕事を頑張っているのだから、少しの不正は許されるだろう」という考えが浮かんできます。仕事への熱心な態度が道徳的な預金のようになり、その預金で不正を正当化してしまいます。
この傾向は、組織に忠実な従業員に多く見られました。組織に愛着を持つ従業員は、自分の仕事を組織への貢献と強く考えるため、その後の不正も「組織のため」という理由で正当化しやすくなります。
企業の社会的責任(CSR)活動にも、同様の問題が潜んでいます。環境保護活動や地域貢献など、企業が社会に対して行う善行は、組織の評判を高め、従業員の誇りを生み出します。しかし同時に、CSR活動が組織的な不正行為を引き起こす可能性も指摘されています[4]。
CSR活動を行うことで、組織やリーダーは道徳的な信用を獲得します。「私たちは社会に貢献している」という自負が生まれ、この道徳的な信用が後の不正行為を正当化する根拠として機能します。
例えば、環境保護活動に熱心な企業が、その他の分野での法令遵守に甘くなってしまったり、地域貢献活動に力を入れている企業が、内部での不正行為に対して寛容になってしまったりすることがあります。
モラル・ライセンシングという現象は、なかなか信じがたく感じられるかもしれません。しかし、多くの研究を総合的に分析したメタ分析によって、モラル・ライセンシングの存在は確認されています[5]。
マネジャーのモラル・ライセンシング
リーダーの倫理的な行動は、時として部下への侮辱的な行動に変化することがあります[6]。この矛盾する現象の背景には、二つの心理的メカニズムが存在します。
一つは、倫理的な行動を続けることによる精神的な消耗です。公平な判断を心がけ、部下の立場に配慮し、組織の規範を遵守するという自己制御を続けることで精神的なエネルギーが消耗します。その結果、感情的になりやすくなり、些細なミスに対しても強い叱責を行ったり、部下の意見を一方的に否定したりするような行動が出やすくなります。
もう一つは、道徳的な信用の蓄積であり、まさにモラル・ライセンシングです。倫理的な行動を続けることで「私は良いリーダーだ」という自己認識が強まり、それが部下への侮辱的な行動を正当化する根拠となります。普段から部下の育成に熱心なリーダーが、時として過度に厳しい指導を行うのは、このためです。
ただし、上司のモラル・ライセンシングには少し難しい側面もあります。部下もまたモラル・ライセンシングが作動する可能性があるのです。上司の道徳的な振る舞いは、部下の心理にも大きな影響を及ぼします。
調査によると、上司が過去に善行をとっていると、その後の不適切な行動に対する部下の受容度が高まることが判明しています[7]。部下は上司の善行を通じて、その上司を善良な人物として認識します。この認識が心理的な緩衝材となり、後の不適切な行動に対する批判的な見方を和らげます。
例えば、部下の個人的な問題に理解を示し、支援的な態度を見せていた上司が、その後に厳しい要求をしても、部下はそれを受け入れやすいということです。また、上司の不適切な行動を目にした際にも、部下が通常感じるはずの不満や怒りの感情を抑制するかもしれません。過去の善行によって形作られた好意的なイメージが、感情的な反応を抑える働きを持つことを意味しています。
上司の道徳的な行動が内面からの動機に基づくと認識された場合、部下の受容度は一層高まります[8]。例えば、残業して部下の業務を手伝う行動が「部下への思いやり」という内面からの動機に基づくと認識された場合、部下はその後の厳格な指導や高度な要求をより受け入れるようになります。
対照的に、同じ残業でも「会社の指示」や「業績評価」といった外部からの動機によると認識された場合は、心理的な作用は弱まります。部下は、このような動機に基づく善行を、上司の人格や価値観の表れとしては捉えないのです。部下は上司の不適切な行動を解釈する際にも、「個人の性格や意図の表れ」としてではなく「外部の要因による一時的な現象」として捉えます。
意外なモラル・ライセンシング
モラル・ライセンシングには、興味深い特徴があります。将来行う予定の良い行いが、現在の問題行動を許してしまうことがあるのです。いわば「未来のライセンシング」が、研究で確認されています[9]。
例えば、将来の献血を予定している人は、そうでない人と比べて差別的な判断をする傾向が強まりました。将来の募金活動への参加を約束した人も、採用面接で偏見に基づく判断をしやすくなりました。
特徴的なのは、この効果が実際の約束だけでなく、良い行いへの関心を示しただけでも起きることです。募金活動に興味があると答えただけの人でも、その後の判断で偏見的な態度を見せました。
この背景にはやはりモラル・ライセンシングがあります。人は将来の良い行いを予定することで、その時点で既に道徳的な点数を得たような感覚になります。そして、この点数を使って現在の非倫理的な行動を許してしまいます。
将来の良い行いと現在の非倫理的な行動の種類が異なる場合でも、この効果は起きます。道徳的な信用が特定の分野に限らず、広く一般的な「道徳的な財産」として働くことを表しています。
加えて、モラル・ライセンシングは自分の行動だけでなく、他者の行動によっても起こることが分かっています[10]。この「代理的モラル・ライセンシング」は、組織の中で重要な意味を持ちます。
自分の集団が道徳的な行動をしたという情報を受けた人は、その後に非倫理的な判断をする傾向が強まるということです。例えば、所属する組織が公平な採用を行ったという情報を得た人は、その後の採用判断で偏見的な態度を見せやすくなります。
代理的モラル・ライセンシングの効果は、自分と集団の一体感が強いほど大きくなります。自分の集団との結びつきが強いほど、集団の良い行いを自分の道徳的な財産として捉え、その後の非倫理的な行動を許しやすくなるのです。
組織の評判や社会的な位置づけも、代理的モラル・ライセンシングの強さに関係します。評判の高い組織に所属する人々は、その組織の道徳的な行動をより強く自分の財産と考えます。組織の高い評判が個人の自己肯定感を高め、結果的に道徳的な優越感につながるためです。
モラル・ライセンシングへの対処
このような現象に対して、私たちはどう対処すれば良いのでしょうか。研究によると、行動を抽象的に理解することが効果的だと分かっています[11]。行動の背景にある価値観や信念に注目する見方を持つと、人は自分の価値観に沿って一貫した行動をとることができます。
例えば、募金を単なる「お金を寄付する行為」として捉えるのではなく、「他人を助ける行為」という大きな価値観から考えることで、その後も倫理的な行動を続けやすくなります。同様に、環境保護活動も「ゴミを拾う」という具体的な行為としてではなく、「地球環境を守る」という価値の実現として捉えるということです。
また、行動の背後にある自分の価値観を意識し、大切にすることも有効です。行動を「目標への達成度」としてではなく「価値への献身」として捉えることで、その後の行動も変わります。目標への達成度として考える場合、「これだけやれば十分」という感覚が生まれやすく、その後の行動がおろそかになる可能性があります。これに対し、価値への献身として考える場合は、その価値に沿った行動を続けます。
自分の行動を客観的に見ることも、モラル・ライセンシングを抑える効果があります。研究によると、人が自分の行動を「自分の目」で見る場合と「他人の目」で見る場合では、その後の行動に違いが生まれます[12]。
自分の目で見る場合、道徳的な行動が許可証となり、その後の非倫理的な行動を許しやすくなります。一方、他人の目で見る場合、道徳的な行動は手本として働き、その後も道徳的な行動を続けようとします。
興味深いことに、この他人の視点の効果は、想像上の観察者でも働くことが分かっています。例えば、「誰かに見られている」と想像するだけでも、モラル・ライセンシングを抑える効果があります。人間の行動が社会的な関係の中で形作られることを示す証拠と言えるでしょう。
良い行いを他人に報告するように記録することも一策です。自分の道徳的な行動を日記のように主観的に記録する場合と、他人に報告するように客観的に記録する場合では、その後の行動に違いが現れます。
主観的な記録では、その行動が道徳的な財産として積み重なる感覚が強まり、モラル・ライセンシングが起きやすくなります。一方、客観的な記録では、その行動が自分の道徳的な基準として働き、一貫した倫理的行動を促します。
さらに、オンライン上での良い行いは、モラル・ライセンシングが起きにくいことが分かっています。オンラインで道徳的な行動をした人と、そうでない人の間で、その後の行動に大きな違いは見られませんでした[13]。
これは、オンライン環境の特徴が関係していると考えられます。オンラインでは他人からの評価や観察が直接的でないため、道徳的な行動が「預金」として働きにくいのです。
このことから、オンラインでの善行は積極的に行っていくと良いでしょう。オンライン上での道徳的な行動は、現実世界での行動とは異なる判断基準で評価される可能性があります。例えば、SNS上での良い意思の表明は、実際の寄付行動とは異なる文脈で受け止められ、その結果、モラル・ライセンシングを引き起こしにくいということです。
あえて恩恵を考える
モラル・ライセンシングは基本的には望ましくない現象ですが、人間の心理や組織の健全性という観点から、あえて恩恵がないかを少し考えてみたいと思います。
この現象は人間の精神的な持続可能性に寄与しているかもしれません。完璧な倫理的行動を維持することは、大きな精神的負担を伴います。継続的な自己制御は精神的資源を著しく消耗させ、最終的にはバーンアウトや意思決定の質の低下を引き起こすでしょう。
その意味では、モラル・ライセンシングは一種の心理的な「安全弁」として機能し、持続的な倫理的行動を可能にする緩衝材となっていると考えられなくもありません。ただし、反動が深刻ではないなら、という条件付きではありますが。
あるいは、モラル・ライセンシングが倫理的な学習の機会を提供する可能性も探索できます。倫理的行動からの「逸脱」を経験し、その結果を認識することができれば、より深い倫理的理解につながるかもしれません。
善行の後に不適切な行動をとってしまったという経験は、自分の行動パターンへの気づきを促し、より成熟した倫理的判断力の発達を支援する可能性があります。
この学習効果は個人レベルだけでなく、組織レベルでも考えられます。チームのメンバーが時として倫理的な「緩み」を経験することで、かえって組織の倫理的な基準について活発な議論が生まれ、結果として組織全体の倫理的な成熟度が高まり得ます。
ただし、これらの利点は、モラル・ライセンシングを積極的に許容し活用すべきだということを意味するわけではありません。この現象を人間の心理の自然な一部として理解し、その上で適切な対処法を考えることが重要でしょう。
定期的な振り返りの機会を設けたり、倫理的な行動の意味を継続的に議論したりすることで、モラル・ライセンシングの否定的な影響を最小限に抑えながら、その潜在的な利点を活かすこともできます。
おわりに
モラル・ライセンシングは、私たちの心の中に潜む不思議な矛盾を映し出しています。これまで見てきたように、この現象は職場の様々な場面で発生し、組織に影響を及ぼす可能性があります。同僚への支援、仕事への熱心な取り組み、CSR活動など、私たちが良いと信じて行っている行動が、思いがけない形で問題を引き起こすかもしれません。
この現象が個人の心理の問題ではなく、組織に影響を及ぼし得ることは注目に値します。上司と部下の関係、同僚間の協力、組織の評判など、様々な要素が複雑に絡み合って、モラル・ライセンシングの効果を強めたり弱めたりします。さらに、将来の善行の約束や他者の良い行いさえも、この現象のきっかけとなり得ます。
しかし、このことは決して善行を控えるべきだということを意味するわけではありません。私たちは善行の意味を理解し、それを価値ある行動として継続していく必要があります。そのためには、行動を抽象的に捉え、その背後にある価値観を意識し、客観的な視点を持つことが重要でしょう。
デジタル時代における新しい可能性として、オンライン環境での善行に着目する価値があります。モラル・ライセンシングが起きにくいという特徴を活かし、新しい形の倫理的な行動を模索していくことができるでしょう。
結局のところ、大切なのは善行そのものではなく、その行動の意味を私たちがどのように理解し、位置づけるかということです。一時的な道徳的な達成としてではなく、継続的な価値の実現として捉えることで、私たちは意味のある善行を実践していくことができるのではないでしょうか。
Q&A
Q:評価基準に倫理的な行動を含めることで、逆にモラル・ライセンシングを助長してしまう可能性はないでしょうか。部下の評価を行う際に気をつけるべき点があれば教えてください。
近年、コンプライアンスの重要性が叫ばれており、マネジャーの評価項目に「倫理的な行動をしているか」を含める企業もあります。こうした評価項目は必要だと思いますが、その「評価の仕方」がポイントになりそうです。
例えば「単発的に良い行動をした」という評価だけをすると、本人が「自分は十分に良いことをしたから、多少は大丈夫だろう」と考えてしまい、モラル・ライセンシングが起こりやすくなります。
具体的な行動を評価すること自体は大切ですが、倫理面ではむしろ「その背景にある価値観」や「長期的に一貫した行動パターン」を見るほうが、モラル・ライセンシングを抑えやすいと考えられます。
評価面談などで「なぜその行動を取ったのか」「そのとき何を大切に考えたのか」を対話することで、抽象度の高い価値観を共有しやすくなり、モラル・ライセンシングを防ぐ効果も期待できます。評価項目に入れること自体が悪いわけではなく、運用の仕方が重要だと思います。
Q:部下の倫理的な行動を褒めたいときに、モラル・ライセンシングを促進しないためのコミュニケーション方法はありますか。
ポジティブなフィードバックは必要ですが、やり方によっては「これだけ褒められたのだから、少しぐらい…」という気持ちを引き出してしまう恐れがあります。大切なのは、単発的な行動だけでなく、その背景にある価値観や組織への貢献まで含めて伝えることです。
例えば「あなたの今回の行動は、組織の大切にしている価値観を体現してくれていて助かりました」といったように、抽象度の高い意味づけを加えるということです。そうすると「まだ道半ばであり、今後も続けていく必要がある行動なんだ」という認識が育ちます。
また、「その行動が周囲にとってどんな影響を与えたか」を伝えると、自分の行動が社会的に意義あるものだと思えるようになり、継続意欲が高まるでしょう。
Q:企業のダイバーシティ&インクルージョン(D&I)推進において、形式的な数値目標を達成した後にモラル・ライセンシングが働き、組織文化の変革が停滞するケースがあります。こうした事態を防ぐためのアドバイスをお願いします。
D&Iの数値目標を達成したときに「自分たちは良いことをやり遂げた」と思うあまり、その後の取り組みが進まなくなるというケースでしょうか。そうだとすれば、モラル・ライセンシングの一例と言えます。対策としては「数値目標をゴールではなく通過点と位置づける」「その目標はどんな価値観を実現するために必要なのか」を明確に示すことが挙げられます。
D&I推進においては、従業員一人ひとりの体験や気づきを共有する機会をつくり、数値には表れにくい現状や課題を見せ合うことも重要です。そうすると、組織文化を変えるにはまだやるべきことがある、と実感しやすくなり、数値を達成したことで「もう十分だ」と思う状態を防げるでしょう。
Q:成功している社員が独善的になってしまうケースがあります。過去の成功経験がモラル・ライセンシングとなり、学びや成長を妨げないようにするにはどのようなアプローチが有効でしょうか。
「自分はこれだけ良い行いをしてきた」という意識が強いほど、モラル・ライセンシングは起きやすいものです。学びや成長を促すには、自分の過去の成功を相対化して新しい意味づけをする機会が必要だと思います。
例えば越境学習のように、普段とは異なる環境に身を置くのも一つの方法です。NPOでのプロボノ活動や出向など、様々な価値観や働き方に触れる場に移ると、自分の「道徳的な得点」を相対化しやすくなります。すると「もっと学ぶべきことがある」と気づくことができます。
要するに「過去の良い行い」を固定的な資産として扱うのではなく、「価値観を行動で示せた一つのステップで、これからも続けていくものだ」と再定義すると、モラル・ライセンシングが抑えられ、本人の成長意欲も維持しやすくなります。
脚注
[1] Hughes, I., Levey, Z., Lee, J., and Jex, S. (2023). Doing good to be (subtly) bad: A moral licensing view on the relations between organizational citizenship behavior and instigated incivility. Human Performance, 36(5), 201-218.
[2] He, P., Anand, A., Wu, M., Jiang, C., and Xia, Q. (2023). How and when voluntary citizenship behaviour towards individuals triggers vicious knowledge hiding: The roles of moral licensing and the mastery climate. Journal of Knowledge Management, 27(8), 2162-2193.
[3] Kong, M., Xin, J., Xu, W., Li, H., and Xu, D. (2022). The moral licensing effect between work effort and unethical pro-organizational behavior: The moderating influence of Confucian value. Asia Pacific Journal of Management, 39(2), 515-537.
[4] Bouzzine, Y. D., and Lueg, R. (2023). CSR, moral licensing and organizational misconduct: A conceptual review. Organization Management Journal, 20(2), 63-74.
[5] Blanken, I., Van De Ven, N., and Zeelenberg, M. (2015). A meta-analytic review of moral licensing. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(4), 540-558.
[6] Lin, S. H. J., Ma, J., and Johnson, R. E. (2016). When ethical leader behavior breaks bad: How ethical leader behavior can turn abusive via ego depletion and moral licensing. Journal of Applied Psychology, 101(6), 815-830.
[7] Effron, D. A., and Conway, P. (2015). When virtue leads to villainy: Advances in research on moral self-licensing. Current Opinion in Psychology, 6, 32-35.
[8] Wang, R., and Chan, D. K. S. (2019). Will you forgive your supervisor’s wrongdoings? The moral licensing effect of ethical leader behaviors. Frontiers in Psychology, 10, 484.
[9] Cascio, J., and Plant, E. A. (2015). Prospective moral licensing: Does anticipating doing good later allow you to be bad now? Journal of Experimental Social Psychology, 56, 110-116.
[10] Kouchaki, M. (2011). Vicarious moral licensing: The influence of others’ past moral actions on moral behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 101(4), 702-715.
[11] Mullen, E., and Monin, B. (2016). Consistency versus licensing effects of past moral behavior. Annual review of psychology, 67(1), 363-385.
[12] Hu, T.-Y., and Tao, W.-W. (2021). The influence of visual perspective on moral licensing effect. Basic and Applied Social Psychology, 43(6), 341-355.
[13] Rotella, A., and Barclay, P. (2020). Failure to replicate moral licensing and moral cleansing in an online experiment. Personality and Individual Differences, 161, 109967.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。