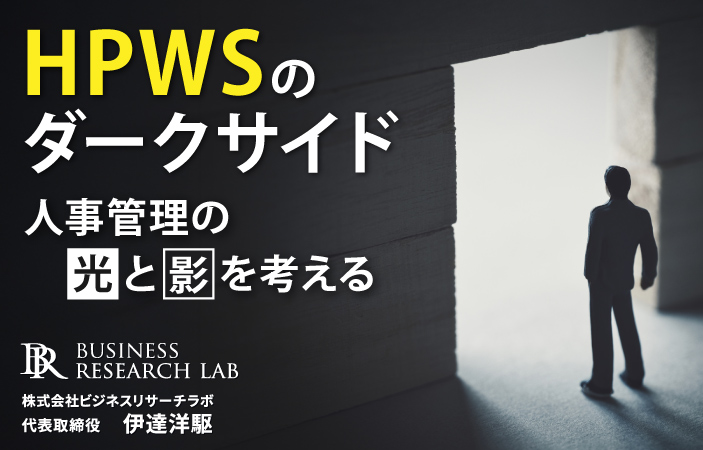2025年2月17日
HPWSのダークサイド:人事管理の光と影を考える
「人は組織の宝である」といった趣旨のフレーズをよく耳にします。その中で注目を集めているのが、ハイパフォーマンス・ワーク・システム(HPWS)です。従業員の能力開発や動機づけを高めるために、採用・研修・評価・報酬などの人事施策を戦略的に組み合わせたこの仕組みは、多くの企業で導入が進んでいます。
一見すると万能の解決策のように思えるHPWSですが、その実態はそれほど単純ではありません。むしろ、従業員に予期せぬストレスや負担を強いるケースも少なくないのです。管理職の期待と現場の実感の乖離、従業員の疲弊、仕事の強化による弊害など、HPWSには表には出てこない「影」の部分が存在します。
本コラムでは、これまでHPWSの「光」の部分に注目が集まりがちだった中で、あまり語られてこなかった「影」の部分に焦点を当てます。日本の金融機関、中国の製造業・サービス業、イギリスの公的機関など、様々な組織での実証研究を紹介しながら、HPWSが抱える課題と、その背後にあるメカニズムを探っていきます。HPWSの真の姿を理解することは、これからの人材マネジメントを考える上で必要な視点となるはずです。
管理職と従業員の評価は異なる
日本の大手銀行の支店を対象とした調査では、HPWSに対する認識が管理職と従業員の間で異なることが明らかになりました[1]。この調査では、従業員の対応に従事するフロントラインの従業員たちに焦点が当てられました。
管理職の多くは自分の支店でHPWSがしっかり実施されていると考える一方、従業員の間ではその認識にばらつきがありました。管理職は広範なサービス研修、サービス品質を重視した評価制度、チームでの意思決定や情報共有など、様々な施策が十分に行われていると評価していましたが、従業員たちはそれほど実感を持てていないことが分かりました。
この認識の違いが生まれる背景には、複数の要因があります。管理職は制度を「導入した」という事実だけを見て評価する傾向にありますが、従業員は実際にその制度を活用できているかどうかで判断します。研修制度が整備されていても、業務が忙しすぎて参加できない従業員も多いのです。
上司との関係性によって受けられるサポートの程度も変わってきます。ある従業員は上司との関係が良好で多くの研修機会を得られる一方、別の従業員はそうした機会にあまり恵まれないこともあります。人事制度の運用には、こうした非公式な人間関係が影響を及ぼします。
調査では、HPWSが従業員のサービス・パフォーマンスに及ぼす影響も検証しました。その結果、一般的なサービス・パフォーマンスと知識集約型のサービス・パフォーマンスの両方に、HPWSの効果が確認されました。ただし、その効果は従業員の心理的エンパワーメントや組織からのサポートを通じて発揮されることも分かりました。
従業員が「自分の仕事は意味があり、組織から支援されている」と実感できることが、HPWSの成功には必要です。このような実感がないままでは、いくら制度を整えても形骸化してしまう恐れがあります。管理職が考える「制度の充実」と、従業員が体験する「制度の活用」には隔たりがあることを認識する必要があるでしょう。
支店全体のサービス水準と顧客満足度の関係も注目に値します。従業員が総じて高いサービス・パフォーマンスを示す支店では、顧客満足度も高くなる傾向にありました。これは銀行のような業態では、顧客が複数の従業員と接する機会が多いため、支店全体のサービス水準が顧客の総合的な評価に影響することを示唆しています。
従業員の疲弊というネガティブな効果を持ちうる
中国企業を対象とした調査では、HPWSが従業員にネガティブな影響を及ぼす可能性が明らかになりました。研究は「仕事要求・資源モデル」に注目し、HPWSが従業員に与える負担とサポートのバランスを分析しています[2]。
HPWSは研修制度や支援体制といった「仕事資源」を提供する一方で、成果目標の高さや責任の増加といった「仕事要求」も同時に高めます。このバランスが崩れると、従業員はストレスを感じることになります。例えば、新しい研修が導入されても、それを受講する時間的余裕がない場合、かえって従業員の負担が増すことになるのです。
動機づけの面でも課題が浮かび上がりました。HPWSは成果主義的な評価や外的報酬を重視する傾向にありますが、これが従業員の内発的な動機づけを阻害する可能性があります。本来、仕事へのやりがいや興味から生まれる内発的動機づけこそが重要なはずですが、外的な報酬が強調されすぎると、従業員の自主性や創造性が損なわれてしまいます。
また、HPWSを「従業員を管理するための道具」として導入していると従業員が感じると、かえって反発や不信感が生まれることも分かりました。従業員が「結局は自分たちをもっと働かせたいだけだ」と受け取ってしまうと、制度そのものへの抵抗感が生まれ、モチベーションの低下につながってしまいます。
「良いことのやり過ぎ効果」も見過ごせない問題です。研修や自己啓発の機会を増やすことは本来良いことですが、やりすぎると逆効果になります。業務時間外にまで「学習」を強要されるようになると、従業員は十分な休息を取れなくなり、疲弊してしまうのです。この効果は、HPWSの施策が充実すればするほど顕著になる可能性があります。
個人の資源(スキルや心理的資本、社会的サポート)の違いも、HPWSの影響を左右する要因となります。スキルが高く、周囲のサポートが得られる従業員は、HPWSのネガティブな影響を受けにくい傾向にあります。一方、そうした資源が乏しい従業員は、HPWSによる負荷を強く感じることになります。
組織文化やタスクの特性も重要です。個人主義的な文化では、HPWSの成果主義と相まってストレスが強まりやすくなります。創造性が求められる職務で成果主義を過度に強調すると、かえってモチベーションを低下させる可能性があります。こうした文化やタスクの特性を無視してHPWSを導入すると、期待とは異なる結果を招くことになります。
仕事の激化につながり悪影響をもたらすことも
中国の製造業とサービス業を対象とした別の調査からは、HPWSが業務の激化を引き起こし、従業員の満足度を低下させる可能性が指摘されています[3]。この研究では感情イベント理論という枠組みを用いて、HPWSが従業員の感情や態度に与える影響を検証しました。
注目すべきなのは、職場での出来事が従業員の感情を刺激し、その感情が仕事への態度を左右するというメカニズムです。HPWSによって業務量や要求水準が上昇すると、それが従業員のストレスや焦りといったネガティブな感情を生み出します。このネガティブな感情は、最終的に職務満足度を低下させることが分かりました。
中国企業の場合、文化的な特徴がHPWSの負の影響を増幅させる可能性があります。上司と部下の間の距離が大きい組織文化では、従業員が業務上の問題を相談しにくい状況が生まれます。人間関係を重視する文化では、チーム内での対立を避けようとするあまり、必要な改善提案さえできなくなってしまうことがあります。
職務裁量も要因として浮かび上がりました。自律性が高い仕事の場合、HPWSによる負荷をある程度自分でコントロールできます。しかし、裁量が限られている場合、従業員は過度な要求にただ耐えるしかなくなってしまいます。これは従業員の無力感を増大させ、職務満足度の低下につながる要因となります。
HPWSの評価に対する従業員の解釈も、満足度に影響を及ぼすことが明らかになりました。同じ制度であっても、「自分の成長をサポートしてくれる仕組み」と捉えるか、「会社に搾取される仕組み」と受け取るかで、従業員の反応は異なってきます。この解釈の違いは、上司の伝え方や組織の文化によって左右されます。
職場の状況や従業員の特性によっても、HPWSの受け止め方は変わります。業務が繁忙な部署では、新しい施策の導入がかえって負担増につながりやすいでしょう。経験の浅い従業員や、スキルが十分でない従業員にとっては、高い要求水準がストレス要因となることもあります。
HPWSを導入しても裁量がないと悪影響に
イギリスの公的機関を対象とした調査では、HPWSが従業員に与える影響は、仕事の裁量の大きさによって異なることが明らかになりました[4]。HPWSと職務裁量の相互作用が、従業員の不安や役割過重、さらには離職意向にまで影響を及ぼす点は注目に値します。
従業員が仕事の進め方を自分でコントロールできる裁量が低い場合、HPWSの導入は深刻な問題を引き起こします。高い業績目標を求められるにもかかわらず、自分で仕事の調整ができないため、従業員はストレスにさらされることになります。このストレスは不安や役割過重として現れ、最終的には離職意向の増加につながっていきます。
対して、従業員に十分な裁量が与えられている場合は、状況が異なります。自律的に仕事を進められる余地があることで、「無理やりやらされている」「過剰に要求されている」というストレス感が軽減されます。その結果、不安や役割過重も抑制され、離職意向も低く抑えられる傾向にあります。
調査では、職務裁量が従業員の感情にも影響を与えることが分かりました。裁量があると、従業員はポジティブな感情を抱きやすくなり、それが職務満足度の向上につながります。逆に、裁量権が制限されていると、ネガティブな感情が増加し、職務満足度も低下してしまいます。
HPWSの導入が従業員の離職意向を高める過程では、不安や役割過重が媒介要因として機能することも明らかになりました。HPWSによる高い要求と裁量権の欠如が不安や役割過重を引き起こし、それが「この職場を去りたい」という気持ちの増幅につながっているのです。
従業員の個人特性や職場環境によっても、裁量の効果は異なることが分かりました。自己効力感の高い従業員は、裁量があることでよりポジティブな効果を得られます。一方、不確実性を避けたい従業員にとっては、裁量の付与がかえってストレス要因になる可能性もあります。
HPWSの「影」を考慮した導入に向けて
ここまでの研究から、HPWSの功罪に関する職場のマネジメントへの示唆が得られます。HPWSを導入する際には、管理職の認識と従業員の実感の間にギャップが生じやすいことを認識する必要があるでしょう。制度の存在だけでなく、従業員が実際にその恩恵を受けられているかどうかを丁寧に確認することが求められます。このギャップを埋めるためには、定期的な従業員との対話や、制度の利用状況のモニタリングが不可欠です。
また、HPWSが従業員に過度な負担やストレスをもたらす可能性にも十分な配慮が必要です。とりわけ、仕事要求と仕事資源のバランス、内発的動機づけの維持、従業員の心理的負担に注意を払うことが大切です。中国企業の事例が教えてくれるように、組織の文化的背景によってHPWSの受け止められ方は異なります。そのため、制度の導入前には組織文化との適合性を慎重に検討し、必要に応じて段階的な導入や修正を行うことが望ましいでしょう。
そして何より、従業員に適切な裁量を与えることがHPWSの成功には不可欠です。イギリスの公的機関での調査が明らかにしたように、仕事の進め方を自分でコントロールできる環境があってこそ、HPWSは本来の効果を発揮することができます。裁量の欠如は、従業員の不安や役割過重を引き起こし、最終的には離職意向の増加にもつながりかねません。この裁量の付与は、単純な権限委譲ではなく、適切なサポート体制や明確な責任範囲の設定を伴う必要があります。
人材マネジメントの成功は、業績向上と従業員のウェルビーイングのバランスを取ることにかかっています。HPWSは確かに有効な手法ですが、それを機械的に導入するのではなく、組織の文化や従業員の実情に合わせて柔軟に運用することが求められます。時には「やり過ぎ」を戒め、従業員の視点に立ち返ることも必要でしょう。
制度の効果を定期的に検証し、従業員からのフィードバックを積極的に取り入れながら、継続的な改善を図ることも重要です。従業員の成長と組織の発展を両立させるためには、HPWSを管理ツールではなく、相互の信頼関係を築くための基盤として位置づける必要があるでしょう。HPWSの真価は、こうした繊細なバランスの上に成り立つものなのです。
脚注
[1] Liao, H., Toya, K., Lepak, D. P., and Hong, Y. (2009). Do they see eye to eye? Management and employee perspectives of high-performance work systems and influence processes on service quality. Journal of Applied Psychology, 94(2), 371-391.
[2] Han, J., Sun, J.-M., and Wang, H.-L. (2020). Do high performance work systems generate negative effects? How and when? Human Resource Management Review, 30(2), 100699.
[3] Chang, P.-C., Wu, T., and Liu, C.-L. (2018). Do high-performance work systems really satisfy employees? Evidence from China. Sustainability, 10(10), 3360.
[4] Jensen, J. M., Patel, P. C., and Messersmith, J. G. (2013). High-performance work systems and job control: Consequences for anxiety, role overload, and turnover intentions. Journal of Management, 39(6), 1699-1724.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。