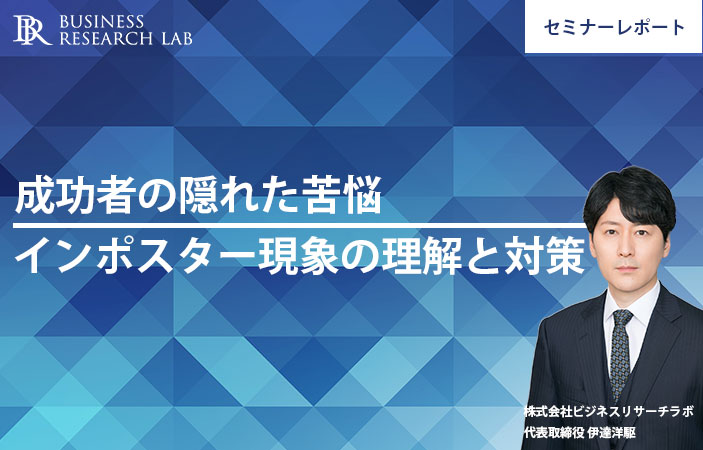2025年2月3日
成功者の隠れた苦悩:インポスター現象の理解と対策(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年1月にセミナー「成功者の隠れた苦悩:インポスター現象の理解と対策」を開催しました。
成功を収めているにもかかわらず「自分には本当の実力がない」「いつか正体がばれてしまうのではないか」という不安を抱えていませんか。
これは「インポスター現象」と呼ばれる状態で、決して特別なことではありません。むしろ、優秀で真面目な人ほど経験する可能性が高いことが明らかになっています。
本セミナーでは、インポスター現象のメカニズムと、それが個人のキャリアや組織にもたらす影響について解説しました。
特に注目すべきは、この現象が単なる自信の欠如や謙虚さとは異なるという点です。成功すればするほど強くなることもあり、時には組織全体のパフォーマンスにも影響を及ぼす可能性があります。
経営者、管理職の方々はもちろん、キャリア開発に関心のある全ての方々にとっておすすめの内容です。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
自分は周りをだましているのではないか。いつか正体がばれてしまうのではないか。そんな不安を抱えながら、日々の業務に取り組んでいる人がいます。高い評価を受け、順調にキャリアを重ねているように見える人ほど、このような感情に苛まれることがあります。これが「インポスター現象」です。
インポスター現象は、単純な自信のなさや謙虚さとは異なります。むしろ、周囲からの期待が高まれば高まるほど強くなり、そのことがさらなる不安を生み出すという悪循環に陥りやすいものです。インポスター現象に苦しむ人々は、自分の成功を運や偶然に帰属させ、自身の能力や努力を正当に評価しにくい状態にあります。
しかし、学術研究により、インポスター現象は決して珍しいものではないことがわかってきました。また、適切な理解と対策によって軽減できることも明らかになってきています。本講演では、インポスター現象に関する研究知見をもとに、その本質と対処法を解説していきます。
皆さんや皆さんの周りの人が、もしかしたらインポスター現象に悩んでいるかもしれません。本講演を通じて、その状態を理解し、乗り越えるためのヒントを見つけていただければ幸いです。
インポスター現象とは
インポスター現象は、個人が自身の能力や成功を正当に評価できず、自分を「詐欺師」のように感じることを指します。高い能力を持ち、成功を収めている人が、自分の成功を運や偶然によるものだと考え、自分は無能であると信じ込む傾向があります。優れた実績を上げているにもかかわらず、その事実を素直に受け入れることができないのです。
インポスター現象は三つの要素から構成されています[1]。一つ目は「フェイク」で、これは自分の知性や能力に対する深い疑念を指します。インポスター現象を経験する人は、周囲を騙していると感じ、いつか「正体がばれる」という不安に苛まれます。高評価の仕事をしても、自分は運が良かっただけだと考えてしまいます。
二つ目は「ラッキー」で、成功を運や偶然に帰する傾向です。努力や能力の結果と認識できず、「たまたま上手くいっただけ」と考えます。昇進やプロジェクトの成功を、自分の実力ではなく周囲の助けや運によるものだと解釈します。自分の貢献を評価できないため、次の機会に対する自信にもつながりにくく、新しい挑戦を躊躇する原因となります。
三つ目は「ディスカウント」で、自分の良いパフォーマンスや成果を認めないことを指します。高評価を受けても素直に受け入れず、自分の業績を過小評価します。同僚から優れた発表だったと褒められても、「準備が足りなかった」「もっと上手くできたはず」と否定的に考えます。
インポスター現象に関する研究は年々増加しており、特に近年、急激な伸びを示しています[2]。特に2009年以降、2022年以降に段階的に急増しています。この増加は、職場におけるメンタルヘルスの重要性が認識されるようになったこと、そしてコロナ禍などの働き方の大きな変化が、この分野の研究を加速させたことによるものと考えられています。
どんな人に多いのか
アジアとヨーロッパの文化的差異を比較した研究によると、アジアの参加者がヨーロッパの参加者よりも有意に高いインポスター現象のレベルを報告しました[3]。文化的な価値観や社会的期待の違いが影響している可能性があります。
例えば、アジアの文化では謙虚さが美徳とされ、これがインポスター感を強める要因となっているかもしれません。自己主張を控え、成功を控えめに表現することが望ましいとされる文化的背景が、インポスター現象を強める可能性があるのです。
さらに、集団主義的な価値観も影響している可能性があります。個人の成功よりも集団の調和を重視する文化では、個人の成功を強調することへの躊躇が生まれやすいということも関係していそうです。
管理職を務めるプロフェッショナルを対象にした研究では、インポスター現象に性別による有意な差異は見られませんでした[4]。男性と女性が同程度にインポスター現象を経験していたのです。これは見方によっては意外な結果かもしれません。
このような結果が出た理由として、社会の変化が影響している可能性があります。近年、ジェンダー意識が高まり、職場における男女の役割の違いが徐々に縮小してきつつあります。そのため、男女で関係なくインポスター現象が発生していたということです。
また、調査対象が管理職に限定されていたことも重要です。管理職についている女性は、一般的な女性と比較して、より高い自己効力感や目標志向性を持っている可能性があります。そのため、インポスター現象の経験頻度が男性と同程度になったという捉え方もできます。
男性のインポスター現象に対する認識が変化してきたということもあり得ます。従来、男性は弱さや不安を表現することを避ける傾向がありましたが、自分の感情をより正直に表現するようになってきました。男性のインポスター現象がより可視化されるようになってきているとも考えられます。
キャリアに対する影響
インポスター現象は個人のキャリアの楽観主義にマイナスの影響を与えます[5]。キャリアの楽観主義とは、将来のキャリアに対して前向きな期待や希望を持つことを意味します。インポスター現象を経験する人は、自分の成功を一時的なものや運によるものと考えるため、将来的に失敗するのではないかという恐れを抱きやすくなります。
その結果、キャリアに対する楽観的な見方が減少し、長期的なキャリア計画を立てることが困難になります。新しい機会に対しても消極的になりやすく、自己成長の機会を逃してしまうこともあるでしょう。インポスター現象は個人のキャリア発達を阻害する要因となり得るのです。
インポスター現象はリーダーシップの意欲も減退させます。リーダーシップポジションに就くことは、多くの場合、高い可視性と責任を伴います。インポスター現象を経験する人は、自分がリーダーシップを発揮できる能力があると信じておらず、リーダーとして失敗することを恐れます。リーダーシップの機会が与えられても、それを避けようとします。
この傾向は、組織にとっても損失となります。潜在的な優秀なリーダーが、自信の欠如によってその機会を逃してしまうことは、組織の人材育成や成長にとってマイナスとなるからです。リーダーシップ役割を避けることで、その人自身の成長機会も失われてしまいます。
さらに、インポスター現象は、個人の内部市場性(組織内での価値)と外部市場性(他の組織での価値)の認識にも影響を与えます。インポスター現象を感じる人は、自分のスキルや経験を過小評価し、昇進や新しい職を探すことに消極的になります。今の地位は運が良かっただけで、他の組織では通用しない、自分のスキルは特別なものではないといった考えが、キャリアの停滞や機会の喪失につながるのです。
実際に、インポスター現象は長期的なキャリア成功にも影響を与えることが研究によって明らかになっています。インポスター現象は外的雇用能力(他の組織での雇用可能性)と客観的キャリア成功(昇進、パフォーマンス評価)に負の影響を与えることが実証されています[6]。
外的雇用能力に関しては、インポスター現象を経験する個人は自分の能力や経験を過小評価するため、新しい職を探すことに消極的になります。「他の組織では通用しない」「今の成功は運が良かっただけだ」といった思考が、キャリアの可能性を狭めてしまいます。
客観的キャリア成功については、インポスター現象が昇進や高評価の獲得を妨げる可能性があります。自分の能力に自信がないため、昇進の機会を自ら断ったり、重要なプロジェクトのリーダーシップを避けたりすることで、キャリアの進展が遅れます。自分の成果をアピールできないことで、能力や貢献が正当に評価されないかもしれません。
そればかりか、インポスター現象は反芻、失敗反芻、自己卑下という三つのメカニズムを通じて、抑うつを引き起こします[7]。反芻とは過去の出来事や自分の行動について繰り返し考え続けることで、失敗反芻とは特に失敗経験に焦点を当てて繰り返し考えることです。自己卑下とは自分を他人より劣っていると感じ、否定的に評価することを指します。
これらのメカニズムは、文化的背景を問わず、インポスター現象と抑うつ症状の関係を部分的に説明しています。とりわけ、失敗についての反芻は、将来の失敗への不安を強め、それがさらなるインポスター感を生み出すという悪循環を引き起こします。
パフォーマンスに対する影響
インポスター現象が強い人は、課題遂行中や課題終了後の評価において、自分のパフォーマンスを過小評価することが明らかになっています[8]。実験において、参加者に論理的な問題を解決するタスクが与えられました。
インポスター現象が強い参加者は、タスク中に自分のパフォーマンスをより否定的に評価しました。問題を解いている最中に「自分はうまくできていない」と感じやすいのです。このような否定的な自己評価は、タスクへの集中力を低下させ、実際のパフォーマンスにも悪影響を及ぼし得ます。
インポスター現象は、他者との比較評価においても同様の傾向が見られました。インポスター現象が強い人は、実際の成績や他の参加者との比較において、自分のパフォーマンスを過小評価していました。
たとえ同じ成績であっても、インポスター現象が強い人は「自分の成績は平均以下だ」と考えやすいということです。これは、客観的な評価基準がある場合でも同様で、自己評価と実際の評価との間に乖離が生じることがあります。
加えて、インポスター現象は恥の感情を生み出し、それが創造性に負の影響を与えます[9]。創造的な活動には、新しいアイデアを提案したり、リスクを取ったりすることが必要ですが、恥の感情はこれらを抑制します。
自分のアイデアが批判されることを恐れ、新しい提案を控えるようになるのです。例えば、革新的なプロジェクトのアイデアを持っていても、「このアイデアは愚かだと思われるかもしれない」という気持ちから、それを提案することができない場合があります。
組織市民行動についても、インポスター現象が複雑な影響を与えることが分かっています。組織市民行動は、正式な職務範囲を超えて行われる自主的な行動のことを指します。インポスター現象を経験する個人は、自分の能力や地位に対する不安から、組織市民行動を通じて自分の価値を証明しようとする傾向があります。例えば、同僚を助けたり、追加の仕事を引き受けたりすることで、自分の存在価値を示そうとするのです。
これは短期的には組織にとってプラスに働く可能性がありますが、長期的には個人の燃え尽きや過剰適応につながるリスクもあります。本来の業務に注力すべき時間が失われる可能性もあります。いずれにせよ、持続的な動機とは言いにくいものです。
企業レベルのパフォーマンスに影響する条件もあります。女性のトップマネジャーがインポスター現象を強く経験している場合、企業の業績が低下する傾向が見られました[10]。なぜ女性のトップマネジャーの場合において、インポスター現象が企業業績に悪影響を与えるのでしょうか。研究者たちは、いくつかの可能性を示唆しています。
一つの説明は、社会的および文化的なプレッシャーの影響です。女性のトップマネジャーは、しばしば「ガラスの崖」と呼ばれる状況に直面します。これは、リスクの高い、失敗の可能性が高いポジションに就きやすいことを指します。このような状況下で、インポスター現象を経験することは、大きなストレスと不安を引き起こし、結果的に業績に悪影響を与える可能性があります。
また、女性のトップマネジャーはジレンマに直面することがあります。リーダーシップを発揮すれば「攻撃的」と見なされ、協調的であれば「弱い」と見なされるというものです。このような状況で、インポスター現象を経験することは、自信を失わせ、効果的な意思決定を妨げます。
インポスター現象への対処
コーチングがインポスター現象の軽減に効果的であることが明らかになっています。コーチング、トレーニング、そして対照群の3つのグループに分けて、インポスター現象の軽減効果を比較した研究があります[11]。その結果、コーチングを受けたグループが最も顕著なインポスター現象の減少を示しました。この効果は時間が経過しても持続していました。
コーチングが効果的であった理由として、コーチングは個別化されたアプローチを取ることができる点が挙げられます。インポスター現象は個人によって異なる形で現れるため、一人一人の状況に合わせたサポートが可能なコーチングは有効です。
また、コーチングでは、クライアントの強みに焦点を当てることで、自己認識の偏りを修正することができます。自分の成功体験を振り返り、それが実際には自分の能力や努力の結果であることを理解する手助けとなります。
インポスター現象を緩和させるために、コーチングにおいては、目標設定と達成のプロセスを重視すると良いでしょう。研究結果によると、コーチングを受けたグループは目標達成度が高く、その効果が持続していました。目標を達成する経験を積み重ねることで、自己効力感が高まり、インポスター感情が軽減される可能性があります。
さらに、コーチングは否定的評価への恐怖を軽減するのに効果的です。研究では、否定的評価に対する恐れの減少が、インポスター現象の低下に有意な影響を与えていることが明らかになりました。コーチは、クライアントが失敗を学習の機会として捉え直すことを支援し、完璧主義的な思考パターンを緩和します。
もう一つの切り口として、自己効力感がインポスター現象の予測因子であることが明らかになっています[12]。自己効力感とは、特定の課題を遂行する能力に対する個人の信念のことを指します。「自分にはこのタスクを成功させる能力がある」と信じる程度のことです。研究では、自己効力感が低いほど、インポスター現象を経験する可能性が高くなることがわかりました。
自己効力感が低い人は、自分の能力や実績を過小評価します。例えば、プロジェクトが成功しても、それを自分の能力のおかげだとは考えず、運や他人の助けによるものだと考えがちです。これは、インポスター現象の特徴と一致します。
インポスター現象を緩和させるために、達成可能な小さな目標を設定し、それを達成していくことで、自己効力感を徐々に高めることが有効です。また、自分と似た立場の人が成功する姿を観察することで、「自分にもできるかもしれない」という感覚を得ることができます。
他者からのポジティブ・フィードバックを受け入れ、それを自分の能力の証拠として認識する練習をすることも大切です。ストレス管理やリラクセーション技法を学び、不安や緊張を和らげることで、自己効力感を高めることができます。先ほど述べたコーチングも、自己効力感を高める効果的な方法の一つです。
おわりに
本講演では、インポスター現象について様々な角度から検討してきました。インポスター現象は、単なる自信のなさや謙虚さとは異なる問題であり、個人のキャリアやパフォーマンス、そして組織全体にも影響を与えることがわかりました。
アジアではヨーロッパよりもインポスター現象が多く見られますが、管理職においては性別による差は見られないことも明らかになりました。この現象は、キャリアの楽観主義を低下させ、リーダーシップへの意欲を減退させることで、個人の成長を妨げる可能性があります。また、創造性や企業業績にも悪影響を与える可能性があることがわかりました。
しかし、コーチングや自己効力感の向上といった対処法が効果的であることも示されました。組織としても、メンタリングプログラムの提供や、失敗を許容する文化の醸成など、様々な支援が可能です。
最後に、注意すべき点として、「戦略的インポスター」の存在が挙げられます。従来のインポスター現象(「真のインポスター」)とは異なり、戦略的に自己表現を行う人々がいることがわかってきました[13]。これらの人々は、自己疑念にそれほど影響されず、むしろインポスター的な振る舞いを意図的に用いています。
例えば、自分の能力や成果を過小評価することで、他人の期待を低く保とうとしたり、謙虚さを表現しようとしたりする場合があります。短期的には効果的な印象管理戦略かもしれませんが、長期的には組織内のコミュニケーションや信頼関係に悪影響を及ぼし得ます。注意したいところです。
Q&A
Q:インポスター現象に悩む部下に対して、具体的な成果や数値を示しても受け入れてもらえません。どのようなコミュニケーションが効果的でしょうか。
これは難しい課題ですが、いくつかの対応策が考えられます。数値による客観的な評価を示すことは有効な方法の一つですが、それに加えて成果に至るまでのプロセスや努力を言語化して伝えることも重要です。そうすることで、部下は自身の頑張りを実感しやすくなります。
また、フィードバックの頻度も重要でしょう。定期的なフィードバックを通じて、小さな成功体験を積み重ねていくことができます。
ポジティブ・フィードバックは特に有効です。ポジティブ・フィードバックを通じて部下の強みや独自の貢献に焦点を当て、それらが組織やチームにどのように貢献しているのかを説明することで、自身の価値を認識しやすくなります。
Q:社内でコーチングを導入する場合、どのような点に注意すべきでしょうか。また、外部のコーチと内部のコーチのどちらが望ましいでしょうか。
コーチングの効果を最大化するためには、コーチのスキルはもちろんですが、コーチとクライアントの信頼関係も大事です。
内部コーチ(社員がコーチを務める場合)のメリットは、組織文化への理解があることです。一方で、社内の人間であるため、クライアントが本音を話しにくいというデメリットもあります。外部コーチの場合は、客観的な視点を提供できるという強みがありますが、コストが高くなる可能性があります。
実際には、両方を組み合わせるのが良いでしょう。例えば、外部コーチによる定期的なコーチングを実施しながら、内部コーチも育成していくという方法です。また、インポスター現象に関するコーチングでは個人のプライバシーに関わる問題が多く出てくるため、プライバシーを守る仕組み作りも必要です。
Q:戦略的にインポスター的に振る舞う人々について、長期的にどのような悪影響があるのでしょうか。
戦略的なインポスター的振る舞いの影響は、その人の意図によって異なります。組織にとって良いことを目指している人が戦略的にインポスター的な振る舞いをする場合は、大きな問題にはなりにくいかもしれません。
しかし、自分の利益を優先し、組織の利益を軽視する人が戦略的にインポスター的振る舞いをする場合は問題です。周囲の期待値を意図的に下げることで、同じ成果でもより高い評価を得やすくなります。これは組織にとってリスクとなり得ます。
特に部下にとっては深刻な問題となる可能性があります。上司の本意が分かりにくく、どのように振る舞えば良い評価が得られるのか判断が難しくなります。その上司に評価されようとすることが、組織の利益に反する可能性もあります。
Q:本来のインポスター現象と戦略的な振る舞いをどのように見分ければよいでしょうか。また、昇進の判断にどう影響させるべきでしょうか。
本来のインポスター現象は、高い実績やスキルがあるにもかかわらず、継続的に自信が持てない状態を指します。一方、戦略的なインポスター的振る舞いは、状況に応じて態度が変化する特徴があります。
これらを見分けるためには、360度評価などの多面評価を活用することが有効でしょう。日常的な業務での振る舞いについて、部下からの評価も含めて様々な角度から情報を収集し、上司からの評価と照らし合わせることで、より正確な判断が可能になります。
Q:会社の成長に伴い、20代後半から30代前半の若手管理職が増えています。年上の部下をマネジメントする際にインポスター現象が現れていますが、どのようにサポートすればよいでしょうか。
若手管理職が経験するインポスター現象には、年齢に起因する不安が影響している可能性があります。このような場合、マネジメント能力と年齢は必ずしも相関しないということを組織として伝えることが大切です。
若手管理職が選抜された理由や期待されている役割を明確に伝えるのも良いでしょう。管理職は孤立しやすい立場にあるため、他部署の若手管理職との情報交換の機会を設けることをお勧めします。共通の課題を見出し、解決策を共有することで、自己効力感を高め、インポスター現象の緩和につながることが期待できます。
脚注
[1] LaVelle, J. M., Jones, N. D., and Donaldson, S. I. (2024). Addressing the elephant in the room: Exploring the impostor phenomenon in evaluation. American Journal of Evaluation, 45(2), 186-202.
[2] Demirbas, H., and Altintas, F. C. (2023). Mapping the landscape of impostor phenomenon research in organizational behavior: A bibliometric study between 2003 and 2022. Cumhuriyet Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 24(4), 560-572.
[3] Cheung, J. O. H., and Cheng, C. (2024). Cognitive-behavioral mechanisms underlying impostor phenomenon and depressive symptoms: A cross-cultural analysis. Personality and Individual Differences, 227, 112716.
[4] Rohrmann, S., Bechtoldt, M. N., and Leonhardt, M. (2016). Validation of the impostor phenomenon among managers. Frontiers in Psychology, 7, 821.
[5] Neureiter, M., and Traut-Mattausch, E. (2016). An inner barrier to career development: Preconditions of the impostor phenomenon and consequences for career development. Frontiers in Psychology, 7, 48.
[6] Hudson, S., and Gonzalez-Gomez, H. V. (2021). Can impostors thrive at work? The impostor phenomenon’s role in work and career outcomes. Journal of Vocational Behavior, 128, 103601.
[7] Cheung, J. O. H., and Cheng, C. (2024). Cognitive-behavioral mechanisms underlying impostor phenomenon and depressive symptoms: A cross-cultural analysis. Personality and Individual Differences, 227, 112716.
[8] Gadsby, S., and Hohwy, J. (2024). Negative performance evaluation in the imposter phenomenon. Current Psychology, 43(10), 9300-9308.
[9] Hudson, S., and Gonzalez-Gomez, H. V. (2021). Can impostors thrive at work? The impostor phenomenon’s role in work and career outcomes. Journal of Vocational Behavior, 128, 103601.
[10] Guedes, M. J. (2023). Can top managers’ impostor feelings affect performance?. Journal of Strategy and Management, 17(1), 188-204.
[11] Zanchetta, M., Junker, S., Wolf, A. M., and Traut-Mattausch, E. (2020). Overcoming the fear that haunts your success? The effectiveness of interventions for reducing the impostor phenomenon. Frontiers in Psychology, 11, 405.
[12] Vergauwe, J., Wille, B., Feys, M., De Fruyt, F., and Anseel, F. (2015). Fear of being exposed: The trait-relatedness of the impostor phenomenon and its relevance in the work context. Journal of Business and Psychology, 30(4), 565-581.
[13] Leonhardt, M., Bechtoldt, M. N., and Rohrmann, S. (2017). All impostors aren’t alike? Differentiating the impostor phenomenon. Frontiers in Psychology, 8, 1505.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。