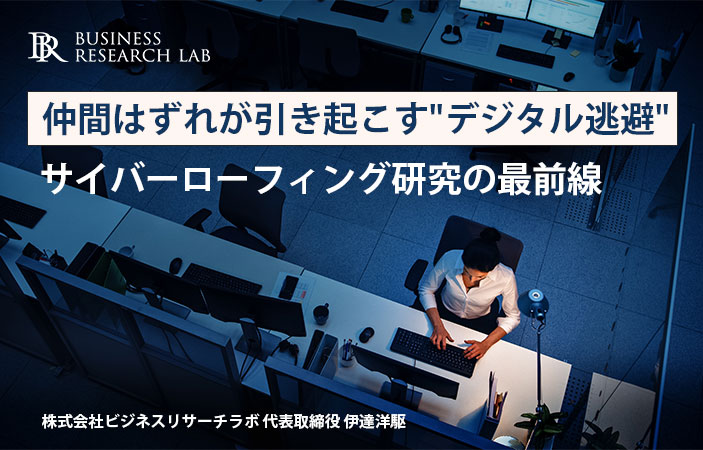2025年2月3日
仲間はずれが引き起こす”デジタル逃避”:サイバーローフィング研究の最前線
仕事中にスマートフォンでSNSをチェックしたり、ニュースサイトを閲覧したりした経験はありませんか。業務時間中の私的なインターネット利用は「サイバーローフィング」と呼ばれています。
何が従業員をサイバーローフィングへと導くのでしょうか。退屈感や仕事への低い関与、職場での人間関係のストレス、メールでの無礼な対応など、様々な要因がサイバーローフィングを引き起こすことが分かってきました。
組織にとって、従業員がなぜサイバーローフィングを行うのか、そのメカニズムを理解することは重要です。サイバーローフィングは、怠慢や規律の欠如とは限りません。職場環境や人間関係、個人の特性など、多様な要因が絡み合って生じます。
本コラムでは、職場での性差による違い、オストラシズム(仲間はずれ)の影響、メールコミュニケーションの在り方など、様々な角度からサイバーローフィングを促す要因を検討します。これらの要因を理解することは、職場環境の改善と生産性の向上につながる第一歩となるでしょう。
サイバーローフィングには性差がある
サイバーローフィングの頻度や認識には、性別による差異があることが実証的に示されています。アジアの大学を卒業した500名を対象とした調査では、男女間で興味深い違いが見られました[1]。
サイバーローフィングの時間に差が存在します。男性は1日平均61分、女性は1日平均46分をサイバーローフィングに費やしています。この差は、インターネット利用に対する自信や態度の違いを反映しています。男性はインターネット利用に自信を持ち、娯楽的な利用を好む傾向があるため、サイバーローフィングの機会を積極的に活用します。
サイバーローフィングが仕事に及ぼす影響についても、性別による認識の違いが顕著です。女性は「締め切りが延びる」「作業が残る」といった否定的な影響を強く意識する一方、男性は「仕事が面白くなる」「生産性が向上する」といった前向きな影響を報告しています。
この違いの背景には、インターネット利用に対する心理的な差異があります。女性はインターネット利用への不安感が強く、サイバーローフィングを心理的な負担として捉える傾向にあります。対照的に、男性は娯楽的な感覚で利用し、気分転換や発想の転換の機会として好意的に捉えています。
サイバーローフィング後の仕事への復帰時間にも男女差が見られます。男性は平均4分で仕事に戻れるのに対し、女性は平均10分を要します。この差は、インターネット利用への不安感や中断後の集中力低下が女性において大きいことを示唆しています。
女性の場合、サイバーローフィング中に未完了のタスクに対する罪悪感や焦りを抱きやすく、これが心理的な負担となり、仕事への復帰を遅らせる要因となっています。一方、男性は仕事の中断を「充電期間」としてポジティブに捉え、スムーズに仕事に戻ることができます。
オストラシズムがサイバーローフィングを増やす
職場での人間関係、特に仲間はずれ(オストラシズム)は、サイバーローフィングを促進する要因です。マレーシアの上場企業に勤務する従業員243名を対象とした調査では, オストラシズムがサイバーローフィングに結びつくメカニズムが解明されました[2]。
職場で無視されたり排除されたりすることは、従業員の心理的資源を消耗させます。その結果、従業員は「道徳的離脱」と呼ばれる状態に陥りやすくなります。道徳的離脱とは、内面的な道徳基準を一時的に無効化して非倫理的行動を正当化するプロセスです。
調査では、オストラシズムを経験した従業員の道徳的離脱が高まることが確認されました。そして、この道徳的離脱は、サイバーローフィングの増加につながります。要するに、「自分は正当な評価を受けていないから、多少サボっても問題ない」というような認識が形成され、道徳的な判断が弱まるのです。
興味深いことに、従業員の組織への忠誠心(組織的コミットメント)は、オストラシズムとサイバーローフィングの関係を弱めることができませんでした。これは、従業員の忠誠心の高低にかかわらず、オストラシズムがサイバーローフィングを引き起こす可能性が高いことを表しています。
この結果の背景には、二つのメカニズムが存在します。忠誠心の高い従業員は、オストラシズムを「問題ではない」と認識する傾向があり、心理的負担が軽減される一方で、サイバーローフィングを行う可能性は依然として高いままです。他方、忠誠心の低い従業員は、そもそも組織に対する期待が低いため、オストラシズムを感じても別の形で対処する可能性があります。
また、オストラシズムは従業員の感情的疲労を引き起こし、この感情的疲労がサイバーローフィングを促進することも明らかになりました。感情的疲労は、オストラシズムとサイバーローフィングの関係を部分的に媒介しています。
制約があってもオストラシズムはサイバーローフィングを促す
職場でのインターネット利用規定や監視システムなどの制約要因は、一見するとサイバーローフィングを抑制するように思えます。しかし、これらの制約はオストラシズムとサイバーローフィングの関係を予想に反して強化することが分かりました[3]。
調査結果によると、促進条件(制約要因)は、オストラシズムとサイバーローフィングの関係を強める方向に作用します。これは、仲間はずれにされた従業員が、厳しい監視や規制を「不公平」な扱いとして受け止め、その結果としてサイバーローフィングを増加させる反応を示すためです。
この予想外の結果には、複数の要因が関係しています。第一に、オストラシズムを経験している従業員は、職場環境全体に対して不信感を抱きやすくなります。そのような状況で制約が強化されると、それを「自分をさらに追い詰める圧力」として認識し、反発心からサイバーローフィングを行う可能性が高まります。
第二に、従業員が「不公正な扱いを受けている」という認識を持つと、組織に対する忠誠心が低下し、制約を無視する行動を正当化しやすくなります。オストラシズムと制約の組み合わせは、従業員の不満を増幅させ、サイバーローフィングという形での抵抗行動を引き起こすのです。
感情的疲労が高い状態では、従業員は制約を無視してサイバーローフィングを行う傾向が強まります。感情的疲労の高い従業員は、規制に従うためのエネルギーや意志力を持たず、自分の心理的負担を軽減することを優先します。
さらに、制約が強ければ強いほど、従業員はそれを「負担をさらに増やすもの」と認識し、逆に規則を破る意欲が高まる可能性があります。制約が従業員のストレスを増加させ、その対処行動としてサイバーローフィングが選択されることを示唆しています。
この研究は、制約要因がオストラシズムとサイバーローフィングの関係を強化するという発見を通じて、職場での規制がかえって逆効果をもたらす可能性を示しています。この知見は、組織が従業員のサイバーローフィングに対処する際に、単純な規制強化ではなく、より包括的なアプローチが必要であることを意味しています。
無礼なメールがサイバーローフィングを促す
職場でのメールコミュニケーションの在り方も、サイバーローフィングに影響を及ぼします。113名の正社員を対象とした10日間の調査では、メールでの無礼な行為とサイバーローフィングの関係が分析されました[4]。
メールでの無礼行為は、「能動的」と「受動的」の2種類に分類されます。能動的な無礼行為は侮辱的な発言を含むものを指し、受動的な無礼行為は質問への返信を無視するなどの行為を指します。
調査結果から、受動的な無礼行為は従業員の否定的感情を引き起こし、最終的にサイバーローフィングの増加につながることが判明しました。受動的な無礼行為の曖昧さが従業員の反芻(同じ出来事を繰り返し思い返すこと)を促し、否定的感情を増幅させるためです。
受動的な無礼行為が否定的感情を引き起こすメカニズムは、その行為の曖昧性に起因します。返信を無視されたり、あいまいな返答を受けたりすることで、従業員は「自分が軽視されているのではないか」「何か問題があるのか」といった不安を抱き、それを繰り返し考えることで心理的負担が増大します。
対して、能動的な無礼行為は、その意図が明確であるため、受け取る側の解釈が比較的単純です。侮辱的な発言は直接的であり、その意図が明らかなため、反芻が起こりにくく、感情的な反応も短期的なもので終わりやすいという特徴があります。
個人の特性によって、メール無礼行為の影響は異なることも分かりました。「特性予防焦点」(望ましくない状況を避けようとする傾向)が高い人は、能動的な無礼行為に対してより強い否定的感情を抱きます。規範違反に敏感な性格が、明確な無礼行為をより強く認識するためです。
仕事量の多さも、受動的な無礼行為の影響を増幅させることが明らかになりました。仕事量が多い状況では、認知資源(思考や判断を行うためのエネルギー)が不足し、曖昧な行為に対して過剰に敏感になります。その結果、受動的な無礼行為がより大きなストレスとして感じられ、否定的感情が強まるのです。
サイバーローフィングを促す要因とは
サイバーローフィングの背景には、様々な要因が存在することが分かっています。54件の独立した研究を分析したメタ分析では、サイバーローフィングと関連する要因について、その相関関係が評価されました[5]。
メタ分析の結果によれば、退屈感は、サイバーローフィングを促す主な要因の一つです。仕事中に退屈を感じると、従業員は刺激を求めてインターネットやデジタルデバイスを利用し、仕事から気を逸らす行動を起こしやすくなります。
これは、仕事が単調であったり、従業員に適切な挑戦を与えられていなかったりする場合に顕著です。刺激の欠如を補うため、従業員は手軽にアクセスできるインターネットで気分転換を図ります。
仕事へのエンゲージメント(関与)も、サイバーローフィングと密接な関係があります。仕事に対する関心や意欲が低い従業員ほど、業務時間中にネットサーフィンで気を紛らわせます。業務に集中するための内発的なモチベーションが欠如している状態を反映しています。エンゲージメントの低い従業員は、仕事への共感や意義を覚えず、業務以外の活動に時間を費やすようになります。
職場の規範も、サイバーローフィングの頻度に影響を与えます。サイバーローフィングが職場で一般的な行動とみなされるほど、その行動は増加します。同僚が自由にスマートフォンを使用している環境では、自分も同じ行動を取ることへの罪悪感が薄れるのです。職場文化がサイバーローフィングを容認する場合、それが行動の正当化要因となり、組織全体でサイバーローフィングが増加します。
個人の自己抑制力は、サイバーローフィングを抑制する要因となります。自制心が強い人は、「SNSを見たい」という衝動が湧いても、それが仕事に悪影響を及ぼすと考え、自ら行動を制御することができます。自己抑制は、衝動的な行動を防ぐために必要な能力です。高い自己抑制力を持つ人は、誘惑に直面しても合理的に行動を選択しやすく、サイバーローフィングを制御することができます。
性格特性も、サイバーローフィングと関連があります。勤勉で規律正しい従業員(誠実性が高い人)は、職務に対する責任感が強いため、サイバーローフィングを行いにくい傾向があります。このような従業員は、職務の遂行に重きを置き、効率的であることを目指します。そのため、自己管理能力が強く、仕事以外の行動をすることに抵抗を感じます。
情緒的に安定している人は、ストレスや不安が少なく、集中力が高いため、仕事に専念しやすく、サイバーローフィングの必要性が低くなります。不安定な情緒は、気晴らしや気分転換を求める動機につながりますが、情緒安定性が高い人は感情の起伏が少なく、外部の刺激に頼らずとも職務を継続することが可能です。
他方で、自己効力感は予想外の影響を持つことが分かりました。高い自己効力感は本来望ましい性格特性とされますが、サイバーローフィングを増加させる要因にもなり得ます。これは、自己効力感が高い人が「自分は必要な仕事をこなしている」という安心感を持ち、仕事以外の行動を正当化するためです。
年齢、性別、収入、勤続年数などの人口統計学的指標は、サイバーローフィングにほとんど影響を与えないことが分かりました。従来、若年層や特定の職位の人がサイバーローフィングを行いやすいと考えられていましたが、メタ分析では、そのような傾向は確認されませんでした。サイバーローフィングは年齢や性別よりも、職場の文化や個人の性格特性に依存することを示唆しています。
テクノロジーの普及が進む現代では、若者だけでなく幅広い年代がインターネットを利用するため、行動が年齢に依存しにくくなっています。また、収入や勤続年数はサイバーローフィングを直接的に制約する要因とはならないことも明らかになりました。
脚注
[1] Lim, V. K., and Chen, D. J. (2012). Cyberloafing at the workplace: Gain or drain on work?. Behaviour & Information Technology, 31(4), 343-353.
[2] Koay, K. Y., and Lai, C. H. Y. (2023). Workplace ostracism and cyberloafing: a social cognitive perspective. Management Research Review, 46(12), 1769-1782.
[3] Koay, K. Y. (2018). Workplace ostracism and cyberloafing: A moderated-mediation model. Internet Research, 28(4), 1122-1141.
[4] Zhou, Z. E., Pindek, S., and Ray, E. J. (2022). Browsing away from rude emails: Effects of daily active and passive email incivility on employee cyberloafing. Journal of Occupational Health Psychology, 27(5), 503-514.
[5] Mercado, B. K., Giordano, C., and Dilchert, S. (2017). A meta-analytic investigation of cyberloafing. Career Development International, 22(5), 546-564.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。