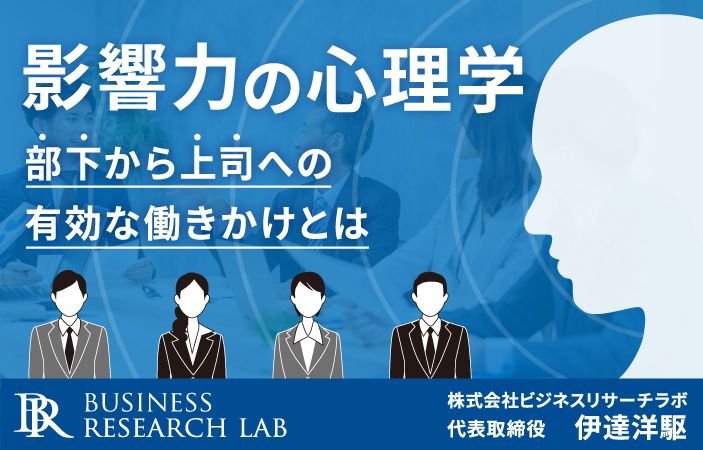2024年6月26日
影響力の心理学:部下から上司への有効な働きかけとは
部下が上司に影響を与える行動、いわゆる「上方影響戦術」については多くの研究が行われています。部下が上司にどのようにアプローチするかは、部下の動機やスキル、上司との関係性など、さまざまな要因で変わってきます。また、選んだ戦術によって効果にも違いが生じることがわかっています。
本コラムでは、これまでの研究知見を紹介しながら、部下による上方影響力の実態と、その背景にあるメカニズムについて考えます。
職場で同僚や部下が上司に働きかける様子を目にしたことがあるでしょう。こうした行動の背後にある心理を理解することで、組織内の人間関係をより深く理解するヒントが得られるはずです。
影響戦術は大きく3つに分けられる
上方影響力の戦術には、大きく分けて3つのアプローチがあります。非営利組織の従業員225名を対象にした調査において、上方影響戦術が「ハード戦略」「ソフト戦略」「合理的戦略」の3つに分類できることが明らかになっています[1]。
- ハード戦略:自己主張や上方アピール、連合の戦術から成り、例えば、重要な業務への協力など、部下が持つ何らかの力を利用して、上司に対して影響力を行使するのが特徴です。
- ソフト戦略:取り込みと交換の戦術で、上司の歓心を買ったり、お返しを約束したりすることで、上司の自発的な協力を引き出そうとします。
- 合理的戦略:主に論理的説得に基づく戦術で、一部に互恵的な交渉の要素も含まれます。
失敗の原因を相手のせいにする傾向
上方影響のプロセスを部下と上司の両方の視点から分析した研究があります。影響力の行使の成功と失敗について、部下と上司の受け止め方の違いに着目しています[2]。
調査の結果、部下と上司は影響力の行使が失敗したケースにおいて、その原因が何かという点で、部下と上司は受け止め方にズレがありました。部下は失敗の原因を上司の心が閉ざされているせいだと考える一方、上司は部下の能力不足のせいだと考えました。
失敗の責任をめぐる認識のズレは、帰属理論から説明できます。人は物事がうまくいかない時、自分の評価を守るために原因を外的要因に求めます。部下にとって面白くない影響力行使の失敗は上司のせいにし、上司にとって困る結果は部下の力不足のせいにする。ここには自我を守ろうとする認知のメカニズムが働いています。
影響戦術の成否の原因を歪んで考える傾向
インドの男性管理職を対象に、上方影響戦術の成功と失敗に関わる原因の考え方が検討されています[3]。
その結果、推論戦術が成功した場合、部下はそれを自分の論理的能力のおかげだと考え、失敗した場合は上司の非協力的な態度のせいにする傾向が見られました。自分の価値に関わる事柄では、物事の受け止め方が防衛的になりやすいのです。
一方、強引な戦術である条件付き協力や対立が失敗した場合、部下は失敗の原因を上司との関係性の悪さや自分の要求内容の問題に求めました。影響力の行使の仕方によっては、原因の考え方にゆがみが生じにくいこともあります。
また、地位の高い部下は推論戦略が成功した場合、それを自分の手柄だと考え、逆に地位の低い部下は影響力行使が失敗した場合、それを自分の立場の弱さのせいにしていました。自分の行動の原因を解釈する際、自分が置かれた立場が大きな役割を果たします。
上方影響の試みは、上司との関係を良好に保ち、自分の評価を高めるための部下の戦略的行動です。その成否の原因をどう考えるかによって、部下の自尊心が守られたり傷つけられたりします。
印象管理のスキルと動機が上方影響行動を促す
自分の印象をコントロールして他者に良い評価を得ようとする印象管理は、多くの人が日常的に行っている行動です。部下が上司に働きかける際も、意図的な印象操作が行われています。部下の印象管理スキルと動機が、上方影響戦略の選択にどう影響するかを調べた研究を見てみましょう[4]。
調査の結果、印象管理が高い部下ほど、上司に影響を与えるためにハード、ソフト、合理的な影響戦略を幅広く使いこなしていることが分かりました。印象管理の技術と意欲を兼ね備えた部下は、上司の顔色をうかがいながら計算高く立ち回ります。
上司との良好な関係では強引な戦術は避ける
上司と部下の関係の良し悪しが、部下の影響力行使の仕方をどう左右するか。この問題を正面から扱った研究があります[5]。LMX理論に基づいて、上司との関係が良好な部下(内集団)と希薄な部下(外集団)で、影響戦術の使い方が異なることを予測しました。
LMXとは、上司と特定の部下の間に形成される一対一の関係の質のことです。内集団の部下は上司からの信頼が厚く、重要な仕事を任されるなど優遇されますが、外集団の部下は必要最小限の関わりしか持てません。内集団の部下ほど建設的で穏当な影響戦術、つまりオープンな説得と戦略的説得を多用し、強引な操作的戦術を避けるだろうと考えました。
実際、オープンな説得と戦略的説得は内集団の部下に多く、操作は外集団の部下に多く見られました。内集団の部下は上司を味方と捉えて率直に意見を主張し、外集団の部下は表立った働きかけを避けて密やかに影響力を行使していました。
研究者は、上司との良好な関係がオープンなコミュニケーションを促し、ゆがんだ伝え方を減らすと指摘しています。逆に、関係が希薄だと部下は操作的な戦術を使うリスクが低いと感じるのかもしれません。
上司を信頼できるパートナーと見なせるかどうかが、影響力の行使の仕方を方向づけます。部下から見た上司との心理的な距離が近いほど、より健全な形で意見を主張できます。上下関係のあるべき姿を考える上で、重要な視点を提供してくれる研究です。
仕事重視と上司重視のどちらが昇進に有利か
自分の仕事ぶりを周囲にアピールすることが大切だと考える人もいれば、上司の歓心を買うことを重視する人もいます。こうした考え方の違いが、実際のキャリアの成功にどう影響するのでしょうか。
政治的影響行動を「仕事重視型」と「上司重視型」に分類した上で、それぞれがキャリアの外発的成功(昇進や報酬など)と内発的成功(仕事や人生の満足度など)に与える影響が比較されています[6]。
分析の結果、政治的影響行動がキャリアの成功を予測すること、影響行動の種類によって効果に違いがあることが実証されました。具体的には、仕事重視の自己宣伝的行動はキャリア成功を阻害し、上司重視の取り入れ的行動はキャリア成功を促進することが示されました。
影響戦術をキャリア戦略として用いることだけを考えれば、自己宣伝より取り入れに頼る方が賢明だと受け止められるのですが、次に紹介する研究は、この見方には慎重になるべきであることを示唆しています。
昇進につながる影響戦術とそうでない影響戦術
部下の影響力戦術と個人差が、昇進可能性に関する上司の評価にどのように影響するか。この問題を調べた研究を紹介します[7]。
まず、影響力戦術を「取り込み」「推論」「自己主張」の3つに分類しました。取り込みはソフト戦術、自己主張はハード戦術、推論は合理的説得に相当します。調査の結果、昇進可能性の評価には影響力戦術と個人差の両方が重要であることが示されました。
- 取り込みは昇進可能性と負の関係にあり、おべっかを使う人は出世に不利だと見なされやすいことがわかりました。
- 推論は昇進可能性と正の関係があり、論理的で客観的な情報提示が有利に働くと考えられます。
- 自己主張は昇進可能性にマイナスの影響を与え、上司の反発を招く恐れがあります。
- 学歴と在籍期間の長さは昇進可能性を高め、男性・白人であることも有利に働く傾向が見られました。
全体として、影響力戦術は重要であるものの、個人差要因のほうが昇進可能性をより強く予測していました。
この研究が興味深いのは、昇進の可能性の評価が客観的なプロセスだけではなく、影響力戦術や主観的な反応の影響を受けることを示した点です。特に、取り込み戦術が逆効果になりうるという知見は注目に値します。
部下の上方影響力に対する含意
ここまでの研究から、部下が上司に働きかける際の様式や心理的メカニズムについて、いくつかの示唆が得られます。
まず、部下が上司に影響を与えようとする際、ハード戦略、ソフト戦略、合理的戦略という3つのアプローチを使い分けていることがわかりました。状況に応じて適切な戦術を選択することが、影響力行使の成功につながると考えられます。いずれにしても、強引な戦術は上司との関係を損なう恐れがあるため、慎重に用いる必要があるでしょう。
また、部下の印象管理スキルと動機が、上方影響行動を促進することも明らかになりました。自己呈示の技術と意欲を兼ね備えた部下は、上司の反応を見極めながら巧みに立ち回ります。
一方で、上司との関係性の質が、部下の影響力行使の仕方を左右することも示されました。上司を信頼できるパートナーと見なせる部下ほど、率直に意見を主張します。健全な上下関係を築くことが、建設的なコミュニケーションを促進します。
さらに、影響力戦術とキャリアの関連性も注目に値します。自己宣伝より取り入れに頼る方が昇進に有利だと思われがちですが、おべっかを使う人は出世に不利だと見なされやすいことがわかりました。論理的で客観的な情報提示が、昇進可能性を高めるようです。
以上の知見は、部下が上司に影響を与える際の行動指針を検討する上で役立ちます。状況に応じて適切な戦術を使い分け、上司との信頼関係を構築することが肝要です。そして、論理的な説得を心がけることが、キャリアの成功につながるでしょう。
上方影響力は、組織の中で生き抜くための処世術とも言えます。うまく使いこなせば、キャリアの成功に近づくことができるでしょう。しかし、だからと言って、安易に上司に迎合したり、同僚を出し抜いたりすることが良いとは言えません。影響力行使は、あくまで手段であって目的ではないのです。大切なのは、組織と個人の健全な発展につながるような影響力行使を心がけることではないでしょうか。
脚注
[1] Farmer, S. M., Maslyn, J. M., Fedor, D. B., and Goodman, J. S. (1997). Putting upward influence strategies in context. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 18(1), 17-42.
[2] Schilit, W. K., and Locke, E. A. (1982). A study of upward influence in organizations. Administrative Science Quarterly, 304-316.
[3] Tandon, K., Ansari, M. A., and Kapoor, A. (1991). Attributing upward influence attempts in organizations. The Journal of Psychology, 125(1), 59-63.
[4] Deluga, R. J. (1991). The relationship of upward‐influencing behavior with subordinate-impression management characteristics. Journal of Applied Social Psychology, 21(14), 1145-1160.
[5] Deluga, R. J., and Perry, J. T. (1991). The relationship of subordinate upward influencing behaviour, satisfaction and perceived superior effectiveness with leader-member exchanges. Journal of Occupational Psychology, 64(3), 239-252.
[6] Judge, T. A., and Bretz Jr, R. D. (1994). Political influence behavior and career success. Journal of Management, 20(1), 43-65.
[7] Thacker, R. A., and Wayne, S. J. (1995). An examination of the relationship between upward influence tactics and assessments of promotability. Journal of management, 21(4), 739-756.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。